���E���l�����ʐ^�� �y�d������������ Version�z
�����ƁA���ƉƃR�[�i�[
57��
������ ����/Gennai Hiraga 1728-1779.12.18 �i�����s�A�䓌��A���ꌹ���揊 51�j2000��04��06 �����w��
 |
 |
  |
| �揊�͂ƂĂ�������ɂ����B�����ʂ�� �w�j�֕��ꌹ���搶�V��x�ŋȂ��� |
�Z��X�̒��Ɍ����̕揊���|�c���Ƃ��� |
�������������̕�����Ă��̂́A����̐e�F�E���c���� |
 |
 |
|
| ��ˁE�ٍ˂ƌĂ��]�˂̃_�E�r���` |
�ȑO�͖�����1�y�E���Ɩ�����18������ ��Q�ł��Ȃ��������A���܂͖������J�ɁH ���ߏ��̐l���Ǘ����Ă���炵���i2004�j |
������̍ہA����J�ƒm�炸�ɖK��� �K�b�N���B�ŁA�F�l�̌��Ԃŕ��̊O���� �p�`���B���̈Â���ɕ悪����i2000�j |
 |
 |
| ������͍L�������ہi�Ƃ��j�̉Y�ɂ���w���� �������K�i�������j�x�B�g���K�h�Ƃ͗D�ꂽ �l���O�̂������J�����g�₵��h�̂��Ƃ� |
�����͒���ŗ��w���w�э]�˂ɖ߂�r���� ���n�̍a��Ƃɑ؍݂��A���l�ɓ��@�i�����āj�� �`�����B����Ɋ��ӂ����a��Ƃ�1754�N�i������ ����15�N�O�j�ɁA�ނ�_�Ƃ��Ă������J�����Ƃ��� |
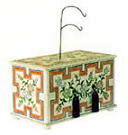 |
 |
 |
| �G���L�e�� | ���m�w�l�}�i������j | �����v |
|
�]�˒����̔����w�ҁE��ƁE��ƁE���|�ƁE�����ƁB�����镪��ɍ˔\���������{�̃_�E�r���`�I�{���A���ρi���ɂƂ��j�B�����ˑ��y���Ηǖ[�̎O�j�B24�̎��ɔ˂̖��߂Œ���ɗ��w�A���w���C�߂�B�����č]�˂ɂ����ĐA������ɂ���������w�́g�{���w�h���w�ԁB1757�N�i29�j�A�S���̓��Y�i���W�߂����{���̔�������J���A��������ɐ}�Ӂu���ޕi�(�Ԃ邢�Ђ�)�v�����s�B���l�̒��ڂ𗁂т�B
�{���w�҂Ƃ��Ė��𐬂����ނ́A�����˂̖�V��i�ƂȂ������A�˂̋����Ȃ��Ă͍��������R�ɍs�����ł��Ȃ����ɕs�ւ������E�˂���i33�j�B���̍ہA�����˂͌������u�d����\�i�����܂��j�v�ɏ������B����͑��˂֎d�����邱�Ƃ��֎~������̂��B�����͎���g�V���Q�l�h�Ɩ����A�H�c�����ł̍z�R�J���A�ؒY�̉^�����ƁA�r�������ĖѐD�����Y�A�A�o�p�̓��퐻��A���E��̃u���[�J�[�ȂǁA�l�X�Ȏ��ƂɎ���o�����B�܂��Ód�C�������u�g�G���L�e���h�A�g�R���Ȃ��z�h�Ο��z�i������ՁA�Ζȁj�A�����v�A���g�v�A���j��A���̑�100��ɂ��y�Ԕ����i���c�����B�����ɏ��w�Ŕ������N���̔j������l�Ă����̂��������B����A��ˁA���˂��ɂ��݂Ȃ������B�ނ͖��G���K�����ē��{���̗m����u���m�w�l�}�v��`���A�i�n�]���A���c�쒼���i�u��̐V���v�̑}�G��Ɓj��ɐ��m��@���������B�����G�ł͑��F����̋Z�@��҂ݏo���A���̔ʼn�v�����ĐF�Ƃ�ǂ�̃J���t���ȕ����G���a�������B
��ƂƂ��Ẵy���l�[���́u�����S�O�i��ڗ����j�v�u�����R�l�i�Y�썆�j�v�ƂȂ��Ȃ��V�����Ă���B35�̎��ɏ������w����u�(�˂Ȃ�����)�x�w�����u�����`�x�͍]�˂̃x�X�g�Z���[�ƂȂ�A�������܂ŏd�ł��J��Ԃ����B��҂͎�l�����A���l�̍��A���l�̍��A���r���A���㍑�A�������܍��ȂǗ�������̂ŁA�]�˔ŃK���o�[���s�L�Ƃ������������B�i�������ł�����A�����������2�N�O�ɉp���Ŋ��s���ꂽ����̃K���o�[���s�L��ǂ�ł����Ƃ͎v���Ȃ��B�j�w�����i�ق��Ёj�_�x�ł͂܂��u���ɎO������B�u�c�Ɩ���̏�i�ɂ��Ă��̌`�~(�܂�)���A�u�E�Ɩ���̒��i�ɂ��Ă��̌`���тȂ�A�X�[�Ƃ��������̉��i�ɂčג����v�ƛ��̌`�Ԃ�_������A�����]�˂Ɏ��݂������̋Ȍ|�t�i�O�����̔��t��{�̖�����t�ł��j�����������ɏo���u�Í������A���̂悤�Ȃ��Ƃ��v�����A�H�v�����l�͒N�����Ȃ��v�Ə̎^���A����ɔ��Ύ��}�C���Ɂu�킵�͑吨�̐l�Ԃ̒m�炴�邱�Ƃ��H�v���A�G���L�e�������߁A���܂œ��{�ɂȂ������̎Y���������B��������Đl�͎����R�t�ƌ������B���v���ɁA����܂��ċ�J���Ĕ���A�����čD�ӂ�s�����đ�������B�c�������G���L�e�����փ��L�e���Ɩ���ς��A����������j�̒�q�ɂȂ낤�v�ƌ���Ă���B���Ȃ݂Ɂu�y�p�̉N�̓��͂��Ȃ���H�ׂ�ƌ��C�ɂȂ�v�́A���ĉ��̒m�l�ɗ��܂�Č������l�����R�s�[�ŁA����܂ʼnĂɃE�i�M��H�ׂ�K���͂Ȃ������B
�����ʂɂ킽��˔\���������A�L�����m��������ē����̎Љ�Ɏ����ꂸ�A�₪�Ĕގ��g�����Ԃɑ��ė�ΓI�ȑԓx�����n�߂�B����ł͕����Љ���������낷��i�\���A���{�s���̗l�X�Ȗ�����ɗ�ɖ\�I�����B
�ӔN�i1778�N�j�A50�ɂȂ��������͎�����F�߂Ă���ʐ��ɕ��S���A�G���L�e���̍������g�p�l�̐E�l�ɉ���肳�ꂽ���Ƃ������Đl�ԕs�M�A��Q�ϑz���g�債�ߌ����N����B�����K�ꂽ��H�̓���2�l�Ǝ������ݖ����������̂��ƁB�������钆�ɖڊo�߂ĕ֏��֍s�����Ƃ���ƁA���ɓ���Ă��������̑�Ȍ��z�v�}�i�c���ӎ��̕ʑ��j���Ȃ��B�Ƃ����Ɂg���܂ꂽ�I�h�Ǝv�����ނ͑�H�����ɋl�ߊ��A�����ⓚ�̖��Ɍ������A����2�l���a��E���Ă��܂��B�������̐}�ʂ́A�����̉��ł͂Ȃ��A�т̊Ԃ���o�Ă����̂ł������c�B�������������́A�����̏��`�n���̘S���Ŕj�����ɂ������č��������i���N51�j�B
�����̕�W�����Ă��̂́A�ނƓ��l�ɍD��S��������������̐e�F�A���c�����B�����́u�������̐l�B���̂��Ƃ��D�ށB�s�Ȃ�������Ȃ�A�Ȃ��Ɏ������v�ƌ����̕�W�ɍ��B��͊p����Ŋ}�t�A��i�p�Ɂu���i���Ȉ�\�\���� �q����Y���m ���ꌹ����v�ƒ����Ă���B 1928�N�ɕ���Ǘ����Ă��������ړ]�������A��͂��̂܂c���ꂽ�B�R�N���1931�N�i���a�U�N�j�A�������˓���E�������悪�z�n���i�����ׂ��A�y�ǁj�����A1943�N�ɍ��w��j�ՂƂȂ����B ��́g�������̃W���[�h�̒O���W���ŗL���ȟ����̋߂��ɂ���B�ނ������C�^���A�ɐ���Ă����Ȃ�A�ԈႢ�Ȃ����l�T���X�̋��l�Ƃ��Đl�ނ̗��j�ɖ�������ł������낤�B��O�Ŗ������F�����B
|
 |
| �����̕�̔w��ɂ͒�q�E�����������Ă���A�u���ꌹ���Ɨ��v�ƍ��܂�Ă��� |
���G�W�\��/Thomas Edison 1847.2.11-1931.10.18 �iUSA�A�j���[�W���[�W�[ 84�j2003 ������
Edison National Historic Site, West Orange, Essex County, New Jersey, USA
�u���͎��s�͂��Ă��Ȃ��B����ł͂��܂������Ȃ��Ƃ����������P�����̂��v�i�G�W�\���j
 |
|
| 2000�N7���B�G�W�\���������Ղ͉��C���ŁA�ނ������Ă��� ���@�ւ̌��w�c�A�[�͂Ȃ������B���������j���[�W���[�W�[ �܂ŗ����̂Ɂc�g�z�z�B���C�͂��ƂR�T�ԂŏI�������� |
������2003�N8���Ƀ��x���W�B�M���[�I�Ȃ�ƍĂщ��C�� �����Ă����I���̊J�ق�2�N��Ƃ̂��ƁB��ȃA�z�ȁI ���{�f�B���C���̂������Q���̐[����\���Ă���I |
 |
 |
 |
| ���̏����ɂ����q����Ɂu��ڂ����ł� ��Q�����ė~�����v�Ɨ܂̒��i�B�R�N�O�̎ʐ^�� �����A�ĖK�ł��邱�Ƃ�`����ƁA�G�W�\���@ �̕��p�������Ă��ꂽ�i�l�ɂ͌����A���j |
���̕��p�ւǂ�ǂ�s���ƁA�Q�[�g���s�����j �B���̐�͍����Z��X�ʼn��X�̎҂͎��R �ɓ��邱�Ƃ͏o���Ȃ������B�ӂ������Ė�� �����֓ˌ��I��͂�R�N�O�̎ʐ^�������āI |
�u�����ɋA���Ă��邩��v�Ɩi���܂���ƁA �u���������B�s���ė����I���o���ĉE���� �����Ă���I�����W�̉Ƃ��I�v�B�����B �F����A���ꂪ�G�W�\���@�����I |
 �@ �@ |
| ���@�̗���ɃG�W�\���v�Ȃ͖����Ă����I�����g�[�}�X�B��A���ɃG�W�\���Ɖy������I�d���A�~���@�A �f��i���t���j�A�A���J���d�r�ȂǁA�����ɑ��邨���`�����B��̍��E�ɂ͓�{�̐Γ��U������B����� �d���̃t�B�������g�ɓ��{�̒|���d�����Ƃ��琶�܂ꂽ�Ȃ��肩�炫�Ă���B�����̔ߊ萬�A�������I |
 �@ �@ |
| �u�ʐ^�͎B�ꂽ�����H�v�Ɩ�Ԃ���B�悭�˔j�����Ă��ꂽ�I���Ȃ��͐_�ł��I�I |
| �A�����J�̐��E�I�����Ƃɂ��ċN�ƉƁB�������Ƃ������U�̔����i��1300���u�������v�ƌĂ��B�~���@�A���M�d���A�A���J���~�d�r�A���d�V�X�e���A�f��Ȃǂ��܂��͉��ǂ��Đl�X�̐�������ς������B 1847�N2��11���A�I�n�C�I�B���܂�B�n�����ޖ؏����������̂V�l�Z��̖����q�B�V�̎��Ƀ~�V�K���B�֓]�������w�Z�ɒʂ������A�u�Ȃ��P+�P�͂Q�Ȃ̂��B�Q�̔S�y�����킹����P�ɂȂ�̂Ɂv�ȂǑS�Ă̋ǖʂŁu�Ȃ��H�v��A�����A�S�C����́u���������Ă���v�A�Z������́u�ފw�����߂܂��v�ƌ����A�������R�J���ŏ��w�Z�𒆑ނ����B�ȍ~�͕�e�����炵�A�}���قœƊw�ɗ�B10���牻�w�����ɖ����ɂȂ�A��i���ׂɖ�ؔ���̃o�C�g���n�߂�B���̎����Œn�����ɉ��w��������������B12�ɂȂ�Ƃ���ɖ�i���~�����Ȃ�A��Ԃɏ�荞�ސV�����q�ƂȂ����B���U���ɉƂ��o�Ė�10���ɋA��Ƃ��������Ŏ������Ԃ��m�ۂł��Ȃ��ׁA��Ԃ̎�ו����ɖ�i���������ݎ������s�����B1861�N�i14�j�A��k�푈���u�����A�V������Ԃ悤�ɔ���A�萻�̃��[�J���V��������Ȃǂ������A��Ԃ̎��������Ύ��ɂȂ�N�r�ɂȂ����B 15�̎��ɉw���̎q�ǂ���瀎����O�ŋ~�o���A���Ƃ��ēd�M�i�d��j�Z�p�������A���ꂪ�����ɖ𗧂��Ă����B1863�N�i16�j�A�d�M�Z�t�ƂȂ�Ƃ��o�āA�t�@���f�[�̑S�W���w�����d���C�w�����������B17�A�ŏ��̔����i�w�d�M�������u�x�𐧍�B���̋@�B�́A�J�i�_�ʼnw�̖�Γd�M�W�����Ă����G�W�\�����d�����T�{�邽�߂ɍ�����B�[����Ζ��ɏA���Ă���؋��Ƃ��ĂP���Ԃ����ɏ�i�M���𑗂�˂Ȃ�Ȃ��������A�G�W�\���͋@�B�Ŏ����I�ɓd�M�𑗂点�ďn�����Ă����B��i�͂P�b���덷�Ȃ�1���Ԃ����ɓd�M���͂����Ƃ�s�v�c�Ɏv���A�G�W�\����K�˂Ė����Ă���̂����u�莞�A���̈Ӗ����Ȃ��I�v�ƌ��{���ނ����ق����B���̌�G�W�\���̓j���[�I�����Y�܂œ암����Q�B 1868�N�i21�j�A�X�C�b�`�ɂ�铊�[�V�X�e���w�d�C���[�L�^�@�x���{�X�g���Ŕ��������߂āg�����h���擾�B�Ƃ��낪�c������́u������p���ł��Ȃ��v�ƍ̗p���ꂸ�A���T�[�`�̏d�v�����w�B���N�ANY�ɓ]�����w��������\���@�x���B����͑�D�]�ŁA���������G�W�\���̗\�z���W�{������S���h���i���݂̖�Q���~�j�Ŕ���V�����B1871�N�i24�j�A16�̏��胁�A���[�ƌ������R�l�̎q����������B�����̔��p�v�������Ƃ��āA1876�N�i29�j�ɔ����H�ꁁ�������p�[�N���������j���[�W���[�W�[�B�ɐݗ��B1�̉���ŕ����̐M�����ɑ��M����Z�p������ȂǁA�������̕����Ǝ������d�˂Ė�p�����ɔ����i�ݏo���Ă������B 1877�N�i30�j�A�~���Ղɉ����L�^�����w�~���@�x�����p���B�G�W�\���͓��w�wMary had a little lamb�i�����[����̗r�j�x���ŏ��ɘ^�������B����@�B�E�~���@�͐l�X�����������A�哝�̂܂ł������������A�G�W�\���͎Ќ��E�̉Ԍ`�ƂȂ����B���N�A�O�N�ɃO���n���E�x�������������d�b�@�i�ߋ�����p�j�����ǂ��ăJ�[�{���d�b���b����A�܂��U���R�C���ɂ���đ��b������L���d�b���p���̓����Ђ炢���B 1879�N�i32�j�A�O�N�ɉp���̉Ȋw�҃W���[�t�E�X�������������Ƃ������M�d���͂������P����������Ȃ����t�B�������g�̎������Z���Ƃ������_���������B�����ŃG�W�\���̓X�����̂悤�Ȏ���Y���������t�B�������g�ł͂Ȃ��A�ʂ̑f�ނ��t�B�������g�Ɏg�����Ƃɂ����B�l�X�ȑf�ނ����������ɁA�����Y�̒|��200���Ԃ����������Ƃɋ����A����Ɋe�n�̒|�Ŏ�����i�߂����ʁA���s�E�ΐ��������{�̋����ɐ����Ă���^�|�i�܂����j���u1200���ԁv�Ƃ������ٓI�ȑϋv�͂������Ƃ����A�d���̎��p���ɐ��������i�|�͌�Ƀ^���O�X�e���Ɏ���đ�����j�B ���N�A���d�@�����ǁB1882�N�i35�j�A�j���[���[�N�ɐ��E���̑�K�͔��d����ݒu���A���d���瑗�d�܂Œ����ɂ��g�d���̎��Ɖ��h�ɐ��������i��N�A�G�W�\���̒������d�@�͌������̔����ƃe�X�����E�F�X�e�B���O�n�E�X�̌𗬔��d�@�ɒn�ʂ�D��ꂽ�j�B 1883�N�A�M�����t�B�������g�̋߂��ɋ������������Ɠd���������g�G�W�\�����ʁh���B����͌㐢�ɐ^��NJJ���̊�b�ƂȂ����B1884�N�A���A���[�v�l���a�v�i���N29�j�B�Q�N��Ƀ}�C�i�v�l�ƍč����A�j���[�W���[�W�[�B�E�F�X�g�I�����W�Ƀ��B�N�g���A����23�����̑卋�@�gGlenmont�i�O���������g�j�h���w���B���̍ہA�j�Y���Ă��Ƒ��ɉƂ��c��悤�v�l���`�ʼnƂ��������B�ނ͍ĂтR�l�̎q�Ɍb�܂��i�P�l�̓j���[�W���[�W�[�B�m���ɂȂ��Ă���j�B 1887�N�i40�j�A�E�F�X�g�I�����W�ɋ��匤���������݁B�Ő����̃X�^�b�t�͂P���l�ɒB�������̃v���W�F�N�g�������ɐi�s�����B1889�N�̃p������������ł̓A�����J�ق̂R���̂P���G�W�\���̔����i�Ŗ��܂����B 1891�N�i44�j�A�����̊G��A�������ē���ɂ���w�̂����ዾ���f�ʋ@�L�l�g�X�R�[�v�x���A�Q�N��i1893�N�j�ɃL�l�g�X�R�[�v�ʼnf�������f�����B���X�N�A���̃L�l�g�X�R�[�v�Ɏh�����ꂽ�t�����X�̃����~�G�[���Z�킪�B�e���f�ʋ@�V�l�}�g�O���t�������i�G�W�\���̃L�l�g�X�R�[�v�͔`�������ł��������A�V�l�}�g�O���t�̓X�N���[�������j�B1900�N�i53�j�ɃA���J���~�d�r���B 1910�N�i63�j�A�g�[�X�^�[���A�����œd�C�A�C�����ȂǓd�C���i�����A�d�C���ƒ�ɕ��y���Ă������B1913�N�i66�j�A�~���@�ƃL�l�g�X�R�[�v�����̂����A���E���̉����ł銈���ʐ^�𐧍�B�R�_�b�N�Ђ̑n�n�҃C�[�X�g�}���Ƌ��͂��ăZ�����C�h���̒��ڃt�B�����A35mm�t�B�������J�����A���E�ŏ��̉f��X�^�W�I���J�݂����B 1914�N�i67�j�Ɍ��������Ύ��őS�Ă���200���h���̑����ƂȂ������A�u����Ŗ��ʂȕ��͂�������Ȃ��Ȃ����B���ꂩ��܂��V���ȋC�����ŐV���Ȍ������n�߂���v�ƃ^�t�����������B�ӔN�͎��҂Ƃ̌�M�̎����𑱂��A�~��p���M���Ă����i�l�Ԃ̍����G�l���M�[�ł���Ȃ�G�l���M�[�ۑ��̖@���ō��͎�������݂���ƍl�����j�B1931�N10��18���A�E�F�X�g�I�����W�Ő��U���I����B���N84�B�ՏI�̌��t�́u�����A�������͂��ꂢ���c�v�B�R����ɑ��V���Â���A�G�W�\���̌��т��]���Ď������ߑS�ĂŌߌ�10������1���ԓd���������ꂽ�B ���E��24�N��A1955�N�Ɏ���ƌ��������G�W�\���������j�قƂȂ����B���݁A�G�W�\�����₵��500�����ȏ�̃�����L�^�������Ƃ��������Ă���B �G�W�\���́u�Q��̂̓o�J���B�݂�ȐQ�������B���͎����Ƃ����Ղ薰��v�Ƃ������t�ɏے������悤�ɁA��O���̃o�C�^���e�B�[�Œ���W�Ȃ��s���s�x�̌��������𑗂����B�����͖�30���̉�����1������A�v�R���Ԃ̂݁B80��ɂȂ��Ă�1��16���Ԃ̃y�[�X�Ō������A�u�܂�15�N�ȏ�͓����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƌ���Ă����B�Ȃ�Ƃ������x�Ȑ��_�́B���x�����Ɏ��s���Ă��u���s�ł͂Ȃ��B���̕��@�ł͏�肭�����Ȃ��Ƃ����������o�����B�����炱�̎����͐����Ȃv�u����ł͏�肭�����Ȃ��Ƃ����������P�����̂��v�ƌ��������A�����ԗp�̃A���J���~�d�r�Ɏ����Ă͊����܂łɂT����ȏ���������J��Ԃ����B�G�W�\����10��̍����璮�͂ɏ�Q�����������A�u����̎G���ɔY�܂��ꂸ�����ɏW���ł��邩��A�������čD�s���v�Ƌ�ɂ��Ȃ������B�u�V�˂Ƃ͂P�p�[�Z���g�̂Ђ�߂���99�p�[�Z���g�̓w�͂ł���v�i�G�W�\���j�B ���t�����X���{���烌�W�I���E�h�k�[���M�͂��A��p�鍑�Z�p�����A���o�[�g�M�͂��Ă���B �������j�Ƃ��āA�W�����W���E�����G�X�́w�����E���s�x�����J�O�ɖ��f�ŕ������A�����J���̉f��قɔ�������z�̕x�Ă���B���̈���ŁA�����̌�������邽�ߑ����̑i�ׂ��N�����u�i���v�ƌĂꂽ�B�d�C�֎q�ɂ�鎀�Y�̕��@���j���[���[�N�s�ɒ�Ă����̂��G�W�\���B�q�ǂ�����ɂ́u�Ȃ����͔R����̂��v��m�邽�߂ɘm��R�₵�A����̔[����S�Ă����Ă���B�z�R���Ƃł͎��s���A�呹�Q�����B ���G�W�\�����~���@������20�N��Ƀx�����i�[���~�Տ�̃��R�[�h���B ���K�\���������Ԃ������g�����ԉ��h�w�����[�E�t�H�[�h�́A���ăG�W�\���d����Ђ̎Ј��������B ���G�W�\�������M�d���̉��ǂɎg�p�����|�̎Y�n�����s�̐ΐ��������{�����A�����ēd�C�̎��_�E�d�d�{�����鋞�s���R�̖@�֎��ɋL�O�肪���B�Ȗ،��p�����̃o���_�C�~���[�W�A���ɂ̓G�W�\���̔����i����������Ă���B �y�揄��z �G�W�\���̕�Q�ɂ͑�ϋ�J�����B�ŏ��̏����2000�N�̉āB�G�W�\���̕揊�͎��@�g�O���������g�h�̕~�n�ɂ��邽�ߎ��R�ɕ�Q���邱�Ƃ��o�����A600m�قǓ��ɂ���j�Ձw�G�W�\���������Ձx�̃r�W�^�[�E�Z���^�[�Ō��w�c�A�[�g�O���������g�E�c�A�[�h�ɎQ������K�v������B�w�G�W�\���������Ձx��K��ďՌ������B���������C���ŕ�Q�c�A�[���Ȃ������I���������j���[�W���[�W�[�܂ŗ����̂Ɂc�B��q����Ɂu���C�͂��ƂR�T�ԂŏI��邩�炻�̍��ɗ����v�ƌ���ꂽ���ǁA�l�̋A���ւ͂Q�T�Ԍゾ�����B ���ꂩ��R�N�ԁA�G�W�\���ɍď��炷�邽�߂̏�����i�߁A2003�N�W���ɍĂуj���[�W���[�W�[�B�֑����^�B�g���x������Q�c�A�[�ɎQ�����邼�h�ƈӋC���݁w�G�W�\���������Ձx�ɒ����ƁA�l�̋C�z���Ȃ��B���ȗ\���������B�M���[�X�I�w�G�W�\���������Ձx�͈�x�J�ق�����A�Ăщ��C�ɓ����Ă����I��q���킭�u���̊J�ق͂Q�N�ゾ��v�B��ȃA�z�ȃb�I�g�n�C�A�����ł����h�ƈ����������킯���Ȃ��B���́A�����������Ƃ����낤���ƂR�N�O�Ƀ^�C�}�[�B�e�����u���C���̌����̑O�ŋ������Ă���p�v�̎ʐ^�����Q���Ă����B�������q����Ɍ����āg���{���炱���܂ŗ���̂��ǂꂾ����ς��h�g�����ɃG�W�\���h���Ă��邩�h��M�ق��A�u��ڂ����ł���Q�����ė~�����v�ƐH�����������B ��q����͂R�N�O�Ɠ������N�̍��l�j���B�ŏ��͂����Ɓu�\�[���[�v�u�C���|�b�V�u���v��A�����Ă������ǁA�Ō�ɍ����������̂��A�G�W�\���@�́g���p�h�����������Ă��ꂽ�i��������������̂͂����܂ł��A�Ƃ��j�B�����Ă�����������i����1km�j�ɂǂ�ǂ�����ƁA�S�̃Q�[�g���s�����j�B���̊X�i�E�G�X�g�E�I�����W�j�͎����������A�������͈ꃖ���ɏW�܂��āg��ǁh�̒��ŕ�炵�Ă����̂��I��قǂ̎�q����́A���̃Q�[�g�����邩��u�C���|�b�V�u���v�ƁA�G�W�\���@�ɂ͍s���ʂƌ����Ă����̂��B �Q�[�g�̖�ԏ����ɔ��l�j���������B�u���[���A�s�������Ȃ��I�v�B�ӂ������Ė�ԏ����ɓˌ��I�g�����オ�Ȃ����I�h�l�̓V�F�C�N�X�s�A�o�D��ɁA�܂𗭂ߐ���k�킹�A�Ɍ��܂ŃI�[�o�[�ȉ��Z�Ŗ�Ԃ���Ɂu�����ɋA���Ă��邩��v�Ɩi���܂������I�����Ă����ł��R�N�O�̎ʐ^���З͂����B�u�Q�x�ڂ��c���������B�s���ė����I���o���ĉE���Ɍ����Ă���I�����W�̉Ƃ��I������30���������B����܂Ŏ��͓d�b�ŋC�Â��Ȃ��B�����ɉו��͒u���Ă����v�B�������Ėl�͕�O�ɂ��ǂ蒅�����B�G�W�\���v�Ȃ̕�͗����ɓ��{�̐Γ��Ă������Ă����B�d���̃t�B�������g�ɓ��{�̒|���d�����Ƃ������āA�d���ɂ��Ȃ�œ��U�����{�̃G�W�\���E�t�@�����瑡��ꂽ�Ƃ����B�ǂ��b����Ȃ����B |
���O�[�e���x���N/Johannes Gutenberg 1398-1468.2.3 �i�h�C�c�A�}�C���c 70�j2005 ���ň���Ǝ�
Franciscan Church (no longer in existence), Mainz, Germany
 |
 |
 |
| �E�M���[�I�X�b�|���ƕ����Ă��� | ���̃v���[�g | �O�[�e���x���N�� |
�悪�������Ƃ����ꏊ�ɂ͑�w�������Ă���A�ǖʂɂ��̎|�����v���[�g������c�͂��Ȃ��ǁA���������I
��w�����C������Ȃ����I�������y���L��h��ׂȂ̂��A�̐S�̃v���[�g�Ƀr�j�[�����������Ă�I�E�G�[���A�����Ȃ��I
�������߂��ɃO�[�e���x���N�����ق���B

������̓t�����X�E�X�g���X�u�[���ɂ���O�[�e���x���O���B�h�C�c�����ɋ߂����̊X�́A�h�C�c�̂������������������B
�������~�G�[���Z�� �f��̕�
�I�[�M���X�g�E�����~�G�[��/Auguste Lumiere 1862.10.19-1954.4.10 �i�t�����X�A������ 91�j2005
���C�E�����~�G�[��/Louis Lumiere 1864.10.5-1948.6.6 �i�t�����X�A������ 83�j2005
Cimetiere de la Guillotiere, Lyon, France
 �@
�@
| ���E���̉f��w�D�Ԃ̓����x��1895�N�Ƀ����~�G�[���Z�킪�p���Ŕ��\������i�B�ނ�̓p���̃J�t�F�Ɏ��琻�삵���f�ʋ@���������݁A35�l�̊ϋq��1�t�����i���̐�~�j�ŏ�f�����B�����~�G�[���Ƃ͊X�̖��m�i���ƉƁj�B�ꑰ�̕�̈�ԉE�[�ɌZ��̖����������B���̃����~�G�[���͕���Łu���v�̈ӁB���R�Ƃ͂����f���2�l�ɂӂ��킵�����O���ˁB �����̌�f��Y�Ƃ͔��W���A���݂̑S���E�̉f�拻�s�����͖�258���h���A����3���~�ɂ��̂ڂ�B���{�ł͔N��400�{�����삳��Ă���B |
�����[���X/Samuel Morse 1791.4.27-1872.4.2 �iUSA�A�j���[���[�N�B 80�j2009
Green-Wood Cemetery, Brooklyn, NY, USA�@Plot: Section 25/32, Lot 57161-69
 |
 |
| ���[���X�M�����I | �l�ԂƂ̔�r�ō����͂U�����炢�H |
���E�B���o�[�E���C�g/Wilbur Wright 1867.4.16-1912.5.30 �iUSA�A�I�n�C�I�B 45�j2009
���I�[���B���E���C�g/Orville Wright 1871.8.19-1948.1.30 �iUSA�A�I�n�C�I�B
76�j2009
Woodland Cemetery and Arboretum, Dayton, Montgomery County, Ohio, USA�@
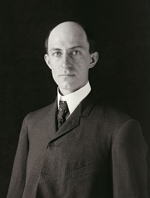 |
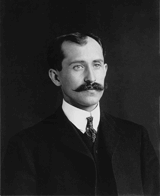 |
| �Z�̃E�B���o�[ | ��̃I�[���B�� |
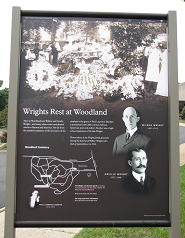 |
 |
 |
| �Z��̕�}�b�v����̑��ɂ��� | �X�~�\�j�A���iD.C.�j�̃��C�g�E�t���C���[�� | ���͂��Ώ�̂Ƃ��Ă����h�ȃ��C�g�Ƃ̕�I |
 |
 |
 |
 |
| �Z�M�̃E�B���o�[�B45�ŕa�� | ��n�̒����t�߂ɖ����Ă��� | ���C�g�� | ��̃I�[���B�� |
| �A�����J�̔�s�@�J���ҁB�E�B���o�[�ƒ�̃I�[���B���̓O���C�_�[���̎������d�˂��狦�͂��ĕ��t�@���������A1903�N�A�l�ލŏ��̃K�\�����@�ւ��g�������͔�s�ɐ��������B �l�ނ̔�s�ւ̒���͒���^���邱�Ƃ���n�܂������A�t�����X�̃����S���t�B�G�Z�킪�u�M�C���v������Ƃ����v�����N�������B1783�N10��15���ɒ�G�e�B�G���k�E�����S���t�B�G�����[�v�ɌW�����ꂽ��ԂŎj�㏉�߂ċC���ɏ�����ƌ����Ă���B���N11��21���A�W�����Ă��Ȃ��M�C���ɂ��j�㏉�̗L�l��s���s���A�Ȋw�҃s���[�g���E�h�E���W�F�ƁA�R�l�̃t�����\���E�_�������h��݂����悵�A�p�����̍��x��900m��25���Ԃɂ킽���ĂXkm��s�����B��s���I�������A����҂̓V�����p���Ő������j���A����͋C�����̓`���ƂȂ����B�Q�N���1785�N6��15���A�s���[�g���E�h�E���W�F�͎��g���l�Ă������W�F�C���ŃC�M���X�C�������f���悤�Ƃ��ċC���Ɉ����A�唚���Ƌ��ɍ��x400m���痎���A�j�㏉�̍q�̋]���҂ƂȂ����B 1849�N�ɍŏ��̍q��H�w�ҁA�g�q��w�̕��h�W���[�W�E�P�C���[�iSir George Cayley,1773�N12��27��-1857�N12��15���j���O�t�̗L�l�O���C�_�[�삵�A10�̏��N���悹�Ă̊���ɐ��������B�P�C���[��1853�N�ɒP�t�̗L�l�O���C�_�[�삵�A�P�C���[�̌�ҁi���l�j���j�̑��c��100m�ȏ�̔�s�ɐ��������B 1891�N�A�h�C�c�̃I�b�g�[�E�����G���^�[���iOtto Lilienthal �A1848�N5��23��-1896�N8��10���j���W���[�W�E�P�C���[�̃O���C�_�[�����ǂ����n���O�O���C�_�[�u�_�[�E�B�b�c�@�[�E�O���C�_�[�v�������25m�̔�s���s���B1893�N�ɍō��L�^�ƂȂ�250m�̔�s������B�����A���N�ɖ_�������đ��c����n���O�O���C�_�[�̓������擾���Ă���B2,000��ȏ�̔�s���s���A����s���ԂT���ԂɒB���������G���^�[���ł��������A1896�N�W���A�O���C�_�[�Ŗ�15m�̍�������ė��������ɑ��E�����B���N48�B�Ŋ��̌��t�́u�]���͕����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B�������̌�����n�ɖ��������B 1899�N�A�C�M���X�̃p�[�V�[�E�s���`���[�iPercy Sinclair Pilcher �A1866�N1��-1899�N10��2���j���S�n�͂̎O�t�@����邪������s�̐����O�ɃG���W�����̏�B��s�����ɏC�����Ԃɍ��킸�A�W�܂����ϋq�����]�����Ȃ��悤����ɃO���C�_�[�Ŕ�s���ė�����B���N33�B���E���̗L�l���͔�s�̐����҂ɂȂ�����������Ȃ��l���B �|�| �E�B���o�[�E���C�g��1867�N4��16���ɃC���f�B�A�i�B�~���r���ɂďo���B���͖q�t�B������A�S�ΔN���̒�I�[���B���ƈ�������c�ݐ�������B���̌�A1892�N�i25�j�Ɏ��]�ԏC���H��������A�h�C�c�̍q��Z�p�҃I�b�g�[�E�����G���^�[���ɉe�����ꋻ���͔�s�@�ֈڂ����B1896�N�A�����G���^�[�����x�������Œė�������B 1900�N�i33�j�A�Z��̓m�[�X�J�����C�i�B�L�e�B�z�[�N�̃L���f�r���̍��u�Ŏ���O���C�_�[���e�X�g��s�B���̃f�[�^����ɉ��x�����ʂ̋C���̉e���ׁA�O���C�_�[�̊��������1000����s�����B ������1903�N�A�Z��͏]������35%�������̂悢�v���y���𐧍삵�A12�n�͂̃G���W�����̂���337kg�A6.6m�̋@�́g���C�g�t���C���[���h�������������B�Q�̃v���y���𓋍ځA�嗃���˂��邱�ƂŐ��䂳�ꂽ��s���\�ɂ��A��s�@�̎��p���ɓ����J���B ���N12��17���ߑO10��35���A�A�L���f�r���̍��u�ɂĎj�㏉�߂ē��͕t����s�@��120�t�B�[�g�i��36.5m�j�A12�b�Ԕ�Ԃ��Ƃɐ��������B�Ƃ��ɃE�B���o�[36�A�I�[���B��32�B���̓��̂S��ڂ̃t���C�g�ł�59�b�ԁA852�t�B�[�g�i��259.6m�j��Ԃ��Ƃɐ������Ă���B���c������I�[���B���E���C�g�͐��E���̔�s�@�p�C���b�g�ƂȂ����B�������A�ϋq���T�l�Ƃ������Ƃ�����A���Ԃ͂��̉������^���A�V���Ɂu�Ȋw�I�ɕs�\�v�Ə������ȂǁA�Ȃ��Ȃ��M���Ă��炦�Ȃ������B ��1904�N�ɂ�1km���z�����s���������A1905�N�ɂ�30km�̔�s�𐬂��������B 1908�N�X��12���A�I�[���B���i����37�j�͂P����15��20�b�Ƃ����P���ԑ�̔�s���Ԃ����߂ċL�^���A��75km���B�����T����̂X��17���A�I�[���B���̓��C�g�t���C���[�̃f���t���C�g���ɍ��x25m����ė����A���E�ŏ��߂Ĕ�s�@���̂��N�������l���ƂȂ�B�I�[���B���͕����ōς��A����҂̃g�[�}�X�E�Z���t���b�W���R���сi26�j�����S���A���̔�s�@���̋]���҂ƂȂ����B ����ɂS����̂X��21���A�Z�E�B���o�[�̓t�����X�̃��E�}���ߍx�̃I���[���̉��K�n�łP����31��25�b�Ƃ����t���C�g�̐��E�V�L�^��@���o�����B�ŏI�I�ɃE�B���o�[�͔N��12��31���ɑ؋ԂQ����20���A��s����125km�܂Ŏ��g�̋L�^���X�V�����B 1909�N�A�E�B���o�[�͐V��ЃA�����J���E���C�g�E�J���p�j�[�i��̃��b�L�[�h�E�}�[�e�B�����ŐV�s�X�e���X�퓬�@F-22��F-35���J���E�����j�̎В��ƂȂ�B�X���A�t�����X�ɍ��ꂽ���C�g�Z��̉�Ђ̃`�[�t�E�p�C���b�g�A�E�W�F�[�k�E���t�F�[�u���iEugene Lefebvre �A1878�N-1909�N9��7���j���e�X�g��s���ɂUm�̍�������ė��A��s�@���̂Ŏ��S�����ŏ��̃p�C���b�g�ƂȂ����B 1911�N�A�I�[���B���i40�j�̓O���C�_�[�ő؋ԂX��45�b�Ƃ������E�L�^������Ă���B 1912�N�T��30���A����s����X�N��A�E�B���o�[�͒��`�t�X�M�ŕa�v�����B���N45�B�I�[���B���͂��̌�����炭��s�@�����Ɋւ���Ă������A�Q�N��ɑ�ꎟ���E��킪�u�����A�킢���D�������Ă���1916�N�A�I�[���B���͔�s�@��������g���������B 1928�N�ɂȂ��Ă��A�����J�ł̓��C�g�Z��Ɏ��i��������������A�}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�̑q�ɂɖ�����Ă������C�g�t���C���[���������h���̉Ȋw�����ق�����������B 1942�N�A����E���̑����A�I�[���B���͋�P�ŊX���j��A�����̐l�����D���Ă��邱�Ƃɋ���ɂ߁A�����ԉ��w�����[�E�t�H�[�h�ɓ��͔�s�@���������Ƃ���������e�̎莆�𑗂����B ���N�A�X�~�\�j�A������͂悤�₭���C�g�Z��̈̋Ƃ�F�߁A������Z��ɒӂ����B�I�[���B���͂��̎Ӎ߂�����A���C�g�t���C���[�����A�����J�ɖ߂����Ƃɍ��ӂ����B �Z�̎�����36�N���1948�N1��30���A�I�[���B���̓I�n�C�I�B�f�C�g���ɂĐS������ő��E�����B���N76�B���V�ł̓A�����J��R���S�@�̐퓬�@�ŏ���Ǔ���s�����B ���N���A����s���炿�傤��45�N�ڂ� �Ȃ�12��17���A���V���g�����������قɃ��C�g�t���C���[�����W������ ����ȓW�����������s��ꂽ�B 1978�N�A�I���W�i���ʂ�̕����@���A�����J�l�̐N���R�N������Ő��삵�A�L�e�B�z�[�N��24m�̔�s�ɐ��������B ���Z��́u���[�Ɣ�s�@�𗼕��Ƃ��{���͖̂��d�Ȏ��݂��v�ƌ����Đ��U�Ɛg�������B ���Z��ƕ���ŏ����̖��O�̕�肪����B�Z��͓Ɛg�䂦�A�v�l�ł͂Ȃ����L���T�����B ������s�ɐ��������ꏊ�́u���C�g�Z�퍑���L�O���v�Ƃ��č��������ǂ��Ǘ��B ���h�C�c�o�g�̃A�����J�̍q��Z�t�O�X�^�[���E�z���C�g�w�b�h�iGustave Whitehead�A1874�N1��1��-1927�N10��10���j�����C�g�Z�킪����s����1903�N12��17�������Q�N�S�J�����O��1901�N8��14���ɃR�l�e�B�J�b�g�B�t�F�A�t�B�[���h�Ő��E���̗L�l���͔�s�ɐ��������Ƃ�����������B�����̃j���[���[�N�E�w�����h���ȂǂR�����u�z���C�g�w�b�h�̓G���W���t���̋@�́g�i���o�[21�h���ɂ����800m�̋��������x15m�Ŕ�s�����v�ƋL���������Ă���B�ʐ^�͂Ȃ����A����ɂ����L�҂����ɕ������@�̂̃C���X�g��`���Ă���B�����A�z���C�g�w�b�h�̓��C�g�Z��̏���s�����ꂽ����24�N�������Ă����̂Ɉ�x�����͔�s���Č����悤�Ƃ��Ȃ������_�A�L���Ɩڌ��҂̏،����������Ă���_�A���؉\�ȏڂ����L�^����x������Ă��Ȃ��_�Ȃǂ���A�X�~�\�j�A������͐��䓮�͔�s�����C�g�Z��ȑO�Ɏ����������Ƃ������ے肵�Ă���B�������A1986�N�Ƀ��v���J�@��A����̌y���G���W���𓋍ڂ����Ƃ����100m��s�����Ƃ����B |
���T�~���G���E�R���g/Samuel Colt 1814.7.19-1862.1.10 �iUSA�A�R�l�`�J�b�g�B 47�j2009
Cedar Hill Cemetery, Hartford, Hartford County, Connecticut, USA
  |
 |
 |
| ����ɖX�q��u���Ă݂��B10���ȏ゠��̂͊m�� | �Ă���̏��_�� | ����Ȕ蕶 |
���{���o�[�����e�̖{�i�I���p���ɐ����B�Õ��Ȃǂ͕ʂƂ��āA�l�̕�ł�����傫�Ȃ��̂��������Ƃ��Ȃ��B�R���g�͈̐l���A
����Ƃ������̕��폤�l���B�l�͂܂����_�ɒB���ĂȂ��B�����A����̏e�̖��O���u�s�[�X���[�J�[�v�Ƃ����Ƃ���ɔނ̗ǐS�����o�������B
���W�����E�n�[���F�C�E�P���b�O/John Harvey Kellogg 1852.2.26-1943.12.14
�iUSA�A�~�V�K���B 91�j2009
Oak Hill Cemetery, Battle Creek, Calhoun County, Michigan, USA
 |
 |
 |
 |
| �傫�ȃP���b�O�Ƃ̕�̑O�Ɍl�悪���� | �W�����E�n�[���F�C�E�P���b�O | �P���b�O�Ƃ͒n���̖��m�� | �P���b�O�̃I�[���h�e�C�X�g |
 |
 |
 |
| ��ŃP���b�O�Џ���В��̃E�B���E�L�[�X�E�P���b�O�͏������ꂽ�ꏊ�ɖ���B |
��Q�̋A��A�P���b�O�Ђ̃��S����C���� �^�ԎԂ����R�O�𑖂��Ă����I |
|
�X�V���B�W�����E�n�[���F�C�E�P���b�O�͒�Ƌ��ɃT�i�g���E���i�ۗ{���j�̕a�l�H�Ƃ��ăR�[���t���[�N�̊J���ɐ����B
��͓�������낤�Ƃ������A�Z�̔ނ͖{���ɍ����Ă���l�����������Ȃ��Ɠ����\���ɔ������B
���W�����ES�E�y���o�[�g��/John Pemberton 1831.7.8-1888.8.16 �iUSA�A�W���[�W�A�B 57�j2009
Linwood Cemetery, Columbus, Muscogee County, Georgia, USA
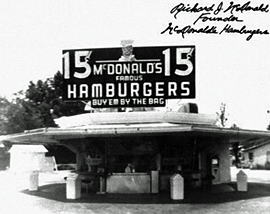
�}�N�h�i���h�Z�킪�n�߂��L�O���ׂ���1���X
 |
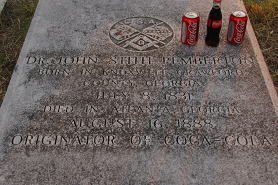 |
 |
| �W���[�W�A�ɒ��ޗ[�z�Ƌ��� | �Ō�̍s�ɁuORIGINATOR OF COCA-COLA�v�Ƃ��� | �R�J�R�[���鍑�̐��݂̐e�͎��f�ȕ悾���� |
�����`���[�h�E�}�N�h�i���h/Richard McDonald 1909.2.16-1998.7.14 �iUSA�A�j���[�n���v�V���[�B
89�j2009
Calvary Cemetery, Manchester, Hillsborough County, New Hampshire, USA / 474
Goffstown Rd Manchester
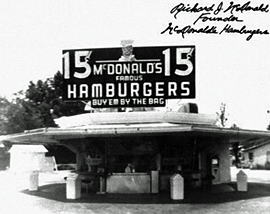
�}�N�h�i���h�Z�킪�n�߂��L�O���ׂ���1���X
 |
 |
 |
 |
| �}�N�h�i���h�n�Ǝ҂͂��̗�_�ɁB�܂����u�����v�� �܂ŌĂ���ƂɂȂ�Ƃ͎v��Ȃ������낤 |
����ɉ��F��M�̕����I�������ł����ɕ������� |
�u���������b�ɂȂ��Ă܂��I�v �ߏ��ŃQ�b�g���ĕ�[�I |
����������Ɉ�ԋ߂��X�B�`�r�b�R�p�� �`���[�u�^�W�����O���W�����[�� |
| ���E�ő�̃t�@�[�X�g�t�[�h�`�F�[����n�n�B�������璲���A�T�[�r�X�܂ŗ����悤�ɍs�����݂̃t�@�[�X�g�t�[�h�����̃V�X�e������}��听�������߂��B
���`���[�h�E�}�N�h�i���h�iRichard/1909�N2��2��-1998�N7��14���j�ƂV�ΔN��̌Z���[���X�E�}�N�h�i���h�iMaurice/1902�N11��26��-1971�N12��11���j�̌Z��́A�j���[�n���v�V���[�B�}���`�F�X�^�[�Ő��܂ꂽ�B�e�̓A�C�������h�n�i�X�R�b�g�����h�n�H�j�ږ��B 1940�N5��15���A���`���[�h�i31�j�A���[���X�i38�j�̌Z��̓J���t�H���j�A�B�T���o�[�i�[�f�B�m�Ƀ}�N�h�i���h��1���X�ƂȂ�A�h���C�u�X���[�`���̏����ȃo�[�x�L���[���X�g�������J�X�����B 8�N���1948�N�A���`���[�h�i39�j�ƃ��[���X�i46�j�͓X�܂�S�ʓI�ɉ������A���j���[��9��ނ̂݁�15�Z���g�̃n���o�[�K�[�A�`�[�Y�o�[�K�[�A�\�t�g�h�����N�A�~���N�A�R�[�q�[�A�|�e�g�`�b�v�X�A�p�C�Ȃǂɍi���ă��j���[�A���E�I�[�v�������B�ނ�͐v���Ɍ����悭���i����邽�߂̒����H����Z���t�T�[�r�X�ɂ��̔��������l�āB������30�b�ŏ��i���o���u�X�s�[�h�E�T�[�r�X�E�V�X�e���v�A�N�ł������i���̃n���o�[�K�[���ł���u�T�[�r�X�̃}�j���A�����v�A�H�ꎮ�̃n���o�[�K�[�������@�ȂǁA�t�@�[�X�g�t�[�h�^�T�[�r�X�̌��^��҂ݏo���A���E�I�ȃn���o�[�K�[�`�F�[���X�̊�b��z�����B ���̃��X�g�����͐������A�Z��́u50�ɂȂ�O��100���h�����҂����v�ƖڕW���f�����B 1952�N�A�Z��̓T���o�[�i�[�f�B�[�m�Ƀn���o�[�K�[���X�g�����̓X�܂�V�z���悤�ƍl���A�l�ڂ����������̊O�ςɂ��邽�߁A���`���[�h�͉��F���u�S�[���f���A�[�`�v���l�Ă��A2�̔��~��X�̗��[�ɒu�����}��`�����B 1953�N�A�A���]�i�B�t�F�j�b�N�X�̃��X�g��������ɁA���̃V�X�e���̃t�����`���C�Y�����J�n�����B���̃t�F�j�b�N�X�̓X�܂ł́A���`���[�h���`�����S�[���f���A�[�`�̔��~���A���z�ƃX�^�����[�E�N���[�N�E���X�g�����������ꂽ�������̃f�U�C���ɂ��A�Ŕ̍H�������l�W���[�W�E�f�N�X�^�[���ŏ��̃A�[�`�삵���B�������ɂ̓f�N�X�^�[�̏������������Ƃ����B 1954�N�A���`���[�h45�A���[���X52�̂Ƃ��ɁA�~���N�V�F�C�N������̃Z�[���X�}���Ŋ�ƉƂ̃��C�E�N���b�N/ Raymond Albert Kroc (1902-1984�����[���X�Ɠ��N)���~�L�T�[�邽�ߗ��X���A�����̋q�����X�Ƃ����V�X�e���A�q�Ȃ̉�]���̍����ɃN���b�N�͖ڂ����������B�N���b�N�͌Z��Ɂu�V�X�e�����t�����`���C�Y�`���ɂ��āA�V�X�e�����̂��̂鏤�����n�߂Ă͂ǂ����v�Ɗ��߂��B�Z��́u���������̂��߂ɂ��̓X������Ă��邾���ŁA�t�����`���C�Y���������͂Ȃ��v�Ə��ɓI���������A�����d�˂����ʁA�u�Z�킪���Y�H���ɂ��ĐӔC���A��Ђ̊����ɂ�闘�v�����B�����ɃN���b�N���̔��g���̑S�ӔC���v�u�}�N�h�i���h�Ƃ������ƃV�X�e���́A�N���b�N�����ƂɎg���v�ƍ��ӂ����B�Z��̓��C�E�N���b�N�ƒ�g������A1961�N�ɃN���b�N�ɔ��������܂Ōo�c�𑱂����B �N���b�N�������t�����`���C�Y���ł́A�t�����`���C�U�[�i�����X�̖{���j�͑������1.9�������A���̂����}�N�h�i���h�Z���0.5������邱�ƂɂȂ����B�N���b�N�̓}�N�h�i���h�荞�ނ��߂ɔM�S�ɓ������B 1955�N3���A�t�����`���C�Y�W�J���邽�߂̐V�������"McDonald's Systems Inc."�i�}�N�h�i���h�V�X�e����Ёj�����A�����ɃN���b�N�����c�X1���X�i�}�N�h�i���h�S�̂ł�9�Ԗځj���V�J�S�x�O�ɃI�[�v���������B�f�����T�[�r�X�A����ꂽ���j���[�A�育��ȉ��i�Ƃ��������́A���̂܂܃t�@�[�X�g�t�[�h�E���X�g�����̒�`�ƂȂ����B�N���b�N�ɂ��t�����`���C�Y�����͍�����������������]���̕����Ƃ͈قȂ�A�������킸��950�h���Ƃ������̂ŁA�H�ޔ[���Ǝ҂���̃��x�[�g���������Ȃ����j�͓X�ܐ��̐L���ɑ傫���v�������B 1960�N�ɂ́A�Ж����u�}�N�h�i���h�R�[�|���[�V�����v�ɕύX�B 1961�N�A���`���[�h�i52�j�ƃ��[���X�i59�j�B�N���b�N�̊g�����͂��ǂ炸�A���[���X�����ނ������Ƃ���A�Z���270���h���Ƃ������z�Ń}�N�h�i���h�̑S�����i�����j���N���b�N�ɔ���n�����Ƃɍ��ӂ����B�N���b�N�͓����҂��炱�̎����������W�߂��B���N�A�uMcDonald's�v�Ƃ������̂ƁuDrive-In Restaurant Services�v�Ƃ������e�̕č����W���o�肵�A��d�A�[�`�̃��S�}�[�N�̏��W���\�������B���E�W�J���J�n����B 1962�N�A���S�́u�S�[���f���E�A�[�`�v�����E���ʂ̃��S�ƂȂ����B1955�N�̃N���b�N�̒��c1���X�͓X�܂̍��E�ɉ��F���A�[�`���������B���`���[�h�͂������物�F���S�[���f���A�[�`�̃��S�̌��Ă��l�����BM�^��"McDonald's"��"M"��͂��Ă���̂ł͂Ȃ��A2�̃A�[�`���d�˂Ė͂������́B 1965�N�A���C�E�N���b�N�͐�����McDonald's Corp.��ݗ��A�������J�B���Ђ͒������@���܂߂��`�F�[���S�X�̌o�c�ꂷ��O�ꂵ�����S�}�j���A�������グ�A���E�e���ւ̓W�J���͂������B���N�A�}�X�R�b�g�Ƃ��ăs�G���̃��i���h�E�}�N�h�i���h���o�ꂷ��B 1968�N�A1000�X�܂�B���B 1970�N�܂ł�2000�X�܂Ɋg��B �P�X�V�P�N�A���{�}�N�h�i���h���A���G�ݏ��̓��c�c(�ł�)�В���ɂ���Đݗ�����A�V���ɋ��4���ڂɑ�1���X���I�[�v���B���c�c�̓s�G���́u���i���h�E�}�N�h�i���h�v�����{�l�ɂ͔������Â炢���߁u�h�i���h�E�}�N�h�i���h�v�Ƃ����B ����������1996�N�ɂ͍���2000�X�܂��A���㍂��2988���~�ɒB�����B2013�N6���ɂ͑S����3265�X�܂ɒB�������A�s�̎Z�X�̐����Ȃǂ�2021�N�͖�2900�X�܂ƂȂ��Ă���B ���N12��11���A���`���[�h62�̂Ƃ��ɁA���[���X���J���t�H���j�A�B�p�[���X�v�����O�X�̎���ŐS�s�S�ɂ��69�ő��E�B�f�U�[�g�E�������A���E�p�[�N�ɖ������ꂽ�B 1973�N�A���H���j���[���B 1975�N�A�h���C�u�E�X���[�X���J�� 1984�N1��14���A�}�N�h�i���h���t�����`���C�Y�W�J���āA���E�ő�̃t�@�X�g�t�[�h�`�F�[���Ɏd���ďグ���l���A���C�E�N���b�N�����A�a�ɂ��81�ő��E�B�ނ͐��E34������8300�X�܂��J���A���U��6���h���̕x��z�����B ���N11��30���A�j���[���[�N�̃O�����h�E�n�C�A�b�g�z�e���ŁA���ă}�N�h�i���h�̐~�[�ɂ����ŏ��̃R�b�N�A���`���[�h���č��}�N�h�i���h�̎В�����500���ڂ̃n���o�[�K�[������Z�����j�[���s��ꂽ�B �����C�E�N���b�N�̍����j�B�i1�j�����ŌZ��́u�}�N�h�i���h�v�̖��̂��g���Ȃ��Ȃ�"The Big M"�̖��ʼnc�Ƃ𑱂������A�N���b�N���Z��̓X�̂����߂��Ƀ}�N�h�i���h�̑�^�X�܂��o�X��������"The Big M"�͓|�Y�����B�i2�j�o�c���Ϗ��̍��ӎ����ɂ́A�������`�F�[���̔���グ��1%���x�����Ƃ����u�a�m����v�����������A�_�ɂ͋L�ڂ��ꂸ����Ȃ������B�i3�j�N���b�N���E����1�N�ԁA�}�N�h�i���h�Ђ͑n�ƎҒǓ��L�����y�[���Ɩ��ł����Z�[�����s�����B�����m�������`���[�h�͌��{�����Ƃ����B 1990�N�A1���X�ܑ̐���B���I���N�̓��X�N���ŋ��Y�����̃}�N�h�i���h���J�X�B 1990�N��ɓ��蔄�グ�͏㏸���A1993�N��74��0800���h�����A5�N���1998�N�ɂ�124��2100���h���Ɣ{�������B90�N��̂����ɑS���E��2���X�܈ȏ��W�J���鐢�E�ő�̊O�H�Y�Ƃɋ}���������B 1997�N�ɐV�K�I�[�v���������O�X�܂͂���50���ȏ���I�[�X�g�����A�A�u���W���A�J�i�_�A�C�M���X�A�t�����X�A�h�C�c�A���{�Ȃǂ���߂��B 1998�N7��14���A���`���[�h�̓j���[�n���v�V���[�B�}���`�F�X�^�[�̘V�l�z�[���ŐS�s�S�ɂ��89�ő��E�����B�ނ̓}���`�F�X�^�[�̃}�E���g�E�J���o���[��n�ɖ������ꂽ�B 2001�N�̔N�Ԕ���グ��148��7000���ăh���A�����v16��4000���h���B 2002�N�A���{�}�N�h�i���h�͓��{�}�N�h�i���h�z�[���f�B���O�X�Ƃ��Ď�����ЂƂȂ�A�n���o�[�K�[����Љ��������{�}�N�h�i���h��V�݂����B 2004�N�A�����X�͐��E 119������3���X�ȏ�A1�������荇�v�� 4700���l�����p�B 2008�N�ɑS�Ẵn���o�[�K�[�s���46.8���̃V�F�A���l������ʂ̍����ێ��i2�ʂ̓o�[�K�[�L���O��14.2���j�B���N�̑����㍂��235��2200���h���A�����v43��1300���h���B�n��ʔ���\���̓A�����J���O��28���A���[���b�p45���A�A�W�A�E�����m�E�����n��22���A���̑�5���B 2009�N���_�ŁA���E118������3��1000�X�܂�W�J���Ă���A����75���ȏオ�t�����`���C�Y�X���B ���N�A�A�C�X�����h���S3�X�܂�����A���߂ēP�ނ���B���������Z��@�Ɋׂ�A�̎Z������Ȃ��Ȃ������߁B �Q�O13�N�����_�ŔN��15���H�ɋy�сA���E�̓X�ܑ�����3��5429�X�ɂȂ����B���̔N�A�J�i�_�o�g�̏����T���E�J�T�m�o�������{�}�N�h�i���h�̎В��ɏA�C���A�s���l���Ă����ቿ�i�H�����牿�i�т⏤�i�o���G�[�V�����̊g��֕��j�]�������B ���i���i�������ʂɂ��ߍׂ����ݒ肷�邱�ƂȂǂŔ���グ�g���ڎw���B 2016�N�A�`�L�f��wThe Founder�x�Ń}�N�h�i���h�Z��ƃ��C�E�N���b�N�̃r�W�l�X�W���`���ꂽ�B 2018�N�A�{�Ђ��V�J�S�Ɉړ]�B���㍂�Ő��E�ő�̃��X�g�����`�F�[���ł���A2018�N���_��37,855�̓X�܂������i���c�X2770�X�A�t�����`���C�Y�X35,085�X�j�A���E120�̍��ƒn��ɂ���A����6800���l�����p�B �}�N�h�i���h�E�R�[�|���[�V�����̎����́A�t�����`���C�Y�����X���x�����ƒ��A���C�����e�B�A�萔���A����ђ��c�X�ł̔��ォ��Ȃ�B�]�ƈ����́A230���l�̃E�H���}�[�g�Ɏ���170���l�ŁA���E��2�ʂ̖��Ԍٗp�ҁB ��18�N�A�č��Ŕ̔�����Ă���7�̃N���V�b�N�o�[�K�[�i�r�b�O�}�b�N�A�`�[�Y�o�[�K�[���j�ɁA�l�H�I�ȕۑ����A�����A���F����S�ʓI�Ɏg�p���Ȃ��Ɣ��\�B ���}�N�h�i���h�Ђ͐H�ו����s���N�ł���Ƃ̔ᔻ���āA�T���_�A���A�X���[�W�[�A�ʕ��Ȃǂ����j���[�ɉ����Ă����B�����āA�n���o�[�K�[�̃o���Y���獂�ʓ��R�[���V���b�v����菜���A�`�L���}�b�N�i�Q�b�g����l�H�ۑ�������菜���A�}�b�N�i�Q�b�g�Ɋ܂܂��{��A�g�Ԗ��A�N�G���_���A�G���h�E���̂ł�Ղ�A�Ă̂ł�Ղ�A�����������ʏ`�ɒu���������B ���}�N�h�i���h�Ђ̃n���o�[�K�[�͐��E���ɐZ�����A����̔�r���e�ՂȂ��Ƃ���C�C�M���X�̌o�ώ��w�G�R�m�~�X�g�x�͍��ۍw���͕������r����w�W�Ƃ��āu�r�b�O�}�b�N�w���v���l�āB2015�N���_�ŁA���E�ōł������ȃr�b�O�E�}�b�N�̓X�C�X�ł���A�ł������ȃr�b�O�E�}�b�N�������̓C���h�A�������`�B ���}�N�h�i���h�Ђ̗��v�̑����͍��O���Ƃ��琶�������̂ł���A���Ђ̉c�Ɨ��v�̔����ȏ���߂�B ���}�N�h�i���h�Ђ̓A�����J�^��ʏ���Љ��O���[�o�����̏ے��Ƃ��āA�e���œX�܂��P���̑ΏۂɂȂ邱�Ƃ�����B ���A�����J�ł̓h���C�u�X���[�������70�����߂�ƌ����Ă��� ���A�����J�ł͘J���҂�8�l��1�l���}�N�h�i���h�Ɍٗp���ꂽ�o��������Ƃ����B ���}�N�h�i���h1���X�͓��n�O���̎��P�ƃA���o�[�g�E�I�[�N�������L���A�����قɂ��Ă���B ���C���h�Ńx�W�^���A����p�̃��X�g�������I�[�v���B ���}�N�h�i���h�Ђ͎Q�������s��̃T�[�r�X���������コ�����B1975�N�ɍ��`�ŃI�[�v�������}�N�h�i���h�́A�����ȃg�C������т��Ē����ŏ��̃��X�g�����ł���A�ڋq�͑��̃��X�g������{�݂ɂ��������Ƃ�v������悤�ɂȂ����B �����������ł͓X�܂Ńr�[�����̔����Ă���B ���A�����J�����ł͌��N�I�ȃC���[�W�Ŕ���T���h�C�b�`�`�F�[���́u�T�u�E�F�C�v����1�ʂ̃V�F�A�����B ���`�F�[���X�g�A�̓X�ܐ��ł̓R���r�j�ő��̃Z�u��-�C���u���Ɏ������E��2�ʁB |
���J�[�l���E�T���_�[�X/Harland David Sanders 1890.9.9-1980.12.16 �iUSA�A�P���^�b�L�[�B
90�j2009
Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA �@Plot:
Section 33, Lot 57
 |
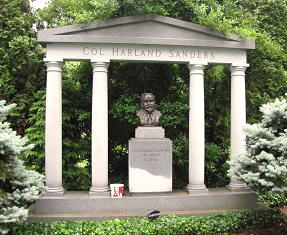 |
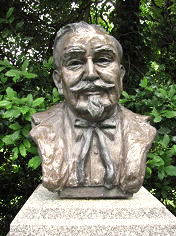 |
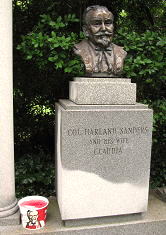 |
| ����ȂɊ炪�m���Ă���n�Ǝ҂����Ȃ��i�j | �{���̓n�[�����h�E�f�[���B�b�h�E�T���_�[�X�I | ���₩�����ȕ\��� | �`�L���R���{�̔����I |
| �A�����J�̎��ƉƁA�P���^�b�L�[�t���C�h�`�L���iKFC�j�n�ƎҁB�{���̓n�[�����h�E�f�[���B�b�h�E�T���_�[�X�B1890�N�A�C���f�B�A�i�B���܂�B�U�ŕ���S�����A10����_��œ����n�߁A16�œ����B���N�A�������̂܂�������ƁA�@�֎ԏC���H�A�{�C���[�W�A�^�C���̔������X�]�E���J��Ԃ��B1930�N�i40�j�A�P���^�b�L�[�B�ŃK�\�����X�^���h���o�c���A�~�n�̈�p��6�Ȃ́u�T���_�[�X�E�J�t�F�v���I�[�v���A���炪���������B�X�͔ɐ����A�T�N��Ɂu�B�̗����ւ̍v���v���]������āu�P���^�b�L�[�E�J�[�l���v�̖��_�̍�������ꂽ�B�܂�A���̃J�[�l���E�T���_�[�X�́g�J�[�l���h�iColonel�j�̓P���^�b�L�[�B�����^�������_�̍��i���_�卲�j�ł���A���ۂ̌R���Ƃ͖��W�B 1939�N�i49�j�A���͊���p�����t���C�h�`�L���̔̔����J�n������A���N�Ύ��ŕX�B1941�N�i51�j�A147�Ȃ̃��X�g�������Č������B1952�N�i62�j�A�T���_�[�X�̓t���C�h�`�L���̒����@�𑼐l�ɋ����ĕ�����V�����r�W�l�X���f���i�t�����`���C�Y�j���J�n�B���^�B�\���g���C�N�Ɉꍆ�X���I�[�v�����A���t�����`���C�Y�X�̓X�����u�P���^�b�L�[�E�t���C�h�`�L���v�iKFC�j�̃u�����h�����l�Ă����B���̌�A�T���_�[�X�̓t���C�h�`�L�������S���Ԃɐς�Ŋe�n�����A�t�����`���C�Y�g��ɐs�́B�o�c����������ނ���1964�N�i74�j�ɂ�600�X�܈ȏ�̃t�����`���C�Y�ԂɂȂ��Ă����B�T���_�[�X��1980�N�ɔx���ő��E����܂ŁA���E�ɓW�J�����X�܁i������6000�J���j������ă��V�s�ʂ�ɐ��@������Ă��邩�`�F�b�N�������A���{�ɂ��R�x�K��Ă���B���N90�B ���u�J�[�l����������l�`�v��3.25�̓x���������{���̘V�ዾ�������Ă���B ��1985�N�A��_���[�O�D�����ɋ��������t�@�������ږx�X�̃J�[�l�����ږx��ɓ��������A24�N���2009�N�ɐ�ꂩ�甭������A���݂͓��{KFC�{�ЂɓW������Ă���B |
����g �ΗY/Shigeo Iwanami 1881.8.27-1946.4.25 �i�_�ސ쌧�A���q�s�A���c�� 64�j1999��09 �o�Ől
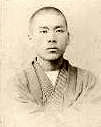 �@ �@ |
| �^���̎�����������ƁA�~���[�̎�܂��l���g���[�h�}�[�N�� |
 |
 |
|
| 1999�@���ׂĂ̕n�R�w���̉��l�I | 2009�@10�N�Ԃ�ɍď���B�E����ɕ掏�������Ă��� | ���c���͌Î��ŕ�͌ܗ֓������� |
| �u�^���̎�����������v�ƃ~���[�̖���g��܂��l�h����g���X�̃V���{���}�[�N�ɑI�сA�o�Ől�Ƃ��ď��߂ĕ����M�͂���͂�����g�ΗY�B���_�e����������ɂ߂��펞���̓��{�ɂ����āA�v�z�̎��R�̂��߂ɋB�R�Ɛ�����C���̐l���B 1881�N8��27���A���쌧�z�K�S���F���i�z�K�s���F�j�̔_�Ƃɐ��܂��B15�ŕ����������A�ꂪ�w�����x���āA20�ő�ꍂ���w�Z�i������j�ɓ��w�B22�A�����ŗF�l�̓������������E�،��̑�Ńy�V�~�Y���i�}���ρj���瓊�g���E�������ƂɏՌ����A�ΗY�͓N�w������ɎR�����ɘU�����40���ɂ킽���Đ��Ǝ��ɂ��čl�����i�،��̑�͐G�����ꂽ�N�̓��g���������A�S�N�Ԃ�40���������j�B�ΗY�͕�̐����Ŏ����Ɏ��邱�Ƃ͂Ȃ����������h�͑����A����̂��������������ɂ���ď������ޏ����ƂȂ����B24�A�ċN���ē����鍑��w�N�w�Ȃɓ��w���ϗ��w���w�ԁB���N�����B���ƌ�A�_�c���w�Z�̋��t�߂����A���E�͕s�����Ǝ��o�����E�B1913�N�W���T���i32�j�A�_�c���_�ے��ɌÏ��X�̊�g���X��n�Ƃ��A�J�Ƃ̈��A��Ɂu�Ⴍ�邵�A�����z���v�i���l���[�Y���[�X�j�ƋL�����B�����̌Ö{�ƊE�͌Ï��̒l�i���q�Ƃ̋삯�����ɂ���Č��߂Ă������A�ΗY�͐����̔��i�Œ艿�i�j�����s�������ƂŒ��ڂ��W�߂��B ��1914�N�A�Ėڟ��̒m�������Ċ�g���X�̏����o�łƂȂ�w���T��x�����s���A�Ö{���̓X�傩��o�ŋƂɓ]���Ă����B�Q�N��ɟ������E����ƁA���N�Ɉꍂ�����̓N�w�ҁE���{�\����Ɓw���ΑS�W�x�����s�����B�����āA�H�열�V��A�X���O�A�g���X�g�C�Ȃǂ̑S�W�����s���A�J���g�A�w�[�Q���A�����ӎO��̓N�w�����o�ŁB�����̑S�W��N�w���ɂ���āA���Ԃ���N�w�A�v�z�̍d�h�ȏo�ŎЂƂ��ĔF�m����Ă������B 1927�N�i46�j�A�����̌ÓT�̕��y��ڎw���āu��g���Ɂv��n�����A�]���͍������������w�����u���ɖ{�v�Ƃ����`�Łg�����h���ɏo�����B����ɂ���Ėړ��Ă̍�i��ǂނ��߂ɑS�W���܂Ƃߔ������Ȃ��Ă��悭�Ȃ�A�w����m���l����M��Ȏx����B�ΗY�͕��ɖ{�����̍ۂɁu�����^�т֗̕����Ɖ��i�̒Ⴓ���ŗD��ɂ����̂ŊO�ς͑e���������e�Ɋւ��Ă͌��I�����v�u�^���͖��l�ɂ���ċ��߂��邱�Ƃ�~���A�|�p�͖��l�ɂ���Ĉ�����邱�Ƃ�����]�ށB�i���j��������s���̏��������҂̏��ւƌ������Ƃ�������ĊX���ɂ��܂Ȃ��������A���O�ƌ��������ł��낤�v�Ɗ��s�̌��t���L�����B������1933�N�ɂ́u��g�S���v���A1938�N�ɂ́u��g�V���v��n�����A����炪���݂̕��ɁA�S���A�V���̌��_�ƂȂ�B ���啶���ƂȂ��Ă����ӔN�̟����A�o�ŎЂƂ��Ă͖����̊�g���X�Ɂw���T��x�̔��s�������A�H�열�V��͈⏑�ŖΗY�ɑS�W�̏o�ł�������B���̎�������ΗY�̐l�Ԑ��������ɑ��҂���M������Ă����̂���������B 1937�N�i56�j�ɖu�����������푈�́A��ǂ̈����Ƌ��ɔ��퐢�_����R���E���{�̌��_��������Ȃ��̂ƂȂ�A�ÓT��w�p���܂Ŕ��֑ΏۂƂȂ��Ă������B�ΗY�́u���{�͂��Ȃ��Ă������푈�����Ă���v�ƌ��ɌR���ɑ��Ĕᔻ�I������Ƃ��Ă������Ƃ��爳�͂���B1940�N�i59�j�A��g���X����o�ł��ꂽ���j�w�ҁE�Óc���E�g�i���������j�̒���w�Î��L�y�ѓ��{���I�̌����x�w�_��j�̌����x�w���{���j�����x�w�����{�̎Љ�y�v�z�x�̂S�_�����֏����ƂȂ�B�Óc�͗��j�w�҂��w���ƕ���x��w�����L�x����̎j���Ƃ����킹�Ď����m�F���s���悤�ɁA�w�Î��L�x�w���{���I�x�Ɏj���ᔻ�������A�_���V�c�ȑO�̐_��j���㐢�̋r�F�E�n�삪�������ƒf���A�_��ȍ~�ɂ��Ă��������q�̎��݂ɋ^�O��\�������B����͍c���̗��j�i�_���j�ρj���^�����Ƃł���^�u�[���������A�Óc�͕s�h�߂����ꂸ�ɏ��߂Ă����֓��ݍ��B���̌��ʁA�Óc�͉E���⍑����`�w�҂Ɍ������U������A�����Ȃ̈��͂�������23�N�Ԗ��߂Ă������勳�������E�ɒǂ����ꂽ�B�ΗY���o�Ō��Ƃ��ċ��e����A���҂́u�c���̑�����`�������v�Əo�Ŗ@��26���ᔽ�ŋN�i����A�Óc�͋����R�����A��g�͂Q�����̗L�ߔ�������i���Ɏ��s�P�\�Q�N�j�B�Q�l�͍T�i���A�㍐����1944�N�Ɏ����ɂ��Ƒi�ƂȂ����B ���������ł��ΗY�͂����܂ł��w��A�|�p�d����p�����т��A���@�w�ҁE���Z���B�g�̓V�c�@���i�V�c�͍��Ƃɏ]���g�ō��@�ցh�ɉ߂����������������ʂƂ������j���x�����铊�e���V���ɍs�����B�������A���{�E�R�����u�V�c�̓������͐�Ζ����ł���v�Ƃ��Ă������Ƃ��瓯�����s�f�ڂƂ������߁A�u�����͈ӋC�n�Ȃ����v�Ɠ{��̐������o�����B 1945�N�i64�j�A�I��B���N�A�M���@�c���ƂȂ邪�]�o���œ|���B��1946�N�P���A�푈�ւ̔��Ȃ��獑���̊Ԃɔᔻ���_��|���G���̕K�v����Ɋ����A���a�Ɩ����`����Ƃ��鑍���G���u���E�v��n���B�Q���ɏo�Ől���ƂȂ镶���M�͂���͂������A�Q�J����̂S��25���ɔM�C�ŕa�v�����B���N64�B�����͕��Q�@�����@���m�B�揊�͊��q�E���c���B �����A�Óc���E�g��1949�N�ɕ����M�͂���͂��Ă���B ����g���X�́g��܂��l�h�͍��������Y�̃G�b�`���O�ɂ����́B |
���A���h���E�V�g���G��/Andre-Gustave Citroen 1878.2.5-1935.7.3 �i�p���A�����p���i�X 57�j2009
Cimetiere de Montparnasse, Paris, France
 �@
�@ �@
�@
�t�����X�̎����ԃ��[�J�[�A�V�g���G���Ђ̑n���ҁB�O�쓮�ԁiFF�j�̗ʎY���ɐ��E�ŏ��߂Đ�������B
�G�b�t�F�������l�I���ŋ���L�����ɕς��Ă��܂��ȂǁA��Ȑ�`���@�ł����̒��̒��ڂ𗁂т��B
���n���[�h�E�q���[�Y/Howard Robard Hughes, Jr. 1905.12.24-1976.4.5 �iUSA�A�e�L�T�X�B 70�j2009
Glenwood Cemetery, Houston, Harris County, Texas, Plot: Oakdale
Section/2525 Washington Ave
 �@
�@
�f��w�A�r�G�C�^�[�x�Ńf�B�J�v���I���������q���[�Y�͋���ȃC���p�N�g���������I
���A���h�����[�E�J�[�l�M�[ Andrew Carnegie 1835.11.25-1919.8.11 �iUSA�A�j���[���[�N�B
83�j2009
Sleepy Hollow Cemetery, Sleepy Hollow, Westchester County, New York, USA
 |
 |
 |
| �Â����j�ŗL���ȁu�X���[�s�[�z���E��n�v | ����ȕ���h�[�� | ��O�̍L���~�n�͑S���J�[�l�M�[��p |
�X�V���B
����� �푾�Y/Yataro Iwasaki �V��5�N12��11���i1835�N1��9���j-����18�N�i1885�N�j2��7��
�i�����s�A�L����A����쉀 50�j2010
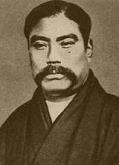 |
| ���������ŋ����̕x��z�� |
 |
 |
| ���ƕ揊�̒ʗp���c�܂��Ă���i2009�j | ��������S�ɕ��Ă���A�������ɂ��Ȃ� |
| 2009�N11���A��̓h���}�w���n�`�x�̉A�̎�l���ł���A�O�H�̑n�ƎҁE���푾�Y�̕�Q�̂��߂ɑ�ォ��㋞�B�����̊��ƕ揊�ɑ����^�ԂƁA�Ȃ�Ɣ߂������Ƃɐ�����ʗp������Ă���A��ʌ��J����Ă��Ȃ������c�I�K�b�N���ƌ��𗎂Ƃ��đ��ɖ߂����B ����l�b�g����������ƁA�����̃T�C�g�Ɂu�ʏ����J���������͈�ʐl����Q�\�v�Ə�����Ă����B�g�Ȃ��ā[�I�h�l�͊��삵�A�R������̖������Q���V����҂����B�������Ă��̓����������A�푾�Y�̕�Q��ɍĒ���I�V������GO�I |
 |
 |
 |
| 2010�N�Q���V���@�g����ȁc���c�������c�h |
�u�R���ƌ����Ă���F�[�b�I�I�v �ߏ��̐l�̏��ł́A���̋����K�v�Ƃ̎� |
�����C���^�[�z���̓d���� ��Ă�����Ɍq���炸�I |
 |
 |
 |
| �אڂ��鏬�w�Z�Ɏ����b���A�~�n����揊�� �`�����Ă�������B����ƁA����̒��ɂ���� �����ЂƂ傪�������I�����A�}�̊Ԃɕ悪������I |
�܁A�܁A�܂����푾�Y�ł̓b�I�H�J������ �]�����ő�ɂ��Ė��O���m�F���Ă݂�Ɓc |
�u���펟�Y�v�A�푾�Y�� �I���W���������`�I �j�āA�V�͉������������ |
 |
 |
 |
| �ߏ��ɂ͎O�H�Б�������̂ŁA�Z���̕��� �����ĕ揊��`���ƁA�Q��̕���I �ł�����͊����a�q�i�푾�Y�̕�j�� ���G��i�푾�Y�̎q�j�������B�푾�Y��`���I |
�g��������H��O�H�̑n�n�҂���H ���n�`�Ŋ���������H��Q�҂� �������Ă���Ǝv���Ă��̂ɁI�h ���D�ɗ������[���ɂ�����x�K�ꂽ |
��͂��͕܂���̋l�������l�I �l�ȊO�ɂ���Q�҂��Q�l���āA �����ɐ���������Ă݂����ǁA�܂����� �������c�B��[��I�����܂ŗ��āI |
| �푾�Y�́w���n�`�x�Œm���x���������Ă���A�l�͑�������揊�ɂ͂Ђ�����Ȃ��ɏ���҂��K��A�O�H�����̍��h��̎Ԃ��s�������Ă���ƐM�����Ă����B�ƁE���E��E���I�傪�܂��Ă����@�A�A�A�I�揊�ɂ܂������l�̋C�z�Ȃ��I�M���[�X�I���̂��߂ɂ����܂ő����^�̂��c�g�z�z�I �l������������ł���ƁA�w�ォ��u�푾�Y����̂���Q��ł����v�Ɛ��B�ށiK����j���r���ɕ��Ă��āA���Ԃ�������߂��������������B�l��͎肪���肪�~�����āA�ߏ��ɂ���O�H�̃X�|�[�c�Z���^�[��揊�ɗאڂ���O�H�̎Б�̐l�ɕ�Q�̕��@��q�˂Ă݂��B�����������Ƃ́A��̓����ɕ��i�͂�����j�̉Ƃ�����A��Q�ɂ͕��̋����K�v�Ƃ������ƁB�����������I�̐S�̕��̉Ƃ͉J�˂��܂��Ă���A�C���^�[�z�����̏Ⴕ�Ă���̂��s���|���Ɩ�Ȃ��i�d�����ʂ��ĂȂ��l�q�j�B �����������Ă��邤���ɁA�揊�̖�������Ă���j����������l�����B�����|���Ă݂�ƁA�r���S�I�ށiM����j���푾�Y�Q��̏���҂������I�R�l���Ε���̒q�d�A��̂��Ƃ͕�n�ɕ����Ƃ������ƂŁA���Ƃ̂S��ڈȍ~������ߏ��̐���쉀��GO�B�E���̕��Ɏ��₵�ďd��Ȏ��������������B���킭�u�ȑO�͕�炪���Ė����Ɍ��J���Ă�������ǁA���͖��l�ɂȂ��Ė���J����l�����Ȃ��B���S�ɔ���J�ɂȂ��Ă���v�B�K�[���B�g���������h�B�l�͂��Đ���쉀�̒�t�̐l���u���ƕ揊�̕��͍���i���k�����H�j�ŋߔN�S���Ȃ����v�I�Ȃ��Ƃ�����Ă����̂��v���o�����B�Ȃ�Ă������B �u��炪���E����p�҂����Ȃ��̂Ŕ���J�v�Ƃ������l�̃P�[�X�́A������������ˉ���̕揊�ł��N���Ă���B�O�H������������c���A�����ق������͗]�T�ł���Ǝv�����ǂȂ��c�i�����W�҂̕������̃y�[�W��ǂ܂�Ă�����A�l�A�푾�Y����Ɖ���l�̖����ɂ̓{�����e�B�A�ŕ��W�����܂��̂ŁI�j�B |
 |
 |
| ������͐��c�J��̊��ƕ_���B�ÉÓ����ɂ� �n�݂�����E����V���̗�_�Ƃ��Č��݁i2013�j |
�ē��ɂ��Ɗ���V���A���푾�� �͂��ߊ��Ƒ�X������Ƃ̂��� |
�������Ȃ邤���́c
�n�オ�����Ȃ�F������揄�炳���Ē����܂��I�O�[�O��MAP�A�X�^���o�C�E�I���I�����I
 |
 |
| �����̗тɈ͂܂ꂽ�ꏊ�����ƕ揊�I | ���S�Ɍ��������푾�Y�I�F�����獇���I |
���Ȃ�ƁA�T�C�g�ǎ҂̕���1980�N�ɏ��炳��Ă��܂����I
 �@ �@ |
|
| �w���푾�Y�V��x 1980�N�R��12����N���B�e����܂����I������24���� ���J����Ă����̂����BN���M�d�ȕ�摜��L��������܂����[�b�I�@m(_ _)m |
| ���ƉƁB�������Ɋ����O�H�����̑n�n�ҁB�y���˂̕��m�̒��ł��ʼn����̒n���i�����j�Q�l�����_�̉Ƃɐ��܂��B���g�o����ڎw���Ċw��ɐ����o���A�y���ˏd�b�̋g�c���m�̖ڂɎ~�܂�B1859�N�i24�j�A�˖��Œ���ɕ��C�������Ƃ��@�ɁA����f�Ղœ��p�������B1861�N�i26�j�A�n���Q�l���狽�m�i�������j�ɐg����������A������1867�N�i32�j�ɂ͏�m�̐g���ł���V���狏�g�ւƏo�������B �����ېV��͔ˑD�̕����������g���ĊC�^�Ƃɐi�o�B1874�N�i39�j�ɖu����������̗����n�߂Ƃ��āA��p�o���A����푈�ȂǂŐ��{�̗A���Ɩ���Ɛ肵�A����ɂ���č����ő�̋D�D��Ђ�z���グ��B����ɖ푾�Y�͊e���ʂő��p�I�Ɏ��Ƃ�W�J���A�����Ƃ��ĎO�H���������グ�Ă������B50�ŕa���B��{���n�Ƃ͓����N�ɐ��܂�Ă���A�푾�Y�͊C�����̌o����S�����Ă����������������B
���푾�Y��20�̎��ɁA���̐Ȃ̌��܂������œ������ꂽ���̙l�߂�i���o�āA������������ꂽ���Ƃ�����B
|
�����c�� ���q/Kahe Takataya ���a6�N1��1���i1769�N2��7���j-����10�N4��5���i1827�N4��30���j
�i���Ɍ��A�F�{�s�A���c���Õ��q���� 58�j2009��10
�k���َs�E�̖����̕�l
 |
  |
| ���َR��w�ɂ����u���I�F�D�̔�v�ƍ��c���Õ��q�� |
���V�A���ƌ��ɒ��މÕ��q�B�E��ɏ��O��s����̏��A����Ɋ͓��Ő����� ���ւ������̈ߕ��������Ă���B���يJ�`100�N���L�O����1958�N�Ɍ��Ă�ꂽ |
 |
 |
| �Ìy�C���Ɣ��٘p�ɋ��܂ꂽ��Δ��̂悤�Ȗ�i |
���َs���̖̏����B���Ă͉p�E���̗̎��ق��u���� �Ă����B�����ɓy���ΎO�ƐV�I�g���m�̋��{�������� |
 |
 �@ �@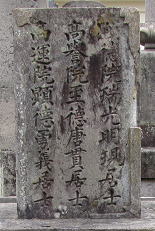 |
| ��̒��̕�i�����j���Õ��q�̕�i2009�j | �^�̉����u���_�@�������ы��m�v���Õ��q |
�k�W�H���F�{�s�ܐF���̕�l
 |
 �@ �@ |
| �w���c���Õ��q�����a�n�x | ���a�n�Ɍ��Õ��q���͖��ɃJ���C�C�B���قƐ^�t |
 |
 |
  |
| �Õ��q�ِ̊ՂɌ��w���c���Õ��q���L�O�فx | �L�O�ق̕~�n�ɂ��錰����͍���6.4m�I | ���a�n���猩����R�̒����ɍ��c���̖䂪�B�揊�����̋߂� |
 |
 |
 |
| �u���{�̌ւ鍂�c���Õ��q�����̒n�ɖ���v �i�E�F���l�X�p�[�N�ܐF/���c���Õ��q�����j |
��O���Õ��q�A������̋����q�̕�B �n���ɂ͒����ނ��g�����Ύ��������Ă��� |
�揊����̋��������Õ��q �i2010�j |
| �]�ˌ���̊C�^�ƎҁB�ڈΒn�J���A���ٔ��W�̊�b��z���������B1769�N�i���a6�N�j�ɒW�H�����݁E�s�u�i���j�̔_�Ƃɐ��܂ꂽ�B�Õ��q�͉Ƃ��n�������ߏ��N���ォ�狙�Ƃɏ]�����Ă����B1790�N�i21�j�ɕ��ɁE�_�˂ɏo�ĒM���D�i���邩������/�ݕ��D�j�̐��v�ƂȂ�B�����ɓ����Q�N��ɑD���ƂȂ�A27�Ŏ����̑D����ɓ���g�D�����h�ւƏo�������B�Õ��q�͂��������ڈΒn�ɒ��ڂ��A���ɂŎ��A�ؖȁA���A�R�`�E��c�ŏ����Ă�ς�Ŕ��قɉ^�сA�A�H�͉ڈΒn�̊C�Y����ςݑ��Ŕ��p����Ƃ����k�O�D�̉c�ƂŁA�T�ǂ̑D�����L���鍋���Ƃ��Đ��������B28�Ŕ��قɎx�X�i��̖{�X�j���J�X�B���N�A�ڈE���O�˂Ŗ��{��l�ɍq�C�̌������q�ׂ�@�����A���S������l���畨���A����C����邱�ƂɂȂ�B �܂��A�T���ƂŖ��b�̋ߓ��d������𑨓��ւ̍q�H�������˗�����A���㓇�̎R�ォ�畗���⒪�������A�𑨓��ւ̍q�H�J���ɐ��������B�Õ��q�͖��{�֑𑨊J��̏d�v��������A�^���Ė����ɂ��āA���A���A�ߕ��A�����𑨓��̓����ɒ����B�����͉Õ��q����J����Ԃ��g�������@���w�ъ�Ƃ����B1800�N�i31�j�A���{�̐M�����Õ��q�͌�p�D���Ƃ��Ėk�C�̊��D���������ׂĔC����A�ڈΒn�̏�����Ɛ�B�Õ��q���J�������𑨓��̋����17�J���ɂ̂ڂ����B�Õ��q�́A�]�ˁA���A���فA���ɓ��ɏ��X���J�������̕x��z���Ă����B 1804�N�i35�j�A���V�A����̑�Q�������g�߂Ƃ��ċM�����U�m�t������ɗ��q�B���U�m�t�͍c��A���N�T���h��1���̐e������ɓ��{�Ƃ̌��Ղ����߂����A���{���͉ɔ��N�Ԃ����������A�ʏ������e���̎����ۂ����B1806�N�A���{�������U�m�t�͔z���Ɋ����i�T�n�����j��N�������A���N�ɂ͑𑨁A����ŗ��D�������B���̎����ɏՌ��������{�́A�w���V�A�D�ŕ��߁x�𐧒肵�A�u���V�A�D���������挂�ނ���v�Ɩ������B 1811�N�A�瓇��I�z�[�c�N���C�𑪗ʂ��Ă������V�A�R�̓f�B�A�i�����A�����̂��ߍ��㓇�ɗ������A�S���[�j���͒��i1776-1831�j�ȂǂV�l���㗤�B���㓇�l�߂̍]�˖��{�x�����͔ނ��ߔ����A���O�┠�قɗH�����B��1812�N�i43�j�A�f�B�A�i�����͒����R���h�͌R�͂Q�ǂŗ������ĂV�l�̕Ԋ҂�v���B���{���ԓ���ۗ������ׁA���R���h�͗H���̕Ƃ��č��㓇�����q�s���������Õ��q�̊ϐ��ۂ�\�߂��A�Õ��q�����v�S�����J���`���b�J�֘A�s�����B�Õ��q�͂��̃s���`�����V�A�l�Ƃ̗F�����ލD�@�Ƒ����A�����Ƀ��V�A����w�ѐ������Ń}�X�^�[�B���R���h�Ɂu�V�l���߂炦��ꂽ�̂͋M���̐N��������������ł���A�~�o�������̂ł���Ύ����ł��邾���w�͂���v�Ɠ`�����B���̌��t�Ɋ���R���h�́A�Õ��q������ɑ���͂��A�Õ��q������ƂȂ��ăC���N�[�c�N���ٖ̕��������ٕ�s�ɍ����o���ꂽ�B 1813�N�i44�j�A���V�A���ɐN���̈Ӑ}���Ȃ��Ɣ��f�������{�́A�S���[�j���͒��͂��߂V�l��������A�Q�N�Ԃ�Ɏ����͉��������B���{�͑ł肪�Ȃ��E����������݂̂ł��������Ƃ���A���a�I�����Ɏ������̂͂��ׂĉÕ��q�̗͂ɂ����̂ƌ�����B1853�N�̃y���[���q���40�N���O�̏o�������B���{���Õ��q�Ɋ��ӂ�\���܋���^�����B �S���[�j��������������T�N���1818�N�i49�j�A�Õ��q�͌�p�D�������߂ĉƋƂ��ɏ���A�̋��̒W�H���E�s�u�ɋA�������B�ߗׂ̒��`�p�̏C�z�Ȃǂɍv�����A�ˎ刢�g�炩�疼���ѓ���������A���₩�ȂX�N�Ԃ̉B���������o�āA1827�N�ɕa�v�����B���N58�B�����́u���_�@�������ы��m�v�B �Õ��q�͈ꐅ�v����g���N�����Ėk�m������J�������l�ł��邾���łȂ��A���Ԑl�ł���Ȃ�����I�͏Փ˂̊�@������{���~�����j�B�ߗ��ɂȂ��Ă����{�ɗ��炸�A����̋@�]�ŋA�����ʂ������B��ɃS���[�j���͊C�R�����܂ŏ��i���A���̒����w���{�H���L�x�i1816�j�̒��ʼnÕ��q�ɂ��āu���̐��ōł��f���炵�����h���ׂ��l���v�Ɛ�^�����B1911�N�A���{���{�͉Õ��q�̐��O�̌��тɑ����܈ʂ�Ǒ������B ��͒W�H���E�F�{�s�ܐF���̐��a�n�ɗאڂ������c���Õ��q�����i�E�F���l�X�p�[�N�ܐF�j�ƁA���َs�̖̏����ɂ���B���a�n�ɂ͈��p�̖]������莆�Ȃǖ�140�_�̎�����W�������w���c���Õ��q���L�O�فx�������A�����̑O�ɍ��쌧�����Y�̉ԛ�����g�p��������6.4���[�g���A�ЂR���[�g���̋���Ȍ����肪���т��Ă���B �k�NjL�l���a230�N�ƂȂ�1999�N�ɁA�Õ��q�̕�̑������Ɂg�Q���"���������ꂽ�B���ߕ�͌ܐF�B ��1807�N�ɏo���ꂽ�w���V�A�D�ŕ��߁x�́A1825�N�ɂ��ׂĂ̊O���D��Ώۂɂ����w�ٍ��D�ŕ��߁x�ƂȂ�B ���c�O�Ȃ���u���c���v�͉Õ��q���E�̂U�N��ɁA�ƋƂ��p�����킪���f�Ղ̋^�����������A���{�ɑS���Y��v������v�������B ���w���c���Õ��q����L�x��R���h�̎�L�����ƂɎi�n�ɑ��Y�������w�̉Ԃ̉��x�����M�B ���x�[�g�[���F���ƂP�ΈႢ�Łi�Õ��q���N��j�A�v�N������1827�N�B�قړ����������Q�l�B |
�����F ���Y/Jiro Shirasu 1902.2.17-1985.11.28 �i���Ɍ��A�O�c�s�A�S���@ 83�j2007 ���Ɖ�
 |
 |
 |
| �ē��ő叕����B ����Ȃ����Ȃ� |
�S���@�ɂāB�������q�A�E�����Y�B���q�̕�ɂ͞����� �u�\��ʊω��v�A���Y�̕�ɂ́u�s�������v�ƍ��܂�Ă��� |
�ܗ֓��𔖂��X���C�X�B�����Y�� �I�сA���q���f�U�C������ |
| �g���a�̈Ɣn�V��h�ƌĂꂽ�`���I���ƉƁB���ɂ̖��Ƃɐ��܂�A10��㔼�ʼnp���P���u���b�W��ɗ��w�B�g��185�Z���`�A�X�|�[�c���\�B���s���h���J�[�E�}�j�A�Ƃ����č��������Ԃ����A20�㔼�ɂ̓X�y�C����[�̃W�u�����^���܂Ń��[���b�p�嗷�s���I���Ă����B1928�N�i26�j�ɋA�����V���L�҂ƂȂ�B���N�A�F�l�̖��ƌ����i���M�Ƃ̔��B���q�j�B���̌�A���Ђ�H�i��Ђ̎�������C���A���p�œn�q����ۂɒ��p�O�����̋g�c�Ɛe����[�߁A�C�M���X��g�ق��z�e������Ɏg���Ă����B1940�N�i38�j�A�����m�푈��\�����Ď��Ƃ��痣��A�_���ɉB�������d���̓��X�𑗂�B�펞���͋g�c�Ƌ��ɔ���̗��ꂩ��I��H��Ɏ��g�B���͋g�c�̗v���ŏI��A�����������ǂ̎Q�^�ɏA�C�B�u��X�͐푈�ɕ������̂ł����ēz��ɂȂ����̂ł͂Ȃ��v�Ɛ�̌R��ɚV����A�}�b�J�[�T�[�����������A��w�͂�J�߂�GHQ�̏y�����u���Ȃ�����������������Ώ�肭�Ȃ�v�Ƃ�荞�߂�ȂǁA���̔j�V�r���͓����̓��{�l�̘g����˂����������݂������B���B��GHQ����u�]���Ȃ炴��B��̓��{�l�v�uMr.Why�v�ƌĂꂽ�B1948�N�A�g���̓��{�͖f�����Ƃ��Ĕ��W���邵���Ȃ��h�Ƃ����M�O����f�Ւ��i�ʎY�ȁj�̏��㒷���ɏA�C�B1951�N�i49�j�A�T���t�����V�X�R�u�a��c�Ɍږ�Ƃ��Đ��s���A����������p��ł��悤�Ƃ���g�c�̌��e�����������A�u�Ɨ����Ȃ̂��v�Ƃ����ē��{��ʼn����������B�㔼���͐����Ɖ����A�d�͉�Ђ��m���Ɓi���}���n�j�A���e���A�،���Ђ̌ږ�Ȃǂ��C�B���{�l�ŏ��߂ăW�[���Y���͂����j�ƌ����A�O��ꐶ�̃��f���߂����Ƃ��B�V���ĂȂ�80�܂�68�N�^�|���V�F911S����������Ă������A1985�N�Ɉݒ�ᇂƓ��������Ŏ����B���N83�B�⌾���ɂ́u�������p �����s�p�v�Ƃ������B�܂��ɃX�[�p�[���{�l�B |
���Ӊ� �d�O�Y/Jyuzaburo Tutaya 1750.2.13-1797.5.31 �i�����s�A�䓌��A���@�� 47�j2007��08 �]�˂̏o�Ől
 |
 |
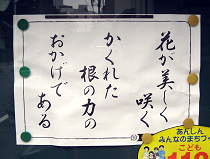 |
| �䓌���HP�ɂ͐��ɕ悪����� ���������A��n��T���Ă����Ȃ����� |
�Z�E�ɐq�˂Ă݂�Ɓu�֓���k�Ђ̑�Ђŕ���Ă��Ă��܂��A �����̂ǂ��ɒӉ��������Ă���̂�������Ȃ��Ȃ����v�Ƃ̂��ƁB �l�͂��̕~�n�S�̂�ނ̕�Ǝ~�߁A���Ɍ����č������� |
�����̊G�t���Ƃ����������Ӊ��B ���̑O�̌��t�́A�|�p�𐢂ɑ����� �ނ�\���Ă��邩�̂悤������ |
����1�N��c
 �@ �@ |
| �䓌��̐��@���ɂ��悪����Ƃ��������L���b�`�I����500m��������Ă��Ȃ��B���@���͖ڂ̑O�܂� ���Ă�̂ɂȂ��Ȃ��ꏊ��������Ȃ������B�����āA�܂�������ȑ傫�ȃr���������Ȃ�Ďv�������Ȃ�������`�I |
 |
  |
 |
| �������I����́I |
��i������R�Ԗڂ̖������h���s�V���I �����́u�H���@�`�R�����M�m�v�Ƃ̂��� |
���ɒӉ��ɕ�Q�ł����I���� ���P�Ŏ����R���A��͋ߔN�Č� |
| �V�F�C�N�X�s�A��x�[�g�[���F���A�S�b�z�̍�i���ǂ�Ȃɑf���炵���Ă��A�����A�y���A��W���o�ł�����ƉƂ����Ȃ���A���S�N��܂ň̋Ƃ��`�����邱�Ƃ͕s�\���B���{�œƎ�������傫�����W�������̂́A�]�ˏo�ŊE�̕��_���A�Ӊ��i����j�d�O�Y���B�Y��҂╂���G�t�̔�҂ł���d�O�Y�͐l�̍˔\�����������ɒ����Ă���A�G�t�̊쑽��̖��A���F�֎ʊy��̖���𐢂ɑ���A�\�ԎɈ��A�Ȓ��n�ՁA�R�����`��Ⴂ��Ƃ����˔\�����������������ĉ������A����̏��^�����q�r�̏o�Ől�B�n�{�≮�u�Ӊ��v�̎�l�ŁA���\���i��l�����̊G����ǂݕ��j�ł������x�X�g�Z���[���o�����B���W�͕x�m�R�`�ɒӂ̗t�B 1750�N2��13���A�Ӊ��d�O�Y�͍]�˂̐V�g���i�悵���/�����j�ɐ��܂ꂽ�B�����͊ێR�h��(����܂�)�B���͍k�����B�̖��A�ӓ���(���̂���܂�)�B���͒Z���g�ӏd�h�i�����イ�j�Ƃ��Ă��B������̃N���G�C�^�[�Ƃ̔N��́A�쑽��̖����R�ΔN���A�����k�ւ�10�ΔN���A�R�����`��11�ΔN���A�ʊy��13�ΔN���A�\�ԎɈ�オ15�ΔN���A�Ȓ��n�Ղ�17�ΔN���A������47�ΔN���̉̐�L�d���d�O�Y�̖v�N�ɐ��܂�Ă���B �g���͍]�ˎ��㏉���ɑn�݂��ꂽ���{���F�̗V�s�ŁA�Ŏ������{�̏d�v�ȍ����ƂȂ��Ă����B���n�͑喼�⍋���ȂǍ]�˂̖��m���W���Ќ��̏�ł��������B�d�O���̕��͔����o�g�̗V�s�ߐl�Ǝv����ێR�d���A�]�ː��܂�̕�͒×^�B7�̎��ɗ��e���������V�U�ǓƂƂȂ�A�V�g���ň��蒃���i�Ђ��Ă����j�u�Ӊ��v���c�ފ쑽�쎁�i�Ӊ��{�Ɓj�̗{�q�ɂȂ����B���蒃���Ƃ͋q��V�����ֈē����钃���ł���A�u�Ӊ��v�͊쑽�쎁�̉������B �g���ň�Ƃ������Ƃ́A�ԊX�̉₩���ƁA���R��D��ꂽ�߂������������̌��Ɖe�A�ߊ삱�������̐l�Ԃ̎p�ɐG��邱�Ƃł���A�d�O�Y�͎q�ǂ����ォ��l������ڂ���܂�Ă������B�g���̕~�n��2���i�b�q������̖�2�{�j�A1���l�����Z���������V���������B�V�������͐e�̎؋���w�����A�킸��3������5���قǂ̂����ƈ��������ɁA�k���Ⓦ�k�̑����甄���Ă����B14���납��q���Ƃ炳��A�N�G�����i�_��I���j��10�N��܂œ����Â߂ƂȂ����B�g���͍������Ɛ��x�Ɉ͂܂�A�V���͑��i��������j����O�ɏo���Ȃ��B5��l�̗V���̂����Ԋ@�i�������j�������ł���̂�60�l�قǂɌ���ꂽ�B24���ɂ��̋�E�i�������j���玩�R�ƂȂ邪�A�唼�̗V��������܂łɐ��a�i�~�Łj��h�{�����A���j�Ŗ��𗎂Ƃ��Ă����B 1762�N�i12�j�A�̂��Ƀ��C�o���ƂȂ�o�ŎҁE�{�����s���q���]�˓��{���ɊJ�ƁB 1765�N�A�d�O�Y��15�̂Ƃ��ɊG�t�E��؏t�M�i1725�H-1770�j���G��i������݁j�̐����ʂ��āA����t�␠��t�Ƌ��͂��đ��F���ؔʼn�i�J���[�����G�j�̋Z�p���J�����A�F�N�₩�ȁg�ъG�h��n�n�����B�����A���{�̕����̒��S�n�͏���ł��������A�ъG���a���������̍�����]�˂ł��V���ɕ������ԊJ���Ă������B���Ȃ݂Ɂg�����G�̑c�h�͂���ɖ�100�N�Â�����Ɋ����H��t��i����̂ԁj�i1618?-1694�j���B 1772�N�i22�j�g�����̊O�ŗ{���̈��蒃���u�Ӊ��v�̌�����Ԏ肵�ď����ȏ��X�u�k�����v���J�ƁB���C�~�ɘb��̖{����ŋg�����̉Ƃ�X��K�˕����A�ݖ{�������Ȃ����B����䂦�g���̎���ɂ��ڂ����Ȃ����B���̍��A�]�˂̊e�n�Ɂu���ꏊ�v�ƌĂ�開�{����F�̐F���������A�g���͗����̈������ꏊ�ɋq��D���i�C�������Ȃ��Ă����B�g���̂܂܂ł͎�������ĂĂ��ꂽ�g�����p��Ă��܂��B�V�����؋���Ԃ��Ȃ��h�A�������O�����d�O�Y�̓��f�B�A���g���ċg����グ�悤�ƍl�����B 1773�N�i���i2�N�j�i23�j�g���ł͖��N�t�ƏH�ɑn��100�N�̗��j���ւ�Ō��i�n�{�≮�j�E�،`���i���낱������j�����q���A�V����X�ʂɏЉ���K�C�h�u�b�N���g�����i��������j�����s���Ă���A�d�O�Y�͕ҏW�ɎQ���B���N�H�̋g�����s���h�ϋʔՁi���̂ӂ݂Â��j�t�̉��t�Ɂu�Ӊ��d�O�Y�v�̖��O�����߂čڂ����B�{��̌��G�i����������G�j��47�̏���t�͂��S���B�d�O�Y�͋g�����̔��s���E�،`���Ɛe�����Ȃ�A���蒃���̗{�q�ŗV�s�Ɋ炪�����d�O�Y�́A�ȍ~�A�g�����̉����ł̕ҏW�≵���������`���悤�ɂȂ����B�g���͎���ɓ��킢�����߂��A�Ăѕ����̔��M�n�ƂȂ��Ă������B ���s���h�ϋʔՁt�@https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300054230/1?ln=ja ������t�́i1726-1793�j�c�]�˒����̕����G�t�B���͐��P�B����܂Ŗ��ҊG�̎嗬�����������h�ɔ�ׂĎʎ����𑝂��A�̕�����҂�͎m�̎���G�ɐV���𐁂����ށB��N�͓��M���l��̐��삪���S�ƂȂ�A�u�t�͈ꕝ�����(�����Ղ�����������)�v�Ə̂�����قǂɂ��̓��M��͒��d���ꂽ�B��\��͖��ҊG�u����(�����܂�����)�E���㒆�������v�A���M��u�w�������\��J���}�v�ȂǁB ���n�{�≮�i���ق�Ƃ��j�c���{�̏o�ŕ����͂��Ƃ��Ƌ��s�̊w�p������n�܂�A������]�˂Ŕ̔�����ۂɏ������́u����{�v�ƌĂB����ɑ��A�]�˂̔Ō��i�͂���Ɓj���g�n���h�ō�����Ǝ��̌�y�{�́u�n�{�v�i���ق�j�ƌĂ�A�n�{�������≮�u�n�{�≮�v�͍]�˂��q�ɐe���܂ꂽ�B�]�˂̏����Ɍ����āA�]�˂̏o�Ől����Ƃ�G�t�Ɉ˗����āA���������ō]�˔��̐��ȓǂݕ��𐢂ɏo�����B�n�{�ɂ́A�}�G����̓ǂݕ��̑��o���i�����������j�A�V�f�ɂ܂�韭���{�i�����ڂ�j�A�����G�Ȃǂ��������B ���]�˂̖{���͍]�ˎ������i19���I���߁j�̎��_�Ŗ�80������A�Ō��E�n�{�≮�͖�20���������i1853�N�ɂ�146���j�B�Ō��́u�n�{�≮���ԁv���������A�����̕����{�g�d�Łh��A���g�������ς��������́g�ޔŁh���֎~���Č݂��̌�����������B �L���ȔŌ��͍]�˂̒��ꓙ�n�E���{���ʖ���(�Ƃ��肠�Ԃ�܂�)�ɓX���\���Ă���Ӊ��d�O�Y�u�k�����v�i�g������ړ]�j�A�߉���E�q��u��ߓ��v�A���c�����Y���q�u�h�W���v�i�̂��Ɉړ]�j�A�����Ėk�ւ́s�y�ԎO�\�Z�i�t�𐧍삵���������^���́u�i�����v�A�L�d�́s���C���E�O���V���t�𐧍삵���|�������́u�ۉi���v�A�g���̃K�C�h�u�b�N��Ɛ�o�ł����،`�������q�u�ߗؓ��v�A�s���ҕ���V�p�G�t�̐����ʼn̐�L������ҊG�̑��l�҂ɐ������a�s���q�u�Ðv�Ȃǂ��m����B ����A��w���A���j���A�����Ƃ������d���{�������u�����≮�i������ǂ��j�v�ɂ͐{�����i���͂��j�Ε��q�A�s��̐V���t�����s�����{�����s���q�������B �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�| 1774�N�i24�j�d�O�Y�͖{���̓X�傩��Ō��ւƓ]�i���A����t�͂ƕ��Ԑl�C�G�t�Ŗk���h�̑c�A�k���d���i1739-1820/����35�j���A�����Ԃ�V���Ɍ����Ăĕ`�����V���]���L�s��ڐ�{ �Ԃ��܂Ёt�㉺2�����A�g�Ō��E�Ӊ��h�Ƃ��ď��߂ďo�ŁB�V���]���L�͌����K�C�h�u�b�N�g�����̕��ǖ{�ŁA�o�Ŏ����͒Ӊ��Ɗe�V�s���o�����B�s��ڐ�{ �Ԃ��܂Ёt�ɂ͐l���悪1�����Ȃ��A���ׂĂ̏������Ԃŕ\�����Ă���A��i�ɗV���̖��͂�`���鐈�ȍ�i�ƂȂ����B ���s��ڐ�{ �Ԃ��܂Ёt�@https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100080738/1?ln=ja �d�O�Y�͖k���d����ʂ��Ă��̖剺�̖k�������i�܂��̂ԁj���R�����`�A�k�������i�܂��悵�j�A�E�t���i���ځE�����܂�j�A�܂��A�剺�ɋ߂��k��L�́i�쑽��̖��j�ƒm�荇���A�̂��ɒӉ����s�̏����Ŕނ�Ƒg��ł����B�Ȍ�A�T�N�قǂ����Ċe���ʂɐl�����L���A�؉��A����t�Ȃǂ̐l�ނ𑵂��A�o�ŎЂ̊�b���ł߂Ă������B ���N�A�d�O�Y���o�ł����w���j�Č�]�ˁx�̏����́A���ꌹ�����u�����S�O�v�̕M���Ŏ��M�����B���̏����ł͋g���̗V�������ւ̌h�ӂ�����������e�ƂȂ��Ă���B ���̔N�A�{�����s���q�����{�ŏ��̖{�i�I�Ȑ��m��w�̖|�s��̐V���t�����s�B��U�}���̗���{�u�^�[�w���E�A�i�g�~�A�v�𐙓c�����E�O��Ǒ�E����~����7�����|��E�Ҏ[�����B 1775�N�i���i4�N�j�i25�j�،`�������q�́A���m����Y��ҁE�����G�t�ɓ]�i��������t���i1744-1789/����31�j�����Ɖ�ɘr��U��������\���w���X�搶�h�Ԗ��x�i�����������̂�߁j�����s���A��O�̃x�X�g�Z���[�ƂȂ�B���e�́A�c�ɂ̕n�R�Ȏ�҂����g���悤�ƍ]�˂ɏo�邪�A���݉��ŋ���������āA��ɓ��ꂽ�h��������������B�ڊo�߂��Ƃ��ɐ����ȂLjꎞ�̖��̂悤�ɂ͂��Ȃ����̂ƋC�Â��A�̋��A���Ă����Ƃ������́B�t���ɂ͕��Əo�g�Ȃ�ł͂̋��{������A���̕���͓��̎���̌̎��w����i����j�̖��x���x�[�X�ɂ��Ă��邽�߁A��l�����̒m�I�ȓǂݕ��ƔF������A�g���\���h�Ƃ����V���ȃW���������J�����i����ȑO�ɂ����\���I�Ȃ��̂͂��������A�x�X�g�Z���[�ƂȂ�F�m���ꂽ�͖̂{�삩��Ɠ�����̍�Ƃ͔F���j�B����܂ŊG����̑��o���i�����������j�i�Ԗ{�E���{�E�{�j�͎q�ǂ��⏗���̂��߂̓ǂݕ��Ǝv��ꂪ�����������A����t���͟������C�ƕ��h������������l�����̍�i�A���\���̑c�ƂȂ����B���o���͎���ɐN�w�A����ɑ�l���ǎ҂Ɋ܂ނ悤�ɂȂ����B���Ȃ݂Ɂu����t���v�̖��͐l�C�G�t�E����t�͂�^���������́B�̂��ɑ}�G��k�ւ�̖��Ȃǂ̐l�C�G�t�����\�����肪���A�]�ˏo�ŊE�͑傢�ɗ��������B ���\���u�[���ō]�ˏo�ŊE�̃g�b�v�ɖ��o���،`�������q�ł��������A���N�āA�g�p�l������̔Ō��̖{�f�o�Łi�d�Łj�����߂ŕ�s�����由�����A���̔N�̋g�����i�K�C�h�u�b�N�j�s�ł��Ȃ��Ȃ����B�g�����͏o�ł���ΕK���q�b�g����g���̂Ȃ�h�ł��������߁A�،`�������q�͐M���ł���d�O�Y�ɐ�����ςˁA�o�Ō���^�����B�d�O�Y�͋g�����̔Ō��ƂȂ�H�Ɂg�Ӊ��Łh�̋g�����u�߁i�܂����j�̉ԁv�����s�B�]��������^�T�C�Y�œǂ݂₷���A�n�}�ƓX�̈ē�����̉��������B�ނ͉E���獶�֒��������铹�̏㉺�ɓX�����V���̖������݁i�㑤�͋t���܂̎��j�A�㉺�]�����ēǂ܂����B�������邱�ƂŁA�܂�Ŏ��������̗����̓X�߂Ȃ���g��������Ă���悤�ȋC���ɂȂ�A�傢�ɐl�C���A��Ԃ悤�ɔ��ꂽ�B ���s�߁i�܂����j�̉ԁt�@https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100388821/1?ln=ja �g�����̐���Ɏ艞�����d�O�Y�́A�{�i�I�ɔŌ��Ƃ��Ċ����̏���L���Ă����B���̔N�A�V���]���L�u�}�Y�Ԃ̖���v�i�k�������j�A���{�u���������Ȃ��v�i�ӓ��ۏ��A�������o��j�����s�B
1776�N�i26�j�d�O���͔N�n�ɗV����150�l�̎l�G�̎p�G�i�|�[�g���[�g�j�ƗV���̎��M�̔o�~��g�ݍ��킹�����F���荋�؊G�{�i��W�j�s�O���l���p���i�����낤�т��킹�����������݁j�t�i�����E�Ӊ��d�O�Y/��E����t�́A�k���d���j3���𑼂̔Ō��Ƌ������s����q�b�g����B���N�A�،`���͋g�����̏o�ł��ĊJ�ł������A�Ӊ��ŁE�g�����̏o�ł�������A���e�ŏ���Ӊ��ł��s���Ȋ������B ���������E������Y�I�����C���s�O���l���p���t�@https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/556070 ����250�N�O�̒Ӊ��̏��Ђ��A���������قɍs���Ȃ��Ă�����̃p�\�R���ŁA�����N���b�N�������Ō�����Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ�����ɐ����Ă��邱�Ƃ������B 1777�N�i27�j�،`���͌o�c�s�U�Ɋׂ�A�g�����̔Ō���Ӊ��ɏ������B���N�A�d�O�Y�͋g�����u�l�G�̑��v�v�A�g�����u�O�Â̍��F�v�����s�B�،`���ꑮ�̉��\���l�C��ƁE��������O��i�ق������ǂ��E�����j�͒Ӊ��Ɉڂ�A�̂��ɗ���t�����Ӊ��Ɉڂ����B �d�O���͕�������O��Ƒg��ŁA�V�s�ł̗V�т������������{�s���ܒn���L�t�i���傤�Ђ��肫�j�i��Җ��͓��֘O�����Ŕ��\�j��A�G�{�s�����]��t�i��������O�A����t����j�����s����B�܂��A��ڗ��E�x�{�i�Ƃ݂��Ɓj�߂̐��{�i���傤�ق�j�i���Ȃ̉̎����L�����{�j�̔Ō����s�v�w��֓z�����t�i�߂��Ƃ��������ʂȂ��Ȃ��j�i�̕���̕���̕\���G�E�k���������R�����`�j�����s���Ă���B�Ӊ��̓X�͋g���{�ƕx�{���{���Ŕ��i�Ƃ����B ���s�v�w��֓z�����t�@https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/assets/776aa936-f129-4747-9447-8cb7508f3ac0?pos=1 1778�N�i28�j1���A�،`�������q�̐g�������f�d�Łi���������̔Ō��̖{�̊C���ŁH1775�N�̎����Ƃ͕ʁH����Ƃ��O��͏���̏d�łł͂Ȃ������H�Ƃɂ����v�����ł��j�̕s�ˎ����N�����āA�����q�͘A�����Ĕ������Ȃ����A�،`���̌o�c�̓K�^�K�^�ɂȂ�B�@�،`���̌o�c�������Ӊ��ɂ��e�����A���̔N�͋g������1�_�����o�ł����B 1779�N�i29�j���̔N���Ӊ��͋g����1�_�A���{2�_�����o�ł����B���͂���܂ŏ��^���{�ł����������̔N����G�{�i���Ăڂ�j�ƂȂ����B���̍��A�d�O���͋��̊E�̗Y�A�l���ԗǁi����̂�����/��c�쐤/1749-1823/����30�j���y���]�i�����炩���j�Əo��A2�N��ɐe�����Ȃ�B 1780�N�i30�j�d�O�Y�͓��N�Ɉꋓ15�_�����s���A�o�ŋƊE�ɑł��ďo��B�l�C��ƁE��������O��i�ق������ǂ��E�����j�̉��\���i���h�ɕx��l�����G�{�j��3�_�o�ł������Ƃ����������ɏo�ŋƂ��g�債�Ă����B�}�G�͖k���d���Ɉ˗������B���N�̉��\���s��쒆�ϕ��i��̂Ȃ�����Ȃ��́j�t�i��E���q����/��E�k�������j�́A�����G���̂��̎R�����`�̕M���ł���B���`�͂܂�19�i�I�j�ł��葁�n�̓V�˂������B ���R�����`�i1761-1816�j�c�]�ˌ���̋Y��ҁE�����G�t�B�{���A�␣��(���ނ�)�B�ʏ́A�����`���B�Z�����]�ˏ�g�t�R�̓����ɓ�����̂ŎR�����A�܂��A�����ɋ߂��̂ŋ��`�ƍ������B�]�ː��܂�B���ߖk���d���ɕ����G���w�іk������(�܂��̂�)�ƍ����A���\���̑}�G�𒆐S�ɔ��l��Ȃǂ���|����B�̂���ƂƂȂ�A���\���E�����{��҂Ƃ��Ė������B���ɉ��\���u�䑶������(�����̂��傤������)�v�u�]�ː����C����(���ǂ��܂ꂤ�킫�̂��₫)�v�A�ǖ{�u���P�S�`�������v�u�̘b(�ނ���������)��ȕ\���v�A�����{�u�ʌ�����(�������܂���)�v�ȂǁB 1781�N�i�V�����N�j(31��)���̃u�[���ƂȂ�A�d�O�Y�͓����̋��́E�Y��E�̒��S�I�l���A��c�쐤�i�Ȃ�ہj�̒m���āA���́E�Y��d�̍ːl�Ɛe����[�߂�B��������O��E�R�����`�E��y���]�E����t���E�X�����ǂ�Ɛe����[�߁A�������̋Y��⋶�̖{�����s���Ă����B ���N�A���\���s�j�ĕs��/���V�����t�i�����܂܂Ȃ��/��̂����Ȃ��j�����s�A��҂͕�������O��̗B��̏������E�T�V�i���䂤�j�A��͂Ȃ�ƘZ�啂���G�t�̂ЂƂ蒹�������i����29�j�I ���s�j�ĕs��/���V�����t�@https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100053558/14?ln=ja �����������i1752-1815�j�c�����h�l��ړ���ɂ��Ē����h�̑�\�I�ȊG�t�B�u�]�˂̃��B�[�i�X�v�ƌĂ�锪���g�̔��l�悪�����B�F�N�₩�ȁg�ъG�h��n�n������؏t�M���͂��߂Ƃ����A�̖��E�ʊy�E�k�ցE�L�d�ƕ��ԘZ�啂���G�t�̈�l�ŁA�t�M�Ɖ̖��ɋ��܂ꂽ�V���N�ԁi1781-1789�j�Ɋ����B���͊��B���������̖�Ɋw�сA���߂͒������̖��ҊG��`�������A����ɔ��l��Ɉڂ�A�唻�̋ъG�Œ��g�̔��l�敗�������B����Ȑ��`�ɂ��Ɠ��Ȕ��l��ňꐢ���r�����B���ۂ̍]�˕��i����l��̔w�i�ɁA�ʎ��I�ɕ`�����̂͐��������Ƃ����B��\��u�������V��(�ӂ����������܂̂ɂ���)�v�ȂǁB63�ő��E�B�揊�͗����̉���@�B�@���͒��щp�����m�B��͒n�k���ЂŎ���ꂽ��2013�N�ɉ�Ƃ���������u������v���������ꂽ�B ����c�쐤�i�Ȃ�ہA1749-1823�j�c�V�������\���镶�l�E���̎t�ł���A���\���A���m�{�Ƒ��ʂȃW�������Ŋ���B�x�z����܂ŏ��l�߂����{�����ł�����B�����A�l���ԗǁB�ʍ��A冎R�l�B�@���͈ljԉ��S����x�B���ߋk�F�E��y���]�Ƌ��ɋ��̎O��Ƃƌ�����B 1782�N�i32�j�ϐ����w�Ȗ{�̊��s���J�n�B����t���i����38�j�̋L�^�ɂ��ƁA���N���ɏd�O�Y�̉ƂɊ������̍�ƁE���̎t�E�G�t���W�܂�A����t���A�l���ԗǁi��c�쐤�A����33�j�A�k�������i1761-1816/����21�j�A�k�������i1764-1824/����18�j��݂�Ȃŋg���̋W�O�J��o���ėV���A�N���̖k���d���i1739-1820/����43�j�͋g���ɍs�����ɋA����Ƃ����B�������A�����ƔN��̋��̎t�E���ۖԁi���Ƃ̂�������/ 1724-1811/����58�j�͍s�����悤���B 1783�N�i�V��3�N�j�i33�j�����K�C�h�u�b�N�̋g�������Ӊ��̓Ɛ�̔��ƂȂ�B���t�ɔ��s�����u�ܗt�̏��v�V���[�Y�́A�������������O��A�㏑�����l���ԗǁi��c�쐤�j�A�j���̌��t��V�����̎l�V���̈�l�E��y���]�i�����炩���j�������ȂǁA�����̗L���l���ꓰ�ɉ�b����ĂB�H�Ɉꗬ�Ō������ԍ]�˂̈ꓙ�n�A���{���ʖ���(�Ƃ��肠�Ԃ�܂�)�i����`�n���������w�̖k���j�ɒn�{�≮(���ق�Ƃ��)�̍k�����E�{�X���\����B�ʖ����̓X�A���ꂪ���ꗬ�̓X�܂̏������B�ނ͕ʂ�Ă������ƕ���ĂъA�ꏏ�ɕ�炵�Đe�F�s�������B ���N�����A��c�쐤�ҁw���ځi�܂��j���̏W�x�i�g��ژa�̏W�h�̃p���f�B�j��{�����ɔ������s�������Ƃŋ��̂������I�ɗ��s����ƁA�d�O�Y�͋��̈��D�Ƃ̃O���[�v�u���̘A�v�Ɂg�ӓ��ہh(���̂���܂�)�̖̉��ŎQ�����A�Q���҂Ɏ��M���˗�����Ȃǐl�����L���Ă������B�����āu�Ӊ��v�����̎t�E�Y��҂Ɋ����̏�i���Ёj��p�ӂ��邱�ƂŁA�V���N�Ԃ̗D�ꂽ�Y��E���̂𐢂ɑ���o�����B�ނ͋��̘A�Œm�荇������c�쐤�����t���Ȃǂ̋Y��҂�������Ƃ��ĉ��\���⟭���{���o�ł��A���̑}�G�Ɏ��E�����̊G�t������ϋɓI�ɋN�p�����B�������Ēӏd�́A�]�˂̃��f�B�A�̒����ƂȂ����B ���̌���ϋɓI�Ɏ��Ƃ�W�J���A�����ō��̍�ҎR�����`�����t���瑽���̐l�C��Ƃ̍�i����舵���A�x�X�g�Z���[�����X�Ɋ��s���Ă����B�c������̊J���I�ȋC���̒��ŏo�ŋƗ����̈ꗃ��S�����B ���̔N�A�Y��ҁE�����Q�a�i�Ƃ��炢����ȁ��d�O�Y�Ƌ`�Z��̌_������ԁj�i1744-1810�j��̟����{�s�ʐ_�E��/�O���F�t�i���������Ⴍ/���傤�����j�����s�A��͓���30����̊쑽��̖��i1753�H-1806�j���S�������B�Ȍ���̖��͒ӏd�̏o�ŕ��ɂ��т��ё}�G��`���Ă���B ���N�A��ԎR���啬�����B�O�N����̗�Q�ŋ�����d�Ȃ�u�V���̑�Q�[�v�i1782-88�j�ɔ��W�A��30���l���쎀����B ���쑽��̖��i1753�H-1806�j�c�]�ˌ���̕����G�t�B�쑽��h�̑c�B�{���A�k��E���B���R�Ή�(��������)�Ɋw�сA���ߖL��(�Ƃ悠��)�Ə̂����B�ӏd�Ƒg��ŁA�G�����̖{����l��̕���Ŋ���B���ɋъG�ɂ����Ĕ��l���G(�������т�)�̗l����n�āA����Ȑl�C�������G�̉��������������B�㐢�̔��l��ɑ傫�ȉe����^����B��\��u�����S�����l���v�u�������v�v�ȂǁB 1784�N�i34�j8�N�O�́s�O���l���p���t�ɑ����A���̍ŐV�łƂ���������l�G�{�s�g���X��@�V���l�����M���t�i�悵��炯������ ����т��킹���Ђ����݁j�����s�B�G�t�͑O��́g����t�́A�k���d���h�ł͂Ȃ��A23�̐V�i��ƁA�k�������i�܂��̂�/�R�����`�j�Ɉ˗������B�����̖͗l��w�i�̒u���܂Ő����ɕ`���ꂽ�����̉�W�ł���A�����G�t�Ƃ��Ă̖k�������̑�\��ƂȂ����B ���s�g���X��@�V���l�����M���t�@https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/217597 �P�V�W�T�N�i�R�T�j�k�������i�捆�j���R�����`�̖��ʼn��\���̒��슈�����J�n�A�����̍�i�ő}�G������肪�����B 1786�N�i36�j����̋��̎t��k���������S�l��ɕ`���A�E�B�b�g�ɕx�̂����߂��w�V���V��\�l���@��ȋȋ��̕��Ɂi�����܂Ԃ肫�傤���Ԃj�x�����s�B���N�A10�㏫�R�E�Ǝ������E���đ�11�㏫�R�E����ƐĂ̑�ƂȂ�B �|�|�|�|�| 1787�N�i37�j�������Q�[�ɂ�薯�O�͊e�n�ňꝄ��ł����n�߂��B���̍��������߂�ׂ��A����g�@�̑��ŗ���(�ނ�)���͔ˎ�E������M���A�˓��ʼn쎀�҂��o���Ȃ��������т������ĘV������ƂȂ�B��M�͓c���ӎ�����ɐ[�܂������ˑ̐��̊�@�����낤�Ɛ����̈�V���͂���A�U�N�Ԃɋy�ԁg�����̉��v�h���X�^�[�g����B��Ȑ���͌���߁E���o(������)�߁E�������ϗ��E�l�Ԃ��E�l�����E�يw�̋ւȂǁB�Q�[�ō]�˂ɐl���W�܂�_�����K���K���ɂȂ������߁A��M�́u����ł͕Ă����҂����Ȃ��v�ƁA�_����c���ɋA�����Ƃ����B�h���I�Ȍ�y������Ɣ_�����]�˂��痣��Ȃ��̂ŁA�]�˂̖��͂��킮���߁A��y���܂ޕ��I���������������Ă������B ���̂��́u�V�ۂ̉��v�v�i1841�`43�j�ł́A���쒉�M���ŋ��������x�O�̐ɋ����ړ]��������A��Ȃ������ȂǁA����Ɍ����������̌�y���K���B 1788�N�i38�j2�N�O�́g�\�l���h�̑��ҁw�V���V��S�l���@�Í����̑܁i�����傤���Ԃ���j�x�����s�B ���s�Í����̑܁t�����̉���t���i�G�o��������̈̋Ɓj�@http://ezoushi.g2.xrea.com/kokonkyoukafukuro.html 1789�N�i39�j�����̉��v�h�����Ӊ��̉��\���s�_���ԕ����i�����ނ������Ԃ�Ԃ̂ӂ��݂��j�t�i��E����t���A��E�k�������j����q�b�g���邪�A����t����45�ŋ}������B���O�ɖ��{����o�����߂��o�Ă������߁A�u�t���͎��������v�Ƃ����\�����ꂽ�B�܂��l���ԗǁi��c�쐤�j�͎���ł͂Ȃ����́i��M�h�j���ނ̍�i�Ɖ\�������A�g�̊댯�������ċ��̂�f�M����B 1790�N�i40�j���{�ւ̔ᔻ�╗���𗐂��o�ŕ��������܂�u�o�œ����߁v���o����A�o�ŕ��ɂ͔Ō��̎������L�����Ƃ����߂�ꂽ�B�o�œ����߂ł́u���̕����𗐂����i�݂��j��ȓ��e�̂��́v�u�Â�������Č���h������́v�u�����̂Ȃ��\�v�A����炷�ׂĂ��֎~���ꂽ�B�ǂ�����Ώ������y���܂����i���o����̂��d�O�Y�͋Y��҂̎R�����`�ɑ��k�B���`�͗V���̎��_�Ń��A���ȏ������������Ƃ��Ă����B 1791�N�i41�j�����A�V�s��ɂ����R�����`���s�єV���t�i�ɂ����̂���j�������r�[�A�d�O�Y�͕�s���ɓE�������ł𖽂�����B�V�s��Ƃ����������o�ł������Ǝ��̂��֗߈ᔽ�Ƃ��ꂽ�B���`�͕��I�ᔽ�̍߂Ŏ荽�܁Z���̌Y�ƂȂ�A�Ō��̏d�O�Y���o�ł�����(�Ƃ�)�ō��Y�̔�����v�������g�g�㔼���h�ƂȂ�i�]���͑S���Y�̔����Ƃ���Ă������A�Ӊ��̔����z�̊���u�g��i�S���Y�j�v�Ƃ��铯����j���͌������Ă��炸�A�������́u�g��i�N���j�v�̔����Ƃ��j�B�d�O�Y�͖��{���o�œ����́g�������߁h�Ƃ��đ��ʂɂ�����قǂ̑��݂ɂȂ��Ă����B �����d�O�Y�̏o�ł̏�M�͏������A���J����A�R�����`���̉��\���s�������ʉ��l���t�i�͂�����ނ��߂߂��ɂ傤�j�����s���A�`���ɏd�O�Y������������ё���œo��A�g�ӔC�͂��ׂĎ����ɂ���h�Ƃ��Ď��̌��t��Y�����B�u��҂̋��`�͏������ꂽ���ƂŕM��܂���肾�����̂ɁA���������������ď������܂����v�B���̏ё���́A�㐢�ɒӉ��d�O�Y�̕��e��`����M�d�Ȃ��̂ƂȂ����B��͂Q�Q�̏���̐�L���Ɉ˗������B�Ȍ�A�L���͈�h�𗦂���啨�ɂȂ��Ă����B ���̐�L���i����j�i1769-1825�j�c�̐�h�̑c�E�̐�L�t�i1735-1814�j�Ɏt���B���͈�z�ցB���l�悩����ҊG�ɓ]���ĉ̐�h�Ɠ��̎���G���J�A�������i1789-1801�j�Ɉꐢ���r�B�ʊy�͖��҂̏㔼�g���N���[�Y�A�b�v���Ďʎ��I�ɏё���̂悤�ɕ`�������A�L���͖��҂��������悭�\�����悤�ƃt�@�����]�ޖ��҂̑S�g�̎p��`�����B����E���F�ȂǑ����̒�q����āA�̐�h�̗����ɍv�������B �d�O�Y�̏����͑啝�ȏk����]�V�Ȃ����ꂽ���A�g�g�㔼���h�ł��������_�͌��݁A�V���ɕ����G�̃W�������ɎQ�����Ă������B�d�O�Y�͓���̊G�t�̒��ł��A�Q���ώ@�͂ʼnԒ��⍩����`�ʂ��Ă����쑽��̖��̍˂ɍ��ꍞ�݁A�u���̉�͂Ŕ��l���`���ǂ��Ȃ邩�v�ƊG���˗������B�̖������ݏo�����̂͏㔼�g���A�b�v���ĕ`�����u���l���i�������сj�G�v�B���������ȂǏ]���̔��l��͑S�g��`���Ă������߁A�]�˂̐l�X�͎a�V�ȑ��G�ɋ������B����҂ɕ\������Ă��đ��Â����܂œ`���悤�������B������_�̊v���́A���l��ɕ`�������f�����g���̉Ԋ@�i�������j�����łȂ��A���̈�ʏ������`�������ƁB���N�́s��g���������t�ł͐E�i�����j���̒��X�œ�������`�����B�g���ɂ͊ȒP�ɍs���Ȃ����A����������Ȃ�C�y�ɍs���邽�߁A�s��g���������t�́g��ɍs����A�C�h���h�ƂȂ����i�̖��͂�������15�_���`���Ă���j�B�̖��̔��l���G�͑�q�b�g�����B ����1791�N���A�Ӊ��͏���t�N�i�����낤�A�̂��̊����k��/����31�j�ɂ�錹������u��m�J�̐킢�v�̕��ҊG�i�����G�j�s���������i�G�t�i������炰���������j���o�ł��Ă���B ���k�ւ͏���t�N������܂߁A�d�O���̐��O�ɖ�80�_�A�v����܂߂�ƒӉ��k�����ł��v250�_�߂����삵�Ă���悤���B 1792�N�i42�j�d�O���͑}�G�ɏ���t�N�i�k�ցj�F���A�u��E�R�����`�A��E�t�N�v�R���r�ɂ��2��A���\���s�����Y���[�b���t�i�������낤�ق�����Ȃ��j�Ɓs���ꋳ�t�u�߁t�i�������傤�����Ȃ������Ⴍ�j�����s����B �O�҂́u�����Y�̑O���͐�萝�v�Ƃ����b�A��҂́u�q�ǂ��D���̐搶�����P�b������v�Ƃ������́B��҂͍�Җ������`�����A���ۂɑ唼���������͔̂n�Ղ炵���i�n�Ֆ{�l�k�j�B ���N�A�Ȓ��n�Ղ̕��˂������d�O�Y�͖{���̎��i�Ă���/�ԓ��ƒ��t�̊ԁA���̌W���j�Ƃ��Čق��Ă���B ���s�����Y���[�b���t�@https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100093609/19?ln=ja 1793�N�i�����T�N�j�i43�j�Ӊ��͉̖��̑�\��s�����O���l�t�i�����O���l�j���o�ŁB��ڗ��̖���A���݁i����ׂ��j���̖��A�������̖���3�����`���ꂽ�B�A�C�h���u�[�����ߔM����Ȃ��A�J�ł́u���I�𗐂��Ƃ��Ė��{���Ӊ��ɍĂѐ��ق��ۂ��v�Ɖ\���ꂽ�B��x���g�g�㔼���h�����炤�ƓX�������Ȃ��B�d�O�Y�͓X�̑�����D�悵�A���G���烂�f���̖��O���폜�����B�����A�̖��͂���ɔ[�������A�ʂ̔Ō��i�ߍ]���j���烂�f���̖��O���c�̍�c��ڂ̊G�ȂǂňÎ����ďo�ł����B����́g�����G�h�ƌĂ�A�u�ؓ�c�v�E�u��v�E�u���v�E�u�c�v�Łu�Ȃɂ�₨�����v�Ɠǂ܂����B���̈ꌏ����̖��͒Ӊ��̂������G�t�łȂ��Ȃ�A���̔Ō��̎d������悤�ɂȂ�B ���N�A������M�����r���Ċ����̉��v���I���ƁA����܂ŋ��s��~�ɒǂ����܂�Ă����ŋ����������𐁂��Ԃ��Ă����B���̍��A�d�O���͓����܂����������̊G�t�A���F�֎ʊy�Əo��A���̌��I�Ȑl���\���Ɋ��Q�B���ҊG�̐l�C���Ăт���Ɨ\�z�����d�O���́A���ҊG�Ŏʊy�𐢂ɏo�����߂̑�v���W�F�N�g�Ɏ��|�������B ���̔N�A�Ȓ��n�Ձi�����Q�U�j�҂ɔ��F������{�i�͂Ȃ��ڂ��b�W�j�s�Ε{�ܗ��āt�i���Ƃ��Ȃ����肽�����߁j���A�k�������̉�Ő��ɏo���B�܂��A�����̍�ƁE�\�ԎɈ��i����29�j������Ɋ�H�����Ă���B���Ɂu��E�R�����`�A��E�t�N�v��3��ځA���\���s�n���������V�L�t�i�Ђ�Ղ���傤�ǂ����イ�̂��j�����s�B���̔N�A�d�O�Y�����������ɑg�G�t�E����t�͂�67�ő��E�B ���Ȓ��n�Ձi1767-1848�j�c�]�ˌ���̋Y��ҁB�{�����B���͉�(�Ƃ���)�B�]�ː[��̐���B�R�����`�Ɏt�����ĉ��\���⍇���Ȃǂ��A���ɓǖ{�ɂ����ꂽ��i�������B1791�N�ɂQ�S�ŔŌ��E�a�s���q���物�\���u�s�p������(�����͂����ĂɂԂ��傤����)�v�\�B�Ȍ�A���P��������{���O�ɁA�Y��ȍ\�z�ƕ��G�ȋؗ��Ă̑����A�둭�ܒ��i�������������イ�j�̗���ȕ��̂Œ������B����(��������)�E�ǖ{(��݂ق�)�𑱁X���\���A�ӔN�A���͂������Ȃ���28�N���₵�āu�쑍���������`�v�������B���u��(����)�|�����v�u�r���m�s������v�u�ߐ��������N�^�v�ȂǁB 1794�N�T���i44�j�d�O�Y�͎ʊy���`�������ҊG28�����u���������v���Đl�X�����������B���̃V���[�Y�͐l���������o�Č�����悤�w�i�̍��ɉ_�ꐠ�i���炸��j���{�������؎d�l�ł���A��x��28�������\���邽�ߏ[���ȏ������Ԃ��������B��_���I�݂Ƀf�t�H�����i�֒��j���ꂽ���ҊG�́A����\���𗘂���������Ȍ��`�ʂ������āA�]�˂��q�̊Ԃő傫�Șb����ĂԁB���N�ɂ�����10�J���Ŗ�P�S�O����̖��Ҏ���G�Ə����̑��o�G�����X�ɔ��\�����B�����A�u�[����1�N�Ƒ������A�ʊy�̔���o���Ɏ��s�����B��c�쐤�͂����L�����B�u�i�ʊy�́j���܂�ɐ^��������ƂāA����ʂ��܂ɂ����Ȃ������i�����Ă͂Ȃ�ʂ悤�ɕ`�����̂Łj�A�������ɍs�͂ꂸ�v�i�����G�ލl�j�B�Z�������̂܂ܕ`�����ʊy�̊G�́A���҂ɔ������߂��]�˂��q�����߂��G�ł͂Ȃ������B�d�O�Y�����ǂ��Ŏʊy�ƒm�荇�����̂��������Ă��Ȃ����A�ʊy�̐��͓̂����ˎ�E�I�{�ꎁ�̂������\���ҁA�֓��\�Y���q�Ɠ`��������L�͂��B ���N�A��E�R�����`�A��E�\�ԎɈ��̉��\���s�������G�X�q���t�i�͂₭�����˂̂��ڂ������j�����s�B�܂��A�Ȓ��n�ՂƏ���t�N�i�k�ցj�����^�b�O�ƂȂ鉩�\���s�����C���ʕi�ʁt�i�ӂ����ォ���ނ�傤�̂��Ȃ��܁j�����s���Ă���B ���s�������G�X�q���t���̉�@https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100053834/15?ln=ja ���s�����C���ʕi�ʁt�n�ՁE�k�֖��̃^�b�O�@https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100053614/1?ln=ja 1795�N�i45�j�d�O�Y�͈��ɕM����邱�Ƃ����߁A��オ���Ɖ�̗�����S���������\���s�S�w���v���t���o�ł��ꂽ�B����Ȍ�A����20�N�ȏ���y�������郍���O�Z���[��ƂƂȂ����B���͓��{�j��A���M�Ƃ����Ő��������ŏ��̃v����ƂƂȂ�B�@ ���ʊy�𐢂ɏo���A�n�ՂƖk�ւ�g�܂��Ă���R�N��A1797�N5��31���i����9�N5��6���j�ɏd�O�Y�͋r�C�ɂ��47�Ől�����I�����B�ՏI�O�u���͍����̒����ɂ͎��ʂ�v�Ɨ\�������̂ɒ��ɂȂ����̂ŁA�u������������Ĕ��q�����Ă������̂ɁA�����Ԃ�x���ȁv�Ə����Ƃ����B�[���ɑ��E�B �v��A�u�Ӊ��d�O�Y�v�̖��Ə��X�u�k�����v�͔ԓ��̗E���i2��ځj���p���B ��1798�N�A�u�Ӊ��v���o�ł����G�����̖{�s�j���́i���Ƃ��Ƃ����j�t�̉��38�̊����k�ւ��A�k���d����ƎQ�����Ă���B ���s�j���́t�k�֒S����@https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/461359 �������k�ցi1760-1849�j�c�]�ˌ���̕����G�t�B�]�ː��܂�B���ߏ���t�̖͂�ɓ���A�t�N�ƍ����A�̂��@���E�拶�l�E�Փl�E��(������)�E�ȂǁA�敗�Ƌ��ɉ捆��ς����B���h�E�y���h�E���m��Ȃǂ������Z���w�сA��z�����`�ʗ͂Ƒ�_�ȍ\���ŕ��i�ʼn�ɐV���Ȗ��͂𐁂����B�ʼn�ł͕��i���Ԓ���A���M��ł͔��l��═�ҊG�Ɍ��삪�����A�u�k�֖���v�Ȃǂ̊G��{��ǖ{�̑}�G�ɂ��G����c���Ă���B�k�ւ̉敗�̓��[���b�p��۔h�̔����ɑ傫�ȉe����^�����B��\��u�x�ԎO�\�Z�i�v�u�k�֖���v�ȂǁB �����{�A���\���A���̖{�A�G�{�A�ъG���肪���A�u�Ӊ��v���]�ˋ��w�̒n�{�≮�ɐ����������d�O���B�ނ̂悤�Ɋ��͂ƍs���͂̂���l�ԂɂƂ��ĂS�V�N�̐l���͒Z���������B���̌�ɑ劈��R�����`�A�\�ԎɈ��A�Ȓ��n�ՁA�����k�ւ̎p�������Ă��������������A�ނ�̍˔\���m�M���Ă����ނɂ͊��Ɍ����Ă����̂����B ����̋�C���s�����ݎ���ď����Ɋ������A���͓I�Ȋ������X�Ƒł��o�����Ӊ��d�O�Y�B���̊������1773�N�i23�j����1797�N��47�ő��E����܂ł̖�25�N�����A���̊Ԃ�800�_�ȏ���o�ł����B�������\����G�t�E�Y��ҁE���̎t��ƌ𗬂��A���ɂ͐ϋɓI�Ɏx�����s���A�˔\��L���菕���������B�d�O�Y�͐V�l���@�̖��l�ł���A�삯�o���̍��̊쑽��̖��A�����k�ւɂ��������}�G���˗����A�R�����`�i�捆�E�k�������j�̉�˂ƕ��˂̗����������A�@�\���ҁE�֓��\�Y���q�̉�˂������o���āu���F�֎ʊy�v�ɑ剻���������B�ʊy�̕����G�ʼn�͂��ׂĒӉ������ɏo���Ă���A�̖��_�Ƃ������l��S���̕����G�E�ɁA�ʊy�̖��ҊG�ňꎞ���z�����B�ʊy�̊G�����̐��ɂ���̂͒Ӊ��̂��������B ���o���i�����������j�╂���G�̕]��������ŏo�ł����ӏd�̍k�����ɂ́A�p���f�B�̓V�ˁE��c�쐤��g���\���̕��h����t��������o���A�����O�̋Ȓ��n�Ղ����i�Ǘ��E�j�Ƃ��ē����A�\�ԎɈ�オ�Z�ݍ��݂ŎG������`���Ă���A18���I�㔼�i�]�˒����j�̍]�˕����̈�唭�M�n�ƂȂ��Ă����B �d�O���v�Q�N��1799�N�A�����k�ւ����̊G�{�w���V�i�����܂����сj�x�̑}�G�́s�G�����X�t�Łu�Ӊ��v�̓X���̗l�q��`���Ă���B�ӏd���������ދC�������������̂�������Ȃ��B ���E�T�N���1802�N�A2��ڂ͊����k�ւ̋��̖{�w�����i�������j���W�x���o�ł������A�u�������ؔ��v�Ƃ������Ƃŏ�������Ă��܂��B���N�A�\�ԎɈ�オ��\��w���C�����G�I�сx�����s����]���ƂȂ�B �v7�N��1804�N�A�쑽��̖��͏��R���������G��`���荽50���̏������Ă���B2�N��ɉ̖��͑��E�B �v10�N�A�k�ւ͔n�Ս�w���|�����i���� ��݂͂�Â��j�x�i1807-1811�j�Ȃǂ̓ǖ{�}�G�Ŗ{�i�I�Ƀu���C�N���A�������n�Ղ��������߂��B���ҊG�̎嗬�͒ӏd���d�p��������t�͂��z��������h����L����̉̐�h�ւƈڍs���Ă����B �v17�N��1814�N�A�Ȓ��n�Ղ��w�쑍���������`�x�����s����B �v64�N��1861�N�A4��ڒӉ��d�O�Y�͔Ō���p�Ƃ��A�Ӊ��k�����̒g�������낵���B�Ȃ������Ȃ����̂��A���m�ȋL�^���c���Ă��Ȃ��B�O�N�ɍ��c��O�̕ς��N���Ă���A�����7�N��̖����ېV�Ɍ����ċ}���ɕω����Ă����B �����̕�͑䓌�擌�̐��@���ɂ��������֓���k�ЂⓌ�����P�̔�Q�ɑ����������Ȃ��B��������̕����ɂ��ƈꑰ�̕������ł����悤�ŁA���͊����ɂ��ΐ��]�i�܂������j��́u�쑽��h���i����܂�j������v�Ƒ�c�쐤�ɂ��d�O�Y�́u���ꌰ���̔蕶�v���������Ƃ����B�@ ��×^�͊���4�N10��26���ɕa�����A�d�O�Y�͗��N�ɐ��@���ɂ�������𗧔h�ȕ�ɍ�蒼���A��c�쐤�ɗ���ŁA�蕶�������Ă�����Ă���B ���@���͓���ƍN���玛�̂�����A�����z�O��̕�ƂȂ����R�����鎛���B�{���͋�P�ŏ��������ɍČ����ꂽ�B�Ӊ��Ƃ̎q���͐₦�Ă��܂������A���̏Z�E�����������ɏd�O�Y�̕悪���������Ƃ�m��A����e�̕�����������B��i������R�Ԗڂɏd�O�Y�̉����u�H���@�`�R�����M�m�v�Ɩ��������܂�Ă���B�������̈⍜��[�߂��������ɂ���A����������Ƃ����ɏd�O�Y�̍��������Ă��邩���m��Ȃ��B �����Ȃ݂ɁA�䓌���HP�ɂ���500m�قǗ��ꂽ���ɂ��ʂ̕悪���������������A���Z�E�ɐq�˂Ă݂�Ƃ�������u�֓���k�Ђ̑�Ђŕ���Ă��Ă��܂��A�����̂ǂ��ɒӉ��������Ă���̂�������Ȃ��Ȃ����v�Ƃ̂��ƁB �����̎t�E�ΐ��]���킭�u�i�d�O�Y�́j�G�ꂽ�C���������A�x�ʂ��傫���ׂ������Ƃɂ�����炸�A�l�ɑ��Ă͐M�`�d����v ������M���Ƃ����T�{�̋Y���Ӊ�����o�ŁB ��2025�N�̑�̓h���}�w�ׂ�ڂ��`�ӏd�h�ؔT�����x�Ŏ�l���Ӊ��d�O�Y�����l������������B1995�N�̉f��w�ʊy�x�ł̓t�����L�[�䂪�A2021�N�̉f��wHOKUSAI�x�ł͈��������d�O�Y���������B ��1995�N�A�c���_�ēƃt�����L�[�䂪�f��w�ʊy�x�̃q�b�g���F�肵�ĕ�Q���Ă���B�Ӊ����������t�����L�[�䂢�킭�u�ǂ����Ă����ʂ܂łɂ��̖�����肽�������v�B���N�A�t�����L�[��͑��E�����B �������^������TSUTAYA�́A�n�Ǝ҂��u����̒Ӊ��ɂȂ肽���v�Ƃ����v���ŕt�������O�Ƃ����B��C��TUTAYA�̍D���x�A�b�v�I �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�| �s�Ӊ��d�O�Y���o�ł�ʂ��Đړ_�̂������l�X�t ���߉���E�q��i���E��������j�i���v�N�s�ځj�c�ӏd�ƕ��я̂��ꂽ�V�܂̔Ō��ŁA�����̑��o���A�ъG���o�ŁB�l�C�̉��\����ƁE�R�����`��3��ڒ߉����ӏd�Ǝ�肠�����B���Ƃ͋��s�̏����≮��16�U�O�N���ɍ]�˂i�o���A���̎x�X���Ɨ����ėL���̒n�{�≮�ɐ��������B�H��t��Ɏn�܂��āA�쑽��̖��A�̐�L�d�A�̐썑��ȂǑ�\�I�ȕ����G�t�̍�i�𑽂��o�ŁB�X�܁u��ߓ��v��1829�N�́u�����̑�v�ŗޏĂ������A���N����1842�N�ɂ����ċY��ҁE������F�i��イ�Ă��E���˂Ђ�/1783-1842�j��́s�i�ɂ��ނ炳���j�c�Ɍ����t�i��E����j���o�ŁA�{��ł͕������������ֈڂ��A���R�����`���̏����̎q�E��������l���Ƃ����B���ꂪ�]�ˎ���ő�̃x�X�g�Z���[�ƂȂ�A��i�̃L�����N�^�[�O�b�Y���o���قǂ��������A�V�ۂ̉��v�ɂ��e������ŏ����ƂȂ�A�ȍ~�͐��ނɌ������B���̊ԁA1833�N�ɉ̐�L�d�́w���C���\�O���x�S55�}��V���̔Ō��E�ۉi���Əo�ł��邪�A���N�ɒ߉���l���}���A���N�̑�ЂœX�܂��R���A�ȍ~�w���C���\�O���x�V���[�Y�͕ۉi���̒P�Əo�łƂȂ����B�߉���E�q���3��ڂ܂ő����A������F���E�̐�L���G�́w�����`�Z�������x��1847�N�̃h�C�c������ɉp�ɕ��o�ł���A���ĂŖ|�ꂽ�ŏ����̓��{���w�ƂȂ�B������F��1842�N�ɘV�����쒉�M�ɂ��V�ۂ̉��v�̈�ł��镗�������܂�ɂ�肯��ӂ��A�Ԃ��Ȃ��v�������߁A14�N�ɂ킽���ď����p���ꂽ�s�i�ɂ��ނ炳���j�c�Ɍ����t�͑�38�ҁi152���j�Ŗ����ƂȂ����B��F�̕�͐ԍ�̏�y������i��̏�y����n�ɉ������ꂽ�B ���،`�������q�i���낱������E�܂��ׂ��j�i���v�N�s�ځj�c�]�˂̑��̒n�{�≮�u�ߗؓ��i�������ǂ��j�v��3��ڎ�l�B����̗،`�������q�i���ւ��j�͋g���̗V���]���L�����s�A2��ڂ̎O���q��́g�����G�̑c�h�H��t��i����̂ԁj�̑}�G����{�𐢂ɏo���ĕ]���ɁB3��ڂ̑����q�͏���ŗ��s���Ă����������q�i�����悼����/���l���w�j�̍]�˂ł̔̔����̓Ɛ�ɐ����B�܂��A�����q�͋g���̗V����X���Љ��l�C�K�C�h�u�b�N�u�g�����i��������j�v�̏o�ł��Ɛ��Ԃ��������A�s�ˎ��ɂ��3��ڂŖv������B ���������^���i���v�N�s�ځj�c�ӏd�A�ߊ�ƂƂ��ɓV���������̑�\�I�ȕ����G�̔Ō��ŁA�n�Ɂu�i�����v���\���A���������̍�i���ł������o�ŁB���l��𐧂��Ă����������ɑ��āA�ӏd�͉̖��A�ʊy��o���đR����B����ɐ������͉̐�L���Ⓓ���։h�V�A�̐썑����N�p���邱�ƂŌ}�������A���l��A���ҊG�̉��ł��葱�����B�̖��̍�i���o���Ă���A�ӏd�Ɖ̖�����肠�����B2��ڂ͗،`�������q�̎��j�Ŗ��{�q�B3��ڂ��L�\�ŁA�ӏd�v��ɖk�ւ̕��i��ɒ��ڂ��ās�y�ԎO�\�Z�i�t�����s�������G���i��̊m���ɍv���B�̐�L�d�̉Ԓ���ɂ����g�B ���{�����Ε��q�i���͂��E���ւ��j�Ɛ{�����s���q�c�{�����͒Ӊ��d�O�Y�ƕ��ԍ]�ˎ���̑�\�I�ȏo�ŋƎҁB�ƍ��͐���[�B����{�����Ε��q�i���v�N�s���j�͋I�ɍ��E����(���͂�)���o�g�B�]�˂ɏo�Ė������N�i1658�N�j���{���ɓX���\�����B�����ās���Ӂt�i�N�ӌ`���̐a�m�^�j��s�]�ˊG�}�t�i�n�}�j���̌��I�o�ŕ��𑽂��肪���č]�ˏo�ŋƊE�̍ő��ƂȂ�A�s���i�������́j���o�����Ӊ��d�O�Y�Ƃ̑Δ�Łu�g���͏d�O�A�Ε��q�͊ۂ̓��v�Ɖr�܂ꂽ�B1660�N�����疾���܂�9�㑱���B��������ŌÂ̊��{��1684�N���̖؉��`�r���̕��@���w���p�ٗ��i�Ԃ悤�ׂ��Ⴍ�j�x�B�l��ڂ͋��s�Ɏd����X���o���Ȃnjo�c�g��ɓw�߂����A�v��͏o�ŕs���ňꎞ���ށB����ږL�i1776-1838�j���s���Ӂt�o�Ō��̓Ɛ�ɐ������A�ċ��𐋂����B�����ɓ���Ɓw�����������x�i����j�Ȃnj��I�o�ŕ���C����ꂽ��1904�N�p�ƁB ���̒g�������X�i���Ɓj�̈�A�{�����s���q�i���͂�₢���ׂ��j�͌��h�ŁA���w�҂̔Ō��Ƃ��ĕ��ꌹ���A���̖�l�̐X�����ǁi���イ��傤�j��̒����A����E���c�����̗��w�������s����ȂǁA�����Ƃ��Ċv�V�I�ȏ����𑽂��肪�����B�s���q��1762�N�ɍ]�˓��{���ɊJ�ƁA1774�N�ɖ��{�̒e��������Ȃ�������w���w��̐V���x���o���B����s���q��1779�N�ɖv�B����13�N��A���ڂ͗юq�����w�O���ʗ��}���x�����{�Ɍ���߂��A��łɂȂ�Ŗؖv���y�яd�ߗ��̏������������B1806�N�̕����̑�Ŕ�Ђ��A�y���������Ȃ��������ߑ傫�ȑŌ�����B�P�W�O�W�N�́w�O���S�`��h���x�i�Ȓ��n�Ձj���Ō�ɒP�Əo�ł��r�₦�A1811�N�ɓ��ڂ��������Ă���͋����o�ł݂̂Ɍg������B�揊�͐̑P�����B ���{�����̂悤�ɍd�h�ȏ����≮�́u���сv�Ƃ��Ă�A1685�N�̋��̈ē����ɂ͋��s���я\�N�Ƃ��āA�̏��A�@�؏��A��㏑�A���֏��A�T���A�^�����A����@�A�w�{�ȂǕ���ʂɒ����ȏ����≮���L����Ă���B1721�N�ɂ͏��R����g�@�̖������剪�����ɂ����46���̖≮�ɂ�鏑���≮���Ԃ��������ꂽ�i1851�N�ɂ�73���j�B���N�́u�ДN�̋֗߁v�Ō��{���n�܂�B ���k���d���i1739-1820�j�c�����G�t�B�k���h�̑c�B��q�ɖk�������i�R�����`�j�������ق��A�Ⴋ���̊쑽��̖����q�̂悤�ɖʓ|�������B ���L�`���ցi���킪�� ���������j/�k�������i�܂��悵�j�i1764-1824�j�c�����G�t�B�k���d���̖�l�B���g�́u���掮�v�Ⓓ�Ոꗗ�}���A�k�ւɁu�k�֖���v��u���C�������ꗗ�v�u�ؑ]�����ꗗ�v���ŏ���Ɉ��p���ꕮ�S�A�u�k�ւ͂Ƃ����l�̐^�����Ȃ��B���ł��Ȃ��n�߂��邱�ƂȂ��v�ƋL�^�B ���ΐ��]�i�܂�����/1754-1830�j�c�Ӊ��d�O�Y�̕����̐��S���B���l�i�h���̎�l�j�ł���A���̎t�A���w�ҁB���s���^��E�K�������E�����Ƌ��Ɂu���̎l�V���v�Ə̂����B�{���͍f�������q�i�ʂ���E�����ׂ��j�B�����͏h���ѐ��i��ǂ�� �߂�����j�B��c�쐤�̂��ƂŊw�сA�Ӊ��d�O�Y�Ƒg��Ŋ��s�����w��ȋȋ��̕��Ɂx�i1786�N�A�k��������j��w�Í����̑܁x�i1787�N�A�k��������j�A�w��{����x�i1787�N�쑽��̖���j�Ȃǂ̋��̊G�{�̊��s�ɂ���āA���̎t�̒n�ʂ�s���Ƃ����B�ƋƂɊւ���l�߂ɂ���āA37����20�N�قNj��̊E����ނ��B���A��A���s���^��Ƌ��̊E������B76�Ŗv�B �|�|�|�|�| �������G�c1680�N�O��ɁA�V������҂Ȃǂ�`���G��Ɂu�����G�v�Ƃ������t���͂��߂ēo�ꂷ��B�����͓������A���y�I�Ȃǂ̈Ӗ������߂��u�����v�̌���������t�����s���Ă����B�����̕����G�͔��l�����ҊG�̐l����ŁA���I�ȊG�͖��G(�܂��炦)�ƌĂꂽ�B�����͖n��(���݂���)�ƌĂ�锒���ʼn�ŁA���Ƃ���M�ōʐF��������ꂽ���̂́A�O�G(����)��g�G(�ׂɂ�)�ƌĂꂽ�B �H��t��i����̂ԁj�i1618?-1694�j�͕H��h�̑c�B�u�����G�̑c�v�Ə̂���A����܂ŊG���{�̒P�Ȃ�g�}�G�h�ł����Ȃ����������G�ʼn���A�ӏ܂Ɋ�������Ɨ������ꖇ�̊G���i�ɂ܂ō��߂��B�Ŗ{�̑}�G��ƂƂ��Ċ�����͂��߁A����͖��L������1671�N���s�̔��{�u������v�i�����j�܂������G���҂ł���Ƃ���A1672�N�̖n���G�{�u���ƕS�l���v�ɂ����Ă��̖��O�i�G�t�@�H��g���q�j�𖾂炩�ɂ����B�u�����S�l�����v�i���s�N���s���j�A1682�N���u�������v�A1683�N���u���l�G�Â����v�ȂǂɎs��̏�������`�ʂ��A���U�ɂ�����100��ȏ�̊G�{��50��ȏ�̍D�F�{�ɕM���Ƃ����B�t��̔��ƍ��̑Δ���������������n���̂���ʼn�\���́A�����̍]�ˎs���̍D�݂ɂ������āA�傢�ɗ��s����B��\��Ɂu�g�����̓����v(1678��)�u������(�Â�)�v(1683��)�u��a�G�����v(1686��)�Ȃǂ�����B ���̌�A1765�N�ɊG�t�E��؏t�M���G��i������݁j�̐����ʂ��āA����t�␠��t�Ƌ��͂��đ��F���ؔʼn�i�J���[�����G�j�̋Z�p���J�����A����������(�ɂ���)�ɂ��Ƃ�����A�F�N�₩�ȁg�ъG�h��n�n�����B���̑��F���ʼn恁�ъG�̑n�n�́A�����G�E�ɂƂ��đ傫�ȏo�����ł������B�ʼn�͗ʎY�ɂ�艿�i���������A�����̎��v�ɂ��������B �����̖ؔʼn�́A�G�t�A���t�A���t�̕��Ɛ��B�ʼn�Ƃ͕ʂ̈�ʓI�ȍʐF��͓��M��ƌĂꂽ�B�H��t��̓��M��ɂ͗L���ȁs���Ԃ���l�}�t������B19���I�ɖk�ւ�L�d�Ȃǂ��o�ꂷ��ƁA�����G�ɕx�m�R�̕��i���Ԓ��悪����ɕ`�����悤�ɂȂ�B 17���I�㔼����18���I�����炢�܂ł����������G����ŁA�������M�A�������{(����܂�)�A���������x(�������ǂ������)�A�{�쒷�t�A�������M�Ȃǂ̍�Ƃ������B 1765�N�̋ъG�����ȍ~�������ŁA��؏t�M�A����t�́A���������A�쑽��̖��A���F�֎ʊy�Ȃǂ�y�o����B ������\����̂́A�����k�ցA�̐�L�d�A�̐썑�F��ŁA�ǖ{�Ȃǂ̕��w��i���G�扻�������̂ɏG�삪�����A���i��ƉԒ���ł��V�@�����������Ă��B�l���`�ʂ͂�蕡�G�ɂȂ�A����S��ɓ������錆��𑽐��������B �����ȍ~�̕����G�́A���ѐ��e��̊��݂�����̂̉��ɂނ����A�����̍�i���C�O�ɗ��o���Ĉ�۔h��A�[���E�k�[�{�[�Ȃǐ��m�ߑ�̌|�p�^���ɑ傫�ȉe����^�����B �k�Q�l�����l�w�G���J���^������S�ȁx�i�}�C�N���\�t�g�j�A�w�������{���j�l�����T�x�i�����V���o�Łj�A�E�B�L�y�f�B�A �u�w�������v�i�l�b�g�ł͂�������ԏڂ����̂ł́B�摜���[���A�J��ɒE�X�ł��j�@https://blog.goo.ne.jp/sesame1952/e/2514e9e6b18e4b664000f96887234af9 �i�K�[���A�����N��j �u���É����������فv�i�،`�������q�ƒӏd�̊W���悭�킩�����I�j�@https://www.meihaku.jp/berabou/urokogataya-magobe/ �u�Ӊ��d�O�Y�o���ڔN�\�v�i�S�o�Ń��X�g�j�i��j�@https://www.jstage.jst.go.jp/article/kinseibungei/35/0/35_71/_pdf/-char/ja�@//�i���j�@https://www.jstage.jst.go.jp/article/kinseibungei/36/0/36_53/_pdf/-char/ja �u�p�Y�����̑I���@��]�˃G���^���v���`���^�E�Ӊ��d�O�Y�v�iNHK�j �u���j�T��@�ׂ�ڂ��R���{SP�`��݂������]�ˁv�iNHK�j |
���ܑ� �F��/Tomoatsu Godai �V��6�N12��26���i1836�N2��12���j-1885�N9��25�� �i���s�A���{���A���s�c��쉀 ���{���n 49�j2014
 |
 |
 |
| �����ƊE�̏d�� | �揊�O�̗��h�Ȓ����͎��̗��N�ɍO���ٖ��������� | ���S�i�B�F���̉��ɒ������q�̈┯���������� |
 |
 |
 |
| �V�����w�̓k�������ɂ���L��Ȉ��{���n�A ���̒����t�߂ɗF���͖����Ă��� |
�w�]�܈ʌM�l�� �ܑ�F����x |
����300m�A���{�ꍂ���g���ׂ̃n���J�X�h�ƌ������� �F���̕�i��ʉE�[�j�B���̔��W�����ł��邾�낤 |
| �����ƊE�̊�b��z�������������̎��ƉƁB���b�g�[�͐M�p���B�����Ƃƌ������������B�F���ˏo�g�B�ʏ̍ˏ��B1865�N�i29�j�A�˖��ɂ���āA�����@���i��́g�d�C�ʐM�̕��h�j�A�X�L��i��́g����̕��h�j��Ɖ��B�����@�B���N�ɋA�����A1867�N�ɒ��萻�S���i���E�O�H�d�H�ƒ��葢�D���j��ݗ��A���N�吭��ҁB �ېV��A�O�������ǔ����A���{�����߁A1869�N�A33�őފ������ƊE�ɓ�����╪�͏���ݗ��B���N�A���{�ŏ��߂ĉp�a�������������B1871�N�i35�j�A�ܑ�̐i�����đ呠�Ȃ���㑢���ǂ�ݗ��B1873�N37�A�S���̍z�R�̊Ǘ��������ł���g�O���فh��ݗ����z�R���ƂȂ�B1878�N�i42�j�ɂ́A��㊔��������i���E���،�������j�A��㏤�@��c���i���E��㏤�H��c���j�𗧂đ����ɐݗ��B���̌�A��㏤�ƍu�K���i���E���s����w�j�A�����d�C�S���i���E�����s�d�ԁj�A��㏤�D�i���E���D�O��j�A����S���i��C�S���j�Ȃǂ�n�݂��A1885�N�A���A�a�ɂ��a�v�B���N49�B �����،�������O�ɓ�������B |
���{�c �@��Y/Soichiro Honda 1906.11.17-1991.8.5 �i�É����A�x���S�A�y�m�쉀 84�j2010
 |
  |
| JR�x�͏��R�w�`�y�m�쉀�̓V���g���o�X���֗� | ���̑傫�Ȑ��_�̒����{�c�Ƃ̕揊�I�O�ɕ\�D���o�Ă��� |
  |
 |
|
| �L����悪�������������ꂽ�{�c�ƕ揊�B�ߗׂɂ͕x�m�X�s�[�h�E�F�C������A���[�V���O�J�[�� �G���W��������O�܂ŕ������Ă����B�Ԃ̃T�E���h���q��̂̂悤�ɕ����āA�@��Y������K�����낤 |
���̈�p�ɂ͖{�c�� ��X�̕����������Ă��� |
|
  |
  |
| ���Ȃ݂ɖ{�c�Ƃ̂Q��捶�ׂ͌������̈��{�� | ����ɂ��̍��͊݉ƁB�y�m�쉀�͒����l������ |
| �{�c�Z���H�Ƃ̑n�ƎҁB�P�Ȃ�o�c�҂ł͂Ȃ��A������Z�p�J���Ɏ��g�݁A�����{���\����Z�p�Ҍ��N�ƉƂƂ��Đ��E�I�ɗL���B�É����o�g�B �{�c�Ƃ͑�X�̒b�艮�B1928�N�i22�j�A�����̕����A�����ԏC���H�ꂩ��g�����Ă��炢�A�l���Ɏx�X���J�Ƃ���B1936�N�i30�j�A��1��S�������ԋ������ɔ�s�@�̃G���W�������ǂ����ԂŒ�ƎQ�킵�A�ō�����120km��@���o���B���̂ɂ���ĎԊO�ɓ����o���ꂽ���Ƃ���A�Ȍ�̓n���h���������ă��[�X�ɗՂނ��Ƃ͂Ȃ��������A�g120km�h�͖�20�N�Ԃ��j���Ȃ������B 1937�N�i31�j�A�G���W�������ڎw���ĕl�������H�Ɗw�Z�i���E�É���w�H�w���j�@�B�Ȃ̒��u���ƂȂ�w�ɗ�ށB�I���A1946�N�i40�j�ɖ{�c�Z�p��������ݗ����A���^�G���W�������]�ԂɎ��t�����u�o�^�o�^�v���q�b�g������B1948�N�i42�j�A�{�c�Z���H�Ƃ��N���グ�O��̃I�[�g�o�C���Y���X�^�[�g�B���N�A�o�c��s����Ǝ��o���Ă����@��Y�͕��В��ɓ��v���}���Čo�c�̈��C���A���g�͋Z�p���Ƃ��Ċ��𗬂����B ���@��Y�Ɠ���͐g������Ђ����Ȃ������B�Q�l�Ƃ��u��Ђ͌l�̎������ł͂Ȃ��v�Ƃ����M�O�������Ă���A�u���������̎q��͓��Ђ����Ȃ��v�Ƃ������K���߂��B��[�傪�Ж����u�\�j�[�v�Ƃ������Ƃ���A�@��Y�͎����̖��O���Ж��ɂ������Ƃ�p�����B 1958�N�i52�j�A����u�X�[�p�[�J�u���v�������B���N���琢�E�ō���̃I�[�g�o�C�E���[�X�A�p���}����TT���[�X�ɎQ�킵�A1961�N�i55�j�ɗD�������B��1962�N�i56�j���玩���Ԑ��Y�ɏ��o���A���^�X�|�[�c�J�[��y�g���b�N���B1964�N�i58�j�ɂȂ�ƁA���x��F1�O�����v���Ƀ`�������W����ȂǖO���Ȃ�����S�������Ă����B1972�N�i66�j�A���߂Ē���QCVCC�G���W�����J�����A�č�����������]������u���E�̃z���_�v�Ƃ��ĔF�m���ꂽ�B1973�N�i67�j�A�В������ނ��ō��ږ�ƂȂ�B���N�A�~�V�K���H�ȑ�w�����_�H�w���m�������^�B�@��Y�́u�S�Ă̏]�ƈ���W�҂Ɉ��A���������v�Ƃ̎v������A�����͂��Ƃ��R�N������Ő��E�e���̃z���_�H���f�B�[���[�ֈ��A�܂����s�Ȃ����B�@��Y����ʍH���Ɠ���������ƒ��i�c�i�M�j�𒅂Ĉ̂Ԃ邱�Ƃ��Ȃ��������Ƃ�����A���̓��n��Ƃő��������J�����c���z���_�ł͈�x���N���Ȃ������B F�P�ł�1986�N�i80�j����v����܂Ńz���_�̃G���W���𓋍ڂ����`�[���������ҕ���^�C�g�����l�����������B 1989�N�i83�j�A���{�l�Ƃ��ď��߂ĕč��̎����ԓa��������ʂ����B1991�N�A�̕s�S�̂���84�ő��E�B���O�ʁE�M�ꓙ��������͂ʂ��ꂽ�B���O�Ɂu�����ԃ��[�J�[�̌o�c�҂����V�ŏa���N�����Ă͂����Ȃ��v�ƌ���Ă���A�⑰�͒ʖ�A�Б����s��Ȃ������B �u�l�ɂ͎��s���錠��������B�����������A����ɂ͔��Ȃƌ����`�����t���v �u�`�������W���Ă̎��s�������ȁB�������Ȃ����Ƃ������v �u�����肪�������Ƃ̂���99%�͎��s�������B1%�̐����̂������ō��̎�������v �u���͔N��肾����V�����J������͂�����������Ă��邪�A�ꉞ���̎Ⴂ�A������������Ă��邩�����Ė���Ă���B�ł��i��������Ă���̂��j�킩��Ȃ��ȁB�����炱���������B���̔N���ɕ���悤�Ȏ�������Ă���̂Ȃ炤���̎Ⴂ�A���̓{���N���ł���B�l�ɕ���Ȃ���������Ă���Ă��邱�Ƃ��l�͈�Ԋ������v ���@��Y�̕��������́u�I���W�v�ƌĂ�ŕ���Ă����B ����R�̖{�Ѓr���͑S�t���A�Ƀo���R�j�[������B����͏@��Y���u�n�k�Ŋ��ꂽ�K���X�����s�҂ɍ~�肩����Ȃ��悤�Ɂv�Ǝw����������B ���{�c�Z���̐����̃Y�{���ɂ̓|�P�b�g���Ȃ��B�H�ꏄ�ɎႢ�H������u�I�b�T���A�]���Ȃ�����|�P�b�g�Ɏ�˂�����ŕ����ȁI�v�ƒ��ӂ��ꂽ�̂����������B �����ċً}�ԗ������ԑ̂ɐԐF���g������������Ȃ������B�@��Y�́u���Ƃ��f�U�C���̊�{�ł���ԐF�ɓ�Ȃ�t����̂͂��������v�ƃ��f�B�A�ōR�c���A�Ԃ̃J���[�����O���F���ꂽ�B |
����[ ��/Masaru Ibuka 1908.4.11-1997.12.19 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 89�j2010
 |
 |
| �����쉀�̉E�艜�̕��B�߂��Ɋݓc�����q����̕� | �����u��[�ƈ��V��v�A�E����[��̕� |
 |
 |
 |
| ���ǂ��r���o���Ƃ��[�i�E�j�Ɛ��c���v�B���Ƀ\�j�[��n�� | ��ɍ��܂ꂽ���t�́g���R舒B�h | �w��ɕ����i�����j |
| ���c���v�Ƌ��Ƀ\�j�[��n�ƁB���F�E�{�c�@��Y�ƕ���Ő����{���\����Z�p�ҁ��N�ƉƂƂ��Đ��E�I�ɒm����B�Ȗ،��o�g�B�R�ŕ���S�����A���m���̑c���Ɉ��������B���̌�A�ꂪ�č����_�˂ň�B 1933�N�i25�j�A����c�̗��H�w���d�C�H�w�Ȃ𑲋ƁB�݊w���ɔ��������u����l�I���v��1937�N�́@�p�������ŗD�G�����܂ɋP�����B���̎��̎G���L���𒆊w���̐��c���v���ǂ�ł���B���ƌ�A�ʐ^���w�������i���\�j�[PCL�j�ɓ��ЁB���̌�A���{�����H�ƁA���{�����ɐЂ�u���B1943�N�i35�j�A�펞�Ȋw�Z�p������̔M���ǔ����e�̊J���O���[�v�ɂāA�C�R�Z�p���т�13�ΔN���̐��c���v�Əo��B 1945�N�i37�j�A�I���ɓ������{���ɒZ�g��M�@�����铌���ʐM��������ݗ��B��1946�N�i38�j�A�Ж����u�����ʐM�H�Ɓv�Ƃ��āA�В��ɋ`���ŕ����̑O�c������}���A��[���Z�p�S���̐ꖱ������A���c���c�ƒS���̏햱������ƂȂ�A20���l�őn�Ƃ����B1950�N�i42�j�A�В��ɏA�C�B���N�A���{���̃e�[�v���R�[�_�[���A������1955�N�i47�j�ɓ��{���̃g�����W�X�^���W�I���B���N�A���c���n�Ă��uSONY�v�u�����h�Ŕ��荞�݂��J�n�B�uSONY�v�̖��O�́gSOUND�i�T�E���h�j�h�̌ꌹ�ł��郉�e����gSONUS�i�\�k�X�j�h�ƁA���C�ŎႢ��Ƃ̃C���[�W����p��́gSONNY�h�i�g�V��h�̈Ӂj���d�˂����́B1958�N�i50�j�A���W���́uSONY�v���Ж��Ƃ����B ���̌���A1960�N�i52�j�ɐ��E���̃g�����W�X�^�e���r�A1965�N�i57�j�ɐ��E���̉ƒ�p�r�f�I�E�e�[�v���R�[�_�[�𐢂ɏo���ȂǁA���{���␢�E���̊v�V�I�ȏ��i�����X�Ɛ��ݏo���A���Ђ𐢊E��Ƃɉ����グ�Ă������B1971�N�i63�j�A��ɏA�C�B1976�N�i68�j�A���_��ƂȂ����B1979�N�A�O�o��ł��l�ʼn��y���y���߂�g�ь^�e�[�v���R�[�_�[�w�E�H�[�N�}���x�����A��O�̐l�C���i�ƂȂ����B ��[�͎q�ǂ����n���f�B�L���b�v�������Ă������Ƃ���A�Ⴊ�����̊w�Z�ݗ��ɐs�͂��A�Ј��̂U�����Ⴊ���҂̍H���u�\�j�[�E���z�v��ݗ��B�܂��c������̏d�v�������������Ђ��o�ł��Ă���B 1986�N�i78�j�ɌM�ꓙ��������́A1989�N�i81�j�ɕ������J�ҁA1992�N�i84�j�ɎY�Ɛl�Ƃ��ď��߂ĕ����M�͂���́B1997�N�A89�ő��E�B �n�Ǝ�20�����������]�ƈ���2010�N���_�Ŗ�17���l�B��[�̕�͑����쉀�ɂ���A��ɂ́u���R舒B�i�������j�v�Ƃ������t�����܂�Ă���B����̓\�j�[�n�Ƃ̐ݗ���ӏ��ɋL���ꂽ�u�^�ʖڂȂ�Z�p�҂̋Z�\���ō��x�ɔ��������ނ�ׂ����R舒B�ɂ��Ė����Ȃ闝�z�H��̌��݁v���炫�Ă���B ���ӔN�A��[�͔�Ȋw�̕���ɂ����������������A1991�N�i83�j�A�\�j�[�Г��ɃG�X�p�[��������ݗ������B�����ł͒��\�͎҂������e���p�V�[�ⓧ���\�͂Ȃǂ̎��������Ă������A��[�̎��̗��N�Ɍ������͕����ꂽ�Ƃ����B ���ѐ��R�Ŏ��n�������Ց��m�E��[�Α��Y�͐�c�̂P�l�B ����[�͓����ʼnY�d�C�i���E���Łj�̗̍p�����ŕs���i�ɂȂ����B�������ŎЈ��ɂȂ��Ă�����\�j�[�͂Ȃ������B ���u���̐l�̔\�͂͂��ꂾ�����ƌ��ߕt���Ă����炻�̐l�̔\�͈͂����o���܂���v�i��[��j |
���c�� �v�d/Hisashige Tanaka ����11�N9��18���i1799�N10��16���j-1881�N1��11�� �i�����s�A�`��A�R�쉀 81�j2010
�P�탍12��31��
 |
 |
 |
| ���őn�ƎҁI�����~���l�߂�ꂽ��� |
�v�d���̗����ƕ��}�B 1875�N�A�����ɓX�܌��H����J���� |
�u���ʂ̋@�B �l�Ă̈˗��ɉ����v �X���̊Ŕɂ��̌��t���f����ꂽ |
 |
 |
 |
| �ΐF�̎��R�̕� | �c���v�d�v�� | ������͂Q��ڋv�d�i�{�q�j�B����̐^������ |
| �]�ˌ���ɐ��܂ꂽ�c���v�d�́A���őn�Ǝ҂ł���Ɠ����ɁA�u���m�̃G�W�\���v�Ƃ��Ēm���锭���ƁB�}�㍑�v���ďo�g�B�ʏ̓c���V�E�q��B���ׂ͂������H�t�ŁA�T��Ŏd�������Ă����v�d�́A��悪��p�ȏ��N�Ɉ�����B�����̏����͍Ղ�̋��s�ʼn�������g���炭��l�`�h��傫�Ȋy���݂ɂ��Ă���A���N�v�d�̓I���W�i���́g���炭��h��v���邱�Ƃɖ����ɂȂ����B������13�ɂ��āA�ƐE���̂Ăāg���炭��h�ɐ����錈�S������B�v�d�͕��Ɂu���͔����H�v�������ēV���ɖ���g�������A�ƐE�͒�Ɍp�����ĉ������v�Ƒi�����B�d�́A���́A��C���ȂǁA�l�X�ȓ��͂��g�����v�d�́g���炭��h�͐l�C���ĂсA10�㔼�ɂ��āu���炭��V�E�q��v�Ə̂��꒬���̐l�X�ɒm��ꂽ�B20��ɂȂ�ƁA���炭�苻�s�t�Ƃ��č]�ˁA���A���s�Ȃǂ����Ƃ��A���X�̏㉉��ʂ��āg���炭��h�ɂ��������n�ӂƍH�v���{����Ă������B�Ⴆ�A�|����˂�l�`�́A�S�{�̖�̂����P�{�̖���킴�ƃ~�X����悤�ɐv���Ċϋq���킹���B�܂��A�����������l�`�Ɋϋq�͊��т𑗂����B �₪�ď��˂̍������v���n�܂�ƁA���炭�苻�s�̊J�Â�����Ȃ�A�v�d�͏�ŊJ����ׂɎ��p�i�̐����E�̔����n�߂邱�Ƃ����ӁB���b�g�[�́u�l�X�̖��ɗ����A���V�������m�����v�B1834�N�i35�j�A�����̖{���n�Ƃ��ď��l���W�����ɏZ�����߂��B�ŏ��̃q�b�g��́A���H���ɂ����^�J�ō�����g�їp�̏��^�C��B��Ԉ�Â̌����A�锼�܂Œ�����ɒǂ��鏤�l���������߂��B �v�d�����Ɉڂ�Z��łR�N��A1837�N�i38�j�Ɂu�剖�����Y�̗��v���u������B��㒆�S���̂T���̂P�i��Q�����j���œy�ƂȂ������̐헐�ŁA�v�d�͉ƍ����R���Ă��܂����B���������O���ɏ���������́A�ăX�^�[�g��]�V�Ȃ������B�����A����Ȃ��Ƃŋv�d�͂߂��Ȃ������B���k��C���g�������Ŗ���⋋���铔����u���s���v�����A�g���܂ł������Ȃ�����h�Ƃ��ď��l���������^���ꂽ�B �₪�ċv�d�̋����̑Ώۂ͐��m���v�̕��G�Ȏ��ԍ\���Ɉڂ�B���ɂ̎��v�ݏo�����߂ɁA���m�̓V���w�␔�w���w�Ԃ��Ƃ����f���A48�œ����̓V����w�̑��{�R�A�y���Ɓi���s�j�ɓ��債���B������1851�N�i52�j�A����܂łɊw���ׂĂ̒m���ƋZ�p�𒍂����݁A���炭�莞�v�̍ō�����u���N�����v�������������I���̎��v�́A�V��E����A�m���E�a���̗������A�j���A���̖��������A���x�A��\�l�ߋC�����ׂĕ\�����鍂���x�̖��N���v���B���̎��v�ɂ���āu���{���H�t�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�A���喼���玞�v�����߂���悤�ɂȂ����B���N�A���s�l���G�ۂɋ@�I���i���炭��ǂ��j���J�X���A�_�����i�艟�����h�|���v�j�A�{��R�V�i�V�̋V�j�A�e��Ɩ����Ȃǂ�E�̔��B�v�d�͂���ɍ��̖ڊo�܂����v�ɂ�����u�����v�v��A���Ԃ��Ƃɑ��ۂ���u���ێ��v�v�Ȃǂ��l�Ă��Ă����B���N�A���C�D�̂ЂȌ^�����A���i�ɂĎ��^�]�ɐ����B 1853�N�i54�j�ɍ��D�����q����ƁA�v�d�̍˔\�ɒ��ڂ�������˗��w�ҁE����햯�i��̓��{�ԏ\���Бn���ҁj�ɐ����Ĕ˂̐��B���i����������Ȋw�������j�ɐg��u���B1855�N�ɓ��{�ŏ��߂ď��C�@�֎Ԃ̖͌^�삵�A����ˎ�E�瓇�����̑O�ő��点���B�����͂���ɍ��܂�A1864�N�i65�j�A�̋��E�v���Ĕ˂̗v�]���ċA���B���̍��Y�A�[���X�g�����O�C�������������ق��A���Ă�͐�@��̊�B���쐬�����B67�A��C�����@�B1868�N�A�����ېV��69�Ō}�����B�v�d��70��ɂȂ��Ă����͓I�Ɋ������A���{���̐��X�@�B�⎩�]�ԁA�l�͎Ԃ̊J���E���ǂɔR�����B 1873�N�i74�j�A�����V���{����v�d���Ɂu�����ŒʐM�Z�p�̋ߑ㉻�ɋ��͂��ė~�����v�Ɨv��������A�㋞�����v�d���͍����\�̃��[���X�d�M�@�������������B1875�N�i76�j�A�v�d���͐��{����̎d���ł͂Ȃ��A�����Ə����̓��퐶���ɖ��������d�����������ƍl���A����W���ڂɍH�ꌓ�X�܂��\�����i���őn�Ɓj�B�X�̊Ŕ� �u���ʂ̋@�B �l�Ă̈˗��ɉ����v�ƋL���A�� �ɉ����ēƎ��̓d�b�@���A���j�ՂȂǂ삵���B 1881�N�A����ł̑n�Ƃ���U�N�ڂɁA�v�d����81�ő��E�����B���̗��N�A�v�d�̗{�q�Œ�q�̓c����g���A�{���̈�u���p���Q���v�d�Ƃ��Ė��Ԃ̓d��@�B�H�Ƃ̐�삯�ƂȂ�u�c���������v�𓌋��E�ʼnY�ɐݗ��B�c����������1904�N�ɎЖ����ʼnY���쏊�ƂȂ�A1930�N�ɓd�C����@�Ɠd�C�①�ɂ̍��Y��P���������B1939�N�ɓ����d�C�ƍ����������ʼnY�d�C�i�����Łj�ƂȂ�B �u�m���͎��s���w�ԁB���𐬏A����ɂ́A�u������A�E�ς�����A�E�C������A���s������A���̌�ɁA���A������̂ł���v�i�c���v�d�j ���ɂ͔����~���l�߂��A����c���v�d�v�ȂƁA�Q��ڕv�Ȃ̕悪���������Ă���B��O�ɂ͏ё��ʐ^�Ɓu���ʂ̋@�B �l�Ă̈˗��ɉ����v�̕������������掏�̂ق��ɁA�u�c���v�d�������v�Ə����ꂽ���̂��������B |
������ �K�V��/Konosuke Matsushita 1894.11.27-1989.4.27 �i�a�̎R���A�a�̎R�s�A�a���V��
94�j2010
���L�c ���Y/Kiichiro Toyoda 1894.6.11-1952.3.27 �i���m���A�����s�A���� 57�j2010
���I�ɍ��� �����q��/Bunzaemon Kinokuniya ����9�N�i1669�N�j-����19�N4��24���i1734�N5��26���j �i�����s�A�]����A�����@ 65�j
 �@
�@ �@
�@
�����q��̂���͒����̋���Δ�ł͂Ȃ��A���[�̃{���{���̕�Ȃ̂ł��ԈႢ�Ȃ��I
���a�� �h��/Eiichi Shibusawa �V��11�N2��13���i1840�N3��16���j-1931�N11��11�� �i�����s�A�䓌��A�J���쉀 91�j2010��11��16��23
�i����I�j2014�N�ɓS��ƕ����Ȃ��Ȃ�A�揊���J������܂����I�f���炵���I
�����c ���v/Akio Morita 1921.1.26-1999.10.3 �i�����s�A�`��A���J�� 78�j2010
���v�c �F/Takashi Masuda �Éi���N10��17���i1848�N11��12���j-1938�N12��28�� �i�����s�A������A�썑�� 90�j2010
 �@
�@ �@
�@
���� ����/Takuma Dan ����5�N8��1���i1858�N9��7���j-���a7�N�i1932�N�j3��5�� �i�����s�A������A�썑�� 73�j2010
�����c �`�O�Y/Denzaburo Fujita 1841�N7��3���i�V��12�N5��15���j-1912�N3��30���i���s�s�A���R��A�m���@ 70�j2012
���ƉƂŖ������̊����E�̏d���B���Ԑl�ŏ��߂Ă̒j�݁B���c�g�̑n���ҁB���B������B20��͊���ɎQ���B1877�N�i36�j�A
����푈�ɍۂ��R���i���B�ɂ���ċ����A���B����w�i�ɐ����Ƃ��Ĕ_�E�сE�z�E���Z�Ƃ��c�B�M�S�ɔ��p�i�����W���A�����ɗ�ނȂǁA
����҂Ƃ��Ă��m����B���E����42�N���o����1954�N�A�j�ϓV�ڒ��q�i����j�Ȃǂ̏����i����Ƃ������c���p�ق��J�ق����B
���j�E�����Y�A���j�E�����Y�A�O�j�E�F�O�Y�B
�����c �P���Y/Zenjiro Yasuda �V��9�N10��9���i1838�N11��25���j-1921�N9��28�� �i�����s�A������A�썑�� 82�j2010��12��19
������ �`��/Yoshisuke Aikawa 1880.11.6-1967.2.13�i�����s�A�{���s�A�����쉀 86�j2010
 �@
�@
������� �F���Y/Hikojiro Nakamigawa �Éi7�N8��13���i1854�N10��4���j-1901�N10��7�� �i�����s�A�`��A�R�쉀 47�j2010
 �@
�@
������ �Q��/Namihe Odaira 1874.1.15-1951.10.5 �i�����s�A�䓌��A�J���쉀 77�j2010
 �@
�@ �@
�@
����q �씪�Y/Kihachiro Okura �V��8�N9��24���i1837�N10��23���j-1928�N4��22�� �i�����s�A������A�썑�� 90�j2010
����� ����/Seiji Noma 1878.12.17-1938.10.16 �i�����s�A������A�썑�� 59�j2010
������ �`��/Yoshisuke Sato 1878.2.18-1951.8.18 �i�����s�A�`��A�R�쉀 73�j2010
���p�� ���`/Genyoshi Kadokawa 1917.10.9-1975.10.27 �i�����s�A�����R�s�A�����쉀�j2017
������ �N��/Yasuyoshi Tokuma 1921.10.25-2000.9.20 �i�����s�A�`��A���J�� 78�j2010
������ �Y��/Yusaku Shimanaka 1887.2.2-1949.1.17 �i�����s�A������A�z�n�{�莛�a�c�x�_�� 61�j2010
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
���z ����/Sonoji Yo 1838.6�|1906.9.24 �i�����s�A�䓌��A�J���쉀 68�j2010
 �@
�@ �@
�@
������ ����/Hirohisa Seki �Éi5�N10��6���i1852�N11��17���j-1939�N1��22�� �i�����s�A�䓌��A�J���쉀 87�j2010
 �@
�@
�����䉥��/Ousuke Hibi 1860-1931 �i�����s�A�a�J��A�ˉ_�� 71�j2010
���� �N���Y/Yasujiro Tsutsumi 1889.3.7-1964.4.26 �i�_�ސ쌧�A���q�s�A���q�쉀 75�j2010
�����O���[�v�n�ƎҁB��44��O�c�@�c���B���ꌧ�o�g�B�ꐧ�N��Ƃ����A�q�ǂ��̐���
�`�����i�F�m��12�l�B���ۂ�100�l�ȏ�Ƃ��������j�B�s�X�g����ٖ̈������B
�y�d�v�z2017�N12���A�ǎ҂̕�����u���́A�Z�R�����|�����Ă��炸�L��ȕ~�n�̒��ɂ���A
��ƒ玁�̓��������邱�Ƃ��ł��܂����v�Ə����܂����I�iM����L��������܂��j
������ �����Y/Kintaro Hattori 1860.10.9-1934.3.1 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 73�j2010
 �@
�@
�Z�C�R�[�O���[�v�n�n�ҁB�����s�o�g�B���v�E�l����n�܂�A���������Ő��E�I�Ȏ��v��ЃZ�C�R�[��z���グ���g���v���h�B
���O�� �C�_/Kaiun Mishima 1878.7.2-1974.12.28 �i�����s�A������A�z�n�{�莛�a�c�x�_�� 96�j2010
���X�i ����Y/Taichiro Morinaga �c�����N6��17���i1865�N8��8���j-1937�N1��24�� �i�����s�A�`��A�R�쉀 71�j2010
���Ĉ� �����Y/Genjiro Yonei 1861.10.19-1919.7.20�i�����s�A�{���s�A�����쉀 57�j2010
�i�ٔ�����ݗ��B���R���o�g�B1887�N�i26�j�A�]�Z�킪�n�Ƃ����������ɓ���A����p���œ��ЂW������B1907�N�i46�j�A
�W���p���E�u�������[�Ђ������i�ٔ���������Ђ�ݗ������B�ӔN�ɗA�o���Ǝ҂̕Ĉ䏤�X�i�����l�C�j��n�ƁB
����� ����Y/Soichiro Asano 1848�N4��13���i�Éi���N3��10���j-1930�N11��9�� �i�_�ސ쌧�A���l�s�A������ 82�j2010
������ �x�Y/Tomiro Nagase ���v3�N11��21���i1863�N12��31���j-1911�N10��26�� �i�����s�A�L����A����쉀 47�j2010��11
 �@
�@
2011
����ؖ{ �K�g/Kokichi Mikimoto ����5�N1��25���i1858�N3��10���j-1954�N9��21�� �i�����s�A�`��A�R�쉀 96�j2010
 �@
�@
�����c ���Y/Teichiro Shoda 1870.3.29-1961.11.9 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 91�j2010
 �@
�@ �@
�@
���������n�ƎҁB�܂��A�������S����ł���M���@�c�������߂��B���q�q�c�@�̑c���B
���� ����Y/Shojiro Ishibashi 1889.2.1-1976.9.11 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 87�j2010
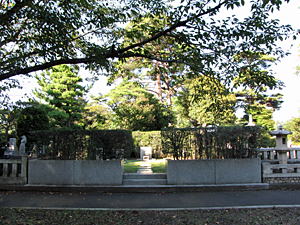 �@
�@ �@
�@
 �@
�@
�u���a�X�g���n�Ǝ҂ł���A�S���ꑫ�܁i�n�����܁j�̍l�ĎҁB77�̎��A���g���o�������v�����X�����ԍH�Ƃ����Y�����Ԃƍ����B
�S���H�ƁA�����ԍH�Ƃ̔��W�ɐs�͂����B���Ȃ݂Ɂg�u���a�X�g���h�Ƃ̓u���b�W�E�X�g�[���A�܂�n�ƎҁE���̖��O���B
���s�� �E/Shinobu Ichikawa 1897.1.9-1973.11.2 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 76�j2010
�ۍg�̏���В��B��錧�o�g�B�_�ˍ����i���E�_�ˑ�w�j���ƌ�Ɉɓ��������ɓ��Ђ��A�ۍg���X�ɓ���B1949�N�i52�j�A�ۍg��
����В��ɏA�C�B���������z�����������Њۍg�Ɣ��W�������B�u���E�V�E�a�v�̐��_���d���B�����͐����@�ߔE���B
���� ����/Naoya Sakai 1927.11.30-1993.4.24 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 65�j2010
 �@
�@ �@
�@
���ΐ� ��Y/Ichiro Ishikawa 1885.11.5-1970.1.20 �i�����s�A�L����A����쉀 84�j2010
 �@
�@ �@
�@
30�ŕ����o�c����֓��_���i���Y���w�H�Ɓj�ɓ��ЁB56�œ��Y���w�H�ƎВ��ɏA�C�B1948�N�i63�j�A�o�c�A�����ɏA�C�B
�����{�o�ς̕�����ڕW�ɍ��E�̃��[�_�[�ƂȂ�B���{�Ȋw�Z�p�A��������߁A���q�͂̋Z�p�J���ɐs�͂����B
������ �m�v��/Chikuhe Nakajima 1884.1.1-1949.10.29 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 65�j2010
���x�R �h�s�Y/Eichiro Tomiyama 1903.1.1-1978.9.1 �i�����s�A������A�썑�� 75�j2014
���x�R ��A/Masanari Tomiyama 1928.7.30-2005.11.7 �i�����s�A������A�썑�� 77�j2014
�����c �`��/Giichi Masuda 1869.11.24-1949.4.27 �i�����s�A������A�썑�� 80�j2014
������E�����핺�q/Yahe Kagiya �i���v�N�s���j2012��16
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
�]�˂��\����ԉΉ��B�ʉ��̃��C�o���I����̌`���ԉʂ��B
������ �ɓ� �����q/Tyube Ito 1842.8.7--1903.7.8 �i���s�{�A���R��A��J��n 60�j2012



���Z�F���F/Masatomo Sumitomo �V��13�N11��11���i1585�N12��31���j-�c��5�N8��15���i1652�N9��17���j�i���s�{�A������A�i�{�� 66�j2011



���O�䍂��/Takatoshi Mitsui ���a8�N�i1622�N�j-���\7�N5��6���i1694�N5��29���j�i���s�{�A������A�^�@�� 72�j2011
 �@
�@ �@
�@
������쑺 ����/Tokushichi Nomura 1878.8.7-1945.1.15 �i���s�{�A���R��A��J��n�@66�j2012
 �@
�@ �@
�@
���������|�����Ă���̂ɁA���܂��ܑ|���Ŗ傪�J���Ăē�����������
������ �M���Y/Shinjiro Tori 1879.1.30-1962.2.20 �i���ꌧ�A��b�R�A��� 83�j2012
�T���g���[�n�ƎҁB1929�N�A50�ŏ��̍��Y�E�C�X�L�[�u�T���g���[�E�C�X�L�[���D�v�i�T���g���[�z���C�g�j�Ɓu�T���g���[�E�C�X�L�[�ԎD�v�i�T���g���[���b�h�j���B
�M���Y�̃`�������W���_������킷���t�u����Ă݂Ȃ͂�v���A�T���g���[�͌��݂��n�Ɛ��_�Ƃ��Čf���Ă���B���j�͓��ڎВ��̍����h�O�B
������ �h�O/Keizo Saji 1919.11.1-1999.11.3�i���ꌧ�A��b�R�A��� 80�j2012
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
���ƉƁB�T���g���[�̑O�g�A������n�Ƃ�������M���Y�̎��j�i�Z�͑����j�B��㐶�܂�B1961 �N�A��Q��В��ɏA�C�B
1963�N�A�扮����T���g���[�ɎЖ���ύX�B �r�[���ƊE�ւ̐i�o�ȂǂŎ��Ƃ��g��A�o�ŁE�L���ƊE�ւ��i�o�����ق��A
�T���g���[���p�فA�T���g���[�z�[���̐ݗ��ȂNJ�Ƃ̎Љ�E���������̐�삯���Ȃ����B�܂���b�Ȋw������M�S�ɃT�|�[�g�����B
������F�����l�Y���Y ����/Kiyonobu Tyayashirojiro 1545-1596.9.19 �i���s�{�A���R��A����J��n 51�j2012
 �@
�@
���������/���{�O�Y�E�q����/Joan Yodoya �i�\3�N�i1560�N�j-���a8�N7��28���i1622�N9��3���j�i���{�A������A��厛 62�j2014
 �@
�@
�E����R��ځA�������A�Q���
���p�q ����/Ryoi Suminokura �V��23�N�i1554�N�j-�c��19�N7��12���i1614�N8��17���j�i���s�{�A�E����A�@�@60�j2012
 �@
�@ �@
�@
���t�F���f�B�i���g�E�|���V�F/Dr. Ferdinand Porsche 1875.9.3-1951.1.30 �i�I�[�X�g���A�A�c�F���A���[�[ 75�j2015
Schuttgutkapelle, Porsche Family Estate, Zell am See�i�c�F���A���[�[�j, Zell am See Bezirk, Salzburg, Austria
�����ԋZ�t�B20���I�ō��̎����Ԑv�ҁB�|���V�F�n�ݎҁB�j��ł�����������O�ԃt�H���N�X���[�Q���E�r�[�g���ȂǁA�����Ԏj�Ɏc��
����Ԃ𑽐��v�B�܂��A�ƌR�G���t�@���g�d�쒀��Ԃ╗�͔��d�@���肪�����i�e�B�[�K�[��Ԃ̖��t���e�ł͂��邪�����̗p�͂Ȃ炸�j�B
���Ȃ́u�Z�p�I�����������邽�߂ɂ͔��I�ϓ_������[���̂������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��v�B
�����揊�ɑ��q�̃A���g���A���Ŗ���911��J������v�����A���N�T���_�[������B
���A�C�E�G�I��/�C�O�҂̖ڎ���
���A�C�E�G�I��/���{�҂̖ڎ���
���W�������ʌ����̖ڎ���
 |
 |
 |
| �̋��͓c��ڂ������ς��B�������琢�E�ցI | ���n�Ŋ��́u��U�i���j�v�w�͖��l�w | �揊�̑Ζʂɂ��鏼������ |
 |
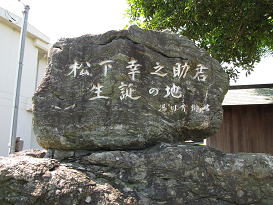 |
 |
| �u�����K�V���N���a�̒n�v ���������Œ鍑��z���グ�� |
�蕶�̊��|�͐�c���I�B�ˎm�̓���G�����m |
�����̖؉A�����a�n�A�E�̕����揊�B ���a�n�Ƃ��悪���Ԍ��i�����߂Č��� |
 |
 |
 |
| �뉀�̂悤�ȕ揊�B�S�̂��X�b�L���Ƃ��Ă��� | ����������ăV���v�� | �ߌ�납�� |
 |
  |
| �揊�̋��ɂ̓��E�\�N�������W�������B �N�ł��g������ۂ��̂͂������V���̏��� |
�揊���ɂ��鐅��B��˃|���v�͓��R�i�V���i�����I |
| �p�i�\�j�b�N�i���E�����d��Y�Ɓj�̑n�ƎҁB���E�L���̓��Ђ����Œz���グ�����Ƃ���g�o�c�̐_�l�h�ƌĂ��B�o�c���O�́u�����̓N�w�v�B����́g�����ʂ�����������镨���͖������R�ɂȂ�h�Ƃ������̂ŁA��ʐ��Y�ŃR�X�g���팸�������Ɠd���[�J�[�̃g�b�v�ɗ������B�a�̎R���o�g�B 1899�N�i�T�j�A���n��̕����đ���Ŕj�Y�B���͘a�̎R�s�ʼn��ʉ����n�߂邪��������s����B�K�V���͂X�ŏ��w�Z�𒆑ނ��A���̉Δ��X�⎩�]�ԉ��֒��t����ɏo���ꂽ�B15�̎��ɑ��d���i���E���d�́j�ɓ��Ђ��A�d���\�P�b�g���l�āB23�őސE���A����Ń\�P�b�g�̐������̔����n�߁A��ғd���\�P�b�g���q�b�g����B��1918�N�i24�j�A���s���ɏ����d�C���쏊��n�ƁB1925�N�i31�j�A�u�i�V���i���v���W��o�^���A���d�r�̔��ł����������B1931�N�i37�j�A���W�I�̐��Y�J�n�B1933�N�i39�j�A���Ɗg��ɂƂ��Ȃ�����^�s�ɍH����ړ]����B�܂��A�Ɨ��̎Z���̎��ƕ����������B1935�N�i41�j�A�Ж����u�����d��Y�Ɓv�։����B�펞���͐��{�̖��߂Ŗ����@���D�A��s�@�Y���A����GHQ����푈���͎҂Ƃ��Č��E�Ǖ���������B 1947�N�i53�j�A�В��ɕ��E�B�e���r�A����@�A�①�ɂȂljƒ�p�d�퐻�i�����X�ƊJ�����A1950�N���玀�v����܂�40�N�ԂɁA10������Ҕԕt�őS��1�ʂƂȂ����B1961�N�i67�j�A��ɏA�C�B�_�C�G�[���Ɠd�������肷�邱�Ƃɔ������A60�N�㒆������30�N�ɋy�ԃ_�C�G�[�E�����푈���u���B������X�ւ̏o�ג�~�Ƃ������d��i���ᔻ�𗁂т��B1973�N�i79�j�A���k���ƂȂ����������ށB81�A���y���ږ�ɏA�C�B1980�N�i86�j�A����70���~�𓊂��ď������o�m��ݗ����A�����E�̎w���җ{���ɓw�߂��B1987�N�i93�j�A�M�ꓙ�����ˉԑ���͂���́B1989�N�A�x���ɂ�葼�E�B���N94�B�����͌��_�@�����K�B �u�Y�Ɛl�̎g���͕n�R�̍����ł���B���ׂ̈ɂ́A�����̐��Y�Ɏ������Y���Ȃ��āA�x�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̐��͉��L�镨�ł��邪�A��H���V������ł���߂��Ȃ��B����͗ʂ������A���i���]��ɂ���������ł���B�Y�Ɛl�̎g�����A�����̐��̔@���A�����s�����炵�߁A����ɓ��������i�Œ��鎖�ɂ���B����ɂ���āA�l���ɍK�������A���̐��Ɋy�y�����݂��鎖���o����̂ł���B�����d��̐^�g���������̓_�ɍ݂�v�i�w�����N�w�x�j �u�����͐l�������Ђł��B���킹�āA�Ɠd�������Ă��܂��v �u����J����B�������o�����ȁB�����A�������炱�̏��i������Ȃ��Ȃ�悤�ȐV���i�������ɍ���Ă�v ����Y���z��2449���~�ō����̍ō��L�^���X�V�����B���̗���Ƒ�͍K�V���̃|�P�b�g�}�l�[�ōČ����ꂽ�B �����{�X�D�̊e�����g�ɑ����āA�ă^�C�������۔ł̕\�����������Q�l�ڂ̓��{�l���ƉƂƂȂ����B |
���L�c ���g/Sakichi Toyoda 1867.3.19�i�c��3�N2��14���j-1930.10.30 �i���m���A�����s�A����
63�j2010
 |
 |
  |
| �L�c�Ƃ̕揊�͋u�̈�ԍ����� | �����璷�j���Y�A���g�A���ɋg�A��c��X�� | ���g�̕�B���Y���R����̕���������Ɍ��Ă� |
|
�����ƁE���ƉƁB�L�c�������D�@�i��������j���B�ʖ��u�D�@���v�B���E�É����ΐ��s�̔_�Ƃɐ��܂��B���w�Z���ƌ�A���e�̑�H�d������`���A��D�@�i�Ă�����j�̉��ǂɒ��ށB
1890�N�i23�j�A�������Ɣ�����Ō����O�����D�@���q���g�ɖؐ��l�͐D�@���B�U�N��ɖؐ����͐D�@�������������B1910�N�i43�j�A���Ăɖa�D�Ǝ��@�̂��ߓn�q�B������1924�N�i57�j�A�ߊ�̎����D�@������B�������1926�N�i59�j�Ɋ�����ЖL�c�����D�@���쏊��n�������B
���̍��A���{�ł͊O���������Ԃ��}���ɕ��y���Ă����B���g�͍��Y�����Ԃ̐��Y�����ӂ��A1929�N�i62�j�A�p����ƂɎ����D�@�̉��B��������100���~�ŏ��n�����B��1930�N�A���̓������������Ɏ����ԍ��Y���̖��j�E���Y�ɑ����đ��E����B���N63�B���N�A���Y��4�n�͂̃K�\�����E�G���W�������������A�V�N��Ƀg���^�����ԍH�Ƃ�n�������B
|
���L�c ���Y/Kiichiro Toyoda 1894.6.11-1952.3.27 �i���m���A�����s�A���� 57�j2010
 |
 |
 |
| ���̕�n�ɗאڂ��āA�{���̎߉� �̍����[�߂�ꂽ����������� |
�����璷�j���Y�A���g�A���ɋg�̕�B�g���^ �����ԍH�Ƃ��n�����ꂽ1937�N�Ɋ��Y������ |
�t�߂ɂ͖L�c�ꑰ�� �悪�ї����Ă��� |
|
�g���^�����ԍH�Ɓi���g���^�����ԁj�̑n���ҁB���͔����Ƃ̖L�c���g�B�É����o�g�B1920�N�i26�j�A�������H�w���𑲋Ƃ��A�L�c�a�D�i�L�c�����D�@���쏊�j�ɓ��ЁB���ƈꏏ�Ɏ����D�@�̊J���ɒ��݁A1924�N�i30�j�Ɋ����������B1930�N�i36�j�A���������ԍ��Y���̖������Y�ɑ����đ��E�B���Y�͉��Ă̎����ԍH������@���A1933�N�i39�j�A�Г��Ɏ����ԕ���ݗ������Y�����Ԃ̐��Y�ɒ��肵���B�Z�p���A����������������1935�N�i41�j�Ɏ���ԁEA1�^��p�ԁ�G1�^�g���b�N�������������B
�g���b�N�ʎY���̖ړr�������A1937�N�i43�j�A�L�c�����D�@���쏊���玩���ԕ���Ɨ������ăg���^�����ԍH�Ƃ�ݗ��B���N�A���E�L�c�s�i���m���j�ɍH������݂����Ƃ��J�n�B1939�N�i45�j�A��O�����̒��^��p�ԁu�g���^�V���{���v�Y�����i400��j�B 1941�N�i47�j�A�Q��g���^�����ԍH�ƎВ��ɏA�C�B��p�ԗʎY�����X�^�[�g���悤�Ƃ������A���N���ɐ^��p�U�������葾���m�푈���u���A�v��͒��f�����B���A���{�̎����ԎY�Ɣ��W�̊�Ղ�z���A1952�N��57�ő��E�����B�Ȃ͌��E�������В��A�ѓc�V���̖��B���j�͂U��g���^�����ԎВ��̖L�c�͈�Y�B���j��7��В��̖L�c�B�Y�B�����݂͂��ً�s���ق̍ȁB�L�c�s�����̍L��Ɋ��Y�̓���������B ���g���^�����ԍH�Ƃ̏���В��͋`�Z�̗��O�Y�����A�����I�ȑn�Ǝ҂͊��Y�B
|
���I�ɍ��� �����q��/Bunzaemon Kinokuniya ����9�N�i1669�N�j-����19�N4��24���i1734�N5��26���j �i�����s�A�]����A�����@ 65�j
 �@
�@ �@
�@
�����q��̂���͒����̋���Δ�ł͂Ȃ��A���[�̃{���{���̕�Ȃ̂ł��ԈႢ�Ȃ��I
| �]�ˑO���̍����B�̋��I�B�݂̂�����]�˂ɉ^�сA�A��̑D�ɂ͉������]�˂������ɉ^��ő听�������߂��B�ʏ́A�I���B�I�ɍ��o�g�B�]�˔����x�ɏZ�ݍޖؖ≮���J�ƁB28���A���{�̘V���⊨���s�ɐڋ߂��A�x�{�̍����E���ؐV���q��ƈꏏ�Ɍ�p�B���l�Ƃ��ď�슰�i�����{�����̗p�ނB���������B40��ɉЂŖ؏���Ď����ޖ؉��͔p�Ƃ���B�g���ō��V���u�I����s�i��������j�v�ƌĂꂽ�B �����̗L���ȍ����͓������Ƌ{�̏C���H���𐿂��������ޗlj����q��B �������̏������̂���� |
���a�� �h��/Eiichi Shibusawa �V��11�N2��13���i1840�N3��16���j-1931�N11��11�� �i�����s�A�䓌��A�J���쉀 91�j2010��11��16��23
  |
 |
 |
| �Ȃ�Ɩ����Ƀp���ŎB�e�I����27�� | 91�܂Ő����� | ����O�A��Ջ������̓��� |
 |
 |
 |
 |
| �揊�͒ʏ����J�����A�쉀������ �ԉ��u�ӂ��ނ��v�Ō�������� |
�������h��B�E�Ɏ��ʂ�����Ȑ��v�l�A ���ɍč��������q�v�l�̕悪���ԁi2010�j |
�u���a��h���v�B�Rm�߂�������A �w�ʂɈ̋Ƃ��]������������������ |
�{�q�E����Y�i��Ȃ̒�j�̕�B��C�푈�� ���R�Ɛ킢���n�B���炵��ɂ��ꂽ�i2011�j |
�i����I�j2014�N�ɓS��ƕ����Ȃ��Ȃ�A�揊���J������܂����I�f���炵���I
 |
 |
 |
| �ȑO�͂��������͂̕����A���������Ɩ��Ă��������A �����������ׂď����A��������Ƃ�����ԂɌ��ρI�i2016�j |
2021�N�ɑ�̓h���}�w�V���Ղ��x�� ���U���`����e���܂��i2023�j |
|
 |
�@ �@ �@ |
|
| �E��O������i��ȁj�A�h�O�i���A�呠��b�j�A �h��A���q�i��ȁj��2023�N�T���B�e |
11���̖����͕�O�Łu�����v���Â���A���������Ԃł��ӂ��B ���͑�́w�V���Ղ��x��������2021�N�A�E��2022�N�i�B�e�E���q�玠���j |
|
| �s�a��h��Ƃ��̎���t ��91�N�̒���������A�������珺�a�̖��B���ςɎ���A2��2�玚�̑s��ȋߑ���{�j�ɂȂ��Ă��܂��B �u���Ƃ����̎��Ƃ����X������̂ł��낤�ƁA�����̗��v�͏��z�ł��낤�ƁA���ƕK�v�̎��Ƃ������I�Ɍo�c����A�S�͏�Ɋy����Ŏd���ɂ����邱�Ƃ��ł���v�i�a��h��j�B �g���{���{��`�̕��h�Ǝ]�����A�Љ�S�̂�L���ɂ�����@���l�������A500�ȏ���̊�Ƃ̐ݗ��Ɋւ�����a��h��B���̋ߑ���{���\�������ƉƂ́A�]�ˎ�������1840�N3��16���ɕ������Y��(�͂�)�S��������(��ʌ��[�J�s)�̍��_�i����j�̒��j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�a��Ƃ͍R�ۂ�h���̍�p������z����������u���ʁv�i�����j��{�\���ƋƂƂ������_�����B�h��͏��N������ƋƂɏ]�����A���Ƌ��ɐM�B���B�܂ŗ��ʂ�����A14�ŗ��ʂ̌����E���t�̎d�����C�����ȂǏ��˂�M������Ă����B�w�Ƃł́A5����蕃�Ɋ��Ђ̎�قǂ����A7�ŏ]�Z�i���̎o�̎q�j�̔����Ւ��i1830 -1901���h���10�ΔN��j�̋��ɒʂ��A�w�_��x�Ȃǂ̒����ÓT��w���{�O�j�x���w�ԁB���p�͐_�����O���B 1853�N�i13�j�A�Y��Ƀy���[������鍕�D�͑������q�B����19����A���R�ƌc��60�ő��E�B�ƌc�̎l�j�E�ƒ肪��13�㏫�R�ƂȂ�B 1854�N�i14�j�A�y���[���ė�������ƁA���{�S���́u���Ęa�e���v�ɒ����B���e�́A�A�����J�D�ɐd�E���E�H���E�ΒY�Ȃǂ��������邽�߂ɉ��c�E���ق��J�`���邱�ƁA�Y���A�����J�l�̕ی�A���c�ւ̗̎��ݒu�A�Ж��I�Ōb���ҋ��ȂǁB�f�Ղ͔F�߂Ȃ���������������Ԃ����ŏ��̏��ŊJ���̒[���ƂȂ����B 1856�N�A�h���16�i����17�j�̎��ɗ̎傩��v�����ꂽ��p���i�Վ��Łj��[�߂��ہA�㊯�̉��\�ȑԓx�����ĕ������x�ɔ���������悤�ɂȂ����B 1858�N�i18�j�A�w��̎t�A�����Ւ��̖��łP�ΔN���̔������i1841-1882�j�ƌ����B ���N�A�V�c�̒������Ȃ��܂ܖ��{�S�����������̎��n���X�Ɓu���ďC�D�ʏ����v�ɒ���B�����ł͂T�ӏ��̍`�̊J�`�⎩�R�f�ՂȂǂ���߂�ꂽ�B���f������u�s�h�v�ƍl��������ˎ�E�����t�ԁA���˂̑O�ˎ�E����ď���S�l�́A�o�邵�Ē��J��₢�l�߂悤�Ƃ����Ƃ���A���J�͕s���o��i���߂�ꂽ���ȊO�̓o��j����ɂ��Č����ɏ������B�����ւ̈٘_�������ŕ�����g�����̑卖�h���n�܂����̂��B���̗����ɉƒ��34�ŕa�v�B�{�q�ƂȂ���12�̉Ɩi��������/1846�|1866�j��14�㏫�R�ƂȂ�B 1859�N�i19�j�A�����̑卖�ŁA���{�����A���O���O�Y�A�g�c���A��W�l���a��ƂȂ�A40�l����������Ǖ��A�����҂������o���B�����҂�100�l�������A�u�m�����̈�ɒ��J�ւ̑����݁A�v��m�ꂸ�B 1860�N�i20�j�A3��24���i����7�N3��3���j�ߑO�X���A�G�ߊO��̑��̂Ȃ��A��ɒ��J�����c��t�߂Ő��˒E�˘Q�m��18���ɏP������▽�B���N44�B���̒��A���J�͏P���̖������Ă������A�x��𑝂₷���ƂȂ��o��̏�̓o�邾�����B 1861�N�i21�j�A�h��͍]�˂ɂ̂ڂ��Ėk�C�꓁���ɓ��債���p������A����ł͋Ή��̎u�m�����ƌ𗬂�[�߁A�h�ꎩ�g���ƋƂ��̂ĂĊO���l�r�ˁ��������Ή^���ɌX�|���Ă����B 1863�N�i23�j�ɂ́u����ˁi�Q�n������j�̕���ɂ��P�������l�O���l���Z�n���Ă��������A�����ɏ悶�Ē��B�˂ƌ��ѓ|�����ʂ����v�Ƃ̉ߌ��Ȍv��𗧂āA���ۂɍ]�˂ŕ���B���A���u70�����W�߂��B�����A��ɝ��Ή^�������Ă����]�Z�i�Ȃ̌Z�j���������Y����u���d������A�ǂ����Ă����Ȃ��ɉ����E���v�ƕK���̐������v���Ƃǂ܂����B ���̌�A���̏�M�}���������]�Z�̏a����i1838-1912������25�j�Ƌ��ɂ̂ڂ邪�A�̐S�̒��B�˂瑸�����Δh���g�����\�����̐��ρh�œs��ǂ��o����Ă���A��64�N�A���č]�ˑ؍݂Őe�����������ꋴ�ƉƐb�E�����~�l�Y�i1822-1864�j�ɐ������ē���E�ꋴ�c��i1837-1913������27�A�h����R�ΔN��j�Ɏd���邱�ƂɂȂ�B�����O�܂œ|��������Ŗ�����̂Ă�o��ł������̂ɁA�ꋴ����Ƃ��x����Ƃ��������̐l������ނ��ƂɁB���N�A�h����������ĂĂ��ꂽ���l�̕����~�l�Y�͐��˔ˋ}�i�h�ɈÎE�����i���N42�j�B �m���ƂȂ����h��͓đ��v�i�Ƃ����䂤�j�A���͐���Y�̒ʏ̂𖼏��B���N�A�V�I�g�����s�O���̗��āE�r�c���ɏW�����Ă����u�m�̈�c����Łi�u�m7�l���S�A23�l�ߔ��j������B�r�c�������ő����̋]���҂��o�����B�˂ł́A���{�ւ̓{�肪�����B���s�ɐi�R���u�֖�̕ρi�����̕ρj�v���u���������A���B�˕�����ÁE�K���E�F���A���R�����ނ����B���Ȃ݂ɁA�h��͓y���ΎO�i1835-1869���h��̂T�ΔN��j�Ƌ��ɕs痘Q�m��ߔ��������Ƃ�����B 1865�N�i25�j�A�ꋴ�ƂɎd���Ĕ��N���o�������A�S���ɂ���ꋴ�Ƃ̗̒n�������č����I�Ȗ���o�����P����l����悤������ꂽ�B�h��͗��ʂ��H�v���ĕĂ�ȉԂ̔_�Ƃ̗��v���������������߂��B 1866�N�i26�j�A���s�ɂĎF���˂ƒ��B�˂��u�F�������v��������A����B�����͒��B�L���ɐi�ށB���R�Ɩ��S�s�S�̂���20�̎Ⴓ�ŕa�v����ƁA���{�͂���𗝗R�ɋx�틦������B���{�̎����I�Ȕs�k�ł���A���B�����̎��s�͖��{���������I�Ȃ��̂ɂ����B 1867�N�i27�j�A�ꋴ�c�삪29��15�㏫�R�ɏA�C���A�h��͈ꋴ�Ƃ̍����^�p�Ő��ʂ��o�������Ƃ��]�����ꖋ�b�Ɏ�藧�Ă�ꂽ�B�����ăp������������̖��{�g�ߐ����ƂȂ�A���R�㗝�Ƃ��ďo�Ȃ���c��ٕ̈��E���쏺���i��������/1853-1910������14�j�̏]�҂Ƃ��ă��[���b�p�����̗�K�ɏo�������B���H�ŃX�G�Y�^�͂̌��ݍH�������āA�����C�ɕς���悤�ȍH�����X�G�Y�^�͊�����ЂƂ�������Ƃ�����Ă���ƒm���āA������Ёi���{�g�D�j�Ƃ������̂́A�l�X���������o�������A����Ȏ��{���W�܂邱�ƂŁA���E�̗��v�ɂ��Ȃ��悤�ȁA�ƂĂ��Ȃ����Ƃ��ł��邱�ƂɋC�t�����������B ���̌�A�h��̓A���N�T���_�[�E�t�H���E�V�[�{���g�i��t�V�[�{���g�̒��j�j�̈ē��ʼn��B�̐i�Ȋw�Z�p��ߑ�I�ȎY�Ɛݔ������������Q�B�����Čo�ϐ��x���Бg�D���悭�w�B�h��́A��s�⊔����ЂȂǂ̎��{��`�̃V�X�e������{�ɍ�낤�ƌ��S����B�܂��A�x���M�[�ō�������S�̔��荞�݂��A����̏��R�����l�̔��荞�݂����Ƃ͍l����ꂸ�A���B�ɂ����鏤�Ƃ̏d�v������������B ���{�ł́A�F���V�c���V�R���̂���35�ŕ���B�a�C���̋}���ł��������ߓŎE�������ꂽ�B�F���V�c�̍c�q�E�����V�c�i�P�S�j���c�ʂ��p���B������11���A�c�삪�����̑�`�������������邽�߁A����ւ̐����ԏ�ƂȂ�u�吭��ҁv��t��B���̗����ɁA�y���ˎm�̍�{���n���ߍ]���ňÎE���ꂽ�B 1868�N�i28�j1��3���i�c��3�N12��9���j�A�����瓢���h�̎哱�Ŗ����V�c���u�������Â̑卆�߁v���������A�V�c�����ւ̕��A���錾�����B���{�����łȂ����������̂����v���ł���A���̃N�[�f�^�[��260�N���܂葱�����]�˖��{���p�~����A���������q�ɖ��{���J���Ė�680�N�ŕ��Ɛ������I������B����A������܂������ɔp��ƂȂ�A����Ɍ`����܂�������́A��1300�N�̖�������B �����āA�V�c�e���̖��̉��ɗL�͔˂����s�ɏW�߁A�����r�����������V���{����������B3�T�Ԍ�A�s�x�O�̒��H����ѕ����ɂ����āA�F���̐V���{�R�Ƌ����{�R���퓬��ԂƂȂ�A���H�E�����̐킢���u���B�����{���͕͂��͂ŏ����Ă������A�V���{�R���f����g�т̌���h�����ē��h�A�c��͒��G�Ƃ����ӂ���������B�]�ˏ�͖����J�邳�ꂽ���A���h�͍~�����悵�Ƃ����A�e�n�ŃQ�����I�����������Ȃ����B���`��4��l�͌c��̉��U�̐��������ꂸ�R��𑱂��A���b�̎q�Ƃ��ē����ɎQ�����Ă����h��̌����{�q�i�݂��Ă悤���A�n�q�O�ɖ���̂��ߐՌp�����w�������ҁj�̏a��Y�i20�j�͏��푈�O�ɏ��`����蕪���ꂽ�U���R�ɎQ�����A�є\�푈�Ŕs�ꎩ�Q�����B 5���ɉh��͐V���{����A���𖽂����A10��19���ɓ앧�}���Z�C������A���̓r�ɂ��A���N12��16���ɉ��l�`�A�������B�A����͓���Ƃ��ڂ�Z��ł����É��ɋ����߂�B 1869�N�i29�j�A�h����É��Ől�X����o�������̂���{�ŏ��̉�Бg�D�ł���u���@��v�������B�r��������G�d�M�i1838-1922�������R�P�j�ɐ�������ĐV���{�ɎQ�����A�呠�Ȋ����Ƃ��Ĉ��]�i������)�呠���(�������炽����)�ƂƂ��ɍ������x�̊m���ɓw�߁A�������x�ݗ��A�ݕ����x�̓����A�ߑ�I�����̓����Ɋ��𗬂����B�܂��A�w���i�����Ă��A�X�ցj��x�ʍt�i�ǂ�傤�����A���[�g����O�����Ȃnjv���̒P�ʁj�̐�����i�߂��B 6��27���i����5��18���j�A�ڈΒn�E�ܗŊs�i���فj�Œ�R���Ă��������{�R�̉|�{���g�炪�V���{�R�ɍ~�����A1�N���ɂ���ԕ�C�푈�͏I���B���N7���A�V���{�́u�ŐЕ�ҁv�����{�A�e�ˎ�ɗ̒n�Ɛl����ɕԊ҂������B�܂��F���y��̎l�ˎ傪��҂��A���˂�����ɂȂ�����B�V���{�͑S���̎x�z�������̎�ɂ����߁A�ˎ��m�ˎ��ɔC�����A�����W�����𐄐i�����B 1871�N�i31�j�A�h��͉ݕ��P�ʂɁu���i�~�j�v���̗p����ݕ��@�u�V�ݏ��v�̐���ɎQ�^�B���N�A��Ђ̐ݗ��Ɋւ���������܂Ƃ߂��w�����(����������Ⴍ����)�x���A������А��x�̒m���y�����A���V�Q�N�Ɂu������s���v���N�����Ă���ȂǁA���Ƃɂ�鍑�Â����ڎw���ĕ��������B 8���A�S���̔˂�p���ĕ{����u���u�p�˒u���v�����{����A�����W���������S�ɒB�����ꂽ�B�u�U���E���߁v�i�f���߁j���o���ꂽ���A�h��͊��Ƀp���Ő��Ă����B�N�����痂�X�N9���ɂ����āA�������{�͏������̏�������C�O���@�̂��ߕĉ��Ɋ�q�g�ߒc��h���B�����S����g�̊�q��A���g�̖،ˍF��E��v�ۗ��ʁE�ɓ������E�R�����F�ȉ��A�����̊������Q���A�Óc�~�q�痯�w�������s���A����100�����������B ���̔N�A�h��Ə��E������ɂ̊Ԃɖ��E���q�i�ӂ݂��j�����܂��B�g���Ɂh�͉��Ȃł��܂������Ƃ��ē����Ă����Ƃ���h��Ɍ����߂�ꂽ�B�̂��ɕ��q�͉h��̍Ȑ��̌Z�����Ւ��̎q�E���Y�ƌ������A��ȉƁE�w���҂Ƃ��Ēm������������i�Ђ�����/1911-1951�j�ށB�̂��ɏ����̎q�E�����i���������j�������Ȏw���҂ƂȂ����B 1872�N�i32�j�A�������{�̐B�Y���Ɛ���̈�Ƃ��āA�呠�Ȃ̉h��Ɩ����Ȃ̔����Ւ��i�`�Z�j�̗��ĂŁA�Q�n���x���ɓ��{�ŏ��̊��c�̊�B�����H��u�x��������v���J�ƁB�t�����X�̊�B��Z�p�����A�����͑S������`�K�H�����W�B��B�J���Z�p���K�������A�ޏ���͋A����e�n�̊�B������̔��W���x�����B���{�݂�2014�N�ɐ��E������Y�ɓo�^���ꂽ�B ���N�A�����痯�琭�{�͑S���ɏ��w�Z��ݗ�����u�w���v�z�B�܂��A�l�g�����̋֎~���߂��|���W�i�������傤���j����߂��o���A���z������������B���̔N�A���{�ɏ��߂ēS�����ʂ�B 1873�N�i33�j�A�h��͍����^�p�̍l�����̈Ⴂ����呠�Ȃ�ފ������삷��B1��7���A���������V���ɋ�s�ݗ��̂��ߓ��{���ƂȂ銔���W�̌������o���B���N7���A�ŏ��̊�����Ёu��ꍑ����s�v�i����s�̑O�g�B���݂��ً�s�j���J�Ƃ��đ��Ė��ƂȂ�A1875�N����1916�N�܂�40�N������߂��B�u�����v�Ƃ��邪�A���̖@���ɂ̂��Ƃ�Ƃ����Ӗ��ł���A�����܂ł����Ԃ̋�s���B�S���ɐݗ����ꂽ�����̍�����s�̎w���A�x�����ꍑ����s��ʂ��čs�����B ���N�A�����{�̊��z�|�i���F�����K�X�j�̈ψ��ƂȂ�K�X���Ƃ��v��B 1874�N�i34�j�A�h��͐��������҂̋~�ώ��ƁE�{��@�̉^�c�Ɍg���B���������͓����{�m���̑�v�ۈꉥ�i1817-1888�j����u�����ϋ��i�݂���j�̉^�p�������ė~�����v�u�n���ҋ~�ς̂��߂Ɏg���Ă���v�Ɨ��܂ꂽ���ƁB100���s�s�ƌ����Ă����]�˂́A�����̍����Ől����50���l�ɂ܂Ō������A����������6�����n���������B�u�����ϋ��v�Ƃ�1791�N�A�����̉��v�̂Ƃ��ɘV���E������M���A�Q�[�ɔ����č]�˂̒�����̐ϗ����̎����ɑ�������Ă���݂������~�������́B�Q�[���N����Ɓu���~���āv�Ƃ��ĕ��o����A�]�˂̐l�X�̂�����Z�[�t�e�B�[�l�b�g�ł���A�^�p������170�����i��170���~��1����1���~�j�������B�h�ꂪ�����{�݂́u�����{��@�v��K���ƁA100���100�l�̘V�l�A�q�ǂ��A�a�l���l�ߍ��܂�Ă����B�u�����ɖ����Ŏ��e���Ă���ɂ��Ă��A����ł͂��܂�ɋC�̓ł��v�A�����������h��͗{��@�̉��v�ɏ��o���B�a�l��V�l�̂��߂ɋߑ�I�Ȑf�Ðݔ���ݒu�A�E�ƌP�������݂��A�q�ǂ������ɂ͊w�⏊�����m�����w�����B �h�ꂪ���ɒ��ڂ������̂́g���h�B���ꂩ��̎���͎�����ʂɕK�v�ɂȂ�Ɨ\���B�a����萼�m���̕������������ł��邽�߃C�M���X�̐����@�B��A�������B1875�N12���A�O��g�A����g�A���c�g�����U���ċ����o�c�̐�����Ёu������Ёv�i���F���q�����j��ݗ����i�����V�c�����w�ɂ����j�A�`���̉���약�O�Y�i�h��̍Ȑ��̎o�݂��q�̎q�j�ɋZ�p�����S���������B���Ђ͌��݁A���{�ő�̐�����ЂƂȂ��Ă���B ������̗��琭�{�͕x���������X���[�K���Ɂu�����߁v���{�s���A�y�n�E�d�Ő��x���v�ł���u�n�d�����v�����s�B�]���̔N�v�Ăɂ�镨�[���x����A�y�n�̉��l�Ɍ����������K��[�߂�����ېŐ��x�ɉ��߂��B 1875�N�i35�j�A���ē��{�㗝���g���I���ċA�������X�L��i����̂�j���A�h��̋��͂ď��Ɗw�Z�u���@�u�K���v�i���F�ꋴ��w�j��n�݁B�h��͌o�c�ψ��Ƃ��ĉ^�c���x�������B ���N�A�������{�͍����𑱂��钩�N�ɊJ���𔗂��ČR�́g�_�g�h��h�������Ƃ���A����i�\�E���j�ɋ߂��]�ؓ��ŖC�������i�]�ؓ������j�B���N�A���N�͓��{�Ƃ̐푈������邽�ߕs�������̓����C�D���K������J���̓�����ށB 1876�N�i36�j�A�h��͖��Ԃ̗��ꂩ�犔����Е����ɂ���Ɛݗ����w���B���̔N�͐ΐ쓇���쑢�D���i���FIHI�A�����U�����ԁj�A�G�p�Ɂi���F����{����j�A���O�����V��i���E���{�o�ϐV���j�̑n�݂��x�����Ă���B �����͏����ɓ��{�̋ߑ�Y�Ƃ̔��B��]���̂ł���A���푾�Y�i�O�H/1835-1885������41�j�A�Z�F�F���i1865-1926�j�A���c�P���Y�i1838-1921�j�A�O�䍂���i1808-1885�j�Ƃ����������̎l������n�n�҂Ƒ傫���قȂ�A�u�a������v�ɂ������Ȃ������B�������₷���Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��A�u������ǂ킸���v��}��v�Ƃ̋����M�O�������Ă����B ���a��Ƃ͎����������Ȃ����ߖ{���̈Ӗ��ł̍����ł͖����������A���GHQ�̌���ō�����̂̎w����邱�ƂƂȂ����B 1877�N�i37�j�A�������{�ɑ���s���m���̍ő傩�Ō�̔����u����푈�v���u���B�s�k����������49�Ŏ��n������͏I������B�h��͍���햯������푈�̏��a����G���������~�삷��ړI�Ŕ����Ёi�̂����{�ԏ\���Ёj��n������ƎЈ��ɂȂ�^�c�ɌW������B 1878�N�i38�j�A�������@��c��(�̂��̓������Ɖ�c��)��ݗ����A��ɏA�C�B���H�Ǝ҂̉��̌q��������A���L�������W�߂��B���N�A�L�����{���W�ߎ��Ƃ��N�������{��`�̍l���������H���邽�ߓ��������������ݗ����A��ꍑ����s�̊����𗦐悵�ď�ꂷ��B�܂��A�h��͑���������{��Ƃ̊C�O�i�o������ɓ���Ă���A���̔N�A��ꍑ����s�Ɋ��R�i�ӂ���/�v�T���j�x�X��ݒu�������B ���N�A�������{�̒��S�ƂȂ��ĐB�Y���Ɛ���Ȃǂ𐄐i�����F���o�g�̑�v�ۗ��ʁi1830-1878�j���A�s���m���E���c��Y���47�ňÎE�����B 1879�N�i39�j�A�h��͉��q�̔R�ɕʑ���݂���B���N�A�O�č��哝�̃O�����g���R���}����J���A�R�̎��@�ł����}������{�B ���̔N�A�����{��@�̉@���ɏA�C�B�܂��A�����C��ی���Ёi���F�����C������Еی��j�n�����N�l�A���k���ɏA���ی��Ƒn�Ƃ��x���B���N�A���{�͗���������p�����ꌧ�Ƃ��ĕ��������B 1881�N�i41�j�A�����{��@�̔p�~�Ă������{�c��ɒ�Ă���A�h��͋c��Ő키�B1879�N����{��@�̉^�c��͎����ϋ��ł͂Ȃ������{�̐ŋ��ʼn^�c����Ă������߁A�x�������_�҂́u�n�����~�����߂ɑ��z�̐ŋ����g���̂͂�߂�v�Ƃ����A�W���[�i���X�g�̓c���K�g�́u�a��͑Ė������̖{�����B�a�悯���Ȃ��������������邩��Ė�����������B�{��@����S���ǂ��o���v�ƌ����������B����ɑ��A�h��́u�ꍑ�̎�{�ɂ��Ă��ꂭ�炢�Ȑݔ���u���ċ������~������Ƃ������Ƃ͐�ɕK�v�ł���B��������L�ׂʂ͖̂����߂Ȗ\���ł���v�ƒ�R���A�{��@�����B ���N����1883�N�܂ŁA�h��͓�����w�ɂ����Ď���u�t�Ƃ��ē��{�����_���u�`�B ���̔N�A�h��͓����ƐX�����ԓ��{�S����Ёi���F�����{���q�S���j�̑n���ɓ������āA��������U���l�ނ��W�߂đn�݂ɐs�͂����B ���E�ł͎F���o�g�̊J���E���c�������A������30�N���Ƃ����D�����ŁA�����̐����E�ܑ�F����ɊJ��g���L�̊��c���Ƃ������悤�Ƃ������Ƃ����o�B���_�Ǝ��R�����h�ɂ�鐭�{�ᔻ����������B����J�݂ƌ��@��������߂鎩�R�����^���̍��܂�ɑ��A������́u����J�݂̏فi�݂��Ƃ̂�A���@�j�v�i���B�N���j���Ē鍑�c��i��@�F�M���@ �A���@�F�O�c�@�j�n�݂̎������u����23�N�i1890�N�j�v�Ɩ������A�^���̒��É���}�����B �n���C�����J���J�E�A���O������Ƃ��Ă͏��߂ĖK����������Ɖ�k�B�h��̓J���J�E�A���̏��҉��R�@�ɂĊJ�Â���B 1882�N�i42�j�A�ȁE��オ�R�����ŕa�v�i���N41�j�B �h�ꂪ�n�Ƃ��x�������ŏ��̖{�i�I�a�ъ�ƁE���a�сi���F���m�a�j���J�ƁB���N�A�����^�A���ݗ����O�H�����̓��{�X�D�ɂ��C�^�Ɛ�ɑR�i3�N��ɎO�H�D�D�ƍ������ē��{�X�D�Ɂj�B�����d����Ёi���F�����d�́j���N�l�ƂȂ�B 1883�N�i43�j�A�|�W�̈ɓ����q�i1852-1934������31�j�ƍč��B���q�͂��Ƃ��ƍ]�ˋ��w�̍����A�ɓ������q�̖��ł��������A�ېV��Ɉב֎��������ʼnƋƂ��X���A�v�����Ă����B���V���A���Y�A���q�A�G�Y�̕�B ���N�A���Z�����g�H��i���F�����m�Z�����g�j�n�Ƃ��x���B 1884�N�i44�j�A�n���ҋ~�ώ{�݁u�����{��@�v�p�~�̊�@������A�h��͕{�m���Ɍ��c�����o���u�������̎{�݂��Ȃ���Ή쎀�҂����H�ɉ������S��ɂȂ�ł��傤�B�������l����Δp�~���ׂ����̂ł͂���܂���v�Ƒi�����B�����A���ɓ����{��@�̔p�~�����肵�Ă��܂��B�h��͋c���ɚV����������u�{�����قǂ܂łɖ���ł���Ȃ�A����͗{��@��Ɨ������Ď����o�c����v�B�h��͖��Ԏ����ʼn^�c���p��������Ɛ錾�A��t�W�߂̂��߁A�O�N�Ɋ�����������̎��قɖڂ������B���{��������E�̕w�l�����ɂ͂��炫�����A���قœ��{���̃`�����e�B�[�o�U�[���J�Â��A��܁A���܁A�l�`�A�G��ȂǁA3��_���I�[�N�V�����ɏo�i�A���グ��3���Ԃ�7500�~�i��6800���~�j�ɂ̂ڂ����B����ɁA�h��͍��E�̓Ďu�Ƃ��ЂƂ�ЂƂ�K�ˁA�^����Ɏ�������t���������ŁA�傫�ȃJ�o���������o�����B�N�����ƊE�̃J���X�}���狁�߂�ꂽ��t��f��Ȃ������B�h��͏W�߂���t���������s�a���ʼn^�p���A�����𑝂₵�Ă����A�����{��@�̎�����1885�N��3��5031�~�i��2��9800���~�j�ł������̂��A5�N���1890�N�ɂ͖�3�{��11��8104�~�i��8��8500���~�j�ɑ����Ă����B�h��͊�t�����̓���݂̏��Ȃ����{�ŁA�����ɎЉ�����Ƃ̎������m�ۂ��A���̌�A�{��@�͓��m��̕����{�݂ƂȂ����B�{��@���O���ɏ悹��ƁA�h��͕��������̑Ώۂ������҂����łȂ��A�ЊQ�ɂ����č����Ă���l��a�C�ŋꂵ�ސl�ɍL���A��Â�w�p�{�݂̐ݗ���^�c�ɋ��͂��Ă����A���H���i�邩�j���ەa�@�A���{���j�\�h����A�����w�������Ȃǂ��x�������B 1885�N�i45�j�A�W���p���u���������[�i���F�L�����z�[���f�B���O�X�j�ݗ��̗������ƂȂ�B���N�A���t�����������A�ɓ�������������t������b�ɏA�C�B 1887�N�i47�j�A�h����j�����ڂ̕������������ɂ����āA���q�ւ̍�������̕K�v���������A�ɓ������A���C�M��Ə��q���珧����ݗ����A������̂Ƃ��ē������w�ق�ݗ������B ���N�A�����g�i���F�������݁j�̌�p�҂��c���̂��ߑ��k���ɏA���o�c�ɂ�����B�D�y�����i�T�b�|���r�[���j�ݗ��ɎQ���B�����z�e���i���F�鍑�z�e���j���N�l����A���{�y�؉�Ёi���F�听���݁j���N�l����B 1888�N�i48�j�A�É͎s���q�̑����z�R�g���i���F�É͋@�B�����A�É͓d�C�H�ƁA�x�m�ʁA�x�m�d�@�A���l�S���j�̐ݗ����x���B�܂��A�V�����̓��u�Ђ̑�w�ݗ�����̕�W��Ǘ��ɐs�́B ���N�A�ɓ��͌��@�E�c���T�͂̐��莖�Ƃɐ�O���邽�߂ɑ�����b�������Đ����@�c���ɓ]���A�F�����̍��c��������Q����t������b�ɏA�C�B 1889�N�i49�j2��11���A���Ă̒��ԓ����ڎw���������{�́A�A�W�A�ŏ��̌��@�u����{�鍑���@�v�����z�B���{�̓A�W�A�ōŏ��̗����N�卑�ƂȂ����B�����Łu����{�鍑�͖����i���j��n�̓V�c��������v�Ƃ������A���Ƃ̓�������V�c�ɏW���B����A�ɓ��͑�4���Łu�V�c�́A���̌���ł����āA�������𑍝��i�������j���A���̌��@�̏��K�ɂ��A������s���v�Ƃ��A������b��鍑�c��ɂ�鐧����ۂ����ƂŁA�V�c�̓ƍق�h���d�g�݂�������B ���N�A�O����b�̑�G�d�M�i1838-1922������51�j�����e�ňÎE���ꂩ������G��������N����B�ݗ��O���l�̎��O�@����P�p���邩���ɁA�O���l���������ٔ��ł͊O���l���ٔ����ɔC�p����Ƃ������ɐ��{�����Ă������Ƃ����o�A�����������m�Ѝ\�����̉E���E�����P�삪��G�ɔ��e�𓊂��A��G�͉E�r�������d�����A�����͌���Ŏ��n����B���c���t�͑ސw���A���B���̎R�p�L���i1838-1922��51�j����R����t������b�ɏA�C�����B 1890�N�i50�j7����1��O�c�@�c�����I�������{�����B15�~�ȏ�i���݂�30���`60���~�H�j�[�ł��Ă��閞25�Έȏ�̓��{�����j���A�S�l���̖�1�����������[�ł����B 11��29���A�������@�{�s�ɂ��킹�Č��I�̏O�c�@�i���@�j�Ɣ���I�̋M���@�i��@�j����\�����ꂽ���{�ŏ��̒鍑�c��J���ꂽ�B 1891�N�i51�j�\�Z�𐬗����������R�p���t�͑����E���A�F�����̏������`����S����t������b�ɏA�C�B5���A�K�����̃��V�A�鍑�c���q�E�j�R���C�i��̍c��j�R���C2���j���A���ꌧ��Ò��Ōx�@���E�Óc�O���ɓˑR�a�����ꕉ��������Î������N����B 1892�N�i52�j�����̒��~���W�߂钙�~��s�̐��x���ł������Ƃ���A�h������s�����̏o���ɂ��A�������~��s�i���E�肻�ȋ�s�j��ݗ����A�h��͎������߂��B ��2��O�c�@�c�����I�������{����A�I�����Ԓ��A�����Ȃ͑�K�͂ȑI�������s���A�����h�𒆐S�Ɏ���25��������388�����o�����B����ɍR�c���ė����_������b�����C�A�₪�đ����E�ցB�ɓ��������ēo���đ�T����t������b�ƂȂ��2���ɓ����t��g�t����B 1893�i53�j�A�C�O����̕o�q�ɑΉ����邽�߂̑g�D�Ƃ��āu�M�o��v��ݗ����������ƂȂ�B�i�̂���JTB�ݗ��Ɍq����j 1894�N�i54�j�A�u���p�ʏ��q�C���v�i�������j��������A�ېV�ȗ��ő�̌��Ă������e���Ƃ̕s�������̉����ɏ��߂Đ��������B7���A���N�̗������߂����đΗ�������{�Ɛ����̊͑������N�������݂Ō�킵�A�����ɓ����푈���u������B 1895�N�i55�j�A�����푈�̍u�a���ł��鉺�֏�A���{�S���ɓ������E�����@���Ɛ����S�������͂Ƃ̊ԂŒ��������B���{�͐����ɒ��N�̓Ɨ���F�߂����A��p�Ɨɓ������i�������k���A�얞�B�j�𐴍����犄���������B�܂��A���̐푈�œ��{�͓����̍��Ɨ\�Z��2�{�ȏ�ƂȂ��2���~�̐������������A��3���~�̋��z�̔��������l�������B����������Ƀ��V�A�E�h�C�c�E�t�����X�R���̊����ɓ�������Ԋ҂���B���̈ꌏ�ŎO���Ɏ肪�o���������́A�h�C�c���P�B�i�������イ�j�p�̑d�i�����Ⴍ���̓y�̈ꕔ��݂��j��F�߂��̂��@�ɁA���V�A�ɗ����E��A���A�t�����X�ɍL�B�p���A�C�M���X�ɎR�������̈ЊC�q���A���X�ɖ����n�����ƂɂȂ����B��p�ł͊������Δh�̐����l�����炪�u��p���卑�v�̌�����錾����B���{�R����p�k���ɏ㗤���J�n����ƁA�R���`�E�������͒�R���A�T������ɏ����p���E���R���I�i����� �����̂�j���S������錾�����B���̊ԁA���{�R�ɎE���ꂽ��p���卑�R�A�`�E���A�Z���̎��҂͌v14000�l�B�܂��A���{�R�̎��҂�4806�l�i�펀��164���A�a����4642���j�A�R�v7000�l�i����j�ɂ̂ڂ����B�a���҂��܂ނƁA�����푈�S�̂ɂ�������{�R�̎��҂̔�������p����ɂ����́B ���N10���A���N�ł͊؍������S�����g�E�O�Y��O���A��26�㒩�N�����E���@�i�R�a�����j�̔܁E�{�܁i�~���s�j�̃��V�A�ڋ߂ɕ��S�A���{���������A��ĉ��{�ɏ�荞�ݔ܂��ÎE�����B�O�Y�͓��{�l�������N�l�̎d�Ƃɂ�����肾�������A�Q�l�̊O���l�ɔƍs��ڌ�����Ă��܂��B���{���{�i�ɓ������j�́A���g���ƒf�ňꍑ�̉��܂��E�Q�������Ƃɋ����B���۔ᔻ�����킷���߁A���N���{�Ɉ��͂������ĂR�l�́g�^�Ɛl�h�i���N�l�j��߂炦�����A�����ɍi��Y�ɏ����āu����l�͓��{�l�ɕϑ��������N�l�v�Ƃ����R�����Ƃ������B 1896�N�i56�j�A�h��͋D�Ԑ����i���F���d�H�Ɓj�n���ψ��ɂȂ�B���N�A�i���}�i��G�j�Ə�����F��������g���Ĉɓ��Ɣ��ځA�ɓ��͐����ێ�������Ƃ݂Ď��E�B�������`����6����t������b�Ƃ��čēo����B 1898�N�i58�j�A�؍������n���@�A�؍��c�鍂�@�ɉy���B�؍��̃C���t���������x�����A�����Ԃ̖f�Ղ�ʂ��đP�חF�D�W�����ڂ��Ƃ̍l������A�����S���A���m�S���̕~�݂ɐs�͂���B ���N�A�����͐i���}�ƘA�g�������n�d�����i�������傤�A���Łj�őΗ��������E�A�ɓ���������7����t������b�ɏA�C�B�����A���}���}�ɓڍ����Ă킸�����N�ő����E�B��G�d�M����8����t������b�ɏA�C���A���̐��}���t�ƂȂ��G���t�i�G���t�j��g�t�����B�������4�J�������������A11���ɎR�p�L������9����t������b�ɏA�C�B��N�Ԃ�3��������鍬���Ԃ�B 1900�N�i60�j�A��p����w�Z�i���F��B��w�j�̊w�Z�ݗ��ɐs�́B���N�A�ɓ����ێ琭�}�u�������F��v�������A���㑍�قƂȂ��10����t������b�ɏA�C�����B 1901�N�i61�j�A�h��͓��{���̏��q��w�u���{���q��w�v�̑n���ɂ����Ă��x�����s�����B�̂��ɍZ���������Ă���B���N�A���B���̌j���Y����11����t������b�ɏA�C�B 1902�N�i62�j�A�h��͉��Ă����@���A�e�n�̏��H��c�������o�[�ƌ𗬁B�Z�I�h�A�E���[�Y�x���g�č��哝���Ƃ���k�����B���[�Y�x���g�͓��{�̗��R����p�Ɋւ��Ċ����̎^�����q�ׂ����A���H�Ƃɂ��Ă͈ꌾ���Ȃ������B����䂦�A�h��͐ȏ�Łu����y���̍ۂɂ́A�o�Ϗ�̐i������ƉƂ̓w�͂ɑ��A�����̔�]������������悤�ɂȂ��Ă������v�ƌ�����B ���N�A���{�E�C�M���X�����V�A�̓��A�W�A�i�o����������ړI�ŌR�������ƂȂ���p����������A�̈������ׂ��R���I�A�o�ϓI�����̏[����}�����B ���{�����O�̑�ؒ鍑�ŏa��h���}���ɂ���������1902�N����04�N�ɂ����Ĕ��s���ꂽ�B����s�͒��N��������16�̎x�X�Ɖc�Ə���W�J���A�a���z�͑�ؒ鍑���{�̔N�ԍΏo���Ă����B�����A��ؒ鍑�ł͂ɂ�������ʂɏo����Ēʉݎ���͍������Ă���A����s�͖�`�́u����s���v�s�B1�~�A5�~�A10�~��3��ނ�����A�\�ʂɈ�����ꂽ�̂���s�n�ݎҁE�a��h��̏ё��������B�̂��Ɋ؍����ĂƂȂ����ɓ������̕��j�Œ�����s�i�̂��̒��N��s�j�������s����悤�ɂȂ�A����s���͉������Ė�4�N�Ŗ������I�����B 1903�N�i63�j�A��G�d�M��Ƌ��ɓ���̐ݗ��Ɍg���B 1904�N�i64�j2��8 ���ɓ��I�푈�u���B���{�C�R�������`�̃��V�A�͑����P���A���R���m��ɏ㗤���ē��I�푈���n�܂����B���N��A�T�؊�T�������R�R�����V�A�͑���n�E�����̕�͐�ɓ˓��B�T�J���ɋy�Ԍ���łU���l�̎����҂��o���Ȃ���A���P�X�O�T�N1���ɏd�v���_�g��Z�O���n�h���ח��������B���łR���ɍő�̗���ƂȂ�����V���𐧂��A�T���ɓ��������Y������A���͑������{�C�Ńo���`�b�N�͑�����ł������B���{�R�͗��C�ɏ����������̂́A���́E�e�ɒ�����A���{�͍u�a���}�����B����A���V�A���������Ŋv���^�����N�������Ƃ���A�����Ƃ��푈�p��������ɂȂ�A�A�����J�̒���ōu�a����������B���{���̐펀�҂͖�W��4000�l�A�폝��14���l�ȏ�B�R����͍��Ɨ\�Z�̂V�N���ɂ�����18���~�ɂ̂ڂ����B 1905�N�i65�j9���A���I�푈�̍u�a���ł���|�[�c�}�X�������B���{�͗ɓ������̐�[�E�֓��B�i�����A��A�j�̑d�،������V�A����l�������B�O�����ŒD��ꂽ���̂����Ԃ����`�B�܂��A�����̓씼����V�A���~�݂����얞�B�S������ɓ��ꂽ�B�������������͈ꕶ���Ⴆ���B ���N�A����؋���B���{�͊؍��̊O������D���ی썑���A����i���\�E���j�ɓ��ĕ{�ݒu���K�肵�A�ɓ��������؍����ĂɏA�C�����B����̓����A���{�R�͉��{�O�L��ʼn��K���s�������̈��͂��������B������̕ی썑�Ƃ��ꂽ�؍����ɂ͔�������Q�����\���ɔ��W�A���̊؍����t���̓@��s���̏Ă������ɂ������B 1906�N�i66�j�A����d�C�S���i���F����z�[���f�B���O�X�j�n���ψ����A�鍑�����Ёi���F����A������فj�n���ψ����A����{�����i���F�T�b�|���z�[���f�B���O�X�A�A�T�q�O���[�v�z�[���f�B���O�X�j�ݗ�����c���߂�B ���N�A�j���Y���t�̓|�[�c�}�X����̑����������Ď��E�B���Əo�g�̐��������]�i��������j����12����t������b�ɏA�C����B 1907�N�i67�j�A�h��͓������b��@�i���F�������b��j�̑��k���A�ψ����ƂȂ���c���ɐs�́B 1908�N�i68�j�A�h��͊�������i���F���L���a�@�j�̐ݗ��ɐs�͂������قƂȂ�B�܂��A�����ƌ��ԓ����D�D��Ђ�ݗ��������C�^�Ƃ̓�����s�����B�L���X�g���n���P�c�̂̋~���R�n�ݎ҂̃E�B���A���E�u�[�X�̗������A�R�@�Ŋ��}�ߎ`����J�ÁB ���N�A���������t�͍��������߂��錳�V�Ƃ̑Η��Ŏ��E�B�j���Y����13����t������b�ɍēo�B ���̔N�A�؍��c��E���@�����؋���̖�����i����ׂ��A�I�����_�E�n�[�O�̑�Q�ە��a��c�ɖ��g��h�������u�n�[�O���g�����v���N����B���{�͊؍��ւ̈��͂�����ɋ��߁A�u�؍����{�̊����ɓ��{�l��o�p�ł��邱�Ɓv�u���������̔C�ƌ�����{���i�؍����āj�������Ɓv�Ȃǂ���߂�ꂽ��O�����؋���i��3�����؋���j������B���N�̓����͊��S�ɓ��{�̊NJ����ɓ������B����Ɋ؍��R�̉��U�A�i�@���ƌx�@���̈ϔC����߂�ꂽ�B8���A�O���������ł͂Ȃ��A�x�@����i�@���܂ŒD���A�R���܂ʼn��U�����ƒm�����������A�Ɨ����f����`���i�s���R�j�ƂȂ��čR�����N�B���{���́w���N�\�k�������x�ɂ��ƁA�����܂ł̂R�N�ԂŎE�Q���ꂽ�g�\�k�h��`���͂P��7718�l�B����A�ߗ���1933�l�������Ȃ��B 1909�N�i69�j�A����70�ƂȂ����h��́A��s����������Čo�ϊE������ނ��A61�̉�Ж��������C����B�ȍ~�͎Љ�������ɐs�͂��Aᚁi�炢�j�\�h����̐ݗ����T�|�[�g���A���{�ōŏ��̒m�I��Q���҂̂��߂̋���E�����{�݁u��T��w���v���㗝�����A���H�����ەa�@���㗝�����ȂǂɏA�C�����B ���̔N�A�h��͑S���̏��Ɖ�c������W�߂��n�Ď��ƒc��g�D���A����𗦂���3���������ăA�����J�e�n��K�ˁA�f�Ֆ��C�̉����A���ݗ����̐i�W�ɓw�߂��B9��19���A�a��̓A�����J�̃~�V�K���ΔȂ��^�t�g�哝���Ɖ���A���Đe�P�̂��߉������s�����B�i�v��j�u���{�����čЊQ�ɂ������Ƃ��A�M���͓����\��������^���ĉ��������B�䂪�S�����͂���ɑ��i�v�ɕς��Ȃ��D���������Ă���܂��B���̗F�D��[�߂邱�Ƃ����{�����S�̂̔M�Ȃ��]�ł���A���������l�̊�]���č����S�̂ɂ��݂��A���������K��鎊�鏊�Ŏ����}�����̏��ƂȂ�܂��B��X�͉��̊��E���тт��ɖK�Ă��܂������A������L�`�ɉ��߂���A���{�������M�����ɑ��Ĕh���������a�̎g�߂Ƃ������܂��B�����X�����{���o������ɂ�����A�V�c�É��͉ߋ��ɖ����قǂ̌������䂪��s�ɗ^�����A���{�ɂĉ����������ĉ������܂����B�䂪���ɂ����ẮA���E��тт��ɊO���ɂ����ނ��҂ɑ��ẮA��O�̖��_�Ƃ����ׂ����̂ł��B�{����b�͒��|��āA��X���ƒc�̓n�Ă͐[���É��̐S�ɉ������̂Ɠ`�����A���ƒc�̐������É��̊�]�Ƃ��q�ׂ��܂����B�����Ԃ̐e�P�Ȃ�F��́A�N�Ƌ��Ɍ��łɂȂ�A���`�E���a�̊�b�̏�ɁA�����ς��Ȃ����Ƃ�]�݂܂��v�B ���N10���A����؍����āE�ɓ������i68�j���n���r���w�ň��d���i�A���E�W�����O���A30�j�Ɍ�����▽����B���͂��Ƃ��Ɛe�����ŁA���I�푈�œ��{�����Ɓg�A�W�A��������|�����h�g���{�̓A�W�A�̊�]�h�Ɗ��т��Ă����B�Ƃ��낪�A���I�푈��̓��{�́A�؍��ɓ��������ĊO������D���A�c���ވʂ����R��x�@�܂ʼn��U�������B�[�����]�������́A�Ɨ��^���̂��߃��V�A�֖S�����āu��؋`�R�v��g�D���A���u�Ƌ��ɖ�w���A���̌��ō����ɑ�ؓƗ��̕������������߂�؋�����̍R�������ƂɂȂ����B�ߕߌ�A���͎�蒲�ׂɍۂ��A�ɓ��ÎE�Ɏ��������R���q�ׂ��B�u�؍��c���p�ʂ��������Ɓv�u�؍��̌R�������U���������Ɓv�u�`�������ɍۂ������̗ǖ����E�Q���������Ɓv�u�s�����������������Ɓv�u�؍��̊w�Z���ȏ����ċp���������Ɓv�u�؍��l���ɐV���w�ǂ��ւ������Ɓv���X�B���̒��ɂ́u�����V�c�̕��N�i�F���V�c�j���ÎE�������Ƃ͊؍����݂Ȃ��m���Ă���v�Ƃ��������̗��R���܂܂�Ă���B�ӔN�̈ɓ������͓��ؕ����ɌX���Ă������A����ł����{���ł͕����T�d�h�������B���͈ɓ����ÎE�������ƂŁA���ʓI�ɂ͕��������������A�Y���T�J����ɑ�ؒ鍑�͒n�}�ォ����ł��Ă��܂����B 1910�N�i70�j5���A�K���H���瑽���̎Љ��`�ҁE�����{��`�҂��g�����V�c�ÎE���v�悵���h�Ƃ��Č������ꂽ�u��t�����v���N����B�����҂͑S���Ő��S���ɂ̂ڂ�A�W�J����ɂ킸���Q�T�Ԃ��܂�̔���J�ٔ��i�P�l�̏ؐl���o�삳������R�����ŏI�R�j��24�l�Ɏ��Y�������������B�����Ĕ����U����Ƃ����ٗ�̑����ōK���H����11�l���i��Y�ƂȂ����i��������ɂP�l���s�j�B12�l�����������Ɍ��Y���ꂽ���A�����T�l�͍����B���Y�͐��E�ɂ��Ռ���^���A���{���{�ɏ��O���̎v�z�Ƃ���R�c����ꂽ�B���A��t�����Ɋւ��č���ɂ�钲���ނ̝s����A�퍐�̑唼�����W���������Ƃ����������B 8���A��R��؍����āE�������B�i�܂������j���؍�����������؍����{�̊t���ɓ`����B�؍����͐V������������{�����߂邱�Ƃɋ����A�؍��̖��̂��c���悤�v�]���邪���ۂ����i���{�����߂��V�����́g���N�h�j�B�����āA���{���؍��x�z�̋����̂���3���ɂ킽�茋����̑����Z�A�u�؍������j�փX�����v�i���ؕ������j���������B����ĂƗ����p������������B�u�؍��c�邪��ؒ鍑�i�؍��j�̈�̓����������S���i�v�ɓ��{���c��i�V�c�j�ɏ��^����v�ƋK��A���{�͊؍��������B�Ȍ�A���{�̓\�E���ɓ����@�ցi���N���{�j��u���A�؍��̑S�����c�̂����U�����A������W����֎~���A���N��̐V����p���ɂ����B���ʏ�́u�؍��c�邪�V�c�ɓ����������n���A�����V�c����������v�Ƃ����`�ɂȂ��Ă���B�������A���̕������x�����Ă����e���h�̐������ЁE��i����߂Ă����̂́u�Γ������v�������B���ꂪ�W���J���Ă݂�u�]�������v�ɂȂ��Ă����B�����A�����𐄐i������i��́g�p�ς݁h�ƂȂ苭�����U��������B1945�N�̔s��܂œ��{��35�N�Ԏx�z�����B 1911�N�i71�j�A�h��͎��P���ƒc�́E�ϐ���i�������������j�̊���W���b�l�ƂȂ�A�������c�ݗ��ɐs�́B2��21���A��2���j���t�̊O����b���������Y�́A�e���Ƃ̒ʏ��q�C���i�������j�������ƂȂ�̂��_�@�ɔߊ�̊Ŏ��匠�ɏ��o���A�܂��A�����J��ɊŎ��匠�̊��S��B�������B�C�M���X�Ƃ̐V�ʏ��q�C���́A���N4��3���ɒ���A7��17���ɔ��������B�������ĕs�������̉������ʂ����A���{�͗Ɗ��S�ɑΓ��ƂȂ�A�܂����̈���ƂȂ����B 8��30���A�j���t�͐l�S�ቺ�ɂ��t���s��v�ő����E�B��14����t������b�ɐ��������]���ēo���A��2�����������t��g�t����B 1912�N�i72�j�č��ŋN�������{�ږ��r�ˉ^���Ȃǂɑ��A�č��l�̑Γ����𑣐i�̂��ߕč��̕@�ւ֓��{�̃j���[�X��`����ʐM�Ђ̐ݗ����āA���ےʐM�Ђ�ݗ�����B���Ђ͎����ʐM�ЁA�����ʐM�Ђ̋N���ƂȂ����B 7���ɖ����V�c��59�ŕ���B�c�ܖ������q�Ƃ̎q�ł���c���q�E�Ðm�i�悵�ЂƁj�e������123��V�c�Ƃ��đH�N���A�吳�Ɖ������ꂽ�B ���̔N�A�ُk�������Ƃ��2�����������t�͗��R�ɂ��2�t�c���݈Ă����݁A�����������R��b�͑吳�V�c�Ɏ��\���o�B�����āg���E�C��b�͌�������I�ԁh�Ƃ������x�𗘗p���āi�����点�邽�߂ɌR�͂킴�ƌ����o���Ȃ��j�A���������t���E�ɒǂ����B��15����t������b�Ɍj���Y���A�C�i3�x�ځj �B 1913�N�i73�j�A�k���ĎO�Y�̓��{���j�\�h����ɕ]�c���Ƃ��ċ��́B���N�A�h��̒��j�ŐՌp���̓ē�i1872-1932������41�j���V���̌|�҂ɂ̂߂荞�݁A�h�ꂪ�J��Ԃ����ӂ��Ă�����݂����u�Ȃ�ǂ��o���Č|�҂ƕ�炷�v�ƌ����o�����̂ŁA�h��͓ē��p���i�͂����Ⴍ�j���A�Ռp���ɓē�̒��j�E�a��h�O�i1896-1963������17�j���g�������B�h�O�͂̂��ɓ���فA�呠��b�Ȃǂ��C����B�������A�h�ꎩ�g����̏����D���ŁA���q�������B ���N�A�����������ؖ����̍����}�}��E�������h��͖��Ԃ��\���ďo�}����B ���N�A�j���t�͌����i��^���ɂ�葍���E�B��16����t������b�ɊC�R�̎R�{�����q���A�C���A�������F��ƘA�g�������t��g�t����B ���̔N�A�h�ꂪ�h�����Ă�������c�삪76�Ŕg���̐��U����Ă���B�h��͈ېV����c����̂��Ƃ�x�X�K�ꋹ�̓����Ă����B 1914�N�i74�j�A�h��͓����o�ϊE�̒�g�̂��ߒ�����K��B���N�A�����d�M�ǂ̔[�����߂����ăh�C�c��ƃV�[�����X�ƊC�R��]�Ƃ̑����d�����u�V�[�����X�����v���N���A�R�{�����q���t�������E�B��17����t������b�ɑ�G�d�M����x�ڂ̏A�C�B 7��28���ɑ�ꎟ���E��킪�u���B���{��8��23���ɎQ�킵�A�����ɂ�����h�C�c�d�ؒn�E���i�`���^�I�j���U�������B 1915�N�i75�j�h��̓p�i�}�����m������Ɠ��Đe�P�̂��ߓn�Ă��e�n���K�A�E�B���\���哝���Ɖ����B���N�A�a��������Ђ�ݗ����A����s�𒆊j�Ƃ���a��O���[�v���`�������B ���̔N�A��2����G���t�͌R���E���E�̑Β��������g��v����21�J���ɂƂ�܂Ƃ߂��u�Ήؓ�\��ӏ�v���v���A�������͐��M�呍���ɓ˂������B���e�̒��S�́A�����E��A�Ɩ��S�̑d�،���99�J�N�ɉ������鏔�v���B�͂͗v��������������A�����l�͎������5��9�������p�L�O���Ƃ��Ĕ����^����W�J�����B ��1916�N�i76�j�A����77�̊���ɂȂ�A����s��������C���A���ƊE�̑������犮�S�Ɉ��ށB�Ȍ�͎�Ƃ��ċ���A�Љ�A�������Ƃɗ͂𒍂��ł����B �h��� �g�_��h��w�i�Ƃ����o�ϓN�w�_�w�_��ƎZ�Ձi�����j�x���A�u�����o�ύ�����v�Ƃ������O��ł��o�����B�u�_��v�Ɓu�Z�Ձv�����т��A�ϗ��Ɨ��v�̗������f���ė��z�̎Љ��������Ƃ����B���ƉƂ͗��v��Ɛ肷��̂ł͂Ȃ��A���S�̂�L���ɂ��邱�Ƃ�S�����A�x�͑S�̂ŋ��L������̂Ƃ��ĎЉ�ɊҌ�����悤���������B �u�_��ƎZ�Ղ͂͂Ȃ͂��s�ނ荇���ő�ςɂ������ꂽ���̂ł��邪�A�x�𐬂������͉����Ƃ����ΐm�`�����B�����������̕x�łȂ���A���̕x�͊��S�ɉi�����邱�Ƃ��ł��ʁB�_��ƎZ�ՂƂ����������ꂽ���̂���v�����߂邱�Ƃ����ɏd�v���v �u�����ɑ��@���ɂ��Γ����ɂ��Ȃ������܂��l���A�������Ă��̓����ɂ��Ȃ���������������ƎЉ�̗��v�ƂȂ邩���l���A����ɂ�������Ύ��Ȃ̂��߂ɂ��Ȃ邩�ƍl����B�����l���Ă݂��Ƃ��A�������ꂪ���Ȃ̂��߂ɂ͂Ȃ�ʂ��A�����ɂ����Ȃ��A���ƎЉ�������v����Ƃ������ƂȂ�A�]�͒f�R���Ȃ��̂ĂāA�����̂���Ƃ���ɏ]������ł���v ���N�A��2����G���t�͓|�t�^�����đ����E�B��18����t������b�ɗ��R�̎������B���A�C����B 1917�N�i77�j�A�h��͎��R�Ȋw�̌����@�ցA�����w�������ݗ��ɍۂ��A�ݗ��ґ���ƂȂ�B���N�A���V�A�Ŋv�����N����B 1918�N�i78�j�A�́E�c������h�炷��h��́A���̎��т𐳊m�Ɍ㐢�ɓ`�������Ƃ̎v������A�w����c����B�x�����s�B ���N�A�h��͓c���s�s������Ёi���F���}�d�S�j�̐ݗ����N�l�ƂȂ�A�Z��n�������ۂɓc����2���������ēc�����z�Ƃ����B�w�O�L��𒆐S�Ɋ�H��ݒu���A����100�`500�̏㥉����������̍����Z��n�Ƃ��Ĕ���o�����B ���̔N�A�ĉ��ُ̈�Ȓl�オ��Ő�����ɂ������܂ꂽ���O�ɂ��S���I�Ȗ\���u�đ����v���u���A��50���ԁA38�s153��177���Ŕ������A���{��h�邪���厖���ƂȂ����B�đ������N�����w�i�ɂ́A�s�s�l���̋}���ɑ��Ă̐��Y���ǂ����Ȃ��������ƁA�Ăւ̓��@�E�O�ėA���̋K�����d�Ȃ��ĕĉ����l�オ�肵�����Ƃ�����B8���̐��{�ɂ��V�x���A�o���錾�ŕĂ̔�����߂ɑ���Ǝ҂������A�ĉ��͂܂��܂������B���O�̕s���͈ꋓ�ɍ��܂�A�\���̈������ɂȂ����B�����҂͖�2��5000�l�ɂ̂ڂ�B�������t�͍����̐ӔC���Ƃ��đ����E���A��19����t������b�ɂ͎F���唴�łȂ����o�g�ŗ������F��̌��h�i�������j���A�C�A���}���t����̖��J���ƂȂ����B���h�͍ŏ��̈���I�Ȑ��}���t��g�D���A�����ɑ��ƌĂꂽ�B��1�����E��킪�I���B 11��11��11���ɑ�ꎟ���E��킪�I������B 1919�N�i79�j�A�J�����c�̊��������z�肳��钆�A�J�g�����𐄐i���邽�߂̊����g�D�Ƃ��āA�u������v��ݗ�������ƂȂ�B�������16�㓖�������ƒB�i�������Ɓj�B���L��ق�J���g���̏W��̉��Ƃ��đ݂��o�����B 1920�N�i80�j�A�ϔN�̌��ɂ��u�q�݁v��������ꂽ�B���̒������ƉƂ͒j�݈ʂǂ܂�̂Ȃ��A�q�ݍ����h�ꂪ�^����ꂽ�̂́A�g���v�h�̎p���������̐l�Ɋ�����^�������ʂ��B ���N�A�C�O�ł͑���̕��a�ێ��̂��߂ɍ��ۘA�����ݗ������B 1921�N�i81�j�A���V���g���C�R�R�k��c�i1921-1922/��ȑS���E�����F�O�Y�C�R��b�j���J�Â���A�h��͉�c�̐������肢�A�܂����Đe�P�ɐs�������߁A�I�u�U�[�o�[�Ƃ��ēn�Ă����B���{�̊C�R�W�҂ɂ͍������R�k���Δh���������߁A�h��͓��{���{���R�k�Ă�����₷���������ׂ��A���V���g����j���[���[�N�ŌR�k�Ɏ^�����邱�Ƃ����������\�����A���̒������x�������B �܂��A�h��͔r�������P�̂��߁A�n�[�f�B���O�哝���Ɖ���Ă���B ���Ȃ݂ɂ��̉�c�̑O�ɁA�h��⌴�h�����S�ƂȂ�A�p�ĂƂ̌o�ϊW�𖧐ڂɂ���ړI�ŖK����ƒc����������A�O������̑����E�c�������c���ɏA�C���Ă���B�R�k��c�ɂ͂��̎��ƒc�����s�����B ���N�A�c���q�T�m�e���i20�j�����N�Ԃ̉��B�K��B�A����A�d�a�̑吳�V�c�ɂ�����Đ��������邽�ߍc���q���ې��ƂȂ�B���̔N�A���������w�ŒP�ƃe���ƂɎh�E�����20����t������b�ɍ����������A�C�����B 1922�N�i82�j�������t���t���s��v�ő����E�B��21����t������b�ɉ����F�O�Y���A�C����B 1923�N�i83�j�A���w�U����ړI�ɒ鍑�c��Őݗ������c���ꂽ�哌��������i���F�哌������w�j�̕]�c���ɏA�C�B�������ݔC����62�ŕa���B 9��1���ߑO11��58���A�}�O�j�`���[�h7.9�̊֓���k�Ђ��N����B���ҁE�s���s����10��5000�l�]�A�Z�ƑS����21���]�A�Ď�21���]�ɋy�сA���l�n�т͉�œI�Ō����������B�܂��k�Ђ̍����̒��A�Љ��`�҂⒩�N�l�Ȃǂւ̕s�@�ߕ߁E�s�E�������N�����i�T�ˎ����E�Ô������Ȃǁj�B�����̕a���Ő����ȑ�����b���s�݂Ƃ����^�C�~���O�������B9��2���A��22����t������b�ɎR�{�����q���ĂяA�C�A�������ܐk�Б�Ɏ��|����B�h��͎����Ў҂ɋ������邽�߂̐H�Ƃ�����ŋߌ�������z�����s�����B �~�ώ��Ǝ������B�̂��߁A��k�БP�����������A�`�����W�߂ɂ��z�����A�h��ƌ𗬂̂������č��̎��ƉƂ���������̋`��������ꂽ�B���{��s�����R�c��̈ψ��ɂ��A���A�c�_�����[�h�������s�s�v����܂Ƃ߂邽�ߐs�͂����B 1924�N�A84�̉h��̍u����̓������������Ă���B�u���̒�������i������ɂ��������āA�Љ�̎������܂��܂����W����B����������ɔ����Ċ̗v�Ȃ铹���m�`�Ƃ������̂��Ƃ��ɐi�����Ă������ƌ����ƁA�c�O�Ȃ���g�ہh�Ɠ�������ʁB�m�`�����Ɛ��Y�B���Ƃ́A�����Ƃ��ɐi�ނׂ����̂ł���܂��v�B �O�N���ɏ��a�V�c���Ԃňړ����ɑ_�������u�Ճm�厖���v���N���A�R�{�����ӎ��C�B��23����t������b�ɐ��Y����i���悤�� �������j���A�C�������A���ʑI���^���̐���オ��ɂ�蔼�N�őސw�����B��24����t������b�Ɍ�����̉����������A�C���A�쌛�O�h���t���g�t���ꂽ�B 1925�N�i85�j�A�O�N�̑I���ň��������쌛�O�h���t�́A�ߊ�ł��镁�ʑI���@�����B����ɂ��A��25�Έȏ�̒j�q�͔[�Ŋz�ɊW�Ȃ��O�c�@�c���̑I�����������ƂɂȂ����B����A�Љ�^���̍��܂�Ɋ�@��������������t�́A�v�z�E���Ђ������܂�u�����ێ��@�v��������킹��悤�ɉ������B1900�N�ɐ��肳�ꂽ�u�����x�@�@�v���Љ�^���Ȃǂ́u��̓I�ȍs�ׁv�������܂�̑Ώۂɂ����̂ɑ��āA�u�����ێ��@�v�͓��̒��́u�v�z�E�M���v�������܂����i3�N��̉����Ō���������A���Ђ̑g�D�ҁE�w���҂ɂ͍ō��Ŏ��Y���Ȃ�����悤�ɂȂ����j�B ��1926�N�i86�j�A�h��͂��̔N���瑼�E�O�N��1930�N�܂ŁA��ꎟ���E���I�����ł���11��11���ɁA���N���W�I�����ŕ��a��i���鉉�����s���B�����āA���{�̖��Ԍo�ϊO���̑g�D���ƁA���U��ʂ��č��ی𗬂ɗ͂���ꂽ���т�]������A���̔N�̃m�[�x�����a�܌��ƂȂ����B ���N�A�����������ݔC�̂܂�66�ŕa���B������b�̎�Η玟�Y����25����t������b�ɏA�C�����B12���A�吳�V�c��47�ŕ��䂵�A���a�V�c��25�ōc�ʂ��p������B 1927�N�i87�j�A�h��͓��{���ێ����e�P���ݗ����A��Ƃ��ē��Ă̐l�`�̌����ɂƂ߁A�A�����J�̐l�`�i���ڂ̐l�`�j�Ɠ��{�l�`�i�s���l�`�j���������A�e�P�𗬂�[�߂�B��x�ڂ̃m�[�x�����a�܌��ƂȂ�B ���N�A��p��s�̕s�Ǒݕt�̖\�I���_�@�ɋ��Z�@�ւ𒆐S�Ɂu���a���Z���Q�v���N����B��Γ��t�͌o�c��@�ƂȂ�����p��s�~�ςً̋}���߈Ă��A�����@�ɔی����ꂽ���Ƃő����E�B��26����t������b�ɐ��F��̓c���`��i������/1864-1929�j���A�C�B���N�A�c��d�����f���郊�x�����̗��������}�����}����A���㑍�قɕl���Y�K���A�ږ�Ɏ�Η玟�Y�炪�A�C�����B 1928�N�i88�j6���A���B�x�z��������ފ֓��R���\�����A���B��тɐ��͂������Ă����R�������ƁE�������i���傤�������j���Ԃ��Ɣ��E�����i���������E�����j�B 11���A�h��̃��W�I�̓������c��B�u�Ȋw�̐i������푈��̓��i�������j�����A��d�ɂ��O�d�ɂ��A����S���炵�߂Ă���܂��B�ꍑ�̗��v�݂̂��咣�����ɁA�����o�ς��ƈ�v�����߂Đ^���Ȃ鐢�E�̕��a���������Ƃ����N�ƂƂ��ɓw�߂����̂ł���܂��v�B 1929�N�i89�j�A���E�勰�Q�B���{�ł����Ǝ҂��������A���k�n���̔_���͐[���ȋQ�[�ɏP��ꂽ�B����ł͕n���҂��~���u�~��@�v�����肳�ꂽ�B�~��@�͕n���҂̋~������⎩���̂ɏ��߂ċ`�������Ă���A�̂��̐����ی�@�Ɍq������̂��B ���N�A���a�V�c�͑嗤�ɂ�����R�̓Ƒ������O���A�u�������R�R�l�͂�����߂����ĂтȂ�����悤�Ɂv�ƁA�c���`��ɒ��������E�����Ɋւ�����l���̌����ƌR�I�l���𖽂����B�c���́u�ӔC�҂������ɏ�������v�ƓV�c�ɖ������̂́A���R�̋������ɂ���ČR�@��c���J�����B�V�c�͔Ɛl�s���ŏI��点�Ă͒鍑���R�̍j�I���ێ��ł��ʂƗ����B�R���ɑ���^�O�͑傫���A6��27���A�c���Ɂu�i�����ɏ����Ƃ����j���O�̍ŏ��Ɍ��������ƂƈႤ����Ȃ����B���\���o���Ă͂ǂ����v�ƌ��������ӂ��A�Ȃ��������悤�Ƃ���Ɂu���O�̘b�͂������������Ȃ��v�Ƙb��ł���A�S�J����V�c�̌ߌ�̗\��͂��ׂăL�����Z���ƂȂ����B�c���͓V�c�̓{��ɃV���b�N���V���Q���ɓ��t�����E�������B������A���������}���فE�l���Y�K����27����t������b�ɔC������A�l�����t��g�t�B�ޔC��̓c�����͍ǂ������ł��܂�l�O�ɏo���A�R�J�����o���Ȃ�9��29���ɋ��S�ǂɂ��65�ŋ}�������B���a�V�c�́A�c���ւ̎��ӂ����t�𐁂���������肩�A���ɒǂ���錋�ʂɂȂ�����������ʂƐӔC��Ɋ����A�u���̎��������Ĉȗ��A���͓��t�̏�t���鏊�̂��͉̂��Ɏ��������̈ӌ��������Ă��Ă��ى�^���邱�ƂɌ��S�����v�Ƃ����B ���N�A�C�O�ł͍���ɂ��푈�̕��������������u�p���s����v�����������B���{���܂ޗ�15�J���������i�ŏI63�J���j�B�p���s����̑����́u���͍��ە����̂��ߐ푈�ɑi���邱�Ƃ��Ƃ��A���Ƃ̐���̎�i�Ƃ��Ă̐푈��������邱�Ƃ��A�e���̐l���̖��ɂ����Č��l�ɐ錾���v�B���͎��q�푈�ȊO�̐푈�A�̓y�g���ׂ̈̐푈��ׂ̈̐푈���֎~���Ă���B���̌��@��X���͂��̖@�K���Q�l�ɂ��Ă���B 1930�N�i90�j�A�O�N�ɋ~��@�����肳�ꂽ�̂ɁA���{�͍����s���𗝗R�Ɏ��{����������B�~��@�̎��{�Ɍ����A���������Ƃ����͕a�C�×{���̉h��ɋ��͂������B����91�̉h�ꂢ�킭�u���͂����ǂꂾ���������邩�킩��Ȃ��B���̖����݂�Ȃɗ^���Ă����͖̂{�]���v�B�h��͈�t�̐��~��U����đ呠��b�ɖʉ�A������������Y�Ƃ̐Ŏ��𓊓����Ăق����Ƒi�����B�u�������i���ƉƁj���ꐶ�����ɓ����Ă��āA���{�̌o�ς����̂悤�ɂ����̂́A���̎��ɂ����F����ɖ𗧂ĂĂ���������������ł���܂����B�a��̍Ō�̂��肢�ł��B�~��@�����{���Ă��������v�B2�N��i1932�j�A�呠��b�͗\�Z���H�ʂ��ċ~��@�����{�A24���l���̐l��������ꂽ�i�h��̖v��j�B 1���`4���ɂ����āu�����h���C�R�R�k��c�v���J�Â���A�C�R�̕⏕�͕ۗL�ʂ̐�������߂�ꂽ�B���{�̌R�ߕ��͏d���m�͕ۗL�ʂ��A�����J��6���ɗ}����ꂽ���ƂƁA�����͕ۗL�ʂ���]�ʂɒB���Ȃ��������Ƃ�2�_�𗝗R�ɏ�ۂ̕��j�����������A�R�k��c�̎�ȑS���E��Η玟�Y�́A�u�[������C�����������Ă��d�����Ȃ��v�ƍ��͂ɂ������R����������B11���R�k���������ƂŌR�ƊW�����������l���Y�K�́A�����w�Ńz�[�����ړ����Ɍ��m�Ќn�E���c�́E�����ЎЈ��Ɏ��ߋ�������e�����ꗂ�N�ɑ��E�����B 1931�N�i91�j�A�����ő吅�Q���N���A�h��͒��ؖ������Г�����ߋ`��������B�����ł͓��{���q��w�̍Z����������B 4���l�����t�͎̕a�����瑍���E�B��Η玟�Y����28����t������b�ɔC�������B9���A���B���ρi�����Ύ����j���u���B���B�̊֓��R�����Q�d�E�_���l�Y�卲�i�͖{�卲�̌�C�j�ƍ���C�Q�d�̐Ό��Ύ��i���j������́A�L�x�ȐΒY�E�S�Ȃǂ̎����̊m�ہA�\��̑O����n�����A�����}���{�E���w�ǂ̓S�����݂ɂ�閞�S���̉ݕ��A�����̌����A�ؐl�̓��{���i�{�C�R�b�g�^���A���a���Q���̕s�i�C�̉����ȂǁA�l�X�ȗ��R����u���͂ɂ�閞�ցi���B�ƖÁj�̗L�v��v�𗧈āB�����ĂX��18����A�������͖̉{���璆�сi���������E�͖̉{���Ƃ͕ʐl�j�ɕ�V�x�O�̖����Α��Ŗ��S���H�j�����i�����Ύ����j�A���̎��쎩���̃e����n���̌R���E���w�njR�̔ƍs�Ƃ݂������A�u�����R�̓��{�ɑ��钧�����v�Ƃ��ĕ��͍U�����J�n�����B�V�c�u�����͍��ېM�`���d�A���E�̍P�v���a�ׂ̈ɓw�͂��Ă���B���ꂪ�킪���^�̔��W�������炵�A�����ɐ^�̍K���������̂ƐM���Ă���B������ɌR�̏o��́A�����̖��߂��������A���d�ɂ��������g�債�A���͂������Ē��ؖ��������|����Ƃ���̂́A�����ɂ��c�O�ł���B�Ђ��Ă͗̊��������A���ƍ�����j�łɊׂ�邱�ƂɂȂ��Ă͐^�ɂ������܂ʁv�i�w�V�c��^�x�j ����ꎟ���E���I�����ł���A���W�I�����ŕ��a��i���鉉�����s���\�肾����11��11���A�h��͔R���@�ɂ�91�ő��E�����B�ʖ�ɓV�c�̒��g�����킳��A�h��̎��т��̂����䍹�������������ꂽ�B����ʌM�ꓙ�q�݁B ���N�A��Γ��t�����R�ɂ�閞�F�������H��ɔ������Ƃ���A�t����_�������R�}�i�h�̃N�[�f�^�[�v�悪���o�B��Γ��t�͑����E���A�������F��فE���{�B����29����t������b�ɔC�����ꂽ�B���{�����B�N���ɔ��ŁA���������������ׂ����Ƃ̎��_�������Ă����B ���N�A���B���������������A���{�͂Q�����o���Ă����B�����F�ɂ͐T�d�ł������B���̌��ʁu�܁E������v�Ŏ͌R���ɈÎE����Ă��܂��B���}���t�͔s��܂œr�₦��B �h���91�N�̒����������āA�����ېV���珺�a�����܂ō��E�̃��[�_�[�ƂȂ�A���U�ɖ�500�̊�Ɛݗ���^�c�Ɋւ��A�ϐ���E���b����Ȃǖ�600�̋���@�ցE�Љ�������Ƃ̎x������і��ԊO���ɍv�������B �ݗ��Ɋւ������Ƃ́A���{���̋�s�ł����ꍑ����s(���݂��ً�s)�A�������~��s�i���E�肻�ȋ�s�j���͂��߁A�����d�́A���{�S����ЁA�����d�́A�����K�X�A�����C��Еی��A���{�X�D�A����{����A�T�b�|���r�[���A�L�����r�[���A���m�a�сA���q�����A�鍑�z�e���A�����Z�����g�i�������m�Z�����g�j�A�����S���A����d�S�A�c���s�s(���E�����}�s�d�S)�A���m�D�D�A�\�E���Ɗ��R�����ԋ����i�����ӁA�L�����u�j�S���i1905�j�AJFE�X�`�[���AIHI�A���{���w�H�ƁA�����ʐM�ЁA�����ʐM�ЂȂǁA�����̉�Ђ��������Ă����B�܂��������@��c���i�������H��c���̑O�g�j�A�����،�������A������s�W���ݗ�����ȂǍ��E�̑g�D���͓I�ɓw�߂��B�������ȑ�w�i���E�ꋴ��w�j����{���q��w�Z�A��p����w�Z�i���E��B��w�j�̐ݗ��ɂ��g������B�ǂ̎��Ƃ��h�ꂪ�n���ɓ������Ĕ��N�l�Ƃ��Ċ��U������A�l�X�͉h��̐M�p�ɂ���Ă����ɎQ�������B�J��Ԃ����A�a�����̂͑n����^�c�Ɋւ������Ƃ�500�����邾������Ȃ��A��Â╟���A�w�Z�Ȃǂ̒c�̂�����ȏ��600�����邱�ƁB �����Ɂu����c����`�v�u�_��u�b�v�u�˂Ɏh�����o��������l�ɂȂ�!�v�u�l���̋}��������!�v�ȂǁB �揊�͓����E�J���쉀�̉�11��1���B�����͑ד��@�a�m�q�`�����勏�m�B�덆�̐��i��������j���ɍ��ށB�a��Ƃ̕揊��2014�N�Ɏ��͂̐�蕥��ꂽ���A����܂ł͒����{������ʏ����J�ɂȂ��Ă����i�����͗쉀�����ɂ���ԉ��u�ӂ��ނ��v�ɐ\�����߂Ό�����邱�Ƃ��o�����j�B �h��̖ڐ���130m��ɂ�18�N�O�ɖv�����c����̕悪����A�i���̒n�Ƃ��Čc����̑���I���Ƃɋ����M���Ȃ�B ��2024�N����1���~�D�̏ё��ɋN�p�����B ���h��͏�����M���������u�S�菑�v�̎ʂ���{��@�̎����̕����ɏ����Ă����B���e�́u�ꖽ�ɂ����Ċ肤�B���̒��ɂ����ƍ������s���n��A���̒��̗��Ē������������܂��悤�Ɂv�Ƃ������́B��M��1790�N�ɉΕt���������J�약���̌��c�ɂ��A�]�ːΐ쓇����ь���錧���Ύs�ɐl�����i�ɂ��悹�j�Ƃ����X���{�݂�����Ă���B���Q�l��Y�������҂����e���A��H���炶���Ȃǎ�ɐE���������A�Љ�A���x�������B ���h��͉Ԗ��E�ł��m��ꂽ�����D���ŁA�q�ǂ���20�l�߂��ɂ̂ڂ�Ƃ����Ă��邪�A50�l�Ƃ�����������B �����E���ތ�Ɂu�a��������Ёv��n�݂��Ă��邪�A�����܂Ŗv��̍��Y������h���ړI�Ŏ�����Љ��������̂ŁA�ۗL���̑����͉�Ђ̊��̐��p�[�Z���g�ɂ������Ȃ����́B�g�����h�ł͂Ȃ��B �����̏a��h�O�͂��ďa��Ƃ̍��J��i�[�����j�ɑ����Ă������A�ߘa2�N(2020)�ɕv�w�悪�V���Ɍ������ꂽ�B ���u�����ېV�����̍��E�ɂ�����O���͎O��̖쑺�����q��i�O������̑n�ݎҁj�ƍz�R���̌É͎s���q�i�É͍����n�ݎҁj�ƓV���̎������Ɠc�������i�����Ƌ��Z�Ő����j�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�i�h��j ��1889�N����1904�N�܂�15�N�Ԃɂ킽���Đ[����c���߂��B ���t�����X���w�ҁE�F�V���F�͉h��̕��s�Y�E�q��̐��Ɓu���̉Ɓv�̏o�g�B �������̎Y�ƐU����ړI�ɓ������Ɖ�ЁE�������Ɖ�Ђ�ݗ��A�������Ƃ̓��������ЁE���m������������B �������{��@�̏ꏊ�ɂ́A���݁A�����s���N������ÃZ���^�[�������A�Ő�[�̃��n�r�����Â��s���Ă���B ��2021�N�A�ΐ��Ɩؐ��̊Ԃɂ��鏬�f���ɏa��h��̖��O������ꂽ�B ���h��͍����I�Ȑl�ԂŁA�n���������Ȃ�ƎЉ�I�Ɍo�ύ������ɂ��킸�A�n�����l����u���Ă���ƎЉ�̂��߂ɂȂ�Ȃ��ƍl�����B�����Ȃ�钆�ɋ����ɏP��ꂽ��A�X���������Ă�����܂Ƃ��Ȏ��{��`�Љ�ɂȂ�Ȃ��B����䂦�A�u��������͍ő�̗��v�ށv�Ƃ��āA��Ɛݗ��ƕn���~�ς������̗��ւƂ��čs�����B |
�����c ���v/Akio Morita 1921.1.26-1999.10.3 �i�����s�A�`��A���J�� 78�j2010
 |
 |
| ��ɂ́g�^��h�̂Q�����ƉƖ䂾���������Ă��� | �K�i�̉E�e�Ɂu���c�v |
 |
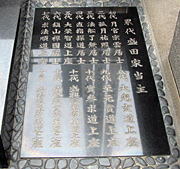 |
 |
| ���ʍ��ɐ��c�Ƃ����m�o�g �ł��邱�ƂȂǐ��̘b�� |
�����Đ��ʉE�ɂ͗�㓖��� ����������`13��܂ł����� |
�ǂ�����ƈ��芴�̂�����I ��[��ƂQ�l�Ń\�j�[��n�� |
| ��[��i�܂���j�Ƌ��Ƀ\�j�[��n�ƁB�g���E�̃Z�[���X�}���h�Ə̂��ꂽ�B���͎ƎҁB���m���o�g�B1944�N�i23�j�A�����̗��w�������w�Ȃ𑲋ƁB�C�R�Z�p���тɂȂ�A�펞�Ȋw�Z�p������Œm�荇����13�ΔN��̈�[��ƔM���T�m�@�̊J���Ɍg���B�I���A1946�N�i25�j�ɁA��[�Ɓu�����ʐM�H�Ɓv�������ݗ��B�햱������̐��c���c�Ƃ�S�����A�ꖱ������̈�[���Z�p�J�����s�Ȃ����B���҂̃��b�g�[�́u�V���i�ŐV�����s��J��v�B1950�N�i29�j�A���{���̃e�[�v���R�[�_�[�u�f�^�v�����������A���c����q�b�g�������B���N�A�O�ȓ��В��̖��ƌ����B ������1955�N�i34�j�ɓ��{���̃g�����W�X�^���W�I�uTR-55�v���B���c�͓n�Ă��āuSONY�v�u�����h�Ŕ��荞�݂��J�n�����B�uSONY�v�̖��O�́gSOUND�i�T�E���h�j�h�̌ꌹ�ł��郉�e����gSONUS�i�\�k�X�j�h�ƁA���C�ŎႢ��Ƃ̃C���[�W����p��́gSONNY�h�i�g�V��h�̈Ӂj���d�˂����́B1957�N�i36�j�A���E�ŏ��E�����\�̃g�����W�X�^���W�I�uTR-63�v���A�����J�Ńq�b�g���A�uSONY�v�̖����F�m���ꂽ�B 1960�N�i39�j�Ƀg�����W�X�^�e���r�A1965�N�i44�j�ɐ��E���̉ƒ�p�r�f�I�E�e�[�v���R�[�_�[���J���B ���c�͓O�ꂵ���C�O�}�[�P�e�B���O���s�Ȃ��A�e���Ɍ��n�@�l�̔̔���Ђ���������Ƃ���ASONY�̖��͐��E�ɍL�܂����B1971�N�i50�j�A��[����ɂȂ萷�c�͎В��ɏA�C�B������1976�N�i55�j�ɂ͈�[�����_��A���c����ɏA�C�����B1979�N�i58�j�A�E�H�[�N�}�����������I�Ƀq�b�g������B1989�N�i68�j�A�Ό��T���Y�Ƌ��������uNO�Ƃ�������{�v���b��ɂȂ����B ���c�͔��Ɍ�w�ɗD��A�p���ł͖��_�p��B�l�܂����B�j���[���[�N�،����������ψ���ψ���IBM�̖�������C���A�����ł�1991�N�i70�j�ɌM�ꓙ����͂���́B���N�A�p����������i�C�g�݂̏̍��Ɩ��_��p�M�͂�ꂽ�B1993�N�i72�j�A�]���o���œ|����E����g�������A�n���C�Ő×{�ɓ���B1998�N�i77�j�A�Ď��u�^�C���v����悵���g20���I��20�l�h�ɁA���{�l�ł���1�l�I�o���ꂽ�B1999�N�A�x���ɂ�葼�E�B���N78�B�����͐����@�V�U�h������B |
���v�c �F/Takashi Masuda �Éi���N10��17���i1848�N11��12���j-1938�N12��28�� �i�����s�A������A�썑�� 90�j2010
 �@
�@ �@
�@
| ���E���̑������ЁE�O�䕨�Y��ݗ��B���{�o�ϐV����n���B���n�o�g�B�]�˂ɏo�ăw�{���m�Ɋw�сA�A�����J���g�قɋ߂ăn���X�ɉp��������Ė�����B1863�N�i15�j�A���{��l�̕��Ɠn�����A�A����ɖ��{���R�ɓ�������B�ېV��A���l�Ŗf�Տ��قɋΖ��B1872�N�i24�j�A���]�̗U���ő呠�Ȃɓ��ȁB1874�N�i26�j�A���Ɛ����Ђ�ݗ������В��ƂȂ�B 1876�N�i28�j�A���O�����V��i���E���{�o�ϐV���j��n���B���N�A�O�䕨�Y��ݗ�������В��ɏA�C����B1880�N�A�����h���x�X���J�݂��ĉ��B�֕Ă�A�o�����B�ΒY�A�Ȏ��ȂǑ��l�ȕ��i���A�W�A�e�n�֗A�o���A���{�̖f�Ց��z�̖�Q�����߂�܂Ő����������B 1889�N�i41�j�A�u�O�r�Y�z�Ёv�i�O��z�R�j��ݗ����c�������������Ɍ}����B1900�N�i52�j�ɑ�p������ݗ��B1913�N�i65�j�Ɉ��ށB���l�E�݉��Ƃ��Ắu���x�ȗ��̑咃�l�v�Ə̂��ꂽ�B1938�N�A90�ő��E�B�j�݁B ���O��Ɓc17���I�Ɉɐ��̏��l�E�O�䍂�����]�˓��{���Ɍ����X�z�㉮�i�O�z�j���J�X���A���֏��ɂ�����L���A���s�A���ɓX�܂��\����O�s��p���l�ƂȂ����B�����V���{�̐����ƂȂ�A�O�䕨�Y�i�v�c�F���o�c�j�A�O���s�i�����F���Y���o�c�j�A�O��z�R�i�č��ōz�R�w���w�c�������o�c�j�̂R��Ƃ����ɔ��W���A�����a�сi�J�l�{�E�j�A���q�����A�ʼnY���쏊�i���Łj�A�x��������Ȃǂ��P���ɂ����B |
���� ����/Takuma Dan ����5�N8��1���i1858�N9��7���j-���a7�N�i1932�N�j3��5�� �i�����s�A������A�썑�� 73�j2010
 |
 |
| �c�Ƃ̕揊�B�E�[�̑傫���悪���� | �����̏�������́A���ō�ȉƂ̈ɋ薁 |
| �O������̑����B�H�w���m�B�j�݁B��ȉƁE�c�ɋ薁�͑��B���������܂�B1871�N�i13�I�j�A��q�g�ߒc�Ɠn�Ă��A�}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�ōz�R�w���w�тV�N��ɋA���B���嗝�w�����������o��1884�N�i26�j�H���Ȃɓ��ȁA�O�r�z�R�NjZ�t�ƂȂ�B�̒Y�Z�p�̏K���̂��߂ɓn���B1894�N�i36�j�A�O��z�R������Аꖱ�����ɏA�C���A�O�r�Y�z�̋ߑ㉻�ɐs�́B���̌��ʁA�O��z�R�̗��v�͎O���s��ǂ������A�O�䕨�Y�ƌ�����ׂ�܂łɂȂ����B�O��O���[�v���Ŕ����͂𑝂��������́A1914�N�i46�j�A�v�c�F�ɂ�����ĎO�䍇����З������ɏA�C���A�O������̑����ƂȂ�B 1922�N�i54�j�A��Q�́g�a��h�ƌ���ꂽ��㏀�V���Ɠ��{�o�ϘA����i�o�c�A�̑O�g�j��ݗ����A�U�N��ɉ�ƂȂ���E�̊�ƂȂ����B���a���Q�̍ۂɎO��������h�������ɂ���ė������グ�Ă������Ƃ���A�E���c�́g�����c�h�Ɂu�������~�݂̂ɖv�������h���y���������������v��Ȃ��Ɉ��l�v�ƌ��Ȃ���A1932�N3��5���A�����E���{���̎O��{�ِ��ʌ��֑O�Œc���E�H���ܘY�Ɍ��e�ňÎE���ꂽ�B�Ɛl�̕H���͖��������������A�킸���U�N�ʼn��o�����A�����ܘN�Ɖ����A1958�N�Ɉ�錧�c��c���ɓ��I���A�W���A�����I�A���c��c���܂Ŗ��߂Č����E�̎��͎҂ƂȂ����B �J���g���@�̐���ɔ����Ă������Ƃ���A�l�͒��N�揄��ɍs���Ȃ���������ǁA�����ˎm�̔n�����̎q�ɐ��܂�A�{�q�ɏo����A����������{���E�̃g�b�v�i���E�o�c�A��j�܂œo��l�߂��o�C�^���e�B�́A����͂���Ƃ��ĕ]���ł���Ǝv���悤�ɂȂ菄��B ����B�V�����V�喴�c�w�O�ɓ��������B |
�����c �`�O�Y/Denzaburo Fujita 1841�N7��3���i�V��12�N5��15���j-1912�N3��30���i���s�s�A���R��A�m���@ 70�j2012
 |
 |
 |
| �������`�O�Y�B�E�͐�c��A���͒��j�����Y | ��������m | ���̓��c���p�ٓ��� |
���ƉƂŖ������̊����E�̏d���B���Ԑl�ŏ��߂Ă̒j�݁B���c�g�̑n���ҁB���B������B20��͊���ɎQ���B1877�N�i36�j�A
����푈�ɍۂ��R���i���B�ɂ���ċ����A���B����w�i�ɐ����Ƃ��Ĕ_�E�сE�z�E���Z�Ƃ��c�B�M�S�ɔ��p�i�����W���A�����ɗ�ނȂǁA
����҂Ƃ��Ă��m����B���E����42�N���o����1954�N�A�j�ϓV�ڒ��q�i����j�Ȃǂ̏����i����Ƃ������c���p�ق��J�ق����B
���j�E�����Y�A���j�E�����Y�A�O�j�E�F�O�Y�B
�����c �P���Y/Zenjiro Yasuda �V��9�N10��9���i1838�N11��25���j-1921�N9��28�� �i�����s�A������A�썑�� 82�j2010��12��19
 |
 |
 |
| �썑���̕揊�͔���J�����NJi�q���猩���� | �����̕悪�{�ƁB���̕�ɂ́g���Ɓh�Ɠ����Ă� | �u���c���ݑ��v |
 |
 |
| �[��ꎞ�ɏ���i2012�j | �����Ǝ�O�Ŏ�����킹�����c |
 |
 |
| �����{���s�̑����쉀�Ɉꑰ�̋���� | �P���Y�̖��{�q�ň��c��s���ق̈��c�P�O�Y�i2010�j |
 |
 |
| �̋��̕x�R�̕�����B���ʂɁu�[���v�̎� | �����ʂɁu���c�P���Y�v�Ƃ���i2019�j |
| ���c�����̑n�n�ҁB�g��s���h�B�x�R���o�g�B�c���A�⎟�Y�B���͕x�R�˂̑��y�Ŕ��_���m�B1858�N�i20�j�A�]�˂ɂ�����ߋ�≮�Ȃǂŕ�����A1864�N�i26�j�A���{���ɊC�Y���������֏��́u���c���v���J�����B�Q�N��A�C�Y��������߂ė����ɓ����B�u���c���X�v�ɉ������A�����V���{�̊������������Ĕ���ȗ��v���B1876�N�i38�j�A��O������s�i��O��s�j��ݗ��B�z���������J��Ԃ��Ďx�X�𑝂₵�A1880�N�i42�j�Ɂu���c��s�v�i���E�݂��ً�s�j��ݗ������B1882�N�i44�j�A�V���ɊJ�Ƃ������{��s�̗����ɏA�C�B�u��s���v�ƌĂꂽ�B 1893�N�i55�j�A�鍑�C��ی��i���E���ۃW���p��)��ݗ����A���N�ɂ͋��ϐ����ی���Ёi���E�������c�����ی��j��ݗ�����ȂǁA���Z�����ւƔ��i����B �吳�����̕s���̒��A�P���Y�͓�����c�u���A����J����A�������w�Z�̍Z�n�Ȃǂ��������A1921�N�A������`�ҁE��������Ɂg�x���Љ�ɊҌ������x���̐ӔC���ʂ����Ă��炸�V�n�ɒl����h�Ƒ��̕ʑ��Ŏh�E���ꂽ�B��������͂��̏�Œ䓁�Ŏ��莀�S�B�����͐����@�ߑP��R�勏�m�B �I�m�E���[�R�̑]�c���ŃV���[���E���m���̍��c���ɂ�����B ���̋��̕x�R�E���~���ɁA�u���c���P���Y�v�̖��Ő�c�̕�����������g����������Ă���B �u�\�A�Z�\�͕@���ꏬ�m�@�j����͔��A��\�v�i���c�P���Y�j |
������ �`��/Yoshisuke Aikawa 1880.11.6-1967.2.13�i�����s�A�{���s�A�����쉀 86�j2010
 �@
�@
| ���Y�����ԁA���Y�R���c�F�����n�n�ҁB�M���@�c���A�Q�c�@�c���A�鍑�Ζ��В��Ȃǂ��C�B�R�����o�g�B��w���ƌ�A�ʼnY���쏊�i���Łj�ɓ���A�Q�N��ɃA�����J�Œ����̐����Z�p���}�X�^�[����B1910�N�i30�j�A�����ɂČ˔�������n�ƁB1928�N�i48�j�A���O������Ёi���J������Ёj�̓��{�Y�Ƃɉ��g����B1933�N�i53�j�A�����Ԑ���������Ёi���E���Y�����ԁj��n�Ƃ��A��p�Ԃ���{�ŏ��߂ėA�o�����B �������ƈقȂ�H���̎��R��`���f���A���Y�����ԁA�������쏊�A���{���Y�A���{�z�ƁiJX�z�[���f�B���O�X�j�Ƃ������L�͊�Ƃ��P���Ɏ��߂��V�������A���Y�R���c�F������z���グ��B 1937�N�i57�j�A���{�Y�Ɩ{�ЂB�Ɉڂ��A�펞���͍q��@�G���W���̐��Y�ȂǍ���ɋ��́B���͐�ƂƂ��đ����S�u���Ɏ��Ă��ꂽ�B���E�Ǖ������������Ɛ��E�ɐi�o���A1953�N�i73�j�ɎQ�c�@�c���ɓ��I�����B1967�N�A86�ő��E�B |
������� �F���Y/Hikojiro Nakamigawa �Éi7�N8��13���i1854�N10��4���j-1901�N10��7�� �i�����s�A�`��A�R�쉀 47�j2010
 �@
�@
| �O�䒆���̑c�B�����́g�Ȃ��݂���h�ƓǂށB�啪���o�g�B���͒��Ôˎm�B���V�@�g�̉��i�ꂪ�@�g�̎o�j�B�c��`�m�𑲋ƌ�A�C�M���X���w���o�čH���Ȃɓ��ȁB���]�̒m���A���ɊO���Ȃɓ������B1887�N�i33�j�A�R�z�S���iJR�R�z�{���j�̎В��ɏA�C�B 1891�N�i37�j�A�o�c��@�Ɋׂ����O���s�����Ē����ׂɁA���]�̗v�����ĎO������ɓ������B�����͉v�c�F�Ƌ��ɕs�Ǎ�������f�s����ȂǍ����̌��S����}��A�ʼnY���쏊�i���Łj�A�����a�сi�J�l�{�E�j�A���q�������P���ɒu���O������̍H�Ɖ���i�߂��B1901�N�A�t�����ɂ��47�̎Ⴓ�ő��E�B |
������ �Q��/Namihe Odaira 1874.1.15-1951.10.5 �i�����s�A�䓌��A�J���쉀 77�j2010
 �@
�@ �@
�@
| �������쏊�n�ƎҁB�Ȗ،��o�g�B1910�N�i36�j�A�v���z�Ə��E�����z�R�̍H��ے������Ă����������A���z�R�̓d�C�@�B�̏C�����s�Ȃ��������쏊��n�Ɓi��錧�����s�j�B�₪�Đ��삵�����[�^�[�┭���@���O���ւ�����n�߁A1920�N�i46�j�A�v���z�Ə�����Ɨ�����B��ɑ��S�H���i�������D�j�Ⓦ�����z�d�C�H�ƂȂǂ��������A�O���[�v�͐������Ă������B1951�N�A77�ő��E�B |
����q �씪�Y/Kihachiro Okura �V��8�N9��24���i1837�N10��23���j-1928�N4��22�� �i�����s�A������A�썑�� 90�j2010
 |
 |
| �����씪�Y�A�E���v�l | ����Ƃ̂悤�ȕ� |
| ��q�����̑n�ݎҁB�z�㍑�i�V�����j�o�g�B1854�N�i17�j�A�]�˂֏㋞�����ߓX�ɋ߂�B20�Ŋ����X���J�Ƃ��A1867�N�i30�j�ɓS�C�X���J���B�܂�����C�푈���u��������̔��ŗ��v���B1872�N�i35�j�A�P�N���������ĉ��Ă����@�����씪�Y�́A�A����ɑ�q�g�����ݗ����A�O���Ƃ̖f�Ղ����łȂ��A��p�o���A����푈�A�����E���I�푈�ɂ�����i�O�H�A�O�����j�R���i���B�Ŕ���ȕx���B �R�ΔN���̏a��h��Ɛ[���e�������сA���͂���1878�N�i41�j�ɓ������@��c��(���E�������H��c��)��ݗ��B1883�N�i46�j�ɓ����d����Ёi�����d�́j�Ǝ��فA1885�N�i48�j�ɓ������z��Ёi�����K�X�j�A1887�N�i50�j�ɒ鍑�z�e���A1893�N�i55�j�ɑ�q�y�ؑg�i�听���݁j�A1906�N�i69�j�ɑ���{������Ёi��ɃA�T�q�r�[���ƃT�b�|���r�[���ɕ����j�A1911�N�i74�j�ɒ鍑����̐ݗ��Ɋւ�����B1915�N�i78�j�A�j�݂����^���ꂽ�B |
����� ����/Seiji Noma 1878.12.17-1938.10.16 �i�����s�A������A�썑�� 59�j2010
 |
 |
 |
| �Ȃ�Ƃ�����K�͂ȕ��I �썑���͍u�k�Ж{�Ђ̂������� |
������͉��������܂ꂽ��i�E�[�j�B ���̕�̔w��Ɍ����Ă������� |
�u��Ԑ�����v�Ƃ��鋐���B�ǂ����� �����̕�ƂQ��ޑ������̂��͕s�� |
| �u�k�Бn�Ǝ҂Łu�G�����v�ƌĂꂽ�B�܂��A��m�V���Ђ�L���O���R�[�h�̎В������߂��B�Q�n���o�g�B���w�Z�A���w�Z�̋��t���o�āA1909�N�i31�j�ɑ���{�Y�ى��n�݁B���N�ɕ٘_�G���u�Y�فv��n������B 1911�N�i33�j�A�u�k�Ђ�ݗ����āu�u�k��y���v��n�����A���̌��10�N�ԂɁu���N��y���v�u�ʔ���y���v�u�w�l��y���v�u����v�Ǝ��X�Ɛl�C�G�������s���Ă������B1925�N�i47�j�ɑn��������O��y�G���u�L���O�v�́A���s����100���������q�b�g��ƂȂ����B���̔N�A�u�k�ЂƑ���{�Y�ى�����������A�Ж����u����{�Y�ى�u�k�Ёv�Ƃ����B 1938�N��59�Ŏ����B���E�̂R�N��A��ԏ܂��݂���ꂽ�B�v��20�N�ɂ�����1958�N�ɁA�Ж����u�u�k�Ёv�ɂȂ����B������[�������Ă������Ƃł��m����B |
������ �`��/Yoshisuke Sato 1878.2.18-1951.8.18 �i�����s�A�`��A�R�쉀 73�j2010
 |
 |
| ���ʉE���������엺 | �V�����ɂ����ς������Ă܂��I |
 |
 |
| �H�ɍĖK | �[��ꎞ |
| �V���Бn�ƎҁB���O�̋`���́g����傤�h�Ƃ��ǂށB�H�c���o�g�B���͍r�����B���w�N�ł���A1895�N�i17�j�ɏ㋞�A�G�p�Ɂi���E����{����j�̍H��œ����B�₪�āA�G���ւ̓��e�����]������čZ���W�ɔ��F����A����o�Ŏ��Ƃ��n�߂��u������B�x���҂�1896�N��18�̎Ⴓ�ŐV���Ёi���E�V���Ёj��n�ƁB��ɓc�R�ԑ܂�̎��R��`���w���o�ł���B1904�N�i26�j�ɕ��|���w�V���x�A1914�N�i36�ɐV�����ɂs�����B1951�N�Ɏ����B���N73�B�����͐^���@�ߋ`�Ƌ��m�B���E�̂T�N��i1956�N�j�ɕێ�n�T�����w�T���V���x���n�����ꂽ�B |
���p�� ���`/Genyoshi Kadokawa 1917.10.9-1975.10.27 �i�����s�A�����R�s�A�����쉀�j2017
 |
 |
 |
| ���͒뉀�̂悤�ȍL�� | ��O�ɕv�Ȃ̋� | ������ɂ���肪���� |
 |
 |
 |
| �p�쏑�X��n�� |
�u�p��ƔV��v�ƒ����Ă��� |
����42�N�v�� �p�쌹�O�Y���c |
| �p�쏑�X�̑n���҂ł��荑���w�ҁA�o�l�B�p�쏑�X�iKADOKAWA�j�̑n���ҁB���`�́g����悵�h�ƓǂށB�o���͌��`�i���j�A���r�i�����悤�j�B
1917�N10��9���ɕx�R���Ő��܂ꂽ�B�����O�Y�͏��l�B���w���ォ��o��ɋ��������B�Ï��X�ō����w�ҁE�܌��M�v(���肭�����̂�)�̒����ɏo��������Ƃ����������ŁA1937�N�A20�̂Ƃ��ɕ��̔����������ē������w�@��w�����ł��� ���܌��̊w���ɂЂ�����w�A�܌��M�v�A���c���j��̎w������B1941�N�i24�j�A�����m�푈���u�����A�Վ��������x�ɂ���đ�w���J��グ���Ƃ���B�펞���͒��w�̋��t�ƂȂ����B�I��܂łɏt����3�l�̎q��������B 1945�N�i28�j11���ɓ����s����Łu�p�쏑�X�v��ݗ��B�����g�t�̃o�C�u���h�Ə̂��ꂽ�������Y�w�O���Y�̓��L�x�����s���Đ��������߂��B �p�쏑�X�n�Ƃ̂��������́A���܂���ɂ������R����`�̓��勳���ŁA�O�N�ɖv�����͍��h���Y�i1891-1944�j�̒������O�Ɂu�ڂ��Ԃ��قǖ{���ǂ݂����v�Ə������݂����芴���������߁B ���͍��h���Y�i1891-1944�j�c����o�ϊw�������B����Ō܁E������A��E��Z�����Ȃǂ̌R����`�⎑�{��`�̐���ᔻ�B�E���E�R���Ȃǃt�@�V�Y�����͂́A�͍����Љ�I�ɖ��E���邽�߁A�u���R��`�I�ł���v�Ƃ��Ēe�������B�͍��͓����� ���u���̗��N�i1938�j�ɑS���씭�ւƂȂ�A�N�i����ē���x�E�̏�������i�͍��h���Y�����j�B�푈�����1944�N2��15���A���ӂ̂�����53�ŕa�v�����B 1949�N�i32�j�A���@�L�O���i2�N�O�Ɏ{�s�j�ł���5��3���Ɂw�p�앶�Ɂx��n���B���ɖ{�Ƃ����W�������́A��O�����g���X�A�V���Ђ��������Ă���A����ɑ����Ă̒���ł��������D�]�������Č}�����A���̕��Ƀu�[���̒[���ɂȂ�B ���̂Ƃ��A���`�͎��̊��s�̎��������ɍ��B���ɁA�����ł���B �s�p�앶�ɔ����ɍۂ��āt�p�쌹�` ����E���̔s�k�́A�R���͂̔s�k�ł������ȏ�ɁA�������̎Ⴂ�����͂̔s�ނł������B�������̕������푈�ɑ��Ĕ@���ɖ��͂ł���A�P�Ȃ邠���Ԃɉ߂��Ȃ����������A�������͐g���Ȃđ̌����Ɋ������B ���m�ߑ㕶���̐ێ�ɂƂ��āA�����Ȍ㔪�\�N�̍Ό��͌����ĒZ���������Ƃ͌����Ȃ��B�ɂ�������炸�A�ߑ㕶���̓`�����m�����A���R�Ȕᔻ�Ə_��ȗǎ��ɕx�ޕ����w�Ƃ��Ď�����`�����邱�ƂɎ������͎��s���ė����B�����Ă���́A�e�w �ւ̕����̕��y������C���Ƃ���o�Ől�̐ӔC�ł��������B ���l�ܔN�ȗ��A�������͍ĂѐU�o���ɖ߂�A�������瓥�ݏo�����Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�B����͑傫�ȕs�K�ł͂��邪�A���ʁA����܂ł̍��ׁE���n�E�c�Ȃ̒��ɂ������䂪���̕����ɒ����Ɗm�����b���i�����j�炷���߂ɂ͐�D�̋@��� ������B�p�쏑�X�́A���̂悤�ȑc���̕����I��@�ɂ�����A���͂����ڂ݂��Č��̑b����ׂ������ƌ��ӂƂ������ďo���������A�����ɑn���ȗ��̔O����ʂ��ׂ��p�앶�ɂ�����B�i�ȉ����j ���l��N�܌��O�� 1952�N�i35�j�ɔ��������w���a���w�S�W�x�i�S60���j�́A1��������15�������̔����I����s���������A�S�W�u�[���̂�������������B�������ĕ��|�o�ŎЂƂ��Ă̊p�쏑�X�̕]�����m�������B ���̔N�A�o�呍�����w�o��x��n���A2�N��ɂ͒Z�̑������w�Z�́x��n�����A�����ŐV�l�܂�݂��Ă���B 1961�N�i44�j�A�w��蕨���|�̔����x�ŕ��w���m�̊w�ʂ���B 1964�N�i47�j�ȍ~�A���w�@��w���w���u�t�߂�B�ӔN�́u�o�啶�w�فv�̌��݂Ȃǔo�d�E�̒d�̋����ɐs�́B 1975�N10��27���A58�ŋ}���B�����͏�؉@�ߋ`���B���N�A��5��W�w���s�̓��x�œǔ����w�܂���܁B4�N��Ɋp�쌹�`�܂����������B �Г��ł́u�p��V�c�v�ƈ���鑶�݂ł������Ƃ����B�������ł͕����̈��l�Ɏ��������Y�܂��A�z���Ȑ��������т����B����Ɂu��蕨���|�̔����v�A��W�Ɂu���_���̎�v�u���s�̓��v�ȂǁB �����쉀�̕�O�ɂ́A�̔�u�Ԃ���ΐ��s�̓��Ǝv�ӂׂ��v�i�w���s�̓��x�����j�����Ă��Ă���B���g�̋�ɂ��Ȃ݊����́u�H�����v�i���イ���j�Ƃ��Ă��B �����ɍ�Ƃ̕ӌ������i1939-2011�j�A���j�Ɋp��t���i�p��t������������В��j�A���j�Ɋp���F�i���Ђ�/KADOKAWA��j������B |
������ �N��/Yasuyoshi Tokuma 1921.10.25-2000.9.20 �i�����s�A�`��A���J�� 78�j2010
 |
 |
 |
 |
| ���S�i�B���J����n�̉��̕� | �{��x�ēɎ��������I | �W�u���̎В��ɏA�C | ��O�ɂ͕������V�̂������� |
| ����̓��ԏ��X�В��B�X�^�W�I�W�u���В����f�В�����C�����B���ƉƂƂ��Ă����łȂ��A�f���R�[�h�E�v���f���[�T�[�Ƃ��Ă��r��U������B1984�N�i63�j�A��ʓI�ɂ͖����ɋ߂������{��x�i����43�j�̍˔\�����o���Đ���ʂŎx�����A�w���̒J�̃i�E�V�J�x�𐢂ɑ���B���̌���A�w�V��̏郉�s���^�x�i1986�j�A�w�ƂȂ�̃g�g���x�i1988�j�A�w�����̑�}�ցx�i1989�j�A�w�g�̓x�i1992�j�Ő����S�����A�w���̂̂��P�x�i1997�N�j����ƂȂ����w��Ɛ�q�̐_�B���x�i2001�j�ł͐��쑍�w���ɂ܂�����B ���ʉf��ł��A�w�����x�i1988�j�A�w���낵�⍑����杁x�i1992�j�A�wShall we �_���X�H�x�i1996�j�A�����K�����E�V���[�Y�Ő��쑍�w���ɂȂ��Ă���B�w�K�����Q ���M�I���P���x�i1996�j�ł͓��t���[�������ŃJ���I�o�������B ���{��ēɂ�����˔\�������Ă����쎑�����Ȃ���Ήf������Ȃ��킯�ŁA���̓_�œ��ԍN���̓A�j���E�t�@���̉��l�Ƃ�������B |
������ �Y��/Yusaku Shimanaka 1887.2.2-1949.1.17 �i�����s�A������A�z�n�{�莛�a�c�x�_�� 61�j2010
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
| �������_�Ђ̖��В��B�R�̒e���Ɛ���������̏o�Ől�B�ޗnj����܂�B1912�N�i25�j�A����c�𑲋Ƃ��������_�Ђɓ��ЁB���ҏW�ґ�c���A�i���傢��j�̏�������Ȃ����悵���w�l�����W���b��ƂȂ�A1916�N�i29�j�ɐV�G���u�w�l���_�v�̕ҏW���ƂȂ�B1925�N�i38�j�A��c�����E���u�������_�v�劲�����C�B1928�N�i41�j�A�������_�Ђ̎В��ƂȂ�B�����͋ߑ�I�Ȍo�c��ڎw���A�A�C���N�ɏo�ŕ���V�݁B�u��������ُ�Ȃ��v����x�X�g�Z���[�ƂȂ��r�����ڂ��ꂽ�B�܂��A�J�菁��Y��i��ו��ȂǍ�Ƃ�ϋɓI�ɉ��������B 1936�N�i49�j�A��E��Z�������u���B�ȍ~�A���R����`�A���R��`�I�Ȏp�����т��������_�Ђւ̒e�����������Ȃ�B1938�N�i51�j�A�u�������_�v�f�ڂ̐ΐ�B�O�w�����Ă�镺���x�����R�I�ł���Ƃ��Ĕ��֏������A������ΐ�͐V�����@�ᔽ�ŋN�i���ꂽ�B�J��̘A�ځw�א�x���u���ǂɑ��������Ȃ��v�Ɠ��Œ��f�����B 1942�N�i55�j�A�����m�푈���̑�K�͂Ȍ��_�e�������g���l�����h���N����B����͐_�ސ쌧�̓����x�@���ˋ�̋��Y�}�Č��d�c���ł��������A�������_�Ђ̕ҏW�҂琔�\�l���������ꂽ���́B��蒲�ׂ͉ߍ����ɂ߂S�l�����������B������1944�N�i57�j�A���ǒʒB�̉��U���߂Łu�������_�v�͔p���ƂȂ�B �I��Ɠ����ɁA�����͒������_�Ђ����O�ōČ����A1945�N�̔N���Ɂu�������_�v������1�������s�B���t�ɂ́u�w�l���_�v�����������B�I�킩��S�N��i1949�N�j�A�����͔g���̐l�������B���N61�B |
���z ����/Sonoji Yo 1838.6�|1906.9.24 �i�����s�A�䓌��A�J���쉀 68�j2010
 �@
�@ �@
�@
| �䂪�����ƂȂ���{��̓����V���u���l�����V���v�n�ƎҁB����o�g�B�ʏ́A�q�V���B�z����i�悤�E���̂��j��30�̎��ɖ����ېV���}�����B1870�N12��8���i31�j�A���l�����V��������B���{�ŏ��̓����M�����ł��邾���łȂ��A���Y�̊������g�p���A�]���̖ؔō��聕�a���ł͂Ȃ��A���ō��聕�m���ꖇ���ʂƂ�������I�V���ƂȂ����B�R�N��Ɉ���Ƃ̌i���Ђ�ݗ������B���͓V�V���m�B �����́u�������l�����V���v���u�����V���v���u���������V���v�Ɩ��O���ς��A���E��34�N��A���ĊJ�풼�O��1940�N�ɔp���ƂȂ����B �����݂́u�����V���v�͓��{�ŌÂ̓������ł͂��邯�ǁA�܂������ʉ�Ђ̂��́B�z�����l�����V����n�����Ă���Q�N��A1872�N�ɒa�������u���������V���v���A1911�N�Ɂu��㖈���V���v�ƍ��́@���A1943�N�ɎЖ����u�����V���v�ƂȂ����B |
������ ����/Hirohisa Seki �Éi5�N10��6���i1852�N11��17���j-1939�N1��22�� �i�����s�A�䓌��A�J���쉀 87�j2010
 �@
�@
| ���n�ƁB�x�R���o�g�B1895�N�i43�j�A�����s���{���ɍL���掟�X�u���v���J�ƁB�����͋���G����Ώۂɂ��Ă������A�V�����ʎ��̍L������舵���悤�ɂȂ����B1910�N�i58�j�A�����w���O�ʐM�x�����A�ʐM�Ў��Ƃɂ����o���B1939�N�ɑ��E�B�Ж��́u���O�ʐM�Д��v���o��1955�N�ɔ��ɖ߂����B |
�����䉥��/Ousuke Hibi 1860-1931 �i�����s�A�a�J��A�ˉ_�� 71�j2010
 |
 |
| �u���䉥���V��v�B���C�I���D�� | �ׂ�ɂ͗{��̖��q���� |
| �O�z�S�ݓX�n�ƎҁB���{���̕S�ݓX��������l���I���͋v���Ĕˎm�B���Ћ߂��o�āA1896�N�i36�j�ɎO���s�ɓ��ЁB�Q�N��ɎO�䒆���̑c�E�����F���Y�̈˗��ŎO������X�ɓ���B1904�N�i44�j�A�O�z�����X���J�Ƃ��ꖱ������ɏA�C�B1906�N�i46�j�A���Ď��@�̍ۂɃ����h���̃n���b�Y�S�ݓX�ɑ傫�Ȏh������B 1913�N�i53�j�A�O�z�����X��ƂȂ�A���N�����ȗm�����z�̓��{���O�z�{�X�����݂����B�q�ǂ��Ɂu�����v�ƕt����قǃ��C�I���D���ŁA�O�z�{�X�̐��ʌ��ւɃ��C�I������ݒu�����B |
���� �N���Y/Yasujiro Tsutsumi 1889.3.7-1964.4.26 �i�_�ސ쌧�A���q�s�A���q�쉀 75�j2010
 |
 |
 |
| �L��Ȋ��q�쉀�̈�ԏ�ɕ揊������ |
��ʐl�͂����܂ł����s���Ȃ��B�Z�R������������ |
����ɕ悪����Ƃ������ǎʐ^�Ō������ƂȂ��c �w���|�[�g�������t���Ă��邻���� |
�����O���[�v�n�ƎҁB��44��O�c�@�c���B���ꌧ�o�g�B�ꐧ�N��Ƃ����A�q�ǂ��̐���
�`�����i�F�m��12�l�B���ۂ�100�l�ȏ�Ƃ��������j�B�s�X�g����ٖ̈������B
�y�d�v�z2017�N12���A�ǎ҂̕�����u���́A�Z�R�����|�����Ă��炸�L��ȕ~�n�̒��ɂ���A
��ƒ玁�̓��������邱�Ƃ��ł��܂����v�Ə����܂����I�iM����L��������܂��j
������ �����Y/Kintaro Hattori 1860.10.9-1934.3.1 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 73�j2010
 �@
�@
�Z�C�R�[�O���[�v�n�n�ҁB�����s�o�g�B���v�E�l����n�܂�A���������Ő��E�I�Ȏ��v��ЃZ�C�R�[��z���グ���g���v���h�B
���O�� �C�_/Kaiun Mishima 1878.7.2-1974.12.28 �i�����s�A������A�z�n�{�莛�a�c�x�_�� 96�j2010
 |
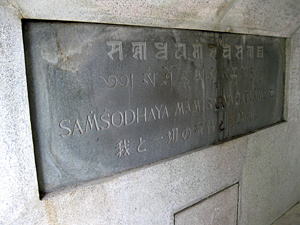 |
| ����ȁu�O���C�_��������v�B�J���s�X�̔����ҁI �O���������S���ň��_�������_�Ƃ��� |
�����̃v���[�g�ɃT���X�N���b�g�����S����� �u��ƈ�̗L��i�����傤�A�����j�Ƃ𐴂߂�v |
 |
 |
 |
| ���ɒ������`�̌ܗ֓� | ���ʂɁu�O���ƔV��v | �g�c�ޏ��Ƃ������I |
| �J���s�X�n�ƎҁB1917�N�i39�j�A���_�ۓ���̃L����������̔����郉�N�g�[��ݗ��B1919�N�i41�j�A�����S���l�̈��ݕ����q���g�ɁA�E��������_���y�����ĉ������A�J���V�E����Y���������_�ۈ���������B�O���͂��̏��i���A�J���V�E���ƞ���i�T���X�N���b�g��j�Łg�ō��̖��h���Ӗ�����T���s�X���������āg�J���s�X�h�Ɩ��t�����B�u�����̖��v�Ƃ����L���b�`�R�s�[���哖���肵�A�����I�Ȉ��ݕ��ɂȂ��Ă������B |
���X�i ����Y/Taichiro Morinaga �c�����N6��17���i1865�N8��8���j-1937�N1��24�� �i�����s�A�`��A�R�쉀 71�j2010
 |
 |
 |
| �X�i�Ƃ̕揊 | ����������Y�B�F�N���X�`�����ő��ʂɐ����̌��t | �u�ߐl�̒� ��͉��Ȃ�v�ƍ��� |
| �X�i���ّn�ƎҁB���ꌧ�o�g�B���Ƃ͈ɖ����Ă̓���≮�B6�ŕ����a�����A��10��㔼����s�����n�߂�B1888�N�A24�ŏĂ�����̔����ׂ��n�Ă��T���t�����V�X�R�Ŋ撣����s�U�ɏI���B�ċN��q�����Q�x�ڂ̓n�Ăŗm�َq�̐����Z�p���w�ыA���B1899�N�i34�j�A�ԍ�ɐX�i���m�َq��������n�Ƃ���B�����̎�͏��i�̓}�V���}���B�U�N��ɃG���[���}�[�N�����W�o�^�B1912�N�i47�j�A�Ж���X�i���قɉ��́B1914�N�i49�j�A�~���N�L�����������B1918�N�i51�j�Ƀ`���R���[�g�A1923�N�i58�j�Ƀr�X�P�b�g�̗ʎY�̐��𐮂���B�A�����J�ŃN���X�`�����̘V�v�w�ɐe�ɂ���ăL���X�g���k�ƂȂ�A�ӔN�̓L���X�g���̓`���ɐs�͂����B���E���{�W�O�v�l�͑\���B |
���Ĉ� �����Y/Genjiro Yonei 1861.10.19-1919.7.20�i�����s�A�{���s�A�����쉀 57�j2010
 |
 |
| �ߌ�̖؉k��z���ǂ������B���K�[�r�[�������݂����Ȃ� | �u�Ĉ�ƔV��v |
�i�ٔ�����ݗ��B���R���o�g�B1887�N�i26�j�A�]�Z�킪�n�Ƃ����������ɓ���A����p���œ��ЂW������B1907�N�i46�j�A
�W���p���E�u�������[�Ђ������i�ٔ���������Ђ�ݗ������B�ӔN�ɗA�o���Ǝ҂̕Ĉ䏤�X�i�����l�C�j��n�ƁB
����� ����Y/Soichiro Asano 1848�N4��13���i�Éi���N3��10���j-1930�N11��9�� �i�_�ސ쌧�A���l�s�A������ 82�j2010
 |
 |
 |
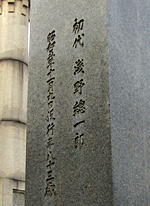 |
| �L��ȕ��I | �E������Y�A�����v�l | ����70�ЂƂ�����������z���� | �w��Ɂu�����쑍��Y�v |
| �������̑n�ݎҁB���l�H�ƒn�т𗧈āB�x�R���o�g�B23�ŏ㋞�B����������A�|�̔�i��p�j������o��1874�N�i26�j�ɐd�Y�i����j���ɂȂ�B�R�[�N�X�i�ΒY�������Ă������R���j�̔̔��Ő������A1883�N�i35�j�A�a��h��̎x���Ŋ��c�[��Z�����g��������n�Ƃ���B�������{�ő�̃Z�����g�E���[�J�[�ɐ��������A�����̋�s�ƁE���c�P���Y�̋��͂ŁA���{���̑����m����q�H�������m�D�D��1896�N�i48�j�ɐݗ��B 1898�N�i50�j�ɐ��Z�����g�i���{�Z�����g�j�A1916�N�i68 �j�ɐ�쑢�D���i���{�|�ǁA��JFE�j�A1918�N�i70�j�ɐ�쐻�S����ݗ�����ȂǁA��1�����E���̓����Ŏ��Ƃ��g�傳�����B���ŃZ�����g�A���D�A�f�ՁA�Y�z�A���S�ȂǁA�W���70�Ђɋy�Ԑ��鍑��z���グ���B |
������ �x�Y/Tomiro Nagase ���v3�N11��21���i1863�N12��31���j-1911�N10��26�� �i�����s�A�L����A����쉀 47�j2010��11
 �@
�@
2011
| �ԉ��n�ƎҁB24�œ����̓��{���ɗm���ԕ����̒����x�Y���X��n�ƁB1890�N�i27�j�A���̃}�[�N�́g�ԉ��Ό��h�̔̔����J�n����B1911�N�ɑ��E�B�����̎�����14�N��A1925�N�ɎЖ����ԉ��Ό��ƂȂ�B���E21�N��Ɂg�ԉ��V�����v�[�h�A���̂Q�N��i1934�N�j�ɐ���Ό��g�r�[�Y�h�A����ɂS�N��ɓ��{�ŏ��̉ƒ�p������܁g�G�L�Z�����h�����A���{�̐Ό��A��܋ƊE�����������B�����͑�@�@�������x���m�B |
����ؖ{ �K�g/Kokichi Mikimoto ����5�N1��25���i1858�N3��10���j-1954�N9��21�� �i�����s�A�`��A�R�쉀 96�j2010
 �@
�@
| ��ؖ{�^��X�i���E�~�L���g�j�n�ƎҁB�^��{�B�̐��҂ł���A�g�^�쉤�h�ƌĂꂽ�B�O�d���o�g�B�Ƃ͂��ǂB���l�ɂ���Đ�ł̉\�����������A�R���K�C�i�^��L�j�̗{�B�Ɏ��g�݁A1905�N�i47�j�A�V�R�ɕC�G����������̐^�~�^��̗{�B�ɐ��������B�C�O�ɂ��̔��Ԃ��\�z���A96�܂Œ��������B |
�����c ���Y/Teichiro Shoda 1870.3.29-1961.11.9 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 91�j2010
 �@
�@ �@
�@
���������n�ƎҁB�܂��A�������S����ł���M���@�c�������߂��B���q�q�c�@�̑c���B
���� ����Y/Shojiro Ishibashi 1889.2.1-1976.9.11 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 87�j2010
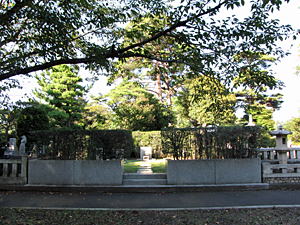 �@
�@ �@
�@
 �@
�@
�u���a�X�g���n�Ǝ҂ł���A�S���ꑫ�܁i�n�����܁j�̍l�ĎҁB77�̎��A���g���o�������v�����X�����ԍH�Ƃ����Y�����Ԃƍ����B
�S���H�ƁA�����ԍH�Ƃ̔��W�ɐs�͂����B���Ȃ݂Ɂg�u���a�X�g���h�Ƃ̓u���b�W�E�X�g�[���A�܂�n�ƎҁE���̖��O���B
���s�� �E/Shinobu Ichikawa 1897.1.9-1973.11.2 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 76�j2010
 |
 |
| �����쉀�͍L�����̕揊������ | �u�s��Ɛ�c��X�V��v |
�ۍg�̏���В��B��錧�o�g�B�_�ˍ����i���E�_�ˑ�w�j���ƌ�Ɉɓ��������ɓ��Ђ��A�ۍg���X�ɓ���B1949�N�i52�j�A�ۍg��
����В��ɏA�C�B���������z�����������Њۍg�Ɣ��W�������B�u���E�V�E�a�v�̐��_���d���B�����͐����@�ߔE���B
���� ����/Naoya Sakai 1927.11.30-1993.4.24 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 65�j2010
 �@
�@ �@
�@
| �����o�g�B1948�N�i21�j�A���������w�@���B1951�N�i24�j�A������`��ݗ��B���W�I�����C���Ɏ戵���L����ЂƂ��ăX�^�[�g�B1961�N�i34�j�A�����ɎЖ���ς��ĎВ��ɏA�C�B�S�N��ɃA�j������̑�ꓮ���ݗ����A1968�N�i41�j�A�S���̃`�r�b�R��k���オ�点���w�d���l�ԃx���x�𐢂ɑ������B���̎��̂U�N��A1999�N�Ɉ��ʐM�Ђƍ������A�Ж����u�A�T�c�[ �f�B�E�P�C�v�Ƃ���B�����L���㗝�X�Ƃ��Ă̔N�Ԕ��㍂�́A�d�ʁA���Ɏ����ő�R�ʁB�A�T�c�[ �f�B�E�P�C�́w�̓K���_���x�w�@����m�K���_��SEED�x�w�@����m�K���_��00�x�w�h��������i��R�j�x�w峎t�x�̐���Ɋւ���Ă���B |
���ΐ� ��Y/Ichiro Ishikawa 1885.11.5-1970.1.20 �i�����s�A�L����A����쉀 84�j2010
 �@
�@ �@
�@
30�ŕ����o�c����֓��_���i���Y���w�H�Ɓj�ɓ��ЁB56�œ��Y���w�H�ƎВ��ɏA�C�B1948�N�i63�j�A�o�c�A�����ɏA�C�B
�����{�o�ς̕�����ڕW�ɍ��E�̃��[�_�[�ƂȂ�B���{�Ȋw�Z�p�A��������߁A���q�͂̋Z�p�J���ɐs�͂����B
������ �m�v��/Chikuhe Nakajima 1884.1.1-1949.10.29 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 65�j2010
 |
 |
 |
| ������s�@�̈ꎮ�퓬�@�g���h | �L��ȕ��A����傫�� | �u�����m�v����v�i2010�j |
| �Q�n���o�g�B�_�Ƃɐ��܂��B���{���̖��Ԕ�s�@���쏊�A������s�@�i�̂��̕x�m�d�H�Ɓj�̑n�n�ҁB���F��ق߂������ƁB�C�R�@�֊w�Z���ƌ�A1908�N�i24�j�A�@�֏��тɔC���A�R�N��ɑ�т܂ŏ��i�B�t�����X��A�����J�̍q��E�����@������A1917�N�i33�j�ɊC�R��ފ����A�Q�n�����c�Ɂu��s�@�������v��ݗ��A1919�N�u������s�@���쏊�v�ɉ��́B1930�N�i46�j�A�O�@�c���ɓ��I�i�ȍ~�T��A�����I�j�B�������F��ɓ��}�B���N�A������s�@�������ɏ���A���H���������ɏA�C�B�S����b�A�吭���^��̎Q�c���C�������A������������邽�߂ɋ��͂Ȑ��}����낤�Ƃ��Ă����B 1941�N�i57�j�A������s�@�̈ꎮ�퓬�@�g���h�����R�ɐ����̗p�����B�č��̍��͂�m���Ă���A���ĊJ��ɂ͔����Ă����B1945�N�A�s���ɌR�����A���H���ƂȂ�A�N����A����Ǝw��i�Q�N��Ɏw������j�B1949�N�A�]�o���̂��ߋ}���B���N65�B������s�@�͗��R�퓬�@�͂��ߍq��@�̂R���߂���Ɛ萶�Y�����B �������m�푈�̎�͋@�g���h�́A�C�R�E�O�H�̗뎮�͏�퓬�@�ɔ�ׂ�ƉΗ͂͗�������������ł͏������B�܂��^�����\�����ɏ��������̂́A�h�e�����ɂ���Ėh��͔͂��̕����D�G�������B�����Y�@����5,700�@�ȏ�B���Ɏ����łQ�Ԗڂɑ����A���R�@�Ƃ��Ă͑�P�ʁB |
���x�R �h�s�Y/Eichiro Tomiyama 1903.1.1-1978.9.1 �i�����s�A������A�썑�� 75�j2014
���x�R ��A/Masanari Tomiyama 1928.7.30-2005.11.7 �i�����s�A������A�썑�� 77�j2014
 |
 |
 |
| �S���̎q�ǂ��B���������ׂ�����I | �u�x�R�Ɓv�Ƃ���B��A�̒��j�E�����Y������ | �u�Ղ��[����A�Ƃ݂����A���������ł��I�v |
 �@ �@ |
 �@ �@ |
| �掏�ł͉h��Y�̖����u�h���Y�v�ɁA ��A�̖��͖{���́u�����Y�v�ɂȂ��Ă��� |
�v�����[�����J�������Q��ڎВ��E�x�R��A�B������ ��1���v�����[���u�v���X�`�b�N�D�ԁE���[���Z�b�g�v�i1959�j |
| �g�~�[�i���^�J���g�~�[�j�n�ƎҁB��ʌ��o�g�B1924�N�A21�̂Ƃ��Ɍ��E�L����ɕx�R�ߋ�쏊��n�ƁB�R�N��ɖn�c��ֈړ]�A�Ж���x�R�H��Ƃ��@�l���B1928�N�i25�j�A���j�̈�A�i�܂��Ȃ�j�a���B1945�N�i42�j�A���^�J���g�~�[�{�Ђ̏��ݒn�A������ֈړ]�B����"Tomiyama"�i�g�~���[�}�j�̃u�����h�ŊC�O�A�o���s����ЂW������B1959�N�i56�j�A��A�i����31�j�͉h�s�Y�̖����ēS���͌^�w�v�����[���x�̌��^�ƂȂ�u�v���X�`�b�N�D�ԁE���[���Z�b�g�v���J���A��������B�����̊ߋ�̓u���L��ؐ����嗬�ł���A�v�����[���̑f�ނ��v���X�`�b�N�����͉̂���I�������B1963�N�i60�j�A�Ж����g�~�[�H�ƂɕύX�B 1965�N�A�����ߋ�g�����Ƃ��ēȖ،��ɂ�������̂܂����H�ƒc�n��������B1970�N�i67�j�A��A�i����42�j���C�O�̃~�j�J�[���Q�l�Ɂw�g�~�J�x���J���A�U�Ԏ������B�g�~�J�E�V���[�Y�͑�q�b�g���A�Q�N��ɂ�60���˔j�����B1973�N�i70�j�A�M�l�����������͂���́B1974�N�i71�j�A�n��50���N���@�Ɉ�A����2��В��ɂȂ�A���g�͉�ɏA�C�����B1978�N�ɑ��E�B���N75�B��A�́u���Ђ���@�ꔭ�v��u�]�C�h�v�Ȃǃq�b�g���i�����X�ƊJ�����A2005�N��77�Ŗv�����B ���w�v�����[���x�͍��������ŗv900��ށA�P��3200���ȏ��̔��B���[���̑������͎��ɒn���Q�����ȏ�ɂȂ�B ���w�g�~�J�x��700���˔j�A2010�N�܂ł̑����Y�䐔��5��3800����B |
�����c �`��/Giichi Masuda 1869.11.24-1949.4.27 �i�����s�A������A�썑�� 80�j2014
 |
 |
 |
| �������썑���E�R�傩��200m���ɂ���̂Œ��� | �g15�ʁh�ɓ����Ĉ�ԉ�����ɕ揊 | �w���c�ƔV��x |
| �o�Ől�A�����ƁB�V�����o�g�B�������w�Z�i������c��w�j�𑲋ƌ�A�ǔ��V���Ђɓ��ЁB1895�N�i26�j�A�F�l�n���́w���ƔV���{�x�̕ҏW�Ɋւ��A���̌�a�ɕ������F�l����ҏW�E���s���������A1900�N�i31�j�A�ǔ���ގЂ��g���ƔV���{�Ёh��n������B�w�w�l���E�x�w���{���N�x�w�����̗F�x�ȂǑ����̎G�������s����B1912�N�i43�j�A�O�c�@�c���i���{�i���}�j�ƂȂ�A��ɏO�c�@���c���߂��B �����������ǁA�l�̕揄�烌�|�[�g��1999�N�ɏ��߂ď��Ёw�����x�ɍڂ��ĉ��������̂����ƔV���{�Ђ������B�{������œ�������Ɏ�������̋����͖Y����Ȃ��B�����l��32�B�E�T�����ĕ��|�����ƂɂȂ�傫�Ȃ��������ɂȂ����B���c�`�ꎁ���n�Ƃ��ĉ����������炱���A�l�ɂ��̂悤�ȉ����K�ꂽ�킯�ŁA���̈Ӗ��ł͉��l�Ƃ�������B�S�����߂ĕ�O�Ŋ��ӂ����B |
������E�����핺�q/Yahe Kagiya �i���v�N�s���j2012��16
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
�]�˂��\����ԉΉ��B�ʉ��̃��C�o���I����̌`���ԉʂ��B
������ �ɓ� �����q/Tyube Ito 1842.8.7--1903.7.8 �i���s�{�A���R��A��J��n 60�j2012



| �ߍ]���l�A���ƉƁB�ɓ��������E�ۍg�Ƃ����Q�̑�葍�����Ђ�n�Ƃ��A���p�I�o�c�ɂ���Ĉɓ����������`�������B
�e�a�̕揊�Ƃ��Ēm���鋞�s�E��J�{�_�ɖ���B2020�N�A�������z���O�H�������ċƊE��ʂɗ������B |
���Z�F���F/Masatomo Sumitomo �V��13�N11��11���i1585�N12��31���j-�c��5�N8��15���i1652�N9��17���j�i���s�{�A������A�i�{�� 66�j2011



| ���X�`���C���h�������Â��A400�N�ȏ�̗��j�������E�ŌÂ̍����ƌn�A�Z�F�Ƃ̌��_�B �z�O���o�g�̍]�ˎ���̏��l�ŏZ�F�Ƃ̏���B���͑m���A�o�ƑO�͕��m�B���Ϗ@�̑m�ƂȂ���e�����A�ґ��i�����j�����ݖ�̑m�ƂȂ�A���s�ŏo�ŋƁE���Ɓu�x�m���v���J�Ƃ����B����A�`�Z�i�o���j�̑h�䗝�E�q�傪��ؐ����Ƃ������������̋Z�p���J�����ē����ƂȂ�A�ꑰ�͔ɉh���Ă����B �Z�F�ł͏��ƁE�Z�F�Ƃ����������F���ƌn��̑c�Ƃ��ĉƑc�A�������̋Z�p���J�������`�Z�E�h�䗝�E�q����Ƒc�Ƃ��Ă���B���s�s������̏�y�@�E�i�{���ɑ�����B ���Z�F��s���J�Ƃ����Ƃ���15�㓖��E�Z�F�F���i�Ƃ����Ɓj�́A���R�V�c�̒j�n�V�����I ������{���̎������ɂ������B��40��̈ꑰ��n�̎�O�����ɕv�Ȃ̕�B�@���E����@���B |
���O�䍂��/Takatoshi Mitsui ���a8�N�i1622�N�j-���\7�N5��6���i1694�N5��29���j�i���s�{�A������A�^�@�� 72�j2011
 �@
�@ �@
�@
| �]�ˑO���̍����B�]�ˁA���s�A���ɓX�܂��\����O�s��p���l�B�����O��Ƃ̉Ƒc�B�ɐ�����̏��l�̎q�i�O��Ƒ���j�B�ʏ́A���Y���q�B
�喼�݂��A�Ă̔����ō���z���A1673�N�]�ˁE���s�Ɍ����X�z�㉮�i�O�z�j���J�ƁA�����ō]�ˁE���ɗ��֏����c�݁A���{�ב�p�B�Ƃ��ċ��z�̕x��~�ρA�O��Ƃ̊�b��z�����B �揊�͐��ʉE�肪�����A���肪�v�l�B |
������쑺 ����/Tokushichi Nomura 1878.8.7-1945.1.15 �i���s�{�A���R��A��J��n�@66�j2012
 �@
�@ �@
�@
���������|�����Ă���̂ɁA���܂��ܑ|���Ŗ傪�J���Ăē�����������
| �쑺�����̑n�n�ҁB���֏��̖쑺���� (����)�̒��j�œ��ځi�c���͐M�V���j�B
1918�N�ɑ��쑺��s�i��̑�a��s�A���݂̂肻�ȋ�s�j��ݗ��A��s�،�����1925�N�ɖ쑺暌��Ƃ��ēƗ������B �����͑�J��n�E�k�J�n��ɂ��邪�A�_���ɂ͌����������Ă���B ����n��O�̉ԉ�����ł���������ƌ��������Ƃ̂��ƁB |
������ �M���Y/Shinjiro Tori 1879.1.30-1962.2.20 �i���ꌧ�A��b�R�A��� 83�j2012
 |
 |
| ����t�@�~���[�̕�� | ���Ձi������j�ɃT���g���[�̃��S������ |
 �@ �@ |
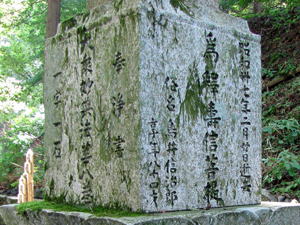 |
| ��ɂ͑�断�T�@�ؔ������[�o����Ă��� | ��������M���Y�Ƃ��� |
�T���g���[�n�ƎҁB1929�N�A50�ŏ��̍��Y�E�C�X�L�[�u�T���g���[�E�C�X�L�[���D�v�i�T���g���[�z���C�g�j�Ɓu�T���g���[�E�C�X�L�[�ԎD�v�i�T���g���[���b�h�j���B
�M���Y�̃`�������W���_������킷���t�u����Ă݂Ȃ͂�v���A�T���g���[�͌��݂��n�Ɛ��_�Ƃ��Čf���Ă���B���j�͓��ڎВ��̍����h�O�B
������ �h�O/Keizo Saji 1919.11.1-1999.11.3�i���ꌧ�A��b�R�A��� 80�j2012
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
���ƉƁB�T���g���[�̑O�g�A������n�Ƃ�������M���Y�̎��j�i�Z�͑����j�B��㐶�܂�B1961 �N�A��Q��В��ɏA�C�B
1963�N�A�扮����T���g���[�ɎЖ���ύX�B �r�[���ƊE�ւ̐i�o�ȂǂŎ��Ƃ��g��A�o�ŁE�L���ƊE�ւ��i�o�����ق��A
�T���g���[���p�فA�T���g���[�z�[���̐ݗ��ȂNJ�Ƃ̎Љ�E���������̐�삯���Ȃ����B�܂���b�Ȋw������M�S�ɃT�|�[�g�����B
������F�����l�Y���Y ����/Kiyonobu Tyayashirojiro 1545-1596.9.19 �i���s�{�A���R��A����J��n 51�j2012
 �@
�@
| �����l�Y���Y�Ə���B�{���͒����B���������܂��O�A�������͕��m����߂ċ��Ō��������J�n�B���R�����`�P�������Ε��̉��~�ɒ������݂ɗ�����������Ƃ���u�����v�������ƂȂ�B
�����͎Ⴂ���ɉƍN�Ɏd���A���c�R�Ƃ̎O�������̐킢���Ŋ��ċk�̉Ɩ���������Ƃ����B �{�\���̕ς̍ۂ́A��ɑ؍ݒ��̉ƍN��s�ɑ��n�ŕς�m�点�A�ƍN�̒E�o���u�_�N�ɉ�z�v�S���ʂŏ����A���̉��ɂ�蓿��Ƃ̌�����p�����Ɉ�����悤�ɂȂ����B �����̖v��A��p�̒��j�E�������}�����A���j�̐����������ŐՂ��p���B1612�N�A�����͎��D�f�Ղ̓����邱�Ƃɐ������A��Ƀx�g�i���Ƃ̌��ՂŔ���ȕx���B �����͒�������W�߁A�{������x��̌|�p�x���ɂ��M�S�ł��������A1622�N��38�Ŏ����B�ƍN�̎����Ƃ�������u��̓V�Ղ�v���x�͍��c����ʼnƍN�Ɋ��߂��̂͐����Ƃ����B �p�q���Ȃ̊p�q�ƁA�㓡�l�Y���q�̌㓡�l�Y���q�ƂƂƂ��Ɂu���̎O���ҁv�ƌ���ꂽ���A������͐��ނ��Ă����A10��ڂ̕s�n���œ����������A�ېV��ɔp�ƁB |
���������/���{�O�Y�E�q����/Joan Yodoya �i�\3�N�i1560�N�j-���a8�N7��28���i1622�N9��3���j�i���{�A������A��厛 62�j2014
 �@
�@
�E����R��ځA�������A�Q���
|
�]�ˎ���̑��Ŕɉh���ɂ߂������B�����Y�͌��݂̖�200���~�ɑ��������20�����B���{�O�Y�E�q��͎R�鍑�̕��Əo�g�B�M���ɓ�����ď��l�ƂȂ�A����̍��𖼏�����B����͕�����̑��c�◄��̒�h���C�H���ō����y�؍H���Z�p�����G�g�ɕ]�������B���̌�A���Łu�����v�Ə̂��ޖ؏����c�B���̐w�œ�������x�����A�y�n��H����A���т��ƍN�ɔF�߂��y�n300�Ɩ����ѓ����������B
�Q��ڂ͎��g�������V���ɑS���̕đ���̊�ƂȂ�Ďs��ݗ����A���V���ɓn�邽�ߗ�����������ʼn˂����B�Ďs�ɏW�܂�Ă����邽�߁A���˂�ď��l�̕Ă����鑠���~�����V���ɂ�135�����������сA�s��Ŏ���������Ă�4���i200���j�����Ŏ���������ȂǁA��₪�u�V���̑䏊�v�ƌĂ�鏤�s�ɂȂ�y���������B�����̕Ďs�ōs��ꂽ��`�ł̕Ď���́A���E�̐敨����̋N���Ƃ����B
�Ƃ��낪�A���܂�ɗ����̍��͂����ƎЉ�ɉe�����邽�߁i���喼�֑݂��t���Ă������z�͌��݂�100���~�j�A1705�N�A�ܑ�ڗ����A�c�i�����Ƃ��j�����{������Y�v�������ɂ���Ă��܂��B���R�́u���l�̕������A�ґ�Ȑ������ڂɗ]��v�Ƃ������̂����A�{���͑喼�̎؋��̒������Ƃ��B�����A�����������Ă��Ȃ��B���̏����ɐ旧���A�ԓ��̖q�c�m�E�q��i���������q�j�ɒg���������s���đq�g�i����j�ɓX���J���A��ɍĂь��̑��̒n�ōċ������B�������J�����V���Ɋ|���闄�����������ɍ��������c��B
��������n�Ƃ������{�Ƃɂ����̂��O�������A�q�c�Ƃɂ��ċ����ꂽ���̂���������B
|
���p�q ����/Ryoi Suminokura �V��23�N�i1554�N�j-�c��19�N7��12���i1614�N8��17���j�i���s�{�A�E����A�@�@60�j2012
 �@
�@ �@
�@
| ���y���R�E�]�ˏ����̍����E�y�؉ƁB���s�o�g�B���͌��D�B����ɏZ�ށB �Z���E�n�����w�сA�G�g�Ɏ���Ĉ���i�x�g�i���j�E����(�g���L��)�Ƃ̎��D�i�p�q�D�j�f�Ղɏ]���B �R��i���s�j����̑剁��(����������)�A������������𓊂��ĊJ�킵���B �܂������ɂ��x�m��A�V����A������Ȃǂ̊J����s���Đ��H���J�����B �s�ł͏��l�Ƃ��Ă����u���^�̕��v�Ƃ��ėL���B�揊�͋��s�s�����̓@�B恂͌��D�B |
���t�F���f�B�i���g�E�|���V�F/Dr. Ferdinand Porsche 1875.9.3-1951.1.30 �i�I�[�X�g���A�A�c�F���A���[�[ 75�j2015
Schuttgutkapelle, Porsche Family Estate, Zell am See�i�c�F���A���[�[�j, Zell am See Bezirk, Salzburg, Austria
 |
 |
 |
| �V�ˎ����ԋZ�t | �����ԃt�H���N�X���[�Q���E�r�[�g����v | �G���t�@���g�d�쒀��Ԃ��v |
  |
 |
| ��Q�ɖK���ƁA���悪��ʂ̕�n�ł͂Ȃ��A�|���V�F�Ƃ̕~�n���̗�q���ɂ���A �g�v���C�x�[�g�h�ƊŔ��o�Ă����̂Œ��ɓ��ꂸ�A��̑O�ŗ���������ł����B ����ƁA���傤�ǔN�z�̕����o�Ă��āu���͑����B��Q��H�����Ă��ꂽ�܂��v�Ƃ̂��ƁI ����������́A�����炭�����̎q�A�t�F���f�B�i���g�E�s�G�q���B�g�}�X�R�~�����̒����h �Ƃ����b�����ǁA���ΖʂȂ̂ɂ߂��Ⴍ����D���������B���Ă������A�n�O���Ă��ꂽ���c |
���̎��݃`���y�����ꑰ�̕揊�B �A�|�Ȃ��ł悭������Ă��ꂽ���ƁI |
 |
 |
 |
| ��z���ɒ��������� | �Ւd�̊�d�ɁuFerdinand Porsche�v�Ƃ����� | �����炭��O�̏����Ɋ� |
�����ԋZ�t�B20���I�ō��̎����Ԑv�ҁB�|���V�F�n�ݎҁB�j��ł�����������O�ԃt�H���N�X���[�Q���E�r�[�g���ȂǁA�����Ԏj�Ɏc��
����Ԃ𑽐��v�B�܂��A�ƌR�G���t�@���g�d�쒀��Ԃ╗�͔��d�@���肪�����i�e�B�[�K�[��Ԃ̖��t���e�ł͂��邪�����̗p�͂Ȃ炸�j�B
���Ȃ́u�Z�p�I�����������邽�߂ɂ͔��I�ϓ_������[���̂������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��v�B
�����揊�ɑ��q�̃A���g���A���Ŗ���911��J������v�����A���N�T���_�[������B
| �����̃T�C�g���d��I �]�ˎ���̗l�X�ȕ������� |
���A�C�E�G�I��/�C�O�҂̖ڎ���
���A�C�E�G�I��/���{�҂̖ڎ���
���W�������ʌ����̖ڎ���
��i���j�Agrave�i�p�j�Atombe�i���j�Agrab�i�Ɓj�Atomba�i�Ɂj�Atumba�i���j�Asepultura�i�|���j
��n�i���j�Acemetery�i�p�j�Acimetiere�i���j�Afriedhof�i�Ɓj�Acimitero�i�Ɂj�Acementerio�i���j�Acemiterio�i�|�j
|
