���E���l�����ʐ^�� �y�d������������ Version�z
�̐l�A�o�l�R�[�i�[
28��
���ΐ� ���/Takuboku Ishikawa 1886.2.20-1912.4.13 �i�k�C���A���َs�A�Z�g��������n 26�j1998��09
 |
 |
 |
| ��Ƌ��c�ꋞ�� | 16�̑�� | JR�����w�̕����g���肨���h�͑�̂��̂� |
 |
 |
 |
 |
| �u�ΐ��ؐ��a�V�n�v | ��͂��̏�����i���j�Ő��܂ꂽ | ������܂ꂽ�����i2012�j | �����ɋ����̐��a��Ɠ����|������ |
 |
 |
 |
| �P����18�܂ʼn߂��������i���j |
�������ꂽ�u��̊ԁv�B�g��h�̃y���l�[���� �����̎���@����ؒ��i�����j���炫�Ă��� |
�[���̊��R�B������̌i�F������ |
 |
  |
 |
| �̋��a���i���Ԃ��݁j�̐ΐ��؋L�O�� | ������w�Z��p��������ɉƑ��ƊԎ肵�Ă����ē��� | �����s���́u��ؐV���̉Ɓv�i���w�����j |
�y�k�C���E���فz
 |
 |
| �g��؈ꑰ�̕�h�͗��Җ��� | ���ɓo�铹�̊C���ɑ�͖����Ă��� |
 |
 |
 |
| 1998�@������B�͂��߂܂��āA�����I |
2009�@11�N�Ԃ�ɏ���B���S�̂������Ȃ��Ă����I �K�i�̐����{�ɂȂ�A�Ί_����グ����Ă����I |
2014�@�T�N�Ԃ�A�R�x�ڂ̏���B�����ɖK�ꂽ |
 |
  |
 |
| 2009�@���J���� |
2014�@���炵�����Ԃ����Ԃ���Ă��� �O�ʂɁu���C�̏����̈�̔����ɂ�ꋃ���ʂ�ĊI�Ƃ��͂ނ�v |
��̔w��ɂ͑�̎莆�̈�߂����܂� �Ă���u����͎��ʎ��͔��ق֍s���Ď��ʁv |
 |
 |
 |
| ��̕悩�生�ق̊X���݂���]�ł��� | ���̓��̒Ìy�C������̕��͉��₩������ | �f���炵���i�ς̒n�ɖ����Ă��� |
 |
 |
 |
| �����߂��ɋ`��̉̐l�{���J�̕�B ��̍Ȃ̖��ӂ��q�ƌ������� |
�揊�̑O�̍⓹��o���Ă����Ɨ��Җ��ɁB ���������ۂ݂�тсA�n�����~�Ƃ킩�� |
�Ìy�C���B�Ί݂͐X�̗��� |
|
��������̉̐l�E���l�E�]�_�ƁB�{���͐ΐ��i�͂��߁j�B1886�N�Q��20���A��茧����S���ˑ��i�������s�ʎR����ˁj�ɐ��܂��B���͓����̏�����Z�E�B��͓암�ˎm�̖��B���N�A�����ߗׂ̏a�����̕��Z�E�ƂȂ�Ƒ��ňڏZ�������̏a�������A��ɑ���r�ށu�ӂ邳�Ɓv�ƂȂ����B�a�����w�Z����Ȃő��Ƃ��A�n���ł͐_���ƌĂ��B�����̒��w�ł͂S�ΔN��̐�y���c�ꋞ���i��̌���w�ҁj���當�w�̖ʔ������������A���|�G���w�����x���n�ǂ��ė^�Ӗ쏻�q�ɉe�������B
1901�N�i15�j�A�w������x���ʂɑ�̒Z�̂����߂Čf�ڂ����B��͍��܂镶�w�M�Ə�M�I�ȏ����̒��Ŋw�Ƃ����낻���ɂȂ�A�J���j���O���Q��A���Ŕ��o�����挈��ɁB1902�N�A���16�Ŏ���ފw���㋞����i�ފw���������Ƃ���������j�B ��́w�����x�ɓ��e�����Z�̂��f�ڂ���A���w�Őg�𗧂Ă����ł������A�^�Ӗ�S���E���q�v�Ȃ̒m�������̂̎d���͉��������炸�A�ƒ���ؔ[���ĉ��h��ǂ��o����A���N���o�����ɋA���B��1903�N�A17�̎��ɏ��߂āg��h�̍��𖼏��w�����x�ɒ����\�����ڂ����B 1905�N�i19�j�A�������W�w��������x�����s�B�ꕔ�œV�ˎ��l�ƕ]�����ꂽ���A�������K�g���u���i�@��ؔ[�j�ŏZ�E���Ƃ���A�܂��T���Ɏ��g�����w���ォ��̗��l�i�ߎq�v�l�j�ƌ����������ƂŁA���e�ƍȂ�{��˂Ȃ炸���w�ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ����B�����ɋA������́A��1906�N�A20�ŏ��w�Z�̑�p�����Ƃ��ē����n�߁A�N���ɒ��������ꂽ�B 1907�N�i21�j�A�Z�E�ĔC�^���ɍ��܂��������Əo�B���ق̕��w���D��猴�e�˗������������Ƃ��@�ɁA�S���ɐS�@��]��}���Ėk�C���ɓn��i�Ȏq�͐����Ő����j�B���ُ��H��c���̗Վ��ق��A��p�����A�V���ЎЈ��ȂǂɏA�����A�ǂ̎d���ɂ������ł����A���ّ�������ĂX������D�y�ōZ���W�ɂȂ�B���̌�A���M�A���H�𗬘Q�B���قŏo��������|���ԁE�{���J�i�������j�͑�̗ǂ������҂ŁA�Ƒ���k�C���Ăъ闷����o���Ă��ꂽ�B 1908�N�i22�j�A�ǂ����Ă����w�ւ̖����̂Ă���Ȃ���́A��J�ɉƑ���a����Ƌ��F�̋��c�ꋞ���𗊂��čĂя㋞����B���c��͑����������ׂɈ����̏��Ђ܂ŏ��������B��͍�ƂƂ��Ă̐������Ď��X�Ə��������������A���d�ł��Ƃ��Ƃ����������B�����ł��ӂ��ꂽ��́A�ނɂƂ��ċC������f���o�����߂́g�ߋ�h�A���Ȃ킿�O�s�̒Z�̂ɓ��X�̈����݂��̂����B 1909�N�i23�j�A�O�N�ɗ^�Ӗ�S���ɘA����ĉ��O�̉̉�ɎQ���������Ƃ����������ɁA�G���w�X�o���x�n���ɎQ���B�������A���ς�炸�����͕]�����ꂸ�A���ӂ̒��œ��������V���ЂɍZ���W�Ƃ��ďA�E����B �e�F�i�{���J�j�ɗa�����܂܂̉Ƒ�����A�g���g�������̂ő����ĂъĂ���h�Ƒ������ƁA�ŏ��W�ƗV�ԂȂǎ��R�Ȕ��Ɛg�����𑗂��Ă�����́A�Ƒ������Ă͏����̍\�z�ɏW���ł�����i�������Ȃ��ȂǂƁA�Ƒ����}����܂ł̖�Q�����Ԃ̋�Y���w���[�}�����L�x�ɋL�����i��ɂ���͓��L���w�̌���Ƃ��ĕ��w�j�ɍ��܂�邱�ƂɁB��������͈⌾�ŔR�₷�悤�v�l�ɖ����Ă����j�B�Ƒ��̏㋞��A�V���ɔ�₳�ꂽ�؋��Ȃǐ����ꂩ��ȂƌƂƂ̑Η����[�������A�Ȃ��q�ǂ���A��Ė�ꃖ�������̎��ƂA���Ă��܂��i���c��̐����Ŗ߂�j�B�N���ɕ����㋞�A�����B 1910�N�i24�j�A�V���̒d�̑I�҂ɔC���������A��炵�͈ˑR�����������B�n�������̒��ō����I�Ȏv�z�ɌX���Ă�����́A�U���ɑ�t�����i�V�c�ÎE������������ɓ��ǂ̃f�b�`�グ�Ɣ����j���N����ƁA�V���̍Z���W�Ƃ������������A�����Ɋւ��鑽���̋L��������L�^��ǂݍ��݁A���̍ٔ������{�ɂ��d���Ɗm�M�B���Ƃɂ��v�z�����E���_�e����[���J�����ĂW���Ɂu�������Ƃ̋������ǓI�ȎЉ�݂����Ă���v�ƕ]�_�w����ǂ̌���x�������i����ɔ��\�j�B�܂��A�g�ђ��̒��h�Ƃ��������ŁA�w�����i������j���x�̎��x�������グ�V���Ɍf�ڂ��˗��������p�����ꂽ�B �u������g���x�̎��h�ɂ��āB���{�̓A�i�[�L�X�g���e���M��̋��M�҂̔@���]���Ă��邪�A���̓A�i�[�L�Y���͂��̗��_�ɂ����ĉ���댯�ȗv�f���܂�ł��Ȃ��B���̗l�ȕ����Ȑ��̒��ł́A�A�i�[�L�Y�����Љ�������Ŏ����g�܂������{��`�҂ł��邩�̂��Ƃ�����������邩������Ȃ����c���������ɖ����{��`�Ƃ��������������Ŕ����Ђ��߂�l�Ȑl������A���̌�����w�E���˂Ȃ�܂��B�����{��`�Ƃ����̂͑S�Ă̐l�Ԃ����~���������āA���ݕ}���̐��_�ʼn~���Ȃ�Љ��z���グ�A�����������Ǘ����鐭�{�@�\���s�K�v�ƂȂ闝�z���ւ̔M��Ȃ铲�ۂɉ߂��Ȃ��B���ݕ}���̊�����ŏd������_�́A�ێ瓹���ƂɂƂ��Ă����������t�ł͂���܂��B���ɂ����ނׂ����\�Ȃ�l�Ԃƌ����Ă��閳���{��`�҂ƁA��ʋ���Ƌy�їϗ��w�҂Ƃ̊ԂɁA�ǂ�قǂ̑�����Ȃ��̂ł���B�i�����j�v����ɁA�����{��`�҂Ƃ́g�ł����}�Ȃ闝�z�Ɓh�ł���̂��v�B �W�����ɒ��N����������A�u�n�}�̏㒩�N���ɂ��낮��Ɩn��h��H�����v�ƋL���B 10���A���j�̐^�ꂪ���܂ꂽ���A�킸���R�T�Ԃŕa���B��͖�Œ��j�̗ՏI�ɗ�����Ȃ������B�u����ċ���A�����邱�Ƌ͂�24���ɂ��ē���27����12���߂��鐔���ɂ��Ď����B���i�������j���\��ɓ���A�A�藈����܂��ɐ⑧������݂̂̏��Ȃ肫�B��t�̒��˂����Ȃ��A�̉��łɎc���v�B 12���A�u���������́v�u���v�u�H���̂�����悳�Ɂv�u�Y�ꂪ�����l�X�v�u�蓅��E���Ƃ��v��5��551��Ȃ�O�s�����̒Z�̂����߂������̏W�w�ꈬ�̍��x�����s�B���ՂȌ��t�œ���̔ߊ삱�������̊����f���ɂ������������Z�̂́A�D���������ĉ̒d�Ɏ����ꐶ���h�Z�̂ƌĂꂽ�B �s�ꈬ�̍��t 20�I�i�J�W�|���I�j 1�D���C�i�Ƃ������j�̏����̈�̔����� ��ꋃ���ʂ�� �I�Ƃ��͂ނ� 2�D���͂ނ�ɕ��w���Ђ� ���̂��܂�y���ɋ����� �O������܂��� 3�D���ɉ�i�ˁj�� �����ӂ��ƂȂ� �킪�z�i�ʂ��j�ɕ����Ē��͋�ɗV�ׂ� 4�D��͂炩�ɐς���� �M�i�فj�Ă�j�ނ邲�Ƃ� �����Ă݂��� 5�D�H�T�i�݂����j�Ɍ��Ȃ��Ȃ��ƙ�i�����сj���� �����^������ �����܂����Ɂ� 6�D�V�����C���N�̂ɂق� ���� �삦���镠�ɟ��ނ����Ȃ��� 7�D�͂��炯�� �͂��炯�ǗP�i�Ȃفj�킪�����i���炵�j�y�ɂȂ炴�� �����Ǝ�����遚 8�D�F���݂Ȃ���肦�炭�������� �ԂЗ��� �ȂƂ������� 9�D�ӂ邳�Ƃ��a�Ȃ��� ��ԏ�i�j�̐l���݂̒��� �����ɂ䂭 10�D�����Ēǂ͂�邲�Ƃ� �ӂ邳�Ƃ��o�i���j�ł����Ȃ��� ����鎞�Ȃ� 11�D���邱���v�ӑ��������Ă݂ނ� ���肵�h���� ���̂ʂ邳���ȁ� 12�D�����Ɩ�}�i�����炵�j�̂��� ��������ᕑ�З����� �т��߂聚 13�D���ɂ����͂Ȃ����ƌ��ւ� ���ꌩ��� ��A���w�i�����j�������������� 14�D�����F�i���т���j�� �Â��蒠�ɂ̂��肽�� ���̉�i���Ђт��j�̎��Ə��i�Ƃ���j���� 15�D���̓��� �����i��Ԃˁj�̂ӂ��ɂ��Ȃ��ڂ� ��邭�����镨�v�Ђ��� 16�D���������d�Ԃ̂Ȃ��ɐ������ꂵ ���̂ЂƗt ��ɂƂ�Č��� 17�D�ق��ڂ��� �����i�����j�獟���i�����j��ɒ��̖� ���̖�ɗ��ēǂގ莆���ȁ� 18�D�邨���� �Ƃߐ��肩�ւ藈�� �����ɂ��Ăӎ�������邩�� 19�D�����H�̋�C�� �O�ڎl���i���₭���ق��j���� �z�ЂĂ킪���̎��ɂ䂫������ 20�D���Ȃ����� �閾����܂ł͎c�肢�� �����ꂵ���̔��̂ʂ����� ��18�`20�͉䂪���ւ̒Ǔ��́B 1911�N�i25�j�A�O�N�ɑ����đ�t�����̌�����ǂ��Ă�����́A�Ǝ��Ɏ�ɓ��ꂽ�ُ�����g�i��ƂƂ����j�K���͌����Ď��獡�x�̂悤�Ȗ��d�������Ă���j�łȂ��h�Ɣ��f���Ă����B���ꂾ���ɁA�퍐26�����A11�����Y�i�����I��ɑS�����߂̍ĐR�����j�Ƃ������ʂɑ傫�ȏՌ�����B���̍��̎��e������̎��W�w�Ďq�ƌ��J�x�ɂȂ����B�ȉ��A��̓��L���B �w1911�N1��18���i���Y�鍐�����̓��L�j �����قǗ\�̓��̍V�����Ă������͂Ȃ������B�������č����قǍV���̌�̔�J�����������͂Ȃ������B�Q�����߂������ł��������낤���B�u2�l���������鐶����v�u���Ƃ͊F���Y���v�u���T24�l�I�v���������������ɓ������B�u�����������Ă��疜�����҂�����܂��v�Ə���N�i�L�ҁj���a�쎁�i�Љ���j�֕��Ă����B�\�͂��̂܁T�����l���Ȃ������B���U�����ƂA���ĐQ�����Ǝv�����B����ł��荏�ɋA�����B�A���Ęb���������̊�ɗ܂��������B�u���{�̓_�����B�v����Ȏ��R�ƍl���Ȃ���ےJ�N��K�˂�10�����܂Řb�����B�[���̈�V���ɂ͍K�����@��Ŕ���������u�����̊�v�Ə����Ă������B�x �w1��24���i������6����j �i�V���j�Ђ֍s���Ă����A�u�������玀�Y������Ă�v�ƕ������B�K���ȉ�11���̂��Ƃł���A���T�A���Ƃ����������Ƃ��낤�B�����F����荇�����B��A�K�������̌o�߂������L�����߂�12���܂œ������B����͌�X�ւ̋L�O�̂��߂ł���B�x �w1��25���i���Y�����j ����̎��Y�����[���n���A���ꂩ�痎���̉Α���̎����V���ɍڂ����B�i���Y���ꂽ�j���R�̒킪�Α���ŋ��Ƃ��ȂĊ���@���������|���̎����������S���Ղ����B���12�l���ɂ��ꂽ�Ƃ����̂̓E�\�ŁA�ǖ�i�K���̍ȁj�͍������ꂽ�̂��B������ɕ��o�N�i���ʕٌ�l�j�ւ���čK���A�ǖ�A��Γ��̍����̎莆���肽�B���o�N�͖��������ɂ��đ傢�ɕ��S���Ă����B�x ��͖����������̎�p��ɔx���j�ǁB�ĂɍȂ��x�J�^���i���ǁj�ɂȂ������ƂŊ��̗ǂ��s�����ΐ�ɓ]���B���̈����z�����������Ă��ꂽ�̂́A�Q�N�O�ɑ�̍Ȃ̖��ƌ������Ă������ق̋`��A�{���J�B�X���A�ȂɁu�N��l�̎ʐ^���B���đ����Ă���v�Ƃ������L���̎莆���͂��A�������J���o�������Ƃ�m������͌��{�B�s��̏؋��Ƃ��čȂɗ�����\���n���A�剶�l�̈�J�ɐ����@���t����B 12���A�������Ɣx���j�������A���M�������B 1912�N�i26�j�A�N�����ɟ����猩�������͂��B�R���ɕꂪ�x���j�ŖS���Ȃ�A�����ɑ���܂��x���j�Ŋ�ĂɊׂ����B�ȉ��̓��L�͎��̖���O�ɏ����ꂽ�Ō�̂��́B �w2��20�� ���L�����Ȃ�������12���ɋy�B���̊Ԏ��͖��������M�̂��߂ɋꂵ�߂��Ă����B39�x�܂ŏオ�����������������B�������Ė���̂ނƊ����o��ׂɁA�̂͂Ђǂ����Ă��܂��āA�����ĕ����ƕG���t���t������B�������Ă���Ԃɂ����̓h���h���Ȃ��Ȃ����B��̖��⎄�̖�オ�����40�K��̊����ł��������B��������o���Ďd���Ē����������Ɖ����Ƃ́A��������ӉƂɒu���������ł܂������ւ��ꂽ�B���̋����s���čȂ̑т������^���Ɉ������B��҂͖̌��������������Ă���Ȃ������B�x ���26�̎Ⴓ�Ŏ��Ɏ���ŔӔN�̗l�q�́A�e�F�̋��c�ꋞ���A��R�q���ɂ���ď����c����Ă���B �s�S���Ȃ�10���O�c���c�ꋞ���t���ꕔ�v�� �ΐ�N�͂��̎��A�w�Ђ���Ƃ����玩�������x�͂��߂��x�ƌ������B�w��҂́H�x�ƕ����ƁA�w�������̂�����A�������Ȃ����A���Ă�����Ȃ��x�Ƃ����B�܂��w�����玩���Ő��������Ǝv�������āA����Ȃł����́x�ƌ����āA�����Ŗ��̘e�������č��̍����������B�����Ɠ˗��������Ղ̎M�B���͊o�����������ɊW������悤�ɂ��āA�w���ꂶ�Ⴂ���Ȃ��A�������A�Ƃɂ����܂��D���Ȃ��̂Ŏ��{�ɂȂ���̂�H�ׂāA��������l�ɂ��Ȃ�����x�ƌ�������A�w�D���Ȃ��̂ǂ��납�I�Ă����c�Ȃ��x�Ɗ��c�߂ď����B�i���c��͏����o�Łw�V����w�x�̒E�e����B����Ɉ����Ԃ��ĉƑ��ɖ{�̎������߁X���鎖��b���A���g�̈ꃖ���̐�����A�\�~�D�������ċ삯�߂��Ă���j�w�ق�̏����ł�����ǁx�Ǝ����A���ނ��Ȃ����������o�������A�ΐ�N���A�ߎq�i�ȁj������A�ق��ĉ��Ƃ�����Ȃ������B�w���^������������x�ƐS�ɋC�����Ȃ����l������ƁA�ΐ�N�͖����Ȃ���A�Ў���o���Ĕq��ł����B�ߎq����́A���������ď�̏�ւۂ���Ɨ܂����Ƃ��Ă����B ���͎��ŋ��������ς��ɂȂ�A�N�Ђ� �蕨�����킸�A���炭�R�l�͖ق肱�����ċ����Ă����̂������B�ΐ�N���ꓙ��Ɍ�����āA�w�����i���a��ŐQ�Ă���ƁA���݂��ݐl�̏���g�ɂ�������x�w�F�����̗F��قNJ��������̂��Ȃ��x�Ƃ����̂Łw���̌���w���E�e�����̂Łi�������������ł͂Ȃ��j�x�Ƙb���ƁA�����̒��q�ł��o�����悤�Ɋ��ł��ꂽ�B �s�O�X���c��R�q���t ���ʑO�X���ɐΐ�N�������ӂƁA�ނ͏�ɑ����Č�����������Ď��Ɍ�����B�w��R�N�A�l�͂܂������閽�����̖������߂Ɏ���E���̂��B�����܂��A�����ɂ������2�A3���f���Ă��邪�A���̖����������������l�͍��������C������̂��A���ɖl�̉Ƃɂ�1�~26�K�̋����������A������������������������ė��錩���͖����Ȃ��Ă���̂��x�ƁB �s�ՏI�L�c��R�q���t �N�����͌��ڂ��ɖ�𒍂����O��G�炷���A�����ĂԂ�炵�Ă��������͂ӂƂ��̏�ɔނ̒����i�U�j�̋��Ȃ��̂ɋC�����āA�T���ɌˊO�ɏo���B�����Ė���ō��̉Ԃ��E���ėV��ł����ޏ�������Ĉ��Ԃ������ɂ́A�V���ƍN�Ƃ��O�ォ��ΐ�N����������ւāA�Ⴂ�Ȃ��琺�����Ăċ����Ă����B�V���͎�������ƁA�����������߂āA�w�����ƂĂ��ʖڂł��B�ՏI�̂悤�ł��x�ƌ������B�����đ��ɂ������u���v����Ɏ���āA�w�X�������x�ƙꂭ�悤�Ɍ������B���v�͐��ɂX��30���ł������B ���O�Ŗ��J�̍����U���Ă����̂ƕ��݂����킹��悤�ɁA�S��13���ɑ�͉ʂĂ��B��̎؋��͑S63�l���瑍�z1372�~50�K�i���݂̖�1400���~�j�ɒB���Ă����B�Q����A�������ő��V���c�܂�A�����Q��B���̓���A�A�Ȃ��������o�Y�B���̂U�����194������߂����̏W�w�߂����ߋ�x�����s����A�e���ʂŌ��܂��ꂽ�B�X���A�ߎq�͈⎙�Q�l����Ă邽�߂ɁA���قɈڂ��Ă������ƂɋA�����B ���O�ɑ�����قŕ�炵���̂͂S�����݂̂����A��قǕ���������C�ɓ����Ă����炵���A�u���ʂƂ��͔��قŁc�v�ƌ���Ă����B���N�̈�������@�ɁA�ߎq�v�l�̊�]�ň⍜�����قɈڂ��ꂽ���A�T���ɂQ�l�̎q���c���ĕv�l��26�ŕa�v�B�⎙�͐ߎq�̕����{�炵���B 1919�N�A�F�l�����̐s�͂ŐV���Ђ���S�W�R�����o�Łi���̌�A�T��ȏ�S�W���o�Ă���j�B1922�N�A�a���ɑS���ŏ��̑�؉̔�w�ӂ邳�Ƃ� �R�Ɍ��Ђ� ���ӂ��ƂȂ� �ӂ邳�Ƃ̎R�� ���肪�������ȁx���������ꂽ�B �v��14�N�ڂ�1926�N�A���َR�̓쓌�[�̒Ìy�C����W�]����f���炵���i�ς̒n�A���ҁi�����܂��j���ɋ{���J���w��؈ꑰ�̕�x�����������B��̑O�ʂɂ́w���C�̏����̈�̔�����/��ꋃ���ʂ��/�I�Ƃ���ނ�x�i�ꈬ�̍��j�̈���荞�܂�Ă���B���̌�A1930�N�ɒ����E���q���}���x���̂���24�ő��E�A������Ɏo�̌��ǂ��悤�Ɏ����E�[�]���x���j�̂���18�ŖS���Ȃ�ȂǁA�ΐ�Ƃ̔ߌ��͑����B���q�͑����������i���q�A�掙�j���������Ă���A����ɑ�̂Б������܂�Ă���B�Б��̖��͐^��i�����j�ł���A����24���ő��E������̒��j�Ɠ������B �s�߂����ߋ�t 30�I�i�J�W�|���I�j 1�D�ċz�i�����j����A ���̒��i�����j�ɂĖ鉹����B �}�i�����炵�j�������т������̉��I 2�D�r���ɂĂӂƋC���ς�A �Ƃߐ���x�݂āA�������A �݂͊����܂�ւ�B 3�D�{�Ђ����A�{�Ђ����ƁA ���Ă��̂���ł͂Ȃ���� �ȂɌ��ЂĂ݂�B 4�D�Ƃ��o�Čܒ�����́A �p�̂���l�̂��Ƃ��� �����Ă݂���ǁ\�\�� 5�D���ƂȂ��A �����͏������A�킪�S���邫���Ƃ��B ��̒܂��B 6�D�r���ɂď抷�̓d�ԂȂ��Ȃ肵�ɁA ���������Ǝv�Ђ��B �J���~��Ă����B 7�D�����Ƃ�� ���̂�����ɂЂ��肽�� �]�̏d�݂������ċA��B 8�D�V���������̗��i�����j���M���Ƃ��� �����̌��t�� �R�͂Ȃ���ǁ\�\�� 9�D�悲�ꂽ�����Ђ����� �������Ȃ閞���� �����̖����Ȃ肫�B�� 10�D���ƂȂ��A ���N�͂悢�����邲�Ƃ��B �����̒��A����ĕ������B�� 11�D�����ۂ�Ɗ��c�����Ԃ�A ���������߁A ����o���Ă݂ʁA�N�ɂƂ��Ȃ��ɁB�� 12�D�S���̑����͎�����߂��Ƃ��ӁB �����ƍ���A ������߂��ށB�� 13�D����܂��Ē��q�����͂��A �������͂��C���̂悳���A �������v�ւ�B�� 14�D�ÐV���I ���₱���ɂ���̉̂̎����܂߂ď����Ă���A ��O�s�Ȃ�ǁB 15�D�ӂɂ��͂ꂴ�肫�\�\ �������Ƒ{�����i�C�t�� ��̒��i�����j�ɂ��肵�ɁB 16�D���̎l�ܔN�A ������Ƃ��ӂ��Ƃ���x���Ȃ��肫�B �������Ȃ���̂��H�� 17�D������݂�A ���̐l���q��������ւ��ƁA �����C�̍ςސS�n�ɂĐQ��B 18�D�w�ΐ�͂ӂт�ȓz���B�x�Ƃ��ɂ��������Ō��ЂāA���Ȃ��݂Ă݂�B 19�D�^�钆�ɂӂƖڂ����߂āA �킯���Ȃ����������Ȃ�āA ���c�����Ԃ��B 20�D�b�������ĕԎ��̂Ȃ��� �悭����A �����Ă����肫�A�ׂ̊��ҁB�� 21�D�Ō�w�̓O�邷��܂ŁA �킪�a�ЁA ��邭�Ȃ�Ƃ��A�Ђ����Ɋ�ւ�B�� 22�D�܂���ӂɎq�����点�āA �܂��܂��Ƃ��̊������A �����Ă䂫�����ȁB�� 23�D����s�i�܂��j�ɂ������̎��Ƃ��āA �F�̌�� ��������ɉR�̌��邩�Ȃ����B 24�D�Ђ����Ԃ�ɁA �ӂƐ����o���ďЂĂ݂ʁ\�\ ���̗���𝆂ނ������ɁB�� 25�D�܍ɂȂ�q�ɁA ���̂Ƃ��Ȃ��A�\�j���Ƃ��ӘI�������i�ȁj�����āA �ĂтĂ͂�낱�ԁB�� 26�D������A�ӂƁA��܂Ђ�Y��A ���̚e�i�ȁj���^�������Ă݂ʁ\�\ �Ȏq�i�܂��j�̗���ɁB 27�D���Ȃ����͉䂪���I �������V����ǂ݂����āA ��ɏ��a�ƗV�ׂ�B 28�D��������A �����āA�Q����ʁB ���������������Q��ɂ��͂�Ă݂邩�ȁB�� 29�D�Ђ�Q�������̖��ӂ� �l�`�З��Ă�����A �ЂƂ�y���ށB 30�D��̂��Ƃ𔒂����䂯��B �ӂ�ނ��āA �������͂ނƍȂɂ͂����B�� |
| �g�k�C��3���ԗ��s�h ���~�x�݂𗘗p���A�����ߖ邽�߁g18�����Ձh�ŏ��郍�[�J���d�Ԃ������g���A��ォ���̖��锟�قɌ��������B�����A����͖��d�������B2���|����Ŕ��ىw�ɂ��ǂ蒅�������ɂ́A�����S�̂悤�ɃR�`�R�`�������B�ǂ�������������悤�ɁA��͂��ɂ���ċu�̏�B�����^�T�C�N�����S�̗��������Ői�܂��A���o��A���O�ő�ɔ���l�B��������ڂɁA�\�����̊ό��q���^�N�V�[��A�˂ĕ�O�ɏ��t�����B�u���A���A���̂�c�v�d�������ʈׁA��ƌ��̂����������ɁA�Ƃ�ڂ�����ő��ɖ߂�B�k�C���̑؍ݎ��ԁA�킸���R���ԁB�ʏ�A�{�B�̐l�ԂɂƂ��Ėk�C�����s�͉������O����呛�������C�x���g�B�l�̏ꍇ�͂܂�Ńg���C�A�X�����������B���ٖ����̊C�N�����[��������i���Ȃ��������ǁA����ł���ɉ���������ŋA��̗�Ԃł͊��ɂ܂��Ă����B |

������b�ɂȂ������c�ꋞ���̕�E�����G�i���J�ɂāi2008�j
���g�c���D/Kenkou Yoshida �O��6�N�i1283�N�j-���a���N/����7�N�i1352�N�j4��8��
�i���s�{�A�E����A���� 69�j1999��2005

�u���D�̑��݂͋�O�ɂ��Đ��v�i���яG�Y�j
 |
 |
 |
| ���D�@�t��Ձi�䂢�����j | ���D�@�t�� | ���M�̏� |
 |
|
| 1999 | 2005 |
 �@ �@ |
| ��͂ƂĂ��`�̗ǂ����R�B���ɂ́u�_��u���ԂƂȂ�т̉��̕ӂɁ@�������̏t���������ށv�̉̔肪������ |
| ���q���㖖���̉̐l�A���M�W�w�k�R���x�̒��҂ł��蓖���̘a�̎l�V����1�l�B�{���m�����D(����ׂ̂��˂悵)�B�O�j�B�Ƃ͑�X�g�c�_�Ђ̐_���߁A�g����ׁh�Ƃ������̒ʂ蒩��ɐ肢�Ŏd���Ă����B���̎���A�c���ł͓V�c�̈ʂ�������2�̌n���i��o��������̓쒩�A�����@������̖k���j�������Ă����B1301�N�A18�̎��ɑ�o�����̌���V�c�����ʂ��A���D�͓V�c�̋@����������舵���g���l�h�Ƃ������E�ɏA�����B�E���͓I�ɂ��Ȃ��A1307�N�i24�j�ɂ́g�]�܈ʍ����q���i���Ђ傤���̂����j�h�܂ňʂ������Ă������A���N�ɓV�c������A�V���������@���̓V�c�̎����ƂȂ����B��o�����̒��ŏo���������D�ɗ₽�����������B�ނ͂��������{����̏o�����[�X�ɋ��������o���n�߁A�Ђ��Ă͐��̑S�Ăɖ���̔O������悤�ɂȂ����B������1313�N�i30�j�A����܂Œz���Ă����L�����A��S���̂Ăďo�Ƃ���B ���ꂩ��́A���k�C�w�@�A�ؑ]�A���q�ȂǂʼnB�������𑗂�a�̎O���̓��X�𑗂����i�t�͓���א��j�B34���납��̐l�Ƃ��Ēm���x��������n�߁w����ڏW�x�w����E��W�x�w����W�x�Ȃǒ����18�I��Ă���B 1331�N�i48�j�A���s�o�P���i�Ȃ�т������j�ɒ�Z�B���N�O���珑�����߂Ă���243�i����Ȃ鐏�M�W�w�k�R���x����������i�������{���J���ꂽ1336�N�Ɋ��������Ƃ�����A���j�B���N�A��ؐ����������B���X�N�ɂ͑���������V�c�`�傪���������q���{������ȂǁA����͓�k���̓����̐��ɓ����Ă����B����A���D�͂���Ȑ��Ԃ̑����͂ǂ��������A�ʐ��E�̏Z�l�̂悤�Ƀq���E�q���E�Ɖ̍��i�������킹�j�ɎQ�����A���Ƃ��畐�Ƃ܂ŕ��L�����ۂ����B 1344�N�i61�j�A�����̒�E���`������R�Ɍo�����[���A���̍ۂɑ����⍂�t���i�����̂���Ȃ��j��Ƌ��ɉ̂��r�B���D�̕��˂ɍ��ꍞ�t���́A�l�Ȃւ̗��������D�ɑ�M���Ă�������Ƃ����B 1346�N�i63�j�A����ƏW�w���D�@�t�W�x�������B�ȉ��A���̏W����3��-- �u����났�̈���Ƃق��Ђ����ɂ����ׂ錎�͉��ɂ��łɂ���v�i��邩�牓���ɕ�����ł��邠�̌��́A�������ɏ�艫�֏o�Ă��܂����悤���j �u�_�̂���ɕʂ���䂭������̊֘H�̉Ԃ̂����ڂ̂̋�v�i����ΎR���̎Q�w�ň���̓����z���Ă���ƁA�邪������ɂ�āA�R�̗䂩�痣��Ă����_��������R���������Ă����j �u�����Ȃт����t���������Ă̓��̂�����ӂ܂܂ɕ������ʂȂ�v�i���ɐ�����đ��t���������ɂȂт��Ă���B�ē����A�蕗���N�������悤���j �ŔӔN�̌��D�ɂ��ẮA1350�N�i67�j�Ɉɉ�̒n�Ŗv�����Ƃ����̂��ʐ����������A�w���Í��W�x�̎ʖ{����Ȃǂ���ɗ��X�N�܂Ŋ��Ă����������������A���Ȃ��Ƃ�1352�N�i69�j�܂Ő����Ă������Ƃ��������Ă���B �v��A����Ɏ���܂ʼn��x���u���D�u�[���v���N�������B����1704�N�i��350����j�ɂ́A��̏ꏊ���ɉꂩ��{�l����]�������s�o�����i�Ȃ�т������j�ɉ������悤�Ƃ����^���ɂ܂Ŏ������B���̎��A���ڂ𗁂т��̂����ꂾ�B �u�_��u���ԂƂȂ�т̉��̕ӂɁ@�������̏t���������ށv�i�����ƈꏏ�ɂ��悤�Ɩ����Ԃƕ���ŋu�̕ӂɁk���o�����̕ӂɁl���N���t���߂��čs���낤�Ȃ��j �������ĕ�͑o�����̒��Ɉڂ��ꂽ�B�����A�ɉꂩ��ł͂Ȃ��A�o�����̃j�̉����[����������ꂽ�Ƃ����������B������ɂ���A�{�l�̊肢�͊����A��̑��ɂ͍��܂ŐA�����ꂽ�B���̍��͐�������d�˂Ȃ�����������A�����t�ɖ��J�̉Ԃ��炩���Ă���B�܂��A���ɂ͖ؑ��̌��D����A���M�Ɠ`���̏W��k�R�����[�߂��Ă���B �w�k�R�Ȃ�܂܂ɁA����炵���i������j�Ɍ������āA�S�ɉf��䂭�R���������@�����͂��ƂȂ���������A����������������������x�i�Ȃ�ƂȂ��Y��Ɉ�����Ɍ������āA�S�ɕ��������Ƃ�Ƃ߂��Ȃ������n�߂���A�܂�ʼn����ɜ߂��ꂽ�悤�ɕM���~�܂�Ȃ��j--���܂�ɗL���Ȃ��̏����Ŏn�܂�k�R���́A�����q�A����L�ƕ���œ��{�O�吏�M�ɂ�������B��700�N���̂ɏ����ꂽ�l�Ԋώ@�L���A���̖l��ɂ��s�b�^���Ɠ��Ă͂܂邱�̖��I����͕�炵���֗��ɂȂ��Ċ��q�����Ƃ͐��������S���Ⴄ�̂ɁA���X�̊�{���y�⎩�R�����łĂ���C���͒����Ƃ܂������ς���Ă��Ȃ��B���D�̃��[���A�͐����o���قNJy�������A���P�b�ɂ͎v�킸�݂��������Ă��܂��B �N���ɒ���֏o�d���A���q���{�A����V�c�A�������{�Ǝ��X���͎҂����ւ���Ă����h�͐�����ڂ̑O�Ō��Ă������D�����A�h�̙R����m��l���̖����M�ō��݂Ȃ�����A�������ĉA�ɘU���邱�ƂȂ��A������Ő゠��A�����̖ʔ����œǂݎ�𖣗����Ă�܂Ȃ��B�]�_�Ƃ̏��яG�Y�́u�k�R���������ꂽ�Ƃ������́A�V�����`���̐��M���w�������ꂽ�Ƃ����悤�Ȏ��ł͂Ȃ��B�����ʼns�q�ȓ_�ŁA��O�̔�]�Ƃ̍����o���������w�j��̑傫�Ȏ����Ȃ̂ł���B�l�͐��Ƃ������������v�Ǝ�����̐�^���B �ǂ�ł���Ɠ����̏K���╗�����ƂĂ��悭������A�a�̖̂���ō������{�������A����ō��́g�m�̕�Ɂh���D���A�㐢�̖l��ׂ̈Ƀ^�C���}�V����p�ӂ��Ă��ꂽ�݂������B �D���Ȓi�Ɍy���G����-- �R���̒��őۂނ��������Ȉ������Ċ��S���Ă���ƁA���ɂ������~�J���̖����d�ɍ�ň͂܂�Ă��邱�ƂɋC�Â���C�ɋ����߂����11�i�A�L���ȎR���ɎQ�w�������m���ӂ��Ƃ̖����������炵�ĎQ�q�����C�ɂȂ�A�R���̖{���ɍs�����ɓ��ӋC�ɋA���Ă�����52�i�A�L���i�����L�j���o��Ɖ\������ɉ̉�Œx���Ȃ��ċA�r�ɂ����m�����A�L���ɏP���č������呛���ɂȂ������A����͎��̎��������m���̑������Ċ������Ĕ�ъ|���������Ƃ�����89�i�A�o�_��K�ꂽ���m���t���܂ɂȂ����R�}����O�Ɂg�������͏o�_���A����͂����Ɛ[���R��������̂��낤�h�Ɨ܂ɂނ���ł��肪�������Ă���ƁA�_�����g�����܂��q�ǂ������Y���������킢�h�ƌ��ɖ߂��ċ����Ă�����236�i�ȂǁA�ߊ삱�������̖ʔ����b�������ς�����B�g����������̂�����ƁA�l�Ԃقǎ������������̂͂Ȃ��B�J�Q���E�͒����܂�ė[�ׂ�҂����Ɏ��ɁA�Z�~�͏t��H��m�炸�ɐ����B���݂��݂ƈ�N���炷�����ł��A���̏�Ȃ��̂ǂ��Ȃ��̂���Ȃ����B�i���j�l�Ԃ͒���������Ɩ��_��ېg�ɑ����ďX�����Ȃ邩��40�܂łɎ��ʂ̂����z�I���h�i��7�i�j�ȂǂǏ����Ă�̂ɁA�����͂��������70�߂��܂Œ������Ă���Ƃ��낪����܂����߂Ȃ��B �Ō�Ɍ��D�����������g�߂ɂȂ�a�̂��Љ�B�����a�̎l�V���̓ڈ��i�Ƃj�ɑ��������̂��B �u��������@�Q�o�߂̉����i����فj�@�薍�i���܂���j���@�^���i�܂��Łj���H�Ɂ@�u�ĂȂ����i���D�j ��͗J���@�˂����䂪�w�q�i�����j�@�ʂĂ͗����@�Ȃق���ɂ��Ɂ@�����ƂЂ܂��i�ڈ��j ���ʂɖ�Ɓu�������邾�B���̈��ł܂ǂ��ł���Ǝ薍�⑳�̊Ԃ������Ă䂭�v�u�h����ł��B�i�܂������Ȃ��͂��ɗ��Ȃ������B�Ȃ�����ł��ǂ�����A�����͖K�˂ĉ������v�ƈꌩ���̂����ɂȂ���ǁA���̉̂ɂ̓g���b�L�[�ȃ��b�Z�[�W������B �u����������/�����߂̂�����/���܂�����/�����ł�������/�����ĂȂ������v �u���������/�������킪����/���Ă͂���/���ق���ɂ���/�����ƂЂ����v ���ꂼ��̕��߂̓��������q����ƁA���D�̏ꍇ�́u��E�ˁE���E�܁E�ցi�ċ���=�Ă��������j�v�ɂȂ�A��납��q����Ɓu���E�ɁE���E�فE���i�K���~���j�v�Ƃ������S�̕��ɂȂ�B�ڈ��̕ԋ傪�܂��y�����u��E�ˁE�́E�ȁE���i�Ă͖����j�v�A�u���E�ɁE���E���E���i�K����=�����Ȃ班���Ȃ�Ƃ��j�v�B 2�l�̗F��ɂ��ݏo�Ă���ǂ��̂��ˁ`�I(*^o^*) �����q��2�x�K��A���l�s�����̏�s�����Ɉ����������Ɠ`�����Ă���B �w�g���͐l�ɂ��ē��ɂ�炸�x�i�g�c���D�j |
������ �m��/Basyo Matuo ���i21�N�i1644�N�j-���\7�N10��12���i1694�N11��28���j �i���ꌧ�A��Îs�A�`���� 50�j1999��2000��02��11
 |
 |
 |
 |
 |
| �^�ӕ����M�u���̍ד������v | �����M�u���̍ד��抪�E�ߐ{��v | �����M�E�m�ԉ� | �[��E�̒����̃��A���� | �������̔m�ԑ� |
 |
  |
 |
| ���V�����E�m�Ԃ̕�O�ň�� �u�t�̓��� �m�Ԃ�K�˂� �O�痢�v �m�ԏ\�N�̈�l�A�u�c�욱�� ��q���욱20����Ɍ����i1999�j |
������͖{��ƂȂ鎠�ꌧ�E�`�����̕�I�g�m�ԉ��h�Ƃ���i2002�j ���ɔm�Ԃ��A����ꏉ�ĂɉԂ��炭���m�Ԃ̊J�Ԃ͂T�N�Ɉ�x |
�E�[���m�ԁB���[�ŗz�ɏƂ炳�� �P���Ă�̂����`�� |
 |
 |
 |
| �����s�̋g�c��n�B150����ɖ�l������ | �����P��11�J���̉䂪�q�Ə���B������}�C���[�i2011�j | �w�ォ��B���Ɍ�����͉̂ԉ����O�r�[�� |
 |
 |
 |
| ���V�����E�~���@�̎R��i2014�j |
���[�u�m�ԉ��v�Ƃ���B�s�������i�ӂ�����E����イ�j ���Č��B�����́u�s����v�͓���̕� |
���E��t���̖�O�Ɂu�m�ԉ��v�̐Δ�B 1793�N�A�m��100����Ō������ꂽ�i2014�j |
 |
 |
 |
| ���s������̏I���V�n��B�������H�̕����� �ɂ���A�݂�ȃr�b�N���B1934�N�����i2014�j |
�u�����ߔm�ԉ��I���V�n�v |
�Δ�͐g���P���[�g�����S�Ɠ����w��i2014�j |
 |
 |
 |
| ������͉��̍ד��ɓ��s��������q�A�͍��\�ǁi����j�̕�B ���쌧�z�K�s�̐��莛�ɖ����Ă���B���ɗǂ����I |
�w�\�ǂ̕�x�̈ē����I �����̋��������Ă��� |
�����ɂ͂Ȃ�Ƒ\�ǂ̓����܂ł������I �i2009�j |
| �{���A�����@�[�i�ނ˂ӂ��j�B�ɉꍑ���i�O�d���j�o�g�A�c������B6�l�Z���̎��j�B�䌴���߁A�ߏ��卶�q��ƕ���ŁA���\3�����ɐ�������i���߂�2�ΔN��A�ߏ���9�ΔN���j�B�����Ƃ͏����m�ҋ��̔_���B12�̎��ɕ��������B18�œ����˂̎��叫�̒��q�E�ǒ��ɗ����l�Ƃ��Ďd����B�������Ղ�ˑc�Ƃ��铡���˂ɂ͕��|���d��˕�����nnn��A�m�Ԃ��ǒ�����o�~�̎�قǂ����ĉr�ݎn�߂��B20�̎��Ɂw���钆�R�W�x��2�傪���W�B22�A�t�Ƌ��ł����ǒ����v���A�߂��݂ƒǕ�̔O����܂��܂��o�~�̐��E�ւ̂߂荞��ł����B�i���s�Ŕo�~�̕���ςƂ��j 1672�N�i28�j�A���̐�W�w�L���قЁx���ɉ�V���{�i���|�E�w��̐_�j�ɕ�[�B�ɉ�o�d�Ŏ��̑�\�i�Ƃ��Ēn�ʂ�z�����m�Ԃ́A�d����ނ��]�˂֏o�āA����ɔo�l�Ƃ��ďC�Ƃ�ςށB31�A���̓��i�Ƃ������j�𖼏��B1677�N�i33�j�A�o�~�t�̖Ƌ��F�`�ƂȂ�A�@���i�������傤�A�t���j�ƂȂ����ނ́A�]�˔o�d�̒��S�n�E���{���ɋ����߂�B�������A�v���̔o�~�t�ɂȂ����Ƃ͂����A�o��̎w�������ł͐������ꂵ���̂ŁA���ƂƂ���4�N�߂��_�c�㐅�̐����H���̎�����S������B �����̔o�d�ł́A���m�̋@�m��₩������������肪���Ă͂₳��Ă����B�������m�Ԃ��ڎw�����̂́A�Î�̒��̎��R�̔���A�����E�m��犿���l�̌Ǎ��A���̋~�ςȂǂ��r�ݍ����E�B�g���h��g�y�����h�����߂�o��ł͂Ȃ��A���R��l���̒T�������ݍ��܂ꂽ�o��B�m�Ԃ͎��g�̎�ŁA�o�~��[���������_�ƌ����������w�ɏ����Ă����B 1680�N�i36�j�A�]�˂̔o�d�ɂ͋��▼���ւ̗~�]�������Ă���A�@�������͒�q�̐��������������ƂɏI�n���Ă����B���̏Ɏ��]�����m�Ԃ́A�]�˂̊X���������āA���c�쓌�݂̐[��ɑ��������щB������B�@���Ԃ̉��l�ςł́A���{�����狎�邱�Ƃ́u�s�k�v�ƌ��Ȃ��ꂽ���A�m�Ԃ̒�q�B�͐[��ւ̈ړ]��傢�Ɋ��}���A�ނ�͈�ۂƂȂ��Ďt�̐������x�������B�����̒�Ƀo�V���E���ꊔ�A�����Ƃ���A�����ȗt�����]���ɂȂ����̂ŁA��q�B�́u�m�Ԉ��v�ƌĂюn�߁A�ގ��g���ȍ~�̍����g�m�ԁi�͂����j�h�Ƃ����B�����̍�����T���w�ԁB �u�m�Ԗ앪����᷁i���炢�j�ɉJ���邩�ȁv�i�m�Ԃ̗t�����Ō������h��A���Ń^���C�̉J�������ł��j 1682�N�A�N���̍]�˂̑�i���S�������̎����j�Ŕm�Ԉ��͑S�Ă������A���N��q�������F�ōČ������B 1684�N�i40�j�A�O�̔N�ɋ����E�ɉ�ŕꂪ���E�������Ƃ��A��Q��𗷂̖ړI�ɁA�ޗǁA���s�A���É��A�ؑ]�ȂǂN�ԏ���B���̗��̋I�s���́A�o�����ɉr�u�살�炵��S�ɕ��̂��ސg���ȁv�̋傩��w�살�炵�I�s�x�ƌĂ��B ���w�살�炵�I�s�x���� �u�살�炵��S�ɕ��̟��ސg���ȁv�g�s���|��č����ӂɎN���o������Ă̗������A���̗₽�����������邱�̐g���Ȃ��h �u�n�ɐQ�Ďc�����������̉��v�g�n��ŃE�g�E�g����������o�߂�ƁA���������ɒ��݂����A���ł͂����𐆂������オ���Ă����h �u�m����Ԃ�@�̏��v�g���炪���x�����Ɛ����J��Ԃ��悤�ɑm�͓��ւ�邪�A���@�͐�N�����鏼�̂悤�ɕς��Ȃ��h �u����̒��ɐ�����������ȁv�g���݂��ɍ��܂ł悭�����Ă������̂��B2�l�̐����̏̂悤�ɁA���J�̍����炫�����Ă����h������E�����̖��J�̍��̉���20�N�Ԃ�ɓ����̋��F�E�����y�F�ƍĉ�����̋�B �u��ɂƂ�Ώ���܂��M���H�̑��v�g��̈┯�͔����������B��Ɏ��ΏH�̑��̂悤�ɔM���܂ŏ����Ă��܂��������h �u���ɂ����ʗ��Q�̉ʂ�H�̕�v�g���ɂ��������̗����I��낤�Ƃ��Ă���B����ȏH�̗[��ꂾ�h ��1686�N�i42�j���̋� �u�Òr��^�i���킸�j�ސ��̉��v�i�w�^���x�j�����̗L���ȋ�͒��M�̒Z�����������Ă���B �u������r���߂���Ė��������v�g�����ɗU���r�̂قƂ���ƕ����A�C���t���Ζ�X���ɂȂ��Ă����h�i�w�Ǐ��x�j �u�����ւΐO���ނ��H�̕��v�i�w�m�Ԉ������Ɂx�j 1688�N�i44�j�A�O�N�̕��ɕ���̕�Q�ňɉ�A�Ȃ��A�N�������č���R�A�g��E���s���A�ޗǁA�_�˕��ʁi�{���E���j�𗷍s�B���̋I�s�́w���i�����j�̏����i���Ԃ݁j�x�ɋL���ꂽ�B �u��t���Č�ڂ̎��@�͂�v�g��t�ŊӐ^�a���̖ӂ������ڂ̗܂�@���Ă������������h�i�w���̏����x�j���ޗǁE�����ŊӐ^�a���������āB���A���̖ؑ��͍���ɂȂ��Ă���B300�N�O�ɔm�Ԃ������������̂��A21���I�̖l����������Ă���c�ȂN���b�Ƃ���B ���N�H�ɂ͒��쌧�Ɍ������A������́w�X�ȁi���炵�ȁj�I�s�x�ƂȂ����B���ɖ������A����ɋ�������X���d�˂Ă䂭�m�ԁB���������[���������Ȃ������B�����y������̂��B�K���ł͓y�n�̒�q���҂��\���Ă��čő���̂��ĂȂ������Ă����B�ߋ��̈̑�Ȏ��l�B�́A����Ȃʂ��ʂ��Ƃ������Ŏ��S����̂ł͂Ȃ��B�����Ǝ��R�ƌ������������N���{���̗������Ȃ��Ắc�B 1689�N3��27���i45�j�A�O�N�͗��s�����ł������̂ɁA�N������S���������n�߂�B�g������_�����ɐ�����ĕY�����i�Ɏ䂩��ė��S��}�����ꂸ�h�g���k�𗷂������Ƃ����v�����S�����������A�����肪���Ȃ���ԁh�g���s�p�̌҈��i�����Ђ��j���C�U���A�}�q����t���ւ��A�������r�ɂ���c�{�ɋ��������Ă���n���h�g�b�ɕ����Ȃ���܂������̓y�n�𗷂��Ė����ɋA�ꂽ�Ȃ玍�l�Ƃ��čō��̍K���Ȃ̂����c�h�B�ނ́u�m�Ԉ��v�蕥���ȂǗ��̎�����P�o���A���t�W��Í��W�Ƃ������ÓT�ɉr�܂ꂽ�̖��i�����j�����炷��ړI�ŁA��q�̑\�ǁi����A5�ΔN���Ŕ��w�j�����ɍ]�˂����B���́w�����̂ق����x�̗��́A���������͎s�i���͊ցj�A�{��A���A�R�`�A�k���n���������ĊE��_�Ɏ���Ƃ����A�s����2400km�A7�����Ԃ̑嗷�s�ƂȂ����B�m�l���w�ǂ��Ȃ����k�n���̒������s�́A�ŏ����瑽��ȍ���\�z����Ă���A�u���H�Ɏ��Ȃ�A����V�̖��Ȃ�v�i���Ƃ����H�̓r���Ŏ���ł��V���ł�������͂Ȃ��j�Ɗo��𐾂��Ă̗������������B -------------------------------------------------------------- ���w�����̂ق����x���疼�偕�G�s�\�[�h�W �u�����͕S��̉ߋq�i���킩���j�ɂ��āA�s�����ӔN���܂����l�Ȃ�v�g�����͉i���̗��l�ł���A�����Ă͗���N���A�܂��������l�ł���h �@  �@�]�ˁ����k���k���������n���ցI�����܂������I �@�]�ˁ����k���k���������n���ցI�����܂������I3��27���]�˂��o���B�u���̌˂��Z�ւ�ゼ�ЂȂ̉Ɓv�g���̔m�Ԉ����傪���邱�ƂɂȂ����B�z���Ă����Ƃ͏���������ƕ����B�E���i�Ȓj���т��炨���l������Ƃɕς��̂��Ȃ��h 4�����{�A�b��i�Ȗ،��ߐ{�S�j�B�u�c�ꖇ�A�ė���������ȁv�g���̐́A���s�@�t���������낵�����̖؉A�ł������S�ɒ^���Ă���ƁA���̊Ԃɂ��c�A�����I����āA�|�c���Ǝ��c����Ă����B�����A���������𗧂����藷�𑱂���Ƃ��悤�h 4��20���A���͂̊ցi�Ȗƕ����̋��j�B�p����ċ����ʂĂ��֏���ʂ��čs���B�g������������Ɨ����i�݂��̂��j���B�́X�A�������i���˂���j���\���@�t���A�݂�Ȃ��̊֏����z���ĉ��B�ɓ������̂��c�h�ƁA������������̉̐l�B�ɐS���d�˂�m�ԁB ���l��ɂ��Ă݂�Δm�Ԏ��g��300�N�O�̐l�Ȃ̂ɁA�ނ��g�̂́c�h�ƁA�����700�N�O�Ɏv����y����̂��A���Ƃ��l�Ԃ̗��j������������B 4�����A�R�i�������S�R�s�j�B�m�Ԃ��h�����镽������̉̐l���������i���˂����A���J���ꂽ�����[���̗��l�j���Ƃɏ������Ƃ����g���݁h�̉Ԃ�T���A�y�n�̐l�ɂǂ̉Ԃ��g���݁h���q�˂邪�A�N���m���Ă���҂����Ȃ��B���n�ɑ����^�ԂȂǁA�u���݁A���݁v�Ɠ�������܂ŒT���ăw�g�w�g�ɂȂ����i���ׂĎ����ւ̓{���̈����痈�Ă���j�B 5��1���A�ђˁi�����E�э�j�B��ςȈ����߂����B�h�̐Q���͓y�̏�Ƀ��V����~���������œ����Ȃ��B�^�钆�Ɍ��������J�ɂȂ�A�J�R��ɔG��Ėڂ��o�߂�B�u�点�����R��A�a�E��ɂ�����ꖰ�炸�A���a�i���Ɂj���ւ�����āA�����������ɂȂ�v�g���m�~�ɐH���܂����A�^�C�~���O���������ɂ܂ŋN�����ŁA�C�����������ɂȂ����h�B 5��2���A�}���i�{�錧����s�j�B�}���i�������܁j�͔m�Ԃ̑�D���Ȑ��s�@�t�����������i�ӂ����̂��˂����j�̕�O�ʼn̂��r�ꏊ�B���Ƃ��Ă��s�������������A�����̕悪����Ƃ��������ւ͑�J�œ����ʂ���ݕ����ɕ����Ȃ��B�̗͂̌��E�ɂȂ���ɕ�Q��f�O�����B�u�}���͂��Â��܌��̂ʂ��蓹�v�g�j�āA�}���͈�̂ǂ��Ȃ̂��c�܌��J�i���݂���j�̓D���łǂ��ɂ��Ȃ炸���O���h�B �������̐l���������i999�N�v�j�͓V�c�̑O�ŏ��Ɠ����s���ƌ��܂�������Ƃ��č��J�A���n���Ĕn�̉��~���ɂȂ莀�S�����B�m�Ԃ͌��c��}�C���[��1�l�B�h�������������T���ɋ{��E�}���̋߂��܂ōs������J�Œf�O�B����500�N�O�ɐ��s�@�t�������̕�O�Łu���������ʂ��̖�����𗯂߂����� �͖�̂����������݂ɂ�����v�i���͂͂�������r��ʂĎ����̖����������̒n�Ɏc��B�͖�ɐ�����X�X�L���܂�Ŏ����̌`���̂悤���j�Ɖr��ł��āA�m�Ԃ͐��sLOVE������A�]�v�Ɍ��n�ɂ��ǂ蒅�����������B���Ȃ݂ɁA�m�Ԃ��v�����Q�N��i1696�j�A��q�̓V�쓍�ׂ��t���̔ߊ���ʂ������ߎ����̕�ɂ��ǂ蒅���A�����r��ł���u�ܗ܂����Ė��݂̂���v�i�ܗ֓��͐܂�ĕ�������̖������y�n�Ɏc���Ă���j 5��7���A�{�錧�����s�B�ޗǎ���̐Δ�����Ċ�������m�ԁB�g�É́i�����j�ɉr�܂ꂽ�����͐��������A���ۂɖK���ƎR�͕���A��̗��ꂪ�ς��A�����ύX����A�͓y���ɖ��܂�A�͘V���Ď�ƌ�サ�Ă���B�����o���Ė����̐Ղ��s�m���Ȃ��̂��肾�B������ɁA���̐Δ�͂܂�������N�O�̋L�O��ł���A���̋�J��������сA�����̗܂����ڂꗎ���������h�B 5��8���A�����i�������܁j�_�ЁB�`�o������ċ��ɐ펀�����a��O�Y�i���B�������̎O�j�j�̊�i�������Ċ�������m�ԁB�g�Гa�O�̐Γ��U�Ɂu�����O�i1187�j�N�A�a��O�Y����[�����v�ƒ����Ă���B�O�Y�͗E�`���F�̎m�B������500�N���O�ɐ����Ă������̐l���̖ʉe���ڂɕ�����ł��āA���͐S��D��ꂽ�h�B 5��9���A���{�O�i�̏����B�h�͓�K���ĂŁA�����ɋ��Ȃ���ɂ��ď�������]���邱�Ƃ��o�����B�g����_�̒��ŗ��Q����悤�Ȃ��̂Ő▭�̐S�n�ł������B���s�̑\�ǂ͋���r���A���͏����̐�i�Ɋ������邠�܂�A�����r�ނ��Ƃ��o���Ȃ������h�B 5��13���A��茧����B�`�o�����Q�����y�n��K�ꂽ�����̐Ղ͑��ނ�Ɖ����Ă����B�g�m��̎��Ɂu���j��ĎR�͂���i���͖ł�ł��R�͂͐̂̂܂܁j�v�Ƃ��邪�A�{���ɂ��̒ʂ肾�B���͊}��u���č������낵�A�����o�̂��Y��āA�����ŋN�����ߌ����v���܂ɕ�ꂽ�h�B�u�đ��╺�i�͂��́j�ǂ������̐Ձv�g���͉đ��������邾���̂��̒n�́A�p�Y�B�����ɏ}�����ՂȂ̂��h�B 5��15���A�A�O�i���Ƃ܂��j�̊֏��B�{��̖q����R�`�ɔ����悤�Ƃ��āA�ő��ɗ��l���ʂ�ʊւ̔Ԑl����s�R�q�����B�悤�₭������ꂽ���̂̎R���œ��v�ƂȂ�A�t�߂̐l���ŏh���肽�B�V�r���3���Ԃ��R�ɕ����߂���n���ɂȂ�B�u�a�l�i�݂̂���݁j�n�̔A�i���Ɓj���閍���Ɓv�g�m�~��V���~�ɐH���邤���A�����ł͔n�����ւ��鉹�܂ŕ�������s��Ȉ�邾�h�B �����A�R�����i�Ȃ�����j�����z���悤�Ƃ������A�h�̎�l�͓����������K�C�h�Ȃ��ł͖��d�Ƃ����B�ē����������͍̂��ɓ��������������Ȏ�ҁB�u���R�X�X�Ƃ��Ĉ꒹���������A�̉��Ŗ荇�ЂĖ�s�����@���v�g�X�͔��Â�������A���̐��ЂƂ����A�铹���s���悤���h�B�m�Ԃ́g�����댯�Ȗڂɑ��������ŐS�z���h�Ɠ��S�r�N�r�N�Ō�ɂ��čs�����B�u���ݕ������ݕ����A����n��A��ɂ܂Â��āA���ɗ₽�����𗬂��āv�悤�₭�ŏ�n���ɏo���B�R�z�����I������ҁg���́A���̓��͂����R�����o�Ėʓ|���N����̂ł����A�����͉������Ȃ��K���ł����h�B�u��ɕ����Ă��ցA���Ƃǂ낭�݂̂Ȃ�v�g��ɕ����Ă����̌ۓ������܂ł����܂�Ȃ������h�B 5��27���A�R�`���E���Ύ��B�u�f���炵���K���̎R���������ł���v�ƒn���̐l�ɋ������A30�L�������������Ԃ��ė��Ύ���K���B�R�[�̏h�ɉׂ�a���A�[���̖{���ɓo��B�y������ÐF�i�����傭�j��тсA�Ȃ߂炩�ȑۂ������Ă���B��̏���オ���Ă悤�₭�{����q�B�u�Ձi�������j�����ɂ��ݓ����̐��v�g�[���ɐÂ܂�Ԃ�Ȃ��A�Z�~�̐���������ɐ��ݓ���悤�ɕ������Ă����h�B 6��3���A�R�`�̐V������M�ōŏ�������B�u�܌��J�i���݂���j�����߂đ����ŏ��v�g�ŏ�삪�܌��J�ő������A���܂����}���ɂȂ��Ă���h�B�r���ʼn��D���ďo�H�O�R�ɓo��A�ĂяM�ʼn�����6�����{�ɍŏ��̉͌��E��c�`�֏o��B�u���������C�ɓ��ꂽ��ŏ��v�g����������ŏ�삪�C�ɗ�������Ă��ꂽ��h�B 6��17���A���̗��̖k�[�ƂȂ�ۊ��i���������A�R�`�ƏH�c�̋��j�ɓ����B���Ă��̒n�ʼn̂��r���s�@�t��\���@�t�ɋC�����d�˂�B�ۊ��͏����╽��ƕ���Ŕm�ԂɂƂ��ė��̃n�C���C�g�ł���A�g���s�@�t�������i�F�������ɗ����Č����Ȃ��c�h�Ɗ����ʂɂȂ����B ���̌�A��c�ɖ߂��Ėk���X���ɓ������i�ΐ쌧�j��ڎw���ĕ���������B���s���l�ɋ���܂ł̋������Ɓu130���i500km�j���炢�ł���v�ƌ����A��u�߂܂��ɏP����B 7��2���A�s�U�i�����Ԃ�j�̊ցi�V���ƕx�R�̋��j�ɓ����B�g�z��i�V���j����9���Ԃ́A������J�ɂ���Ĕ�J���s�[�N�ɒB���L�^�������Ȃ������h�Ɣm�Ԃ͕ٖ��B�u�r�C�⍲�n�ɂ悱���ӓV�́i���܂̂���j�v�g��̍r�C�A�g���̔ޕ��ɍ��X�ƌ����鍲�n�����ɁA�V�̐삪�������|�����Ă���h�B 7��15���A����B�m�Ԃ͓��n�ɏZ�ވ���q�̈�Ƃ̍ĉ���y���݂ɂ��Ă������A�ނ͑O�N�~��36�ő��E���Ă����B�u�˂������킪�������͏H�̕��v�g��擮���Ă���A���̎₵���H���͎��̋��������h�B�m�Ԃ͌��ܜԚL����B 7�����{�A�����_�Ёi�ΐ쌧�����s�j�B��������ɕt�߂̍���œ������ꂽ�V���E�֓������i�ؑ]�`���̉��l�j�̊���O�Ɉ��u�ނ����ȍb�i���ԂƁj�̉��̂��肬�肷�v�B�����肬�肷�͍��̃R�I���M�B 8����{�A�R��������߂���������ő\�ǂ͕��̕a�C�ɂȂ�A�ɐ������̐e�ނ̉Ƃŗ×{���邱�ƂɂȂ����B3�������炸���ƈꏏ�ɗ������Ă����\�ǂ����Ȃ��Ȃ�A�ƂĂ��₵���m�ԁB���������͂܂������B����s�̊O��ɂ���S�����ɔ��܂�A����ɓ���v��𗧂Ă�B���������ׂɓ����~���ƁA�w�ォ��Ⴂ�m���B�����⌥�i������j������āA�K���Œǂ������Ă����B�g�u���ЂƂ������I���ЂƂ��I�v��������Q�ĂĈ����������߂��h�B 8��14���A�։�i���䌧�j�B���̖�̌��͎��ɔ����������B�߂��̐_�Ђ��U������ƁA���̖X�̊Ԃ��猎�����˂����݁A��������ʂɑ���~�����悤�ɋP���Ă����B�h�ɖ߂��āg�����̏\�ܖ���������낤���h�ƒ���ɐq�˂�Ɓg�k���̓V�C�͕ς��₷�����ӂ̂��Ƃ�������ʂ̂ł��h�Ƃ̕Ԏ��B������ ����̗\�z�ʂ�J�~�肾�����B�u������k�����a�i�ق������т��j��߂Ȃ��v�B 8�����A�s���̍ŏI�ړI�n�A��_�ɓ����B�a�C���������\�ǂ��}���Ă��ꂽ�B�g�v���Ԃ�ɉ�e�����l��������������K�˂Ă��āA�܂�Ŏ��������Ԃ������҂̗l�ɁA���̖�������т˂�����Ă��ꂽ�h�B 9��6���A�ɐ��Ɍ������ׂɑ�_���o���B�V���ȗ��̎n�܂肾�B�������Łw�����̂ق����x�͏I����Ă���B�I�s���̃��X�g����M�ɏ�荞�ޔm�Ԃ̌��p�B��������Ȃ�������A�m�Ԃ̐����l���ے������I�������B �@�@  �@�w�����̂ق����x �@�w�����̂ق����x---------------------------------------------- ���ӔN �w�����̂ق����x�̗��̓r���ŁA�m�Ԃ̒��Ɂu�s�Ձi�ӂ����j���s�v�Ƃ����o�~�_�����܂��B�ڕW�Ƃ��ׂ����z�̋�́A����Ƌ��ɕω����闬�s�i�������j���܂݂Ȃ�����A�i�����������S�i���Ր��j��������Ă�����́A�Ƃ����B 1691�N�i47�j�A���k�ւ̗��̌�́A���炭��q�E���������s�E����ɍ\����ʑ��u���o�Ɂi�炭������j�v�ƁA�m�Ԃ���������������̕����E�ؑ]�`���̕悪���鎠���ÁE�`�����̈��Ɍ��݂ɏZ�B���̍��A�w������L�x���L���B48�A�]�˂֖߂�B 1693�N�i49�j�A�]�˂ɖ߂����m�Ԃ�҂��Ă����̂́A�g���Ћ��Ɍ�o�Ȃ��h�g�����̐R�������h�g���̉̂̏o���͂ǂ��ł��傤���h�A����ȗ��q�̗��������B�ߖ��X�P�W���[���ɐS�g�����ʂĂ��ނ́A��˂Ɂu���q�Ӑ�v�Ɠ\����1�����Ԃ��ׂĂ̌𗬂�f�����B�����ĐV���Ɂu�y�݁v�̋��n�Ɏ����˂��J���B�u�y�݁v�Ƃ́g���h���̂ĂĎ��R�ɐg���ς˂邱�ƁB���̗͂����R�ȋ��n�Ŏ��R��l�ԂɂЂ傤�Ђ傤�Ɛڂ��Ă����B�ς̈�ɁA�m�Ԃ͕����������B �����̍��̋� �u�H�߂��S�̊���l�����v�g�₵���ȏH�̋C�z���Y���ƁA�l�����Ō���Ă��邤���Ɍ݂��̐S������݂����Ă䂭�h�i�w���̓��x�j �u�~�����ɂ̂Ɠ��̏o��R�H���ȁv�g���t�̖閾���O�A�~������R�H�̐�ɑ傫�ȐԂ��������̂����Ə���͂��߂��h�i�w�Y�U�x�j 1694�N�A�o�~�I�s���w�����̂ق����x�������B�����400���l�ߌ��e�p��50�����炸�ł��邪�A�m�Ԃ͗���ɗ�����3�N������Ō��e���܂Ƃ߁A2�N�������Đ������s�Ȃ��A���̔N�̏��Ăɂ悤�₭�`�ɂȂ����B5���A�]�˂��o�����Đ����̒�q�B�ցu�y�݁v��`�����闷�ɏo�邪�A4������ɑ��ŕa�ɕ����A�䓰�̗��h�E�ԉ��m���q����ɂāA10��12���ߌ�4���ɉi�������B���N50�B�a��������A�m�Ԃ͏��߂ċ�B�̒n�֑����������肾�����B �⌾�́u����ؑ]�`�����̑��ɑ����ė~�����v�B���̌��t�ɏ]���āA�v������ɒ�q10���i�����A���p���j���S�[���M�ɏ悹�A���������ė����ɋ`�����ɓ����B14����ɖ��80�l������钆�A�`���̕�ׂ̗ɖ������ꂽ�B�┯�͋��F�E�����y�F�̎�Ō̋��̈ɉ�ɓ͂����A�����Ƃ̕�E�����@�ɑ���ꂽ�u�̋��ˁv�ɔ[�߂���B�m�Ԗv��8�N�ڂ�1702�N�A�w�����̂ق����x�����s���ꂽ�B �m�Ԃ̊����́u�������ꉎ���������ق����Ȃ�v�̋�ɂ��Ȃ݁g���J�i������j���h�ƌĂ�A���N11���̑�2�y�j���ɖ@�v���c�܂�Ă���B�܂��A���s������v���Y��4���ڕt�߂Ɂg�m�ԏI���̒n�h�̐Δ肪����B �m�Ԃ����U�ɉr��͖�900��B�I�s���͂��ׂĎ���Ɋ��s���ꂽ�B�g�̂сE���сE�ׂ݁h�̐��_�A�g���ЁE����E�����h�Ƃ������k�o�E���o�E���o����g�������͕\���A�����āu�s���s�v�u�y�݁v�B���̔m�Ԃ̊����͑����̔o�l�𗸂ɂ��A�������w�o���x�ƌĂ��悤�ɂȂ����B �Ŋ��̋�͎���4���O�́u���ɕa��Ŗ��͖͌��������i�߂��j��v�g����Ŏ��̏��ɕ����Ȃ���A���͂Ȃ������̒��Ō��m��ʌ͖���삯����Ă���h�B�m�Ԃ��h�炵�Ă�܂Ȃ��̑�Ȑ�l�����A���s�A�����A�m���Ɠ��l�ɁA�ނ����̓r���ʼnʂĂ��̂������B �����O�Ɋ��s���ꂽ�m�Ԉ��̐�W��6���̉̑I�W�̂݁B�w�~�̓��x�i1684�j�c�ԕ����m���A�w�t�̓��x�i1686�j�c�u�~�̓��v�̑��ҁA�w������x�i1689�j�c���т̋�A�w�Ђ����x�i1690�j���A���ȕ`�ʁA�w�����x�i1691�j�c�m�ԔӔN�̔o�_�f�A�w�Y�U�x�i1694�j�c�y�����B���N�m�Ԗv�B����́w�������x�i1698�j�����āg�o�~�����W�h�ƌĂ��B ���m�ԔE�ҁi�B���j���c�ɉ�̗��̏o�g�҂ł���A�������x���ٗl�ɑ����A�w�����̂ق����x�̓��e�ɕs���R�ȓ_�����邱�Ƃ���A�ɒB���̐��˂̓����ׂ�C�����Ă����̂ł͂ƈꕔ�Ŏw�E����Ă���B�o���O�́u�����̌����y���݁v�ƌ����Ă���̂ɁA���������ɒ����ƈ����r�܂��Ɉꔑ�őf�ʂ肵�A�Ȃ����{���ł�7���A���H�ł�13�������Ă���B���������]�˂��o�鎞����A���s�l�̑\�ǂ̓��L�u3��20���o���v�ƁA�m�Ԃ́u27���o���v�ŃY���Ă���B�����������҂̋L�^�Ⴂ�͖�80����������Ƃ����B�m�Ԃ̔C�������˂̏����W�ł���Β����̘A���������ł���B���������͎��ɑ���Ȃ����Ƃ��B�B�����낤�Ɖ����낤�ƁA�ނ��r����͖{�����B ���m�Ԃ͖��̓m���i�Ƃ����j���g�S���g�̂��h�����Ă����B�m�Ԃ͔ނ�c���̂܂܁u���e�ہv�ƌĂё����A�u������Ǔ�l�Q��邼���̂������v�Ǝc���A2�l�ňɐ�����g��܂ʼnԌ��ɂ��s�����B���̎v���́w�����̂ق����x��̔ӔN�܂ŕς�炸�A���e�ۂƉ�Ȃ����������ƁA�w������L�x�Ɂu���̒��œm�����v���o���A�܂Ŗڂ����߂��v�ƁA�Z���`�ȑz����Ԃ��Ă���B ���v��A�剺����́A�����ȑ��p�A���Z�h�̎x�l�������A�ɐ��h�̗��p�i��傤�Ɓj�≳�R�i���䂤�j�ȂǑ����̔o�l���ł��B �����܂��܂̂��Ƃ��v���o�������ȁi�m�ԁj ���m�ԑ��͑�ʂɂ���I
���������͎s�E���͊ւ̐X�����i�\�ǂ�����j
�{�錧�Ί��s�E���a�R�����i�\�ǂ�����j �O�d�����s�E�ߓS���s�w�O
�O�d���ɉ꒬�E����O
�]����E�m�Ԉ��j�ՓW�]�뉀�i���c��̉͊݁j �]����[��E�̒����� �����拽�y������
���ꌧ��Îs�E����ΎR�w�O �O�d���Îs�E�۔V�����X�X�i���j�U�����j �Ȗ،����H���E�m�Ԃ̗��i�������n�㑜�j
�R�`���E�R���i�\�ǂ�����j
��茧����E���������F���A���̑��܂��܂������ς�����I
���`�����̋����ɂ͒�q�̖����i�䂤����j�ɂ���āu�ؑ\�a�Ɣw�������̊������ȁv�ƍ��܂ꂽ��肪���B�`�����߂��̗��P�u�o�l�˂ɂ͏Ԗ�\�N��1�l�����䑐��o�l17�l�̕悪����B�m�Ԃ̕�͎��ꌧ��Îs�̋`�����A�O�d���ɉ�s�̈����@�̑��A��ゾ���łU�J������I �ȉ����R�`���̃T�C�g�̏��B
��t���F���s�V������[�z�u���c1793�N�A�m��100����Ŗ�O�Ɍ����B�����ɂ͓c�\���|�c�A���c�����ȂǕ����l����������B �~���@�F���s�V������[�z�u���c�s�������������B����̕������B�����́u�m�ԓ��v�͓�����~���@����ڂ����B��t���̑O�B �~���@�F���s�V�����扺�����Q���ځc�m�ԏ\�N�̎u���욱��1734�N�����B1783�N�A�s���������Č��B1694�N�̔m�ԍŌ�̗��œ����K��B �l�V�����F���s�V������l�V�����P���ځc1761�N�A�u���욱�̖�l�E�Δ������_���ɖ욱20����Ō����B�ׂ�ɖ욱�̕�B �S��F���s�Q���挳���P���ځc�����ɂ͐������B�m�ԂƏ\�N�E�i��䑴�p�j�̔�B �g�c��n�F�����s�g�c�S���ځc1843�N�A�m��150����ɖ�l�������������ۂ��B��n�O�ɉԉ����O�r�[��B �m�Ԋ֘A�̂��E�ߎ����E�S�T�C�g3�I�� http://www.asahi-net.or.jp/~ee4y-nsn/oku/aaipi01.htm�@�m�Ԃ̓�������W�� http://www.bashouan.com/index.htm�@�m�Ԉ��h�b�g�R�� http://www.ict.ne.jp/~basho/works/reference.html�@�m�Ԃ̔o��E�����V�X�e�� http://www.ese.yamanashi.ac.jp/~itoyo/basho/haikusyu/Default.htm�@�m�Ԕo��S�W http://www.intweb.co.jp/basyou/naruko_hagurosan.htm�@�A�O�̊ցA�R�������ȂǏ[���摜
|
���`�{ �l���C/Hitomaro Kakinomotono ���v�N�s��660�H-710�H723�H �i�ޗnj��A�V���s�A�a玉��_�� 50�H�j2001
 �@ �@ |
| ��̂������ɃQ�[�g�{�[���ꂪ����A������オ���Ă����B���́u�̒ˁv�̉��ɐl���C�̈┯�����߂��Ă���Ƃ��� |
���������̌˓c���l�ɐl���C�̐��a�n��K�˂�
 |
 |
 |
| 17��14�������B�S�Ȃ����₵�������\ | ���l�w�̉w�ɂׂ̗ɐl���C���a�n�̔� | �����Ȑ��a�n�͂����ƎR���ɂ���B�Ђ�����^���������� |
 |
 �@ �@ |
| �������{���̐��a�n | �Ȃ�ƁA���a�n�ɂ��┯�˂��I��}�C���[�ɂ͊������V���� |
 |
 |
 |
| �揊����O��������B�������̎R���Ɋ`�{�_�Ђ����� |
�l���C���J�����˓c�`�{�_�� |
��N�O�̒n�k�ʼn������̓������Ƃ��� �i���̓��ɃI���W�i���̕悪�������j |
 |
| �������܂����̂͂��́u�l�ےˁv�B���s�p�����̐V�I�g�̕揊���ɂ������I �Ȃ��H�ǂ������o�܂ł����ɁI�H�l���C�̊D�˂Ȃ��āI�i2008�j ���u�l���C�v���u�l�ہv���u�Ύ~�܂�v�ʼnΏ����̂����v������炵�� |
| �`�{���b�i�����݁j�l���C�B���t�W���̉̐l�Łu�̐��v�Ə̂����A�������i686-702�j�E�������i697-707�j�̂��ƂŊ�������̋{��̐l�B�O�\�Z�̐�̈�l�ŁA���t�W�ɂ͒���19��E�Z��60�]��A�v80��ȏオ���߂��Ă���B�ŏ��ɋL�ڂ��ꂽ�u���Ǎc�q�҉́v���r�܂ꂽ689�N�����10�N�Ԃɍł������B�o���n�͋ߍ]�A�Ό��A��a�E�V�����`�{�ȂǏ�������B �l���C�̐g���ɂ��ẮA�Õ����i���j�j�Ɋ��ʂ̋L�ڂ��Ȃ����Ƃ��牺����l�Ƃ�����i5�ʈȏ�Ȃ�L�^�A���j�ƁA�c�q��c���̒Ǔ����T�Ō̐l���̂���u�҉́v���r�ނȂǁA���̏�ōc���Ɋւ���̂��r�ނ��Ƃ�������Ă��鎖���獂�������������Ƃ�����ɕ�����Ă���B 690�N�ɓV�c�̍s�K�ɏ]���ċg���K�ꂽ�ق��A702�N�ɋI�ɂ֓����Ă���B�̂ʼnr�܂ꂽ�n������A�ނ��{��Ƌ�����u����708�N�ȍ~�Ɏl���i�]��j�E��B�i�}���j�A�ߍ]�A�����A�R��ւƗ��������悤���B ��2�l�̏��� �l���C�̉̂ɐG���ƁA�^�������ɐl��������́A�l�̎��ɑ��鋹����������̔߂��݁A�����������l�Ԃ̃G�l���M�[�Ɉ��|�����B �ނ̍Ȃ͎����V�c�Ɏd���銯���ŁA�E�y�̗��i�ޗnj������s�j�ɏZ��ł����B�傫�ȕǂ����z���Č������Ă���A2�l�͐[�����������Ă����B�������A�Ȃ͕a�ɓ|��v�Ǝq���c���旧�B���t�W�ɂ͐l���C���u�������ԁi���イ�������ǂ��j�����v�Ƃ���B���̗܂��o��قNj������̂��B �l���C�͍Ȃ̎����g���̎҂���m�炳�ꂽ���̂��Ƃ������L���B�u���͑ł��Ђ�����A�������A�番�̈�ł��߂��݂�����邱�Ƃ����낤���ƁA�Ȃ����������^��ł����s��ɏo�����āA���܂��Ă݂��B�������A�Ȃ̐��ǂ��납�A�R���̐��������������A���s���l�ɂ��ȂƎ����l�ȂLj�l�����Ȃ��B�����ׂ��p���Ȃ��A�����J��Ԃ��Ȃ̖����ĂсA�Ђ�����ɑ���U�葱���邵���Ȃ������v�B �u�Ȃ��`���Ɉ₵���c�Ȏq���A������~�������ċ������тɁA�^������̂��Ȃ��A�q��e�ɕ����āA���͐S�₵���߂����A��͂��ߑ������������A������Q���Ǘ��ł���Ă��������@���Ȃ��A��R�ɗ������l�̍����߂�Ɛl�ɋ������āA��ݕ����ēo�������A�Ȃ̎p�͉e���猩���Ȃ������v�B �ȉ��A�l���C���Ȃ�z���ĉr�̂��Љ�B���t�W�ɏo�Ă���u���v�i�����j�͍Ȃ���l���������t���B �w�H�R�́@���t�i���݂��j��݁@�f�Ђʂ�@���i�����j�����߂ށ@�R���i��܂��j�m�炸���x �i�H�̎R�ɍg�t�����܂�ɔɂ��Ă���̂ŁA��������ł��܂����Ȃ�{�����߂悤�Ƃ��Ă��A���ɂ͂��̓���������Ȃ��j �����t�̎���A���҂̗�͎R�Ő�������ƍl�����Ă����B�l���C�͗���������ޏ��̌̋��̗��R�ɓ����āA���̐Ȃ����������̂��r�B �w���t�́@�U��䂭�ȂւɁ@�ʈ��i���܂Â��j�́@�g������@���Ђ����v�ق�x �i�g�t���U��G�߂ɂȂ�ƁA���̎g��������ɂ��A�Ȃƈ����������v���o����j �w���N�i�����j���Ă��@�H�̌���́@�Ƃ点��ǁ@���������́@����N���i�����j��x �i���N�Ɍ����H�̌��́A�����ς�炸�Ƃ炵�Ă��邪�A�ꏏ�ɒ��߂��Ȃ͉��������Ă��܂����j �w�W�H�́@�쓇�̍�́@�l���Ɂ@�������т��@�R�����Ԃ��x �i�W�H���k�[�̖������a���v���A�������̎��ɍȂ�����ł��ꂽ�㒅�̕R��l���ɐ����C���Ă����j �w�Ė�s���@�����̊p�́@���̊Ԃ��@�����S���@�Y��Ďv�ւ�x �i�Ă̖���s�����́A�����ւ�����p�قǒZ���ꎞ�ł��A�������čȂ̐^�S�����͖Y��Ȃ��j ��N�̐l���C�́A�����̍��i�i�n�����j�Ƃ��ĐΌ��i����݁j���i�������j�ɕ��C����B����́A�P�Ȃ�l���ٓ��ł͂Ȃ��A���炩�̒����l���Ƃ��ēs���獶�J���ꂽ�Ƃ݂���������B�₩�ȋ{�삩�牓������Q���Ă������A�₪�Ĕނ͂��̐V�V�n�ŐS���爤���邱�Ƃ��ł��鏗���Ə����č����Ă���B�l���C�͓s�֏o���Ō��������ɁA�����̕ʂ�i�Г�29���j��Q���Ď��̉̂��r�B �w�i���j���̓��́@���\�G�i�₻���܁j���ƂɁ@���i��낸�j���с@���ւ�݂���ǁ@���⍂�Ɂ@���͕���ʁ@���⍂�Ɂ@�R���z�����ʁ@�đ��́@�v�Јނ��ĎÂӂ�ށ@�����匩�ށ@�r�i�Ȃсj�����̎R�x �i�s�Ɍ������r��ŁA�Ȃ���p���Ƃɉ��x���U��Ԃ��Ă��܂��c���ɉ��������͗���A�R���z���Ă��܂����B������Ȃ͉đ��̂悤�ɂ�����Ă��邾�낤�B�Ȃ̂���䂪�Ƃ��������̂ŁA�ǂ����R�扡�ɕ��ɂȂ��ė~�����j �w�Ό��̂�@���p�R�́@�̍ہi�܁j���@�킪�U�鑳���@������ނ��x�@�@ �i�Ȃ��Z�ސΌ��̍��p�R�̖̊Ԃ���A��������U���Ă����̂�ޏ��͌��Ă��ꂽ�̂��Ȃ��j ����̎� �l���C�͓ޗNJ��̍�i����������Ȃ����Ƃ���A���鋞�ւ̑J�s�O��ɑ��E�����ƌ����Ă���B�����͏�������A�s���̎��̎��A�u�a���i�֓��g�j�A�����V�c�ւ̏}���A�Y���i�~���ҁj�ȂǗl�X���B���̗l�ɐ����������̂́A���t�W�ɋL���ꂽ�u�l���C�����ɗՂ�Ŏ��珝�i�����j�݂ĉr�v�����̂�A�ȁ��F�l�ɂ��Ǔ��̂����₩�łȂ����炾�B�l���C�̍Ō�͈̉̂ȉ��̂��́B �w���R�i������܁j�́@�⍪�i���͂ˁj�����i�܁j����@��������@�m��ɂƖ����@�҂������ށx �i���R�̊�Ɏ��ɂ��鎄���A�Ȃ͍����뉽���m�炸�ɑ҂���тĂ���̂��낤���j �����čȂ̈˗����q�i�悳�݂̂��Ƃ߁j���A�l���C�̎��ꏊ�ɋ삯���ĉr�̂������B �w�����i���Ӂj�����Ɓ@�킪�҂N�́@�Ό��Ái����݂Áj�́@�L�Ɍ�����ā@����Ƃ��͂�����x�@�@ �i�������������Ƃ��A���҂��Ă������Ȃ��́A�Ό��Ái�l�c��̉͌��j�̊L�ɍ������Ă���Ƃ����ł͂���܂��j ����ɁA�l���C�̗F�l������̔ނ̐S���ق����r�̂��o�Ă���B �w�r�g�Ɂ@��藈��ʂ��@���ɒu���@�䂱���ɂ���Ɓ@�N���������ށx �i�r�g�ɑł�������A���ɂ������������ɂ��鎖���A�N���Ȃɒm�点�Ă��ꂽ�̂��낤�j �ǂ���ُ�ȓ��e���B�ȂƗF�l�́A�l���C�̖S�[������ɒ��݊L�ɍ������Ă���ƒQ���Ă���B�~���҂͐l���C�̍Ō�̉̂��u�����́v�ƌĂ�Ă��邱�Ƃɒ��ڂ����B���t�W�ő��Ɂu�����́v���r�l�́A���t�߂ŌY�������L�ԍc�q�����ł���A�l���C�����炩�̐����Ɋ������܂�Ď��r���A�Ό����ɔz������A�ŏI�I�ɐ����Y�ɏ�����ꂽ�Ɛ�������Ă���B �u�̐��v�l���C�͑��E��ɐ_�ƂȂ����B�������v�c�s�́u�`�{�_�Ёv�͑n����724�N�Ƃ�������A������������ނ��_�i�����ꂽ���Ƃ��f����B�l���C�������ʼnr�u���R�v�́A�v�c�s�̍��É��ɂ������u�����v�̂��ƁB���̓��͐l���C�̎��̖�300�N��i1026�N�j�ɑ�n�k���Ôg�Ő��v���A���͑��݂��Ȃ��B �ޗǁE�V���s�J�{�i�����̂��Ɓj�B�a玉��i��ɂ����j�_�Ђ̐��ɃQ�[�g�{�[���ꂪ����A�~�n�̉��Ɏ��Ɉ͂܂ꂽ�l���C�̕�E�̒˂����B���̒n�͐l���C�̐��n�Ɠ`�����A���Ă͓ޗǎ���ɑn�����ꂽ�u�����R�`�{���v�����������A�������N�̔p���ʎ߂̋]���ɂȂ��āA���݂͋����̐l���C����c���݂̂ƂȂ����B���̕�ɂ͕��C��̐Ό�������A�Ȃ��l���C�̈┯�������A���Ė��������Ƃ����i�⌾�Ō̋��ւ̖�������]�����炵���j�B���݂̔��1732�N�̂��̂ŁA�\�ʂ́u�̒ˁv�̓��́A��111��E�㐼�V�c�̍c���E��̕M�ɂ��B �l���C��̓`���n�͑����A�ޗǂł͐V�����̊`�{�_�ЁA��a���c�s�����`�A�g��S�g�쒬�Ȃǂɕ揊������A�����ɂ��┯�˂�����B ���̐l�Ƃ��Ă̐l���C �l���C�������������́A���T�Ƌ��ɕ����������ė��ĕS�N���o���A�̂���������L�ڂ֓]�����n�߂��v�V�̎���B�l���C�̉̕��́A�����⏘���A������݂Ɋ��p�����i���������́B�ނ�140�킠�܂�̖�������g�������A�����̔����͐l���C���n���������̂Ƃ���Ă���B���������������������ׂ͐l�X�̐S��k�킹�A�w�Í��a�̏W�x�ł́u�̐��v�Ǝ]����ꂽ�B�C��������I�ɐi�������A������������グ�A���́i���傤���j�̊����҂ƌĂ�Ă���B�����́c5��7���ł����ƌJ��Ԃ���ԍŌ��5�E7�E7�Ō��ԉ́B �l���C�͏]���̘a�̂��y���ɋK�͂̑傫�Ȓ��̂�����A5�E7�̒�^���m�����A������5�E7�E7�ɓ��ꂵ���B���̂ƃZ�b�g�ɂȂ������̂ɂ͕����̒Z�̂��������̂������A���̂̓��e������ɖc��܂���\���ɂȂ��Ă���B �Ñ�̒���ł́A���V�Ɣ҉́i�Ǔ��̒��́j�͕s���������B�{��̐l�̐l���C���܂��A�V���ׂ̈ɍ�̂������A����܂ł̉̐l�ƈقȂ�A�P�Ȃ�V��⊵�K�������E�ɂ���A�i�}�̊����L���ɉ̂��グ���B�����ɐl���C�́A���̗���ʼn̂������̂ł͂Ȃ��A��l�̐l�ԂƂ��Ĉ�����҂��������ԚL���A�������c���Ă���B �w���t�W�x�̒���265��̂����ŒZ��7��B��ʂɂ͏\���傩���\���傾�B�������A�l���C��149��Ƃ�����O���́w�q�{(�Ђイ)�҉́x�i���t�W��2���j����̂��Ă���A����͎��ʋ��ɑ������|�����g�a�̂̃G�x���X�g�h�ƌĂ�Ă���B�w�q�{�҉́x�ŒǓ����ꂽ�̂́A696�N��42�ő��E�����V���V�c�̍c�q�A���s�c�q�B�c�q�͐p�\�̗��Ő퓬�̑��w�����Ƃ��đ劈�����Ƃ���A�l���C�͖���������`�ʂ�҉̂ɉr�ݍ��B�ȉ��A���̈ꕔ���B�����̂Ƃ͑S���ʎ�́A�l���C�̍r�Ԃ�C�����������y�Ă���B �w�c��R�m���@���Ђ��܂Ё@���ӂ�@�ۂ̉��́@���́@���ƕ����܂Ł@��������@���p�̉����@�G������@�Ղ�����Ɓ@���l�́@���т��܂łɁ@����������@�����r���́@�~������@�t���藈��@�삲�ƂɁ@���Ă���́@���̋��@�r�������Ƃ��@��莝�Ă�@�|�X�̑����@�ݐ�~��@�~�̗тɁ@�ނ������@�������n��Ɓ@�v�ӂ܂Ł@�����̈��@�������@��̔ɂ����@���́@����ė���@�܂�͂��@�������Ђ����@�I���́@���ȂΏ��ʂׂ��c�x �i�R�����シ��w���ۂ̉��͗��ƕ����܂�������A�����炷�p�J�̉����A�r�ꋶ���Ղ��Ⴆ��Ă��邩�ƒN����������قǂŁA�R�����Ȃт��l�q�́A�t�̖�����ɐ�����ĂɂȂт��悤�ŁA�|��̉��͐�тɗ������������Ǝv���قNj��낵���A���������ꂽ�����̖�́A��Ⴊ����~��悤�ŁA������R���Ă����҂ǂ��́A�����̔@�������s���悤�Ɏv���A�]�X�j ���Ō�Ɂc���I3�� �w�����т��́@�R���̔��́@��������́@�Ȃ��Ȃ�������@�ЂƂ肩���Q�ށx �i�R���̒������ꂽ���̂悤�ɒ������̖���A���͓Ƃ肳�т����Q��̂��낤�j ���L���Ȃ��̉̂́w���q�S�l���x�Ől���C�̍�ƂȂ��Ă邪�A�w���t�W�x�i11���j�ł͍�Җ��ڂɂȂ��Ă���B �w�V�i���܁j�̊C�Ɂ@�_�̔g�����@���̏M�@���̗тɁ@�����B�錩��x �i�Y��ȓV�̊C�ɉ_�̔��g�������A���̏M�����X�̗тɑ��������Ă����̂��������j ���l���C�̏W����B���̉̏W�͖�360��Ȃ邪�A�l���C���������ďW�߂Ă����̂������悤���B �w���i�Ђނ����j�́@��ɉ��i�����낢�j�́@�������ā@���ւ茩����@���X���ʁx �i���̖쌴�ɔR���钩�z������n�߁A�U��Ԃ��Đ��̋������Ǝc�������݂������j |
���I �єV/Turayuki Kino 872�i868�H�j-945.5.18 �i���ꌧ�A��Îs�A�֗��R 73�j2002��12
�����N��866�N���Ƃ������A��
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
 |
 |
 |
| ��Ɍ�������������B�ቺ�ɂ͗Y��Ȕ��i���I |
�@�������I���ɖ������I�R���ЂƂԈႦ�A�ʐ^�� ���Ɍ����鎛����߂��ė���͂߂ɁB�q�[�b�I |
�u���������Ă��Ȃ��c�v�ق�� �ɂ��̃P���m�����s���̂��H |
 |
 |
 |
| ��A����Ɖ���B�Ȃイ�R���I�i2002�j | 2012�N�ɍĖK�B�ē������܂�Ă���c | �u�I�єV���b�V���v�Ƃ��� |
| �����O���̉̐l�E���M�ƁB�O�\�Z�̐��1�l�B�c���͈��Ëv�]�B�c�����ɉ̐l�̕��������B�I�i���́j���ꑰ�͌��X�a�̎R�����_�ɉh���������B�Ⴂ�����犿���w�⏑���悭���A�{���ŏُ��i�V�c�̕��́j�̋N����S��������A900�N�i32�j�ɋ{��̏��Ђ��i��u�䏑���a�i�݂ӂǂ���̂�������j�v�ɏA�C�B20��O�����牽�x���̍��i�������킹�j�ɉ�����ċ{��̒d�Œ��ڂ��W�߂Ă������Ƃ���A905�N�ɑ��V�c�����{���̒���a�̏W�w�Í��a�̏W�x�S20���̐�������߂����ɁA4�l�̐�҂�1�l�ɑI�ꂽ�i��҂̒��ł͍ŔN��37�j�B �w�Í��W�x�̑I���Ƃ��n�܂��ĊԂ��Ȃ��A�N���ŕM����҂������]�Z�̋I�F�������E���A���̌�͎��̐l�̃��[�_�[�i�������єV���I��̒��S�ƂȂ����B�єV�͂܂��\�Ȍ���É̂�e�ƏW�����W���A���ɂ��ꂼ��̉̂��l�G�E���E�G�Ȃǂɕ��ށA���̂���ׂĂ������B���̕��@�͌㐢�̘a�̏W����̋K�͂ƂȂ�B�єV�́w�Í��W�x�̖`���ɕ��w�j��ŏ��̘̉_�w�������x�����M�B�єV�́w�Í��W�x�ɍő�99���߂炽�̐l�Ƃ��Ė�����z���A�܂����w�҂Ƃ��Ă��s���̒n�ʂ���ɓ��ꂽ�B���g�ő��h�ƌ����Ă���Җ{�l�Ƃ����̂������Ȃ��ǃl�i���j�B ���̘_�w�������x �u�g��܂Ƃ����i��a�́��a�́j�h�Ɛ\���܂����̂́A�l�̐S����ɂ��Ƃ��܂��ƁA���ꂩ�琶���Č��ɏo�Ė����̗t�ƂȂ������̂ł���܂��B���̐��ɕ邵�Ă���l�X�́A���܂��܂̎��ɂ������ڂ��Ă���܂��̂ŁA���̐S�Ɏv�����Ƃ��������ƕ��������Ƃɑ����Č����\�������̂��̂ł���܂��B�ԊԂɂ���������i���������j�A�����ɂ��މ͎�(������)�̐����Ă��������B���R�̊Ԃɐ����c�ނ��̂́A�ǂ�����̂��r��ł��܂��B�͂ЂƂ���Ȃ��Ő_�X�̐S�����A�ڂɌ����Ȃ����̐��̐l�̗썰�����������A�j���̊Ԃɐe���̓x�������A�r��Ԃ镐�l�̐S�������a�₩�ɂ���̂��̂ł���܂��v �M���̊Ԃł͊єV�̉̂��ł��d��A�ނ�����ɉ����đ����̛����́i����������G�ƈꏏ�ɏ������a�́j���r���A�����ɔ����Ē���ł̊��ʂ͐��U�Ⴉ�����B���̔w�i�ɂ͋I���S�̂̕s���Ɩv�����e�𗎂Ƃ��Ă���B�єV�����܂��10�N�قǑO�ɍc�ʌp���������čc�q���m�Ő���������A�Z���̕ꂪ�I���A����̕ꂪ�������������B���ʂȂ�Z���c�ʂɏA�����̂����A�����̊g���_���������͍c���ɖҗ�Ȉ��͂������Ē��V�c�ɂ����B�������킪�܂�8���������Ƃ��瓡�����i�����ǖ[�j���c���o�g�ȊO�ŏ��߂Đې��ɏA���A���͂�~�����܂܂ɂ���B �I�����͂��߁A���쎁�ȂnjZ���ɂ��Ă����M���B�́A�ې��̍�����ɓ��ꂽ�������ɕЂ��[����n���֔���ꎸ�r�B���̗l�Ȃ��Ƃ���єV���w�Í��W�x�̒��ŘZ�̐�ɑI�̐l�́A�n�������������ɂȂ������쏬���A�u���V��̕ρv�Ŏ��߂ɂȂ����唺���i����[���j�̈ꑰ�E�唺����A�O�͂ɍ��J���ꂽ�����N�G�A�Ȃ��I���̍��ƕ��i13�N�Ԃ����i���Ȃ������j�ȂǁA���͎҂ɂ���Đh�_���r�߂�����ꂽ�l����B�Z�̐�͂��̉̂��f���炵���������Ƃ����邪�A�єV�̐S��I�ȋ����∣��݂��[���e�����Ă���ƌ����Ă����B ���w�|�敨��x�͓��{�ŏ��̉�������ł���A���삳�ꂽ�N�ォ�����҂͋I�єV�ƌ����A������P�Ɍ������R�����P�`�j�̎Ԏ��c�q�i��������݂��j�͓����s�䓙���I���Ƀ��f���Ƃ���Ă���B 930�N�i58�j�A�єV�͓����Ƃ��Ă͍���̖�60�œy����ɖ������A�s���o�Ďl�����������B���C���Ԃ�4�N�B�y���̑؍ݒ��ɑ��V�c�̒����Łw�V��a�̏W�x��Ҏ[�����B 635�N�i63�j�A�y���ł̔C�����I���ċA������܂ł�55���Ԃ��w�y�����L�x�Ƃ��ĒԂ����B����͗��j�I�ȍ�i�ƂȂ�B�����̓��L�͒j�������ŋL�����̂ł���A���e�͒P�ɋV���̋L�^������x�̂��̂ŁA�l�̓��ʐ��E�i�l���ρj������邱�Ƃ͂Ȃ������B�������u���w�v�Ƃ͂قlj����B�єV�͏��̍�҂��āA���{���w�j�㏉�߂ĕ������œ��L�������A�����Ċ���̕����܂��R�ɕM���ӂ�����B�`���́u���Ƃ������Ȃ���L�Ƃ��ӂ��̂��c�v�g�j�������Ƃ������L�Ƃ������̂����̎������Ă݂悤���Ǝv���h�Ŏn�܂邱�̍�i�́A�a���i���{��j�̕��w�̐�삯�ƂȂ�A�̂��Ɏ���������[���炪���ޏ������w�̓y��ƂȂ����B �w�y�����L�x�̒��ō�����������єV�́A�ƂĂ��e���݂₷�������������B���������̂��Ƃ��u�ꕶ�������ɒm��ʎҁA�������͏\�����ɓ��݂ėV�ԁv�g��Ƃ����������m��Ȃ��j�����ŏ\�Ƃ������������Ă���h�Ɩʔ����Ⴆ����A�_�W��������������O�`�����ڂ����肨�F�C����������A�ǂ��ɂł����镁�ʂ̂��ꂳ��B�����D���̕`�ʂ͂ƂĂ����A���ŁA�ǂݎ�����s���Ă�����o�𖡂키�B�D�q�̑D�����̗l�q�A���ˎs�H���̉������Œj�̎q���u�͂˂��Ē��̉H�H�v�Ɛq�˂܂���đ�l����������ʁA4�N�Ԃɒ��������C���̕Ƀr�r���܂����Ă̖钆�̑D�o�A�ǂ�łđS���ދ����Ȃ��B���L�̍Ō�̈ꕶ�́u�Ƃ܂ꂩ���܂�A�Ƃ��j��Ăށv�g�Ƃ���������Ȃ��̂͑����j��̂ĂĂ��܂����h�B����Ȍ��t�Œ��߂�����ꂽ���w�j�̋��������������ɂ͂����Ȃ��B �y�y�����L/�a��10�I�`����������s����܂ŁE�o�ꏇ�z �����[���A�ɂ��ӂ��y�����L�����A�`������Ō�܂Ŋт��Ă���ЂƂ̔߂��݂�����B����͓s�Ő��܂ꂽ�c�������y���ŖS���Ȃ������ƁB�q�ɐ旧���ꂽ�e�̔ߒɂȒQ�����J��Ԃ�����A�ǂݎ�͋���ł���Ă��܂��B ���D�o�̓��`������ �w�s�ւƎv�ӂ����̂̔߂����́@�A��ʐl�̂���Ȃ肯��x �i���ɓs�֖߂鎞�������̂ɂ������߂����̂́A�ꏏ�ɋA��͂��̂��̖�������ł��܂������炾�c�j �w������̂ƖY��ȂٖS���l���@���Â�Ɩ�ӂ��߂����肯��x �i���̖�������ł��܂������Ƃ�Y��āu�ǂ��֍s�����̂��v�Ɛq�ˁA�n�b�ƋC�Â������̔߂����͂��܂�Ȃ��j �w���i�����j�����ǒ���m��ʂ킽�݂́@�[���S���N�Ɍ��邩�ȁx��������̐l�X�� �i���������Ă��C�̒ꂪ������ʂ悤�ɁA����Ȑ[����D�ӂ����Ȃ������犴���܂����j ���D�́`�D���`�� �w�Ƃ錎�̗���錩��ΓV�̐�@�o�Â鐅��͊C�ɑR�肯��x �i������𗬂�ĊC�֗����Ă䂭�̂����Ă�ƁA�V�̐삪����o��͌��͂���ς�C�̂悤�ł��ˁj �w���g��Ⴉ�Ԃ��Ɛ��������@�l��d��ׂ�Ȃ�x �i�g����ԂɌ��ԈႢ������̂́A�����t���镗�̂�������ł��傤�j �w�s�ɂĎR�̒[�Ɍ������Ȃ�ǁ@�g���o�łĔg�ɂ�������x �i���͂��R�̋��̓s�ł́A�R�ۂɏo���肷�錎����������ǁA�����ł͔g���珸��g�ɒ���ł�����j �w�g�Ƃ݈̂�ɕ����ǐF����@��ƉԂƂɕ��Ђ���Ɓx �i�g�͎��ŕ����ƈ�̉��Ȃ̂ɁA�ڂŐF������ƁA�����g�����ԂɌ�����Ȃ��j �w�������Ă��ЂȂ����̂͂�������@�܂̋ʂ��т��ʂȂ肯��x �i��������Ď��ɂ��Ă��A������܂̋ʂ��т��Ƃ߂邱�Ƃ͏o���܂���j �w�Y��L�E�Ђ�����������i���炽�܁j���@���ӂ�����ɂ��`���Ǝv�͂�x �i�Y��L�ȂE��Ȃ��B����̂悤�ɔ������������̖���������v���C�����́A�����̌`���Ȃ̂ł��j ���G�s���[�O�`���̉Ƃɖ߂��� �w���܂ꂵ���A��ʂ��̂��킪�h�Ɂ@�����̂�������邪�߂����x �i���̉ƂŐ��܂ꂽ���������Ŏ���ŋA���Ă��Ȃ��̂ɁA���璆�ɐV��������������������͉̂��Ɣ߂������Ƃ��j ���̓����A�n���ŋ߂��ʂ����ēs�֖߂��ė�����l�͏o������̂���ʓI���������A�єV�͕������ɋA���Ă��琔�N�Ԃ͉����E�������A���ʂ�8�N��i943�N�j�ɂ悤�₭�]�܈ʉ�����]�܈ʏ�ɂȂ����B�Ƃ���71�B���̏��i�̒x���́A��͂蓡�����Ƃ̍R���ɔs�ꂽ�I���o�g�҂Ƃ�������낤�B�єV�͂���2�N���945�N�ɑ��E�����B���N73�B����20�N��ɐ����[�����A32�N��Ɏ����������܂ꂽ�B ���єV�́w�Í��W�x�w���a�̏W�x�w�E��a�̏W�x�̑S�Ăōő����W�̐l�ƂȂ�A����W�ɂ͑��v475�����Ă���B�q�̎����i�Ƃ��Ԃ݁j���̐l�ƂȂ�w���a�̏W�x��ҏW�����B��������єV�̉̂�1064��Ƃ����B �w�t�̖�Ɏ�܂�Ɨ������̂��@�U�肩�ӉԂɓ��͂܂ǂЂʁx�i�Í��W�j �i���E�����Ǝv���ďt�̖쌴�ɗ�������ǁA�U������Ԃɖ�����ꓹ�ɖ����Ă��܂����b�X�j �w�l�͂����S���m�炸�×��́@�Ԃ��̂̍��ɂɂقЂ���x�i���q�S�l���j �i�l�̐S�͈ڂ낢�₷���Đ悪������Ȃ�����ǁA�×��̔~�̍���͐̂̂܂܂����ƕς��Ȃ���`�j ���� �єV�͓V��@�����̑c�E����̗nj��Ɛe��������A�����b�R�̎R���Ɍ��B��b�R�P�[�u���J�[�́u�֗��i�����āj�R�v�w����o�艺��̂���R�����300���������ꏊ�i10�����炢�B�ׂ��R���Ȃ̂ł����Ɖ����Ɋ�����j�ɁA�ނ̔���܂����߂�ꂽ�˂�����B�єV�͂��̎R���猩���镗�i�������A���n��揊�ɑI�������B�˂́w�y�����L�x�̗������̒n�A�썑�s���瑡��ꂽ�ܐF�ʐŕ~���l�߂��Ă����B�r���̎R������͔��i�������A�J������Ŗ�������������������B���˂̏�̐Δ�͖������N�i1868�N�j�̂��́B |
������ �q�K/Shiki Masaoka 1867.9.17-1902.9.19 �i�����s�A�k��A�嗴�� 35�j1999��2008
 �@ �@ |
| �u�q�K���m�V��v�@�w��̒|�M�ɕ������@�i2008�j |
 |
 |
 |
|
| ��O�Ō��債�悤�ƒ��n�l�i1999�j �����̍��̒|�M�͐��� |
���G���������{�ꂪ�Ղ����Ȃ����͔̂ނ̂������I����܂ňꕔ�� ���w�҂̂��̂��������{����A�N�ł������镽�Ղȓ��{��ɕς��� |
||
|
�����q�K�͖����̔o�l�E�̐l�E�ʐ����ƁB�ߑ���{��̑n���ҁB1867�N10��14�����Q�����R�̐��܂�B�{���͏�K�i�˂̂�j�A�c���́u���i�̂ڂ�j�v�B���i�͒ꔲ���ɖ��邭�A�������Ȃ������B1884�N�i17�j�A������w�\����i�̂���ꍂ�����w�Z�A������w���{�w���j�֓��w�A�o������n�߂�B1889�N�i22�j�A�������̉Ėڋ��V���i���j�Ƌ��ʂ̎�i��ȁj��ʂ��Ė���̐e�F�ƂȂ�A���w�I�E�l�ԓI�e����^���Ă����B�q�K��54��ވȏ�������������̉덆����u���v���������B
���N�A�ˑR�\�����P�T�Ԃ��f�����~�܂炸�A��҂͓����s���̕a�Ƃ��ꂽ���j�Ɛf�f�����B���̕a�ɂ��o�����u�q�K�v�Ƃ����B�g�q�K�h�Ƃ̓z�g�g�M�X�̂��ƂŁA���̒����Ԃ����Ƃɂ��Ȃ�ł���i����f���悤�Ȑ��Ŗ�����Ƃ��j�B �u�䂪���͍����10�N�B�����ƂƂȂ낤���A���w�҂ƂȂ낤���A��͕��w�҂�I�ڂ��B�����ƂƂ������̂́A40���Ȃ���A�V���������Ƃ͂ł��Ȃ��B���[�̖�����܂�Ȃ��g�ŁA�ǂ�����40��҂��Ƃ��ł��悤���B�������A���w�͂����ł͂Ȃ��B40��҂����A30��҂����v�i1899�u�a�枌�/�т傤���傤���v�j �o��̌�����{�i�I�Ɏn�߁A�ߋ��̐����̔o����G���\���̎�ނȂǓO��I�ɕ��ނ��w�o�啪�ޏW�x�ɂ܂Ƃ߂�B���̌��ʁA�ߋ��̔o��͌��肳�ꂽ���t���`���I�ɑg�ݍ��킹�Ă��邾���Ƃ������Ƃ����������B 1892�N�A�����̂��߂ɑ�w�𒆑ނ��A25�ŐV���Ђɓ��ЁB�q�K�͕��|�S���ƂȂ�A�����p�^�[���̌`���I�Ȕo���V������Łu�����݁v�ƍ��]�������ŁA�ǂ�����Ίv�V�ł��邩�Y�B�Ŕj�̂��������ƂȂ����͎̂Ⴂ��Ƃ����Ƃ̌𗬂ŕ��������̌��t�������B�u��z�ŕ`���A�n�������V�l���Ⴂ�҂ɕK�����B�������A�ʐ��Ȃ�A�Ⴂ�҂ł��V�l���������قǂ̍�i��`�����Ƃ��ł���v�i1895�u�o�~��v�v�j�B �q�K�͔o��Ɏʐ��̋Z�@��������邱�Ƃ��v�������B1894�N�i27�j�A���ۂɍx�O�̎��R�̒��Ŏʐ��I�o������݂�ƁA���R�͍��X�ƕω����A�����݂ȑg�������Ȃ��A�ǂ�ǂ�r�ނ��Ƃ��ł����B�q�K�͎ʐ������o�d�ɐV���ȑ����𐁂����ނƊm�M�����B�u����̎蒠�ƁA��{�̉��M�Ƃ��ʐ��̓���ɂ��āA��͎ʐ��I�o������̂ɂ��悤�ƁA��ɉf�邠������̂�߂��āA�\�����ɍ��グ�悤�Ƃ���v�i�u�ԏ㏊���v�j�B 1895�N�i28�j�A�O�N�ɖu�����������푈�̏]�R�L�҂ƂȂ��đ嗤�ɓn��A�T�ΔN��ŌR��̐X���O�i1862-1922�j�ƒm�荇���B�A���̍ۂɑD��ő�\���A�_�˂̕a�@�ɓ��@�B�u�w��͂܂����炸�A�a���͌���������U�ߗ��Ă�B�ߋ��ɉ��������������A�����ɉ������𐬂����Ƃ�����ƂȂ����B����A�������܂��A��͕s�F�i�ӂ����j�̎q�Ȃ肯��v�i�u���̕�v�j�B �މ@��A�×{�̂��߂ɏ��R�ɋA������ƁA�w������̓����������p�ꋳ�t�Ƃ��ĕ��C���Ă����B�q�K�͟��ɗU���āA�����g��ɕ����h�Ɩ��t�������h��52���Ԃ̋��������𑗂�B���̉��h�ɁA�q�K�̔o��v�V�^���ɋ����A�o����w�ڂ��Ƃ��鏼�R�̎�҂������߂������B�q�K�Ɵ��͖�X���܂Łu�����œ��{�̕��w�����i�����j�����v�ƌ݂��ɕ�������荇�����B���ł͎�҂������ǂ�����r�݁A�q�K�́u�ʐ��Ƃ����Z�@�ɂ͓��{�ꂻ�̂��̂��v�V����͂�����v�Ǝ艞����B �o��v�V�̎v�������ɍĂя㋞�B���̓r��A�����痷����������Ă�����ēޗǗ��s���y���B�����ŗL���ȁu�`���ւ@������Ȃ�@�@�����v���r�܂��B���̋�́A���́u�����i�j���@��ǎU��Ȃ�@�������v�̕ԋ傾�B �����ɖ߂�ƁA�V������Łu�o��͕��w�̈ꕔ�Ȃ�v�Ƌߑ�o��̒a����錾�B���݂́u�q�K���v�ɂ͟��≨�O�A���R�̂V�ΔN���̌�y���l���q�i1874-1959�j�ȂǗl�X�ȕ��w�N���W�܂����B�q�K�́u�ʐ��v�Ƃ����l���������w���ԂɍL�܂��Ă����B����A�a�͈����̈�r�B�����̗F�l�ւ̎莆�u�����̖��͖��������͂����ʂ��́B�����̎��Ƃ͏�����l�̑�ŏI��邱�ƂɂȂ�B���̒��ɂ��镶�w�v�z�͈ł���ł֏����čs�����ƂɂȂ�v�B�N���ɍ��l���q�������ɌĂяo���A�o����v�̌�p�҂ɂȂ邱�Ƃ����҂��āu�w�������C�����邩�v�Ɛq�˂邪�A�܂�21�̋��q�́u�����Ȋw������Ă܂Ŗ��_�����߁A��S�����������Ƃ͎v���܂���v�ƒf�����B�q�K�͑ł��̂߂����B�u���͂܂��܂��߂Â����B�����ĕ��w�͂悤�₭�����ɓ������B�������A���������Ǝv���Ƃ��ɁA�����s���Ă��܂����Ƃ������Ƃ��v�B ���N�A���j�ۂ�����N�����������i�ҒŃJ���G�X�j�ɂȂ�B�����x�Ɍ��ɂ����邽�߁A�����ǂ��납�������Ƃ��獢��ƂȂ蒷���a�琶���ɓ���B�u�ɂ݂̗�i�͂��j�������ɂ͎d�l���Ȃ�����A���߂����A���Ԃ��A�������A���͖ق��Ă���ւċ��邩����B����ɂ��߂��A����ɋ��сA����ɋ����ƁA�������ɂ݂�������v�i�u�n�`��H�v�j�B 1897�N�i30�j�A�̋����R�Œ�q�̖����ɓ����A�q�K�����C�Â��邽�ߌ����o�厏�w�قƂƂ����x��n���A�q�K�͑傢�Ɋ�сA�ʐ��̋Z�@���L�߂��Ƃ��Ċ��҂����B�Ƃ��낪�A��������Ԃ��Ȃ��A�w�قƂƂ����x�͋x���̊�@�ƂȂ�B�q�K�͂��̔o�厏��p�������ʂ悤�A�Ȃ�Ƃ������ň����p�����������悤�Əł�B 1898�N�i31�j�A���l���q�Ɂw�قƂƂ����x�̑������肤18m���̎莆�������B�R�N�O�Ɍ�p�����₳�ꂽ���A���q���������҂͂��Ȃ��B�u�M�Z�Ə����Ɠ�l�ł���čs���˂Ȃ�ʁB���������a�C����M�Z��l�ł��˂Ȃ�ʁB�����̐S�̒����@���Ă��ꂽ�܂��B�����M�Z�̌��S���悾�v�B�V����ɋ��q����Ԏ����͂��B�u��Z�i���������j�Ɨ��l�ł��B�ɐH���t���č���G���̌��ō��܂��Ȃ��B�S�N�̌�͓V����̑�Z�̌�p�Ƃ��Ēp���ʂ悤�ɂȂ낤�v�B���q�͎t�̑z�����~�߁A�G�������Ɍ����z�������B �q�K�͑��E����܂ł̂R�N�ԁA�Z�ځi��180cm�j�̕z�c�̒����琢�E�����߂�B���̕z�c�͗c����݂ŏ��R���w�Z�̓����A�H�R�^�V�i��̊C�R�����j�����w��̕č����瑗���Ă��ꂽ���̂��B�u�aଁi�т傤���傤�j�Z�ځB���ꂪ�䂪���E�ł���B���������̘Z�ڂ̕aଂ��A�]�i��j�ɂ͍L�߂���̂ł���B�͂��Ɉ꞊�̊��H�����H�i����j�̓��ɋ��߂�v�i�u�aଘZ�ځv�j�B�q�K�͕������猩���鏬���Ȓ���ώ@���������B�u�ʐ��͓V�R���ʂ��̂ł��邩��A�[�����킦�Ζ��키�قǕω�����������[���v�B �������Ďq�K�́A���߂Č����܂܂͂ɒԂ����u�ʐ����v��a���Ŋ�������B�u��ɓ�\�̏����i���傤����j����B�v�u�j�[�i�����傤�j���q�i�Ȃł����j�͎��ƂȂ蒩��͉Ԃ̂�⏭���Ȃ肵�����̖����҂��ɑ҂������͈��]�i�ق���j�я��i���߁j����B�v�i�u�����̋L�v���j ���u�����̋L�v�S���@https://www.aozora.gr.jp/cards/000305/files/42170_12291.html �q�K�͂��̂悤�ɁA����̏o�����⎩�R�̏�i���A��z����ꂸ�ɕ��ՂȌ��ꕶ�ŏ����ʂ��ʐ����ɂ�镶�͊v�V�^���ɒ��肵�A�Ȍ����Ăŋq�ϓI�ȕ��̂�ϋɓI�ɐ��i�����i��N�̟��w��y�͔L�ł���x�ɉe���������j�B ���N10���A�҂��]���|���w�z�g�g�M�X�x�������Ŕ��������B���R����́w�قƂƂ����x�͔o�厏���������A�����́w�z�g�g�M�X�x�͏������f�ڂ���A�q�K�͎ʐ����w�����̋L�x�\�����B�ǎ҂��q�K�ƈꏏ�ɒ�����Ă��銴�o�𖡂키�{��͑傫�Ȕ������ĂB�ʐ����͐V���ȓ��{��̕\���Ƃ��Ď����ꂽ�B�q�K�́w�z�g�g�M�X�x�ǎ҂Ɏʐ����ɂ����L�̓��e���L���Ăт������B�q�K�͒N�ɂł�������Ƃ������Ƃ�m�点���������B�_���A�{�Y�ƁA��H�A�T�����[�}���A�l�X�ȐE�Ƃ̐l�����L�𓊍e�����B �����I�O�A�Ȓ��n�Ղ̒��ҏ����w�쑍���������`�x�i1814�`42�j�̏����o���́u���s�̏��R�A���q�̕����A���Ёi�Ԃ��j���i���Ƃ�j���ĕΎ��i�ւイ�j�����͐퍑�ƂȂ肵��i����j�c�v�ƌł����̂������B�����Ƃ����s�ׂ́A��ƁA����ƂȂǂ����ꕔ�̐l�Ԃ����̂��̂������B�����A�]�ˎ���̌Â����{����ߑ���{��ɍ�肩�����A���Ղȓ��{���p�����ʐ����̓o��ŁA�N�����C�y�ɂ��̂�������悤�ɂȂ����B �����̓����ƕ��s���āA�q�K�͗^�Ӗ�S���炪�n�߂Ă����Z�̉��v�^���ɉ����n�߁A�w�̂�݂ɗ^�ӂ鏑�x�\�B�q�K�͒Z�̂ɂ����Ă��ʐ����ƂȂ��A���t�W�⌹�����́u���Řa�̏W�v�ɋɂ߂č����]����^�����B�f�p�ŕ����Ȗ��t���̉̕��A���R������̂܂܂ɉ̂����ގʐ��I�Ȏp����M�^�����B ����A���������̐�����͘a�̂̋K�͂Ƃ�����Ă����Í��W���u������ʏW�ɂėL�V��v�Ɣl�|���A�Í��W�̑I�҂ł���O�\�Z�̐�ɂ�����A�˂�I�єV���u����ȉ̂�݂ɂāv�ƍ��]�B�����̒d�̎嗬���������h�a�̂́A�Z�I��`���ɂƂ��ꂽ�Í����̉̂��u���ɂ܂�v�ƖҍU�������B�V�Í��a�̏W�ɂ��Ắu��₷���ꂽ��v�Ƃ����A�I�҂̓�����Ƃɂ��Ắu�����̉̂ɂ͂낭�ȎҖ��V�v�ƕ]���ȂǁA����a�̏W�̍앗�ɂ͔ے�I�ȍl�����������B ���Ȃ݂ɁA�q�K�ƓS���̕s�����͌��ŁA�g���h�ɂ͂����͂��Ȃ��̂Ŏ��������V�h�i���v�ҁj���m�Ŕ�]���������h�Ǝq�K���Ăт����������B�o������]�������p���g�Η��h�Ƌȉ������̂��^�����B 1900�N�A�����C�M���X���w�ɏo���B 1901�N�A�a��͂���ɏd���Ȃ��Ă������A�M�͂܂��܂��Ⴆ�āA�V������ɐ��M�w�n�`��H�x��A�ځB 1902�N�A�T���T�����玀�̂Q���O�̂X��17���܂ł܂łS�����ԓ��X�̐��M�w�aଘZ�ځx��Ԃ�B�����ɂ́A�u�]�͂��܂܂őT�@�̌��Ƃ������̂�������Ă����B���Ƃ́A�����Ȃ�ꍇ�ɂ����C�Ŏ��ʂ邱�Ƃ��Ǝv���Ă����̂͌��ŁA�����Ȃ�ꍇ�ɂ����C�Ő����Ă��邱�Ƃł������v�Ɛ����Ɏ���ӔN�̐��ݐ����S�����f���o����Ă���B�X��19���A�ŏ��̚\������13�N�A�������a�̖��A�q�K��34�ŗ��������B�Z�����U�ɂ����Ĕo��P���Q��]�A�Z��1300��A����3000��ȂǁA����ȋƐт��c�����B�揊�͓����c�[�̑嗴���B���R�̐��@���i���傤���イ���j�ɂ��u�q�K���m�������v�����B���n�ɂ͔���R�l�E����L���̉̔������B�剺���狕�q�A�͓��Ɍ�ˁA�ɓ�����v�A���ː߂ȂǁA�����ꂽ�o�l�E�̐l��y�o�����B 1903�N�A�����A���B�s����Ȉٍ������Ő_�o�����茸�炵�Ă����B���t�ɂȂ�A����ɃX�g���X�𗭂߂Ă����B ���l���q�̓m�C���[�[�C���̟��ɁA�u�����Ȏv��������̂܂ܓf���o���C���炵�ɂȂ�v�Ə����̎��M��E�߂��B���͎q�K�̎ʐ����̎�@�������Ɏ�����A�ǂ݂₷�����͂��������B 1905�N�A�����w��y�͔L�ł���x���w�z�g�g�M�X�x�ɔ��\�A�唽�����ĂԁB���N�ɂ́w�V�������x���Ăсw�z�g�g�M�X�x�ɔ��\�A���͍����I��ƂƂȂ��Ă������B ���q�K�͑�̖싅�D���B�u�Ŏҁi�o�b�^�[�j�v�u���ҁi�����i�[�j�v�u�����i�X�g���[�g�j�v�u�l���i�t�@�[�{�[���j�v�u�����i�f�b�h�{�[���j�v�u�i�t���C�j�v�͎q�K��������B �������́u�q�K���v�ɂ͌��|������Ă������߁A�Z�̂������Ƃ��́u�|�̗��l�i���ƂтƁj�v���g�p�B ���q�K�ȍ~�A�o�~�̍ŏ��̔��傪�o��ƂȂ�A�a�̂��Z�̂ƌĂ��悤�ɂȂ����B ���Q�l�w���̎����j���������`�����q�K�E�]���\�N�œ��{����v�V�����j�x�iNHK�j�A�w���E�l�����T�x�i�����Ёj�A�w�G���J���^������S�ȁx�i�}�C�N���\�t�g�j�ق��B �q�K�̕��i����嗴���́A�R����̓c�[�w����k��15���̊ՐÂȏZ��n�̒��ɂ���i���݂̎q�K�������2�����j�B�������I�ꂽ�̂́A�g�Â��Ȏ��ɑ����ė~�����h�Ƃ����肢���q�����������̂��B��̔w��ɂ͐X�Ƃ����|��Ԃ������Ă��邪�A����͎q�K�̍��g�|�̗��l�h���炫�Ă���̂��낤�B
�E�������ċ��q�����đ�O�\���i�����݂����j �E�~�����萢�Ԃ̉����ċ��� �i��W�g���R���h����j
�`�H�ւΏ�����Ȃ�@����
�������т���̐[����q�˂���
|
���^�Ӗ� ���q/Akiko Yosano 1878.12.7-1942.5.29 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 63�j1991��02��05��10
���^�Ӗ� �S��/Tekkan Yosano 1873.2.26-1935.3.26 �i�����s�A�{���s�A�����쉀 62�j1991��02��05��10
 |
 |
 |
| ���q | �v�Ȃ̃c�[�V���b�g�I | �S���i�{�����j |
 |
||
| 1991�N3�� | 2002�N8�� |
 |
 |
| 2005�N10�� | 2010�N�U�� |
| ���r�܂�������ł���^�Ӗ�v�w�B�����S���A�E�����q�B��̌`�������낢�Ń��u���u�B�ڂ̂���ɍ������i�j�B �������Ă��Ȃ�ǂݐh���������ǁA��ɂ͂��ꂼ�ꎟ�̉̂������Ă����B�u�������܂��������̂ƂȂ肽��� ���тĐQ�˂̂ނ�����v�i���q�j�u�Ȃɂ͒Âɍ炭�̉Ԃ̓��Ȃ�ǂނ��炵����ČN���s���܂Łv�i�S���j |
| ���q�̋����͖P�i�ق��j�A�{�����i���傤�j�B����ɐ��܂��B���w�Z���ォ�猹������▍���q�ȂnjÓT�����ǂ��镶�w�����ŁA10�㔼����Z�̂����n�߂�B��\���ɐV���ŗ^�Ӗ�S���̉̂�m��[���������A1900�N�i22�j�A4���ɓS�����w�����x��n������Ɠ����ʼn̂\�����B8���ɏ��߂ēS���Ɖ���S�������A���Ăɂ͓S����ǂ��ĉƏo���R�ŏ㋞���A�P���q�̖��ő��̏W�w�݂��ꔯ�x�i6��399����^�j�����s�A����2������ɍȂƕʂꂽ�S���ƌ�������B���ɏ��q23�A�S��28�B�����������ɂ��Č�邱�Ƃ��^�u�[�������ێ�I�Ȗ����̐��ɂ����āA���̏�M�����R�z�������\�I�ɉ̂��グ���w�݂��ꔯ�x�͈��Z���Z�[�V�����������N�������B �u��͔��̂��������ɂӂ�����ł��т����炸�⓹������N�v�i�M���قĂ������ɐG�ꂸ�l�����������Ŏ₵���ł��傤�j �u�݂��ꔯ�����̓��c�ɂ��ւ����ӂ��Ă��܂��̌N��肨�����v�i�݂��ꔯ���Y��Ɍ����Ȃ����Ē��Q���邠�Ȃ���h��N�����j �u�t�݂��������ɕs�ł̖����Ƃ����炠�������ɂ����点�ʁv�i�t�͒Z�����Ɍ��肪���邩��ƒe������[�Ɏ���j �u�߂��ق��j���点�Ɣ����悭�����Ȃ�������ꂵ���v�i�ߑ����j�����炵�߂�ׂɉ�͔����������������ꂽ�j �ޏ��͕����I�ȋ������ɔ��R�������Ƃœ`���̒d����ᔻ���ꂽ���A���ɍ������l�Ԑ��̍m��͖��O����M���I�Ȏx�����A�w��؏W�x�̓��蓡���Ƌ��ɘQ����`���w�̊���Ə̂��ꂽ�B ���ꂩ��3�N���1904�N�i26�j�A���I�푈�̍Œ��Ƀ��V�A�̕����g���X�g�C�����}�m�t�����Ɍ����Ĕ��\�����푈�ᔻ�����{�̐V���Ɍf�ڂ���A�G�������̔��탁�b�Z�[�W�ɐ[�������������q�́A���N�O�ɏ��W���ꗷ���U�͐�ɉ�����Ă�����ɌĂт�����`�Łw�����x9�����ɂ����������B �u�N���ɂ��܂ӂ��ƂȂ���@���߂�݂��Ƃ͐�ЂɁA���ق݂Â���͏o�ł܂��ˁ@�����݂ɐl�̌��𗬂��A�b�i�����́j�̓��Ɏ��˂�Ƃ́c�v �i��掀�ȂȂ��ł�����B�V�c���g�͊댯�Ȑ��ɍs�����{���Ɉ��Z���A�l�̎q���b�̓��ɂ������点�Ă���j ���̔���͔̂��\�Ɠ����ɁA���I�푈�ɔM�����鐢�Ԃ���g�c���̍����Ƃ��ĕÉ��ɕs�h�ł͂Ȃ����h�Ɩҗ�Ȕᔻ�ɂ��炳�ꂽ�B���|��]�ƁE�咬�j���́u���q�͗��b�Ȃ葯�q�Ȃ�A���Ƃ̌Y�������ӂׂ��ߐl�Ȃ�v�ƌ������������A���q�͂���ɔ��_���ׂ��w�����x11�����Ɂu�Ђ炫�Ԃ݁v�\�A�g���̍���������C�����͒N�ɂ������ʁh�ƑO�u�����������Łu���Ɛ\�����́A�N���푈�͌����ł��B���߂̂悤�Ɏ��˂掀�˂�ƌ����A�܂����������N�����⋳�璺��������o���Ę_���鎖�̗��s�����A�댯�v�z�ł͂Ȃ����ƍl���܂��B�͉̂̂ł��B���̐S���̂�ʉ̂ɁA���̒l�ł�������ł��傤�v�ƑS�������邱�Ƃ͂Ȃ������B ���q�͔��ɋ�����ǂ��납�A���N���s���ꂽ���̏W�w���߁x�ɍēx�g�N���ɂ��܂ӂ��ƂȂ���h���f�ڂ���B ���̌���������⋳����ȂǂŎw���I�����𑱂��A1911�N�i33�j�ɂ͓��{���̏������|���w���߁x�����ɎQ���A�u�R�̓��������i�����j��B�i�����j���ׂĖ��肵���i���Ȃ��j�����ڊo�߂ē����Ȃ�v�Ǝ^�����Ă��̊���������A43�ŕ����w�@�̑n�݂ɉ���莩�R����ɐs�������B�܂��A���w�҂Ƃ��Ă͒Z�̂����łȂ��A�w�V������x���n�߂Ƃ����ÓT�̌�����ɂ������̒�����c���B 1930�N��ɓ����Ė��B���ρA�܁E������A���ۘA���E�ނƌR�������i�݁A�������Ɍ��_�̎��R���D���Ă������ŁA���q��1936�N�i58�A����6�N�O�j�ɍ��Ƃ̎v�z�����ɂ��Ă��������c�����B�u�ڑO�̓������������l�����́g���R�͎��h�Ɖ]����������Ȃ��B�������g���R�h�͖ʂ��ċ����Ă���̂ł����āA����ł��܂����̂ł͂Ȃ��B�S�̉��ɒN�����g���R�h�̕������F���Ă���̂ł��v �����R�������Ă���A����ȕ\��������̂��c�I �����h�̉̐l�Ƃ��Đ��U�ɂ킽���ēS���̎d�����T�|�[�g���i�S����57�̎��ɐ旧�j�A�ƒ�ł�11�l�̎q����āA�����m�푈�̐^��������1942�N��63�N�Ԃ̐l�����I�����B �E�S���ɂ��āc�u��̍��̐V���̉̂Ə̂��Ă�����̂͒N�������ĒN����Ă����̂ł��邩�B���̖₢�ɌȂ��Ɠ����邱�Ƃ̏o����l�͗^�Ӗ�N�������ΊO�ɂ͂Ȃ��v�i���O�j �E�u���j�i���j�̎q�ӋC�̎q���̎q�邬�̎q���̎q���̎q���T�������̎q�v�i�S���j �E�w�����x�͑�A���������Y�A�k�����H��𐢂ɑ������B |

�����s�@�t/Saigyo Houshi 1118-1190.2.16 �i���{��͓��S�A�͓쒬�A�O�쎛 73�j2005��12
 �@ �@ |
| �G���������Â��ĕ\��悭������Ȃ����ǁA�Ⴂ���͂����������`������������ |
 |
 |
 |
| ���̎R�������s�I���̒n | ���s�̉́u��͂��͉Ԃ̉��ɂďt���Ȃށv������ŁA��̎��ӂɍ�����{�A����ꂽ | |
  |
 |
 |
|
| ���낤���āu���s��l�V��v�Ɠǂݎ��� | �ӔN�̐��s�����߂��i�F�͍����ς�炸 | ���܂�̎��R�̔������Ɏv�킸���� | |
  |
 |
|
| ���s���̐Ւn���������D�B�����Ŗ��키�Ԓ������͍ō����낤�Ȃ� (*^v^*) |
�K�ꂽ�̂�5��3���B�V�̋G�߂̏�A�O���ɉJ���~�����Ƃ��� ���Ƃ�����A���蓾�Ȃ��قǖX�̗t���X�ƋP���Ă����b�I�I |
|
 |
 |
| �Ő��n���̓��R��E�ԗю��i������j�ɂ����{���B���������s�B �E�͌㔒�͖@�c�Ɏd���A���P�J�̎R���ŕ��Ƒœ|�̖��c�ɎQ�����A�F�����S�E������ �r����Ɨ����ꂽ���N���i�₷���j�B�̂��Ɏ͂���ċ��s�֖߂����B ���͓�k������̉̐l�ڈ��i�Ƃj�̕�Ɠ`������i2012�j |
|
|
�{�������`���i�̂肫��j�B�a�̎R���߉�S�œc���o�g�B������[�����߁A�Ԃ⌎������Ȃ����������������̑�̐l�B�w�V�Í��a�̏W�x�ɂ͍ő���94���I���Ă���B�{���Ɋ����̐l�ł͂Ȃ��A�R���̈��̌ǓƂȕ�炵�̒�����̂��r�B
�c�悪���������Ƃ����T���ȕ��m�̉ƌn�ɐ��܂�A�c�����ɖS���Ȃ������̌���p��17�ŕ��q�сi�Ђ傤���̂��傤�A�c���̌x�앺�j�ƂȂ�B���s�͌䏊�̖k�����x�삷��A�@�����̖��_���鐸�s�����u�k�ʂ̕��m�v�i��ʂ̕��m�ƈ���Ċ��ʂ��������j�ɑI��A�����ɂ͔ނƓ����N�̕������������B�k�ʐ����ł͉̉�p�ɂɍÂ���A�����Ő��s�͍̉̂����]�����ꂽ�B���m�Ƃ��Ă����͈͂ꗬ�ŁA��������n�ォ��I���˂�u���L�n�i��Ԃ��߁j�v�̒B�l�������B����ɂ́A�f�i�܂�j�𗎂Ƃ����ɏR�葱����A���Ɓ����m�Љ���\����X�|�[�c�u�R�f�i���܂�j�v�̖���ł��������B�u�k�ʁv�̗̍p�ɂ̓��b�N�X���d������Ă���A���s�͗e�p�[�킾�����Ɠ`�����Ă���B ���E�ɏG�ʼn̂��悭�������s�̖��́A���E�̒����܂ŕ������Ă����B���������Ŕ��`�B�₩�Ȗ����͖���Ă����B�������A���s�́u�k�ʁv�Ƃ����G���[�g�E�R�[�X���̂āA1140�N�A22�̎Ⴓ�ŏo�Ƃ���B�o�Ƃ̗��R�͕��������āA�i1�j���ɋ~�ς����߂�S�̋��܂�i2�j�}�������F�l����l���̖����������i3�j�c�ʌp�����߂��鐭���ւ̎��]�i4�j���g�̐��i�̂��낳�������������i5�j�g�\�������ꂠ��A���鍂�M�ȏ����h�Ƃ̎����B�ނ͉̉�Ȃǂ�ʂ��Ē���[�߂����H�@�̔܁E�Ҍ���@�i�����V�c�̕�j�ƈ��̌_������킵�����A�u����������ΐl�̉\�ɂ̂ڂ�܂��v�ƃt������--���X�A���������l�X�Ȋ�����ݍ��������ʁA�Ȏq�ƕʂ�ĕ����ɓ������悤���B����ɕ��̋Ɋy��y�������ɂ��邱�Ƃ���u���s�v��@���Ƃ����B ���s�͏o�Ƃ�O�ɂ���ȉ̂��r��ł���B �w�����̂�l�͂܂��ƂɎ̂邩�́@�̂Ăʐl�����̂�Ƃ͂��Ӂx �i�o�Ƃ����l�͌���~�������߂Ă���{���ɐ����̂Ă��Ƃ͌����Ȃ��B�o�Ƃ��Ȃ��l�����������̂ĂĂ���̂��j �g�o�Ɓh�Ƃ����s���̂͒������Ȃ����Ƃ����A���s�����ʂ������Ă����̂ɂ�����̂Ă����ƁA�������܂�20�Ή߂��ŎႩ�����_�Ȃǂ���l�̒��ڂ��W�߂��炵���A���̓���b�E���������i��ɕی��̗��Ŕs���j�͓��L�Ɂu���s�͉Ƃ��x�ݔN���Ⴂ�̂ɁA���s���R�Ȃ��������̂ĕ����ɓ���ِ������Ƃ����B�l�X�͂��̎u��Q�����������v�ƋL���Ă���B���s������ȂǑ厛�@�ɏo�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�ǂ̓���̏@�h�ɂ��������n�ʂ▼�������߂��A�����R���̈��Ŏ��Ȃƌ��������A�a�̂�ʂ��Č��Ɏ��낤�Ƃ����̂��ʏ�ƈقȂ��Ă����B �����s����镶���ɂ́A�o�Ǝ��̂��Ƃ��u�Ȏq���̂Ăďo�Ƃ����v�Ƃ��������Ă�����̂������B����݂̂ł͔ނ��ƂĂ��₽���j�Ɍ�����B���ۂɂ͂����ƒ�Ɍ�̎��𗊂�ł��邵�A����Ȍ���k������B�o�Ƃ̐��N��A����K�ꂽ���s�́A5�ɂȂ����͂��̖����C�ɂȂ��āA���������̉Ƃ̖�O���璆�̗l�q�������������B���傤�ǎq�ǂ����V��ł��āA�����L�тĉ��炵���������Ă�������ǁA�ނ�����Ȃ�u�s���܂��傤�B�����̂��V�l���|������v�ƒ��ɓ����Ă��܂����i����̓c���C�j�B���̖��͌�ɗL�͋M������Ƃ̖��E���̗{���ɂȂ��Đ��s������A��ł������ɑ���̕v�������̎����ɂ��Ă��܂����̂ŁA�u����{���ɏo�����̂͏��Ԏg���ɂ�����ׂł͂Ȃ��I�v�Ɛ��s�͔ޏ���A��o���čȂ̏��ɖ߂����Ƃ����B���s�͍Ȏq�̂��Ƃ������ƌ�����Ă����B �o�ƒ���͍x�O�̏��q�R�i����j��Ɣn�R�Ɉ������сA���ɔ鋫�̗��Ƃ��Ēm��ꂽ�ޗǁE�g��R�Ɉڂ����B���s�͒����ϔY�ɋꂵ��ł���A������u���l�v����Ȃ������B�ނ͏o�ƌ�̖�����S�̎コ��f���ɉ̂ɍ��߂Ă����B �w���̊Ԃɒ�������̖����߂ā@�������Ƃ̂����Ƃ���ށx �i���ɂȂ�Β�����������o�߂āA�����ɕs���̐S�������Ƃ��ł���̂��낤�j �w�鎭�R���������悻�ɐU��̂Ăā@�����ɂȂ�䂭�킪�g�Ȃ��ށx���ɐ��Ɍ������r���� �i��������U��̂Ă������ė鎭�R���z���Ă��邪�A���ꂩ�玄�͂ǂ��Ȃ��Ă����̂��낤�j �w���̒����̂ĂĎ̂Ă��ʐS�n���ā@�s�͂Ȃ�ʉ䂪�g�Ȃ肯��x �i���̒����̂Ă��͂��Ȃ̂ɁA�s�̎v���o���ϔY�ƂȂ莄���痣��Ȃ��j �w�Ԃɐ��ސS�̂����Ŏc�肯��@�̂Ă͂ĂĂ��Ǝv�ӂ킪�g�Ɂx���g��ŁB10���{�̍�������B �i���̐��ւ̎�����S�Ď̂Ă��͂��Ȃ̂ɁA�Ȃ�����Ȃɂ����̉ԂɐS�D����̂��낤�j 1146�N�i28�j�A���k�n���ɉ̖��i�a�̖̂����j��K�˂��B���߂Ă̒������B����ɖ{���n�����鉜�B�������͐��s�̈ꑰ�B��~���߂����A�߂��s���N�̕��Ɏ��̉̂��r�ށB �w������S�ׂ����v�ق�� ���̋�ɂĔN�̕��ʂ�x �i�����̔N���S�ׂ�������Ȃ��B���̋�̉��ŔN�����Ă�����j 1149�N�i31�j�A������A������͐^�����E����R�ɓ����Ĉ������ԁB�����̍���R�͗����̉Ђő傫�Ȕ�Q���Ă���A�����ׂ̈̊�t�i���i�j���e�n�ŏW�߂Ď���m�E���쐹�i�Ђ���j�������W�܂��Ă����B���s���ނ�ɉ����A�o������J��Ԃ���30�N�Ԃn�ʼn߂����B 1156�N�i36�j�A�s�ɂāw�ی��̗��x���u���I ���̎���̒��쌠�̗͂���́A���́i�@�c�j���x�́i���͂̎q�j�����H�i�x�͂̎q�j�������i���͔��͂̎q�j���߉q�i���H�̎q�j���㔒�́i���H�̎q�j�B���V�c���ވʂ���Ɓu��c�v�ɂȂ�A��c���o�Ƃ���Ɓu�@�c�v�ɂȂ�B ���͂̓g���f���@�c�ŁA�V���Ă���Ⴂ�{���i�Ҍ���@�j�Ɏ���o���A�����Ɏq�i�����j��g�U�点���܂ܑ��i���H�j�ƌ��������Ă���B���͂̎��j�E�x�͓V�c��22�ő�������ƁA5�̒��H�V�c�ʂ������͂��㌩�l�ƂȂ�@�����X�^�[�g�B���H��19�ɂȂ��Ď��Ȏ咣���n�߂�Ƌ����ވʂ����ď�c�i�������I�����[�j�ɂ��āA�܂�5�̐����ʂ����@�c���g�����������葱�����B ���͖@�c������ł��璹�H��c�̊����Ԃ����n�܂�B���H�͔��͂ƑS���������Ƃ������B���H�͖@�c�ƂȂ��Ĕ��͂̎q�ł��鐒���i����22�j�������ވʂ����ď�c�ɂ��A�܂�3�̎��q�E�߉q�ʂ����A�߉q����������Ƌ߉q�̌Z�E�㔒�͂�i�������B�����Ē��H�@�c�����ʂƁA������c�u�r�㔒�͓V�c�́u�ی��̗��v���u������B�����̎�͂͐������ɁA���Ƃ̎�͂͌㔒�͑��ɂ����B��͌㔒�͂̏����ƂȂ�A�����͎]��ɗ������B���������̗��Ō����̎c�}��j���������́A���ƑS���̎����z���Ă����B���̌�A�㔒�͖͂@�c�ƂȂ���5�l�̓V�c��30�N�Ԕw��ő���A�����ɕ��ƊԂ̑Η�������čI�݂ɗ�����������Ƃ���A�������́u���{��̑�V��v�ƕ]�����B
1168�N�i50�j�A�ی��̗��Ŏ]��ɔz������A4�N�O�ɖ��O�����тȂ��玀�ɁA����ɂƂ��Đ������^�ƕ��ԑ剅��ƂȂ���������c�i���s���t�������܂̎q�j�̒����Ƌ�C�̐��n�T�K�ׂ̈Ɏl�������炷��B �w�悵��N�̂̋ʂ̏��ƂĂ��@������ތ�͉��ɂ��͂���x��������c�̕�i�����ˁj�ɂ� �i���Ă͓V�c�̐g���ƂāA����͒N���������ł͂���܂��B�ǂ������炩�ɂ����艺�����j ���s�͎l�����獂��R�ɋA��O�ɁA���n�ŕ�炵�Ă������̑O�ɗ����ɉ̂����B �w�v�Ɍo�Ă킪��̐����ւ揼�@�Ղ��̂Ԃׂ��l���Ȃ��g���x���]�P�ʎ��ɂ� �i���̖�A���������Ď��̌㐶���Ă�����B���͐�����c�ƈ���ĎÂ�ł����l�����Ȃ��g�Ȃ̂��j ����ɍ���R�ŏC�s�����̂��A1177�N�i59�j�A�ɐ��Y�ֈڏZ�B1180�N�i62�j�A�����̗����u���A�S���e�n���̉�����ݍ��ށB���N�A���Ƃ̓s�����B���s�͈ɐ��̊C�����Ȃ���u������k�A�ǂ��ł��킢���N�����ڂȂ��l������ł���B����͉����̑������v�ƒQ���A���̐헐���r�ށB �w���o�̎R�z���₦�Ԃ͂��炶���� �S���Ȃ�l�̐������x �i�V����S��������Ŗ���D���A���̐��ւ̎R���z���čs���l�̗��ꂪ�₦�鎖�͂Ȃ��̂��낤���B�����펀�҂̘b�����l�������y��ł���j ���������̒��œ��厛�͑啧�a�ȉ����Ƃ��Ƃ��Ď������B1186�N�i68�j�A�����ɏ�M��R�₷���m�E�d���i���傤����j�͐��s��K�ˁA�u�啧��t���i�Ƃ���A���b�L�j����ׂ̍�������Ă��ꂽ���B�������ɁA��������悤�`���ė~�����v�Ɨ��B���s�Ƌ��m�̒��̉��B�����G�t�͂܂������ł���A�d���͐��s���G�t�̌q����𗊂����̂��B�����E�̒��_�ɂ���d���ɓ����������A����̐S�ӋC�ɍ��ꂽ���s�́u������܂����A�����܂��傤�v�B�ނ͎���40�N�Ԃ�ɓ��k�������B ���̎���A70�ɂȂ낤���Ƃ����V�l���A�ɐ��Ɗ�����������̂͑z����₷��قǑ�ςȂ��Ƃ��B�{�S����䕧�ׂ̈Ƃ��������M���Ȃ���Ώo���ł��Ȃ��������낤�B�����G�t�͕���܂ł���ė������s�Ɋ������A�����ɍ�����ޗǂɑ������B �w�N�����Ă܂��z��ׂ��Ǝv�Ђ���@���Ȃ肯�菬��̒��R�x�����B�������� �i�܂����N���Ƃ��Ă����̒��R�����Ăщz����Ȃ�Ďv�������Ȃ������B������������Ă̂��Ƃ��Ȃ��j ���͂��̉��B�s���ŁA���s�Ɛ��Α叫�R�E���������Ζʂ��Ă���B1186�N8��15���A�߉������{�ɗ������Q�w����ƁA�����̎��ӂ�p�j����V�m�������B������ʼnƐb�ɖ���q�˂�����Ƃ��ꂪ���s�ƕ�����A�����������͊قɏ����āA���L�n�i��Ԃ��߁j��̓��̎����ڂ����������B���s�̓q���E�q���E�Ƃ��u�̂Ƃ́A�Ԍ������Ċ����������ɁA�͂��O�\�ꎚ����邾���̂��ƁB����ȏ�[�����Ƃ͒m��܂���v�B���L�n�̂��Ƃ́u��������Y��ʂĂ܂����v�ƃg�{�P�Ă������A���������f����̂Ŕn��ł̋|�̎������A��̎˂�����Ԃ��Ɍ��n�߂��B�����͂����ɏ��L���Ă�ŏ������߂������Ƃ����B2�l�̉�b�͏I�鑱���A�������؍݂����߂�ꂽ���A���s�͐U���悤�ɒ����������B�����͓y�Y�ɍ����ȋ�̔L�������A���s�͊ق̖���o��Ȃ�t�߂ŗV��ł����q�ǂ��ɂ����Ă��܂����Ƃ����B�i�w��ȋ��x�j �����݊��q�̍Ղ�ōÂ���Ă���u���L�n�v�́A���s���R�c��`���������N����s�Ȃ���悤�ɂȂ����B ������܂ŋ`�o��߂炦��ׂ̊֏�������ʂ�K�v���������̂ŁA���̒ʍs�����߂Ɋ��q�֊�����Ƃ������Ă���B 1187�N�i69�j�A���̂��닞�s����̈��ɏZ�ݎq�ǂ��̗V�т��ނɁu���͂Ԃ�́v���r�ށB �w�|�n����ɂ����ӂ͂��̂ނ��ȁ@���i���́j�V�т��v�Ђłx�@ �i�q�ǂ��̍��ɗV�|�n�́A���ł͏�Ƃ��ė��ސg�ɂȂ��Ă��܂����Ȃ��j �w�̂����B��V�тɂȂ�Ȃ�@�Ћ����ƂɊ�蕚����x �i�̂̂悤�ɉB���ڂ��܂���肽���B�������������̕Ћ��Ŏq�ǂ��������ĉB��Ă����j 1189�N�i71�j�A���s�͋��s�����̐_�쎛�֓o�R���铹������A�܂����N���������b��l�ɁA���s���g�����ǂ蒅�����W�听�Ƃ�������a�̊ς�����Ă���B�u�̂͑����@���i���j�̐^�̎p�Ȃ�A����Έ��r��ł͈�̂̕�����グ��v���A�閧�̐^����������v�����v�B���N�A���s�͑��͓��̎R���ɂ���A���i����́j�s�҂��J���A�s����C���C�s�����O�쎛�̗��R�Ɉ������сA�������I���̒n�ƂȂ����B ���s�͖S���Ȃ�\���N�O�ɁA�⌾�̂悤�Ȏ��̉̂��r��ł����B �w��͂��͉Ԃ̂��Ƃɂďt���Ȃށ@���̔@���i�����炬�j�̖]���̍��x���@���̖]��=2��15���B�߉ނ̖����B �i��킭��2��15������A���J�̍��̉��ŏt���������j ���s�������֗��������̂�2��16���B�߉ނ̌�������x��Ă��čs�����B ���E����540�N��̍]�˒����i1732�N�j�A���s��[���炢�O�쎛�Ɉڂ�Z�L���̉̑m�E���_�@�t���A���s�̕���������B�ȍ~�A���_�@�t�͐��s�����������̖��A����͂ނ悤�ɐ�{���A���āA�S����̒����Ƃ����B�����̘V�����R�����n�߁A���ł�1500�{�̍����������R���Ă���B ���̐��E�ɋ�������A�����ւ̎������̂Ă��ꂸ��X�Ƃ��钆�ŁA�C�����ƉԂ⌎�ɐS���̂��r��ł������s�B������̓�����Ƃ�̂悤�ɋZ�I�I�ȉ̂ɑ���̂ł͂Ȃ��A�����܂ł��f�p�Ȍ����ŐS����f�I�����B���R��l����^�������Ɍ��߁A���ʂ̌ǓƂ�₵�������炸�ɉr���s�̘a�̂́A�ǂ��܂ł����R�̂��B
�{��̒��ł͂Ȃ��R���ʼn̂��r�݁A���鎞�͐X�Ղ̐Â����ɖ�����A���鎞�͌ǓƂ̘̂����ɗh�ꓮ���Ȃ���A���������̍��ׂƂ������E�ɂ��āA�����̔��ӎ���l���ς��Ō�܂ŕ`���o�����B 500�N��̔m�Ԃ��n�߁A�㐢�̑����̉̐l�������A���s�̍�i�����̐l���ƍ��킹�Čh�炵�Ă����B���q���ɂ́w�V�Í��x�ɍő��̍�i�����I���A���{�S���ɂ�146����̔肪��������Ă���B���s��800�N�̎����A���Ȃ��l�X�̐S�𑨂��ė����Ȃ��I ���S2090��̂������͖̉̂�300��A���̉̂���230��B����W�ɂ�265����Ă���B55�ΑO��ɂ͉ƏW�w�R�ƏW�x�̌��^���o���Ă����B �����s�ɂ�鐒����c�ւ̕�Q�́A��ɏ�c�H�����w�J������x�̖`���ŕ`���Ă���B ���ɐ��_�{�ɂ��Q�肵�����s�@�t���킭�u�����̂��킵�܂����͒m��˂ǂ��A���������Ȃ��ė܂��ڂ��v�B ���O�쎛�̋����ɂ͐��s�L�O�ق�����A���s���M�̊|�����ȂǑ����̎������W������Ă���B ���ߓS������u�x�c�сv�w��������o�X�͓��s�I�_���ԁB�o�X�̖{�������Ȃ��̂ŕK���A��̎��Ԃ��m���߂邱�ƁB �y���s12�I�`�{�����ɏЉ�ł��Ȃ������I�X�X���Z�̂����z �w�䂭�ւȂ����ɐS�̂��݂��݂ā@�ʂĂ͂����ɂ��Ȃ��Ƃ����x �i�ǂ��܂ł����ɐS������ł����A���̉ʂĂɎ��̐S�͂ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂��낤�j �w�����̉����͂�Ȃ�R���Ɂ@���т����Y�ӂ�品i�Ђ��炵�j�̐��x �i�����̉�����̂���R���ɁA�₵����Y����q�O���V�̐������������j �w�r��n�鑐�̈��ɉk�錎���@���ɂ����ĂȂ��߂邩�ȁx �i�r��ʂĂ����̑����ɍ������ތ������A���ɉf���Ē��߂Ă����j �w���т����Ɋ��ւ���l�̂܂�������ȁ@���Ȃ�ׂޓ~�̎R���x �i�~�̎R���Ŏ��Ɠ������₵���Ɋ����Ă���l������A������ׂē~������̂Ɂj �w�������̖̗t�ݕ����ā@���͌����ƖK�Ӑl�����ȁx �i�����͂�����̗t�ݕ������������Ă���ƁA�N���ƈꏏ�Ɍ������Ȃ��Ǝv���̂��j �w�J�̊ԂɂЂƂ肼�������Ă肯��@���̂ݗF�͂Ȃ����Ǝv�ւx �i���̒n�ɗF�͒N�����Ȃ��Ǝv���Ă�����A�J�ԂɂЂƂ菼�������Ă����j �w�S���ΐ[���g�t�̐F�ɂ��߂ĕʂ�䂭��U��ɂȂ��ށx �i���̐S��[�g�̍g�t�̐F�ɐ��߂ĕʂ�܂��傤�B�U��Ƃ͂����������Ƃł��j �w���̉��͂��т������̗F�Ȃ��@��̗��̐₦�Ԑ₦�ԂɁx �i�琁���t���鋭���̒��ɁA���X���������̉��͎₵�����̗F�Ȃ̂��j �w�ЂƂ�Z�ވ��Ɍ��̂��������́@�Ȃɂ��R�ӂ̗F�ɂȂ�܂��x �i�Ƃ�₵���Z�ވ��ɍ������̌��́A�܂�ŎR���̗F�̂悤���j �w�Ԍ�����̂��͂�Ƃ͂Ȃ���ǂ��@�S�̂������ꂵ���肯��x �i���̉Ԃ�����ƁA����Ȃ����̉����ꂵ���Ȃ�̂ł��j �w�t���Ƃ̉ԂɐS���Ȃ����߂ā@�Z�\�i�ނ����j���܂�̔N���o�ɂ���x �i�v����60�N�]��A�t���Ƃɍ��ɐS���Ԃ߂��Ă����Ȃ��j �w�g��R�Ԃ̎U��ɂ��̉��Ɂ@�Ƃ߂��S�͂���҂�ށx �i�g��R�̎U�������̉��Ɏ��̐S�͒D��ꂽ�܂܁B���̍��͍��N������҂��Ă���̂��낤�j |
���a�� ����/Shikibu Izumi ���v�N�s��970�H�| �i���s�{�A������A���S�@�j2002��03��14
 �@
�@
 2002 |
 �Ƃ��낪�c |
| ��J�̒��A�������͂��Ĕޏ��̘a�̂���ĂɘN�ǁI | ��������̉̔肾�������ƂɋC�t���I |
 2003�@���x���W�I |
 ����Ƃ炷�����肪������ |
 |
| ���N�A��Q�ɍă`�������W�I���x�����ޏ��̂���B ��N�̉̔�Ƃ͑傫�����܂�����������I |
��O�ɂ͎����ɕϐg�ł���g��o���Ŕh���I�܂����A����� ����������Ȃ��^�C���g���l��������ȏꏊ�ɂ������Ƃ� �i�������܂��^�V�����j�I����ȕ�n�͐��E�ŃR�R�����I�V�I |
 |
 |
 |
| ������͋��s�{�ؒÐ�s�ɂ���1.3m�̌ܗ֓� | �n���Ɂu�ؒÏo�g�ŗ]����ؒÂʼn߂������v�Ɠ`�� | �u���Âݎ�����v�ƐΕW�i2014�j |
| �����\���@�֎ԁA�����ŋ��̏�M�I�̐l�E�a���B���ꌧ�n���̕��Ő��܂��B�a���̐��N�ɂ͏������邪�A970�N�O��̂悤���B�ޏ��͓�\���A�{�d�����Ă������e�̕����ƌ�������i�v�̊��E���a��炾�����̂Ŕޏ����w�a���x�ƌĂꂽ�j���A�ːF�����������ޏ��ɓV�c�̑�O�c�q���x�^����B�����͕v�Ƃ̊Ԃɖ����������Ă����ɂ��S�炸�A�������Ă܂ł��̈��������B���e�́u�悭�����𗠐肨���āI�v�ƌ��{���A�ޏ��͗��e���犨�����ꐢ�Ԃ�������w���������l�ɂȂ����B ����قǂ܂łɑS�g�S��𒍂������ł��������A�ߎS�Ȏ��ɂ킸��1�N�]��ő��肪26�ő��E���A�ޏ��͈�l�ڂ����ɂȂ��Ă��܂��B������̍��A�ߒQ�ɕ���ޏ��ɔM���z����ł��������̂́A�Ȃ�Ǝ���O�c�q�̒킾�����B�����̐S�͔R���オ��2�l�̒��͋}���ɐi�ށi���܂�̒����Ԃ�ɒ�N�̐��܂͓{�苶�������Ă��܂��قǁj�B���̋��M���̌o�߂�10�����ɂ킽���ĒԂ������̂��u�a�����L�v���B�������I���̃��������C����5�N�ԂŏI����Ă��܂��B��N��27�Ƃ����Ⴓ�ŕa�ɓ|�ꂽ����ł������c�B ���ׂĂ������Ĉ����������2�x�����ʂ����ޏ��B���̋ɓx�̐�]�Ɣ߂��݂̋��т́u�a���W�v�ɒǓ��̉̂Ƃ��ĕS��ȏ�����ݍ��܂�Ă���B�ӔN��20���N��̕��l�E�����ۏ��ƍč��������A�����ɂ��旧����A1027�N�i60���H�j�̘a�̂��Ō�ɔޏ��̋L�^�͗��j��������Ă��܂��Ă���B �g���ɕx�l������ޔޏ��́A���Â����������������ȉ̂�5��Љ�悤�B �u���炴��̂�̊O�̎v�Џo�ɍ��ꂽ�т̂��ӂ��Ƃ����ȁv�i�S�l���ŗL���j ��/�j�āA�������Ⴂ�����c���̐��ւ̎v���o�ɂ��ƈ�x�����M���ɉ���� �u���납�݂݂̂�������炸�����ӂ��܂Â�����肵�l���������v ��/�����������܂܂Ɏ������������Ă���ƁA���ɗ��ėD���������������łĉ��������M������������ �u�ʂ�Ă������s�ɍ݂肵�����Ƃ��̂��т̐S�n��͂����v�i�������v�ցj ��/�ʂ�ĕ�炵�Ă��Ă��A�����s�ɂ���̂Ȃ炱��ȋC�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂� �u�Ȃ����̂ЂƂ��ɂ��������ʂ͐S�X�ɕ��₩�Ȃ����v ��/�����̐����ЂƂ������ɕ������Ȃ��̂́A���ꂼ��̐S�ɈႤ�߂��݂������Ă��邩��Ȃ̂ł��傤 �u�����Ђ��₠��ĖY��ʂ��̂��g�����݂������݂ɂȂ��ޕ��Ƃ́v ��/�v���Ă��݂Ȃ������c�����g�̐g�̂����Ȃ��̌`���ɂȂ�Ȃ�āc �a���̎���A�ޏ��̈������������s���莛�̓����A�u�����̓`������蕨�ɏ��������܂Ȃ��������v�i���c���j�j���Ƃ�A�ޏ��玩�g���a���̖��Ŋe�n���s�r�����ׁA�����̕�Ɠ`��������̂��A�k�͊�茧�k��s�����͋{��E����܂�15�����ɋy�Ԃ��ƂɂȂ����B�{���̎����̕�Ƃ��ėL�͂Ȃ��̂́A���Ēn�����������s�{���y�S�ؒÒ��̂��́A�����̍č����肪�Z��ł������Ɍ��쐼�s�ɋ߂��ɒO�s�̂��́A���s�s������̐��S�@�i���傤����j�̂��̂����A�Ō�ɂ��������S�@�͎���������Z�E�߂Ă���A�ł��M�ߐ��������Ƃ���Ă���B |
������ ���/Teika Fujiwara 1162-1241.8.20 �i���s�{�A�㋞��A������ 79�j1999��2005��10
 |
 �@ �@ |
| �`���̉̐l�I |
�u���A�˔\���ĉ������c�I�v��Ƃ��S�l����I�肵���n�A ���s�E���q�̎��J���ՂɂāA�䂪�g�̕��˂̂Ȃ�����Y�i2005�j |
 |
 |
 |
| 1999 �������ɂāB���r���� |
2005 �����Ԃ��������Ă��� |
2010 �[�z�𗁂т��� |
�u���Ђ����Ɓ@��Ƃɏł���@���̒n�Ɂ@�Ȃ��Ȃ�������@�ЂƂ肩���Q�ށv�i�Ȃ�̃R�b�`���I�j
 |
| �������Ɓi���q�j�A�����`���i�����j�A�ɓ���t�i�]�ˁj�I���ゲ�Ƃ̕�̌`�̈Ⴂ���悭�킩��i2010�j |
 |
 |
 |
 |
| �ޗǂ̖����E���J���ɂ���ƒ˂����� |
��������ƒˁB���E�̂ǂ��炩�������r�� �̔�Ȃ��Ǖ������Ĕ��ʕs�\������ |
�u��Ɓv�Ɠǂݎ��� �i2008�j |
���Ȃ݂ɒ��J���̒����K�i �͉��ߊ������������Ȃ� |
| ���q�����̉̐l�B���͐�ژa�̏W���i�����̐l�����r���B�c���̍����畃�ɉ̂̎w�����A�܂����s�@�t�╽���x��Ɛe���������A�V���̉̐S�ɖ�����������B1178�N�A16�ŏ��߂ĉ̍��i�������킹�A�a�̃o�g���j�ɎQ���B1180�N�i18�j�A�����������������̑������u���B���̔N�����Ƃ͓��L�w�����L�x��73�܂�56�N�ɂ킽���ď����Â�B���̍ŏ��̔N�ɂ������u���㗐�t�Ǔ����j���c�g���A�V�����[�Y�B�g�����^��K���j��Y�v�B�g���Ԃł͔����ҁi���Ɓj��Ǔ�����ȂǂƑ����ł��邪�A����Ȏ��͂ǂ������Ă����B�g���i����̊��j���f���Đ푈���悤���A���̒m������������Ȃ��h�B�Ⴋ��Ƃ́A������a�̂̐��E�����߂�ׁA�Ǎ��ɉ䂪�����s���Ɛ錾���Ă���B���N�A���̌��t�̒ʂ��19�Łw���w�S��x���A20�Łw�x�͑�S��x���r�B���̓��e�̑f���炵���ɁA���E�r���͊��܂ɂނ��Ƃ����B ��Ƃ͓V�ˌ^�ɑ�������^�C�v�̐��i�ŁA�̐l�ɂ����Č��̋C�������A1185�N�i23�j�A�{���ŏ�������s�ɕ��J����ĉ��肩����A���E����Ǖ������Ƃ����������N�����i���̖z����3������ɋ����ꂽ�j�B���N�A���Ƃ��d�m�Y�ŖŖS�B�V���̕ϓ��ɖڂ����ꂸ�n��ɑł�����ł������A��Ƃ̉̕��͑T�ⓚ�̂悤�ɓ���ƁA���Ԃ���u�B���i����܁j�́v�Ɣ��ꂽ�B�ނ͂���ɋ������A24�̎��ɐ��s���犩�߂��āw�Y�i�ӂ��݂�����j�S��x���r�݁A�����ɖ��́u���킽���ΉԂ��g�t���Ȃ��肯��Y�̂Ƃ܉��̏H�̗[��v�i�Ԃ��g�t�������Ȃ��H�̗[���ɒ��ފC�݂̋��t�����j�����߂��B 1188�N�i26�j�A���̎�ɂ��w��ڏW�x��8����̗p�����B�܂��܂��̓��ɐ��i���A���E�̎��͎ҋ���Ƃɏo�d����悤�ɂȂ��ď����Ɋ��ʂ��グ�A�܂�����Ƃ̉̐l�O���[�v�Ɛe����[�߂�ɂ��Ƃւ̔�掂͏����Ă������B1193�N�i31�j�Ɂw�Z�S�ԉ̍��x�ʼnr�S��́A������35����V�Í��W�ɍ̗p���ꂽ�B34�́w�C�̕S��\����x�ł́u���l�̑������Ԃ��H���ɗ[�����т����R�̒�i�����͂��j�v�i�[�����Ƃ炷�₵���R�̉˂������A���l���H���ɑ��𐁂���Ȃ���n���čs���j�A�u�s���Y�ދ��̕��݂ɗ��o�̕����֔M���Ă̏��ԁv�ȂǂƉr�B���̓~�A���ʐe�̃N�[�f�^�[�ɂ�����Ƃ͎��r�A��Ƃ��o���̖��͏����A�n�R���a�C�����ɂȂ�B36�A�w�m�a���{�\��x�Łu���͔~�̓����ɂ����݂܂���͂Ăʏt�̖�̌��v�i��~�̍���Ɖ��ɖ�����t�̖�̂��ڂ댎�j�A�u�t�̖�̖��̂������Ƃ������ė�ɂ킩��鉡�_�̋�v�i�t�̖�ɕ������̔@���R�����̖�����ڊo�߂�ƁA���Ȃт��_���R�̕�ʂ�Ă����Ƃ��낾�����j���r�ށB���N���q�̈Ƃ��a���B 1200�N�i38�j�A�s���Ȍ����Ŕj���ׂ��A�a�̂�������㒹�H�@�̖ڂɂƂ܂낤�Ɛ��͂��X���āw�@���x�S��x���r�݁u��Ƃ߂đ������͂�ӉA���Ȃ�����̓n��̐�̗[��v�i�n���Ƃߑ��ɍ~��ς��������U�蕥�����A���Ȃ��A����̓n����̐�̗[����j�����߂��B�ʂ����Č㒹�H�@�͂�����^�A�{��ւ̏o����������ꂽ�B���Ă͋���Ƃ̉̐l���������A���ɋ{��̐l�ƂȂ����̂��B���̍��̉̂́u�����̑��̂킩��ɘI�����Đg�ɂ��ސF�̏H�����ӂ��v�i�����߂��������̕ʂ�ɗ܂̘I�����ɗ����A��������H�����g�ɐ��݂܂��j�A�u���Âˌ���炫�S�̉��̊C�撪���̂����̂��ӂ��Ђ��Ȃ��v�i���̐l�̗�߂��S��T���Ă݂�A�������������Ă��C�����߂�Ȃ����Ƃ����������B�����������オ�������̂悤�ɉ����L���b�オ�Ȃ��j�Ȃǂ�����B �㒹�H�@���o�b�N�ɂ��̒d�̑��l�҂ƂȂ�����Ƃ́A�̍��̐R���ɂȂ�ȂǐⒸ���}���A���N�A�@����V�Í��a�̏W�̑I�҂ɔC�������B��������4�N�Ԃ̍Ό��������Ėc��Ȑ��̉̂�I�肵�Ă������ƂɂȂ������A�㒹�H�@�ƒ�Ƃ݂͌��Ɉ�ƌ���������Ƃ��������Ƃ���A�D�݂̉̂������đ匃�ˁB���Ƃ����肪��c���낤�ƁA�̂Ɋւ��Ă͊�łɐ܂�邱�Ƃ�m��Ȃ���Ɓi�܂��đ����18���N���j�͉@�S�����A���X�ɊW�������ɂȂ��Ă������B ���̌�̒�Ƃ͉̂���邱�Ƃ�藝�_���̌����ɋ������ڂ��Ă����B�̘_���̎��M�̖T��ŏ��R�������̉̂�ʐM�Y������Ă����B1216�N�i54�j�A�����̃x�X�g��i�W�w�E��𑐁x�𐧍�B1220�N�i58�j�A���ɒ�Ƃƌ㒹�H�@�ْ̋��̓s�[�N�ɒB���A���{�����@�͒�Ƃ��ސT�����i�̉�̎Q�����֎~�j�ɂ����B �Ƃ��낪���N�Ɍ㒹�H�@�͊��q���{��œ|���ׂ��������i���v�̗��j�A���s������A�B��ɗ�����Ă��܂����B��Ƃ̋����͈�C�ɍD�]���A�������ʂĐ��������肵���B�̒d�̑�䏊�Ƃ��ČN�Ղ�����Ƃ́A���˂Ă���ÓT��M�����Ă������Ƃ�����A����̎��̎d���Ƃ��āA�w��������x�w�y�����L�x�ȂǗl�X�ȍ�i���A�㐢�̐l�X�ɐ��m�ɓ`����ׂɕM���Ƃ��Ďʂ��܂������B 1232�N�i71�j�A��x�͓V�c���V���ȉ̏W�����悤�����A���ʂ������o�Ƃ��đI�̂ɖv���A�O�N��Ɂw�V����a�̏W�x���܂Ƃ߂������B 1236�N�i75�j�A����܂ł̉̏W����̑����Z�I�ȈӖ������Łw���q�S�l���x��I�o�����B���J���^�ɂȂ�̂͐퍑�����Ƀg�����v�������ė��Ă���B 1241�N�A79�ʼni���B����2�N�O�Ɍ㒹�H�@���B��ŖS���Ȃ��Ă����B�@�͗�����鎞�ɂ킴�킴�V�Í��̎������^��ł���A���̒n�Ŏ����D�݂́u�B��{�V�Í��a�̏W�v�����������Ă���B��Ƃ��@���A�{���ɉ̂��D���ōD���ł��܂�Ȃ������ˁB ��Ƃ̕�ׂ̗�200�N��ɖS���Ȃ�������8�㏫�R�����`���A����ɂ��̉��ɂ�600�N��ɖS���Ȃ����G�t�ɓ���t�i�┯�j�������Ă���B���Ƃ��s�v�c�Ȋ獇�킹���B �������`���̋���ЂƂЉ�w�����Â�ɂȂ����Ƃ��Ȃ��@�����Ă��@���Ƃ��������i����j�ނƂ����x�B�`�����n��������t���ɂ́A���{�ŌÂ̎l����������B |
������ ���/Senryu Karai 1718.10�|1790.9.23 �i�����s�A�䓌��A���� 71�j2002��08 ����n�n��
 |
 |
 |
| ����`3��ڂ܂ł̐���v�Ȃ̕揊 |
�������̕� |
�����Ɍ������̋�� �u�،͂��ʼn�𐁂�����v |
 |
|
| 2002�N�A���̎��͑�1��A�[�g���d�c�A�[�� �T�C�g�ǎ҂̊F����Ə��炵�܂����� |
�Ђ傤����ȕ��͋C |
| ����͔o��́u�܁E���E�܁v�`������{�ɂ��ʔ�����Εό`���Ƃ��A�G����g�킸�ɐ��̒��̕��h��@�m���y���Ȗ��킢�ł�݂��ނ��́B�n�n�����͍̂]�˒����̔o�l�E�O��t
(�܂����Â��j�̓_�ҁi�Ă�) �A�������i���炢�����イ�j�B�O��t�Ƃ́A�o�肳�ꂽ���E���̒Z��i�O��j�Ɍ܁E���E�܂̒���i�t��A�����j���q�����̂ŁA�_�҂͍�i�̗D��肷��l�B
��������1718�N�i���ۂR�N�j�H�ɍ]�˂Ő��܂ꂽ�B�c���E�V���A�ʏ̔��E�q��A���͐��ʂŐ���͍��B�ʍ��ɖ������B����Ƃ͂��Ƃ��Ƌ��s�ɏZ��ł������A�\�c���̑�ɍ]�˂ɉ���B38�̂Ƃ��ɐ̗���O�̖���̐E���p���A�����͔o�~�̏@���i�������傤�A�t���j�ł��������A���\�N�ԁi1688-1704�j���珎���̊Ԃɗ��s�����O��t�ɍ˂����B 1757�N10��7���i���7�N8��25���j�A�������i39�j���_�҂ƂȂ��ď��߂Ă̑O�啍���s�u���升�v�i�܂��킹�j���s���B�ۑ�̑O��i��l�����̒Z��j�̍�����̂�z�z���āA�ꎵ�����̕t����W�����B�D�]�āA�Ȍ�����N�u���升�v���s���s���A�T�N��i1762�N�j�ɂ͂P���傪�W�܂�قǂ̗��s�ƂȂ�A�㋉���m�܂ł������ɂȂ����B�������̑I��́u����_�v�ƌĂ�A�̂��ɕt�傪�Ɨ����Đ���ƌĂ��悤�ɂȂ�B �ŏ��́u���升�v����W�N��i1765�N7���j�A���������I��������ˌ��L�i����傤����ׂ��j���Ҏ҂ƂȂ��� 756���I�сA��W�s�������i��Ȃ�����j�t���҂��o�ł����B���ˌ��L�́A�O�傪�Ȃ��Ă��P�Ƃł��Ӗ����킩��g�t��h�������f�ڂ��Ă���A����͓����Ƃ��Ă͈ٗႾ�����B ���^��i�́u�{�~��ɂȂ��ďo�Ă����J�h��v�u�F�s�̂����������ɐe�͂Ȃ��v�u�Q�Ă��Ă��c��̂������e�S�v�u��l�̎q�͂ɂ��ɂ����悭�o���v�u�q���ł��Đ�̎��`(�Ȃ�)�ɐQ��v�w�v�ȂǁA�l��蕗�h����̃c�{����W�͐l�C���A����̗��s�ɔ��Ԃ��������B�₪�đO��Ȃ��ŕt�傪�Ɨ����Ă�܂��悤�ɂȂ����B �s�������t�͍]�ˏ����̈��|�I�Ȏx���A�������͎����ǂމs���A�I��̌���������A�u���升�v�ȍ~33�N�Ԃɂ킽���đO��t�_�҂̑��l�҂ƂȂ�A230����i�I�j���̉������W�߂Ă����B�ނ̑I�傾���Ŏ���10����ɒB�����B �������͔ӔN�܂Łs�������t24�҂̑I��ɂ��������A1790�N10��30���i�����Q�N�X��23���j��72�ő��E����B�����́q�}�i�����炵�j�₠�Ƃʼn���ӂ�����r�Ɠ`���B�揊�͗��A�����́u�_���@����E�ΐM�m�v�A�����́u������v�B�������̕��ɂ͏���v�ȂƂR��v�Ȃ̖������܂�A�E�ׂ̕��ɂ͂Q��v�Ȃ̖������ށi��������҂͌��ݔ��ʕs�\�j�B �s�������t�͔����I���1840�N�܂łقږ��N�i�v167�ҁj���s����A�]�҂⏘���̕M�҂ɂ͏\�ԎɈ��A�����k�ւ炪����A�˂��B�O�啍���s�͕������̍��u����v�̖����@�ƂƂ��ĂT���܂ő�X�p���ꂽ���Ƃ���A������܂��u����v�ƌĂ��ꌹ�ɂȂ����B ���u����v�̖��̂���ʉ������͖̂����̒����납��B ���������̋�͂قƂ�ǎc���Ă��炸�A�m���Ȃ��̂Ƃ��Ĕ���R�傪�`���B ��������I���I����A���Ɂu�Ð���v�ƌĂԁB ���w�������x���т̊��s����250�N��2015�N�Ɂg������250�N���T�h���J�Â��ꂽ�B ���u�o�~�v�͌܁E���E�܂̌`���ŋG����܂݁A�u����v�͌܁E���E�܂������Ƃ��Ȃ���G����܂܂����h�����߁A�u���́v�͒Z�̂̌܁E���E�܁E���E���ɕ��h�����߂����́B |
| ���J�W�|���I�E�������R�[�i�[�i���E�߁I�j |
�����l ���q/Kiyoshi Takahama 1874.2.22-1959.4.8 �i�_�ސ쌧�A���q�s�A������ 85�j1999��09
 �@
�@ �@
�@
 |
 |
 |
| �u���q�v�Ƃ������܂ꂽ��B �o��̂悤�ɃV���v���I |
���q�̌Â���͐ΌA�ɓ����Ă���B�߂��� �ΌA�ɂ͖k�𐭎q�⌹�����������Ă��� |
������n�Ɂu���_�ƔV��v������A �ȑO�͂����炪���q�̕�ƐM�� ����ł����i���j�B���Ԃ��Ɩ�� �����䂦�e���ɂ͊ԈႢ�Ȃ����낤 |
 �@ �@ |
|
| ��b�R�̎R���ɂ͒ܔ����u���q�V���v������i2012�j |
| �{���A���i���悵�j�B�w�����ォ�琳���q�K�̖��ƂȂ�A24�̎Ⴓ�Łw�z�g�g�M�X�x�̎�ɂƂȂ�B�u�t���⓬�u�������ċu�ɗ��v����͎q�K�̌���p�������q���A�����o�d�Ő������V�X���̔o��^���ɑR���A�����Ď�����u�狌�h�v�Ɛ錾�A�`���o������ׂ��g�ė��h�Ƃ������ӕ\�����B���q�͂܂��A���ɏ������������Ƃ�E�߂āw��y�͔L�ł���x�w�V�������x���f�ڂ����l���ŁA���{���w�̑剶�l���B |
|
�u��{�S���Ȃ������Ƃ����������v���ǂݕԂ��قǂɃE���E��
�u�ˈ�t ������Ȃ��痎���ɂ���v���₵���ƒg�����̐_�Z�z�� �u�������� ���i�����܁j���N�݂̍�@���v�������ւ̎E������I �u���̒��̈�̊������Ă�����v���ނ��W�b�Ƃ��Ă銴���ł��� �u�����O�Ƃ��ӂƂ��ւǂ��g�i�����j�ق̂��v�����Ă���ƒW���F���ق�̂�c �u������Č����Q�Ă���e�̏h�v���e���炭���ŐQ�Ă錢�A�ق̂ڂ� �u���ɐL�ьX����~���ȁv���~�̏�i�͐g���������܂邩��D���I �u���R�ɓ��̓��肽��͖삩�ȁv���Ȃ�Ėڂ̑O�Ɍi�F���L����o��Ȃ낤�I ���t���ăX�b�Q�I�I�i����ł����ċ��q�ō��I�j |
���^�� ����/Buson Yosa 1716-1783.12.25 �i���s�{�A������A������ 67�j2002

��ɍ��܂ꂽ���������ɂ��Ȃт��Ă�悤������
| �]�˒����̔o�l�E��ƁB�o�~�Ɖ�̗����������Ȃގ�l�͏��Ȃ��Ȃ����A�����͂��̑o���Ŗ����ɂ߂��V�ˁB�{���J���B�o���͍ɒ��A28����͕����𖼏��B�捆�͎ӓЁi���Ⴂ��j�B�����s�s����ɐ����B�����ɗ��e�������A10��㔼�ɂ͌̋����̂ĂēƂ�]�˂ɏo�āA21����m�Ԃ̒�q���t�Ɏ��o�l�E�锼���̖��Ƃ��Ċw��ł���B �E�s������Ēʂ�l�L�i����j�N�̎s�c�N�̐��̍Q�����]�˂̎s�ŁA���������ʐ��E�ɂ���悤�ɕx�m�����Ȃ�������ǓƂȕ����B�i22�j �E�~��������Ɏt���̐l�ʂ�c�����p�̔~�������Ƃ�Â��ɕ��ޕ����ɁA�l�X���Ԃ�������ɉ����Ă���B�i��̑����j �����͓����̍]�˔o�d�͑������Ƒn���������Ă��܂����ƒɊ����A�u�m�ԂɋA��v�Ƒi�����B���̎p���͎��͂Ƒ��e�ꂸ�u���l������邱�Ƌw�G�̔@�����v�ƋL���Ă���B 26�̎��Ɏt���v����ƁA�Ȍ��10�N�ԁA�]�˂��痣��Ĉ��ȂNJ֓��e�n�ŊG�Ɣo�~�̏C�Ƃ�ςށB�w�����̂ق����x�ɐ[���S�����Ă����ނ́A���̐��E�ςɓ���ĉ������H�܂ő��������A�m�Ԃ̑��Ղ�H�����B 1751�N�i35�j�A���s�ɓ���B �E�H���͂⑴�i���́j品i�q�O���V�j�̖����ȁc�㗌�̍ہA���݂Ƃ����m�l�ւ̋�B�g���̓���炵�h�Ǝ����̋������|���Ă���B�i35�j �s�ɓ����ăn�C���x���ȉ�ɐG�ꂽ���ƂŁA���g�̊G�M�̖��n����Ɋ����A38����3�N�ԋ��𗣂�A���R�L���ȒO��̗^�Ӂi�S��̌̋��j�ŊG�̘r���B���X�ɖ��O������Ă������ƂŁA���ɖ߂茋������l������������B �E�Đ���z�����ꂵ�����ɂ�����c��������Ɏ����A�f���ʼnĐ��n��C�����悳�I�i40�j 1763�N�i47�j�A�w�o�~�ÑI�x�Ɍf�ڂ��ꂽ�͕����̋�́g�]�˂̕��h�ɓ����Ă���A���ɗ���12�N�o���Ă��A�܂����\�҈����������B���̔N����3�N�ԁA�n���ɋꂵ�ޕ����ׂ̈ɒ�q�������F�ś����̒������Ƃ��Ă��Ă��ꂽ�̂ŁA�����͏W���I�ɛ����G��`���Ă���B 1766�N�i50�j�A���s��15�N�߂����b�ɂȂ��Ă����o�~����̒m�l���S���Ȃ�o�~�ւ̎v�����ĔR���A�L�u�Łu�O�َЁv���������B�Ƃ��낪�l���]��ő傫�ȊG�̒���������A2�N�Ԏ]��ɐg���邱�ƂɁB 1768�N�i52�j�A��ƂƂ��ẴL�����A�𒅎��ɐς݁A���̔N�ɋ��s�̕����l�ꗗ�w�����l���u�x�̉�Ƃ̍��ɖ��O�ƏZ�����ڂ�B�]��߂��������́u�O�َЁv���̊�����{�i�I�ɃX�^�[�g������B �E���O�i�ڂ���j�U��Ă��������Ȃ�ʓ�O�Ёc����Ȃɍ炫�ւ��Ă������O�̉Ԃт炪��A�O�ЂƎU���Ă���A���̂̂��͂�B�i54�j �E���i�����̂ڂ�j���̂ӂ̋�̂���ǂ���c��ɕ����������Ĉ�C�ɐ̂Ɏ����������~����v���o���B�N��B�i54�j 1770�N�i55�j�A�o�d�ł͎��͂ɐ�����Ė锼�����p���B�u�t�ɔ�ׂ�Ύ��ȂǃJ�J�V���R�v�Ƃ��������ɁA�F�l�����́u�x���l�ɑ҂���č炫�ɂ���v�ƃG�[���𑗂����B���̍�����G�ɔo���Y���č�i�Ƃ���u�o��v��`���n�߁A���̑n�n�҂ƂȂ����B 1771�N�i56�j�A���s���l��̑o���Ƃ��āA���C�o���ł�����e�F�ł��������r���Ɓw�\�֏\�X�}�x������B �E�̉Ԃ⌎�͓��ɓ��͐��Ɂc�[��ꎞ�A��ʂ̍̉Ԕ��ɂāA�����珸�肭�錎�Ɛ��ɒ��ޗ[�z�߂�i59�j �E�[���␅��i�A�I�T�M�j�����i�͂��j�����c�[���ɐ�����Ȃ����ɂ������ރA�I�T�M�̂ӂ���͂��ɐ����ł��Ă���i59�j 1776�N�i60�j�A�r�������B�����̐����̎�i�͉�Ƃ����S���������A���������܂������Ɍq���炸�A�����̎莆�Łu�������ꂵ�����ɒǂ��Ĕo�~�ǂ���ł͂Ȃ��B�旿�ƌ��n��𑗂��ė~�����v�ƒm�l�ɖ��S���Ă���B�@ 1777�N�i61�j�A���˂��Ⓒ���������o�~�W�w�锼�y�x�����s�B 1778�N�i62�j�A�����ĉ�˂��Ⓒ���������o���听������B
�E�܌��J�i���݂���j���͂�O�ɉƓc�����~�葱�����܌��J�Ő삪��͂ɂȂ��Ă���B���݂̊�2���̉Ƃ��S�ׂ�����ł���B�i62�j �E����������𗣂����̐��c�Ă̒��A���������тɉ����ЂƂЂƂ���Ă����̂��������ŋC�������B�i62�j 1781�N�i65�j�A�u�i�ŋ��́j�Ԃ₩�Ȃ邱�ƁA�܂��Ƃɓs�̕����A�c�ɂɂĂ͂܂����ɂ������ʌ��i�ɂČ�v�����̎莆���畓���͂��Ȃ�̎ŋ��ʂ��������Ƃ�������B�u�L�i���Җ��j�A���肭���A���̓V��Ȃ�B��������Ȃ�B�C�̓ŁA�ڂ����Ă�ꂸ��B�┼�i���Җ��j�A�����͑�ɓ��A��肢�����_����K�v�i�V�v�B�Ȃ��Ȃ��茵�����i�j�B 1783�N�A�H����a�ŕ����A���B�ɊŎ���67�Ŏ����B�����̋�́u����~�ɖ��i�����j������ƂȂ�ɂ���v�i���炩�Ȕ��~�̂ق̔����͖����Ă�����̂悤���j�B �����̕�͋��s���R��̋������i����Ղ����j�ɂ���B���̎��ɂ���m�Ԉ��́A���čr�p���Ă����̂���65�̎��ɗF�l�ƍČ��������̂��B�����āg�m�Ԃ̔�h�̌������ɁA�u��������Ĕ�ɂقƂ肹�ތ͔��ԁi���ꂨ�ȁ��͂�X�X�L�j�v�Ɖr���Ƃ���A���B����]�ʂ�m�Ԉ���蕶�̂������Ɏt�𑒂����B��������͖���w��F�O��}�x�̂悤�ɋ��̒������]�ł���B �o�l�Ƃ��Ĕm�Ԃ⏬�шꒃ�ƕ���ō]�˔o�~���\�����l�ƂȂ�A��ƂƂ��ď_�炩�ȕM�v�Ɖ������W�ʂő����̐l�𖣗����Ă��������B�M��ɔo�~�Ŕ|�����@�m���I�݂ɐD�荞�݁A���̔@���R���ȎR������͂��ߔ��p�j�Ɏc�錆��𑽐��c���Ă���B �����̔���̓Y�o�����Ď��R�`�ʂɒ����Ă��邪�A�����ȍ����̐��Ԃ�Ԃ��J���Ă������܂Ȃǂׂ̍₩�ȕ\���́A��Ƃ����ώ@�͂̎����B���t�Ŏʐ����Ă������ꊴ�o�͂܂��ɓV�˓I�ŁA�킸���ȕ����ŏ�i���X�P�b�`���邾���ŁA�ǂݎ�̊�O�ɔޕ��܂ŕ��i���������B�����̋�͓��{��̌���@�\���Ɍ��܂ň����o���Ă���A�O����ւ̖|��͋ɂ߂č���ƌ����Ă���B�G��̂悤�ȋ�ł���A��̂悤�ȊG��A���킦�ǖ��킦�ǖO�����ƂȂ��B ���{�����ɏЉ��12��̑��ɂ��E�ߋ傪28��܂��i���v40��I�j �y���R�ώ@��13��z �E�݂������ђ��̏�ɘI�i��j�̋ʁc�Z���Ă̖邪������ƁA���̖ђ����I�̋ʂ����炫��P���Ă����B �E�֗����č���̉J�����ڂ�����c�ւ�������ƍ��~�����J���ꏏ�ɂ��ڂ�Ă����B �E�R�͕��Ė�͉����̔��i�������j���ȁc�����̎R�X�͂�����ꂽ���A�ڂ̑O�̃X�X�L�̌��͗[�z�ɉf���Ă���B �E��i�����j�̍���Â��ɂʂ炷���J�i������j���ȁc��̑�̍��������J���Â��ɔG�炵�Ă���B�i52���j �E���ꗈ�Đ������t�̐��ɓ��c������ׂ̍��������A���܂����t�̐��ɍ������Ă����B �E�قƂƂ�����������؈�i���������j�Ɂc�قƂƂ��������������߂ɐ^���������ł����B �E������[�����i�ӂ��j�̂���c���炪�炫�ւ��Ă��钆�A�[�����̂悤�ȗ��F�̈�ւ�����S��D��ꂽ�B �@ �E��������s��G�ɂȂ����c���̓s��G�ɗ���Ă��銛��͌��Ă��邾���ŗ������Ȃ��B �E�����₤�����ʉ_���Ȃ��Ȃ�ʁc���d�������Ă��邤���ɓ����ʂ悤�Ɍ������_���ǂ����֏����Ă����i66�j �E����E�Г���������i�����j�ւ���ݍs���c�H�̗[���A������E���Ȃ�����̓�������ւƈڂ��Ă䂭��B �E��Ƃ��ċq�̐�Ԃ̂ڂ���Ɓc���₩���������q���A�����q�ԁB�������܂ŋC�Â��Ȃ��������O�̑��݊��Ƀn�b�Ƃ���B �E�܂��Ă���ђ��i�����j��ĕ�x���c��R���U�����ɓE�����r����̒��ł������قǒ������Ԃ��o���Ă���̂ɁA�܂����������Ȃ��B�ӏt�̗z�͒����Ȃ��i65�j �E�t�̊C�I���̂���̂���Ɓc�t�̊C�͈�����������g�����˂��Ă̂ǂ����Ȃ��B���g�̂���̂���h�Ƃ��������������ˁi47�j �y�S���10��z �E���~��K��Ƃ����Ӑl����c���~�ɂȂ��Ď₵���S������F��K�˂čs�����Ƃ�����A���������炱����֗��Ă��ꂽ�B�����C���������Ȃ��B �E������Ă��ʼn߂��s���锼�i��́j�̖�c��x���F�l���ނ�̋A��Ɉ���͂��Ă���A����Ă����ƌ����̂ɉ������čs���Ă��܂����B���͗F��ɑł���A��̑O�ł����Ɣw�������Ă����B�i52���j �E�������鉹���ꂵ����т����c���̃q�T�V�ɏ��������Ċ������ȁ� �E�ߓ��֏o�Ă��ꂵ����U�P�i���j���ȁc���R�ߓ��ɏo�Ă�����Ɗ������A���������͂ɂ͖�̃c�c�W���������B �E�H���ʂƍ��_�������隉�i������=������݁j���ȁc�N�V���~�����ďH�̖K���m�� �E���V�S�n��������ʂ肯��c�[��̌�������i�V�S�j�ɋP���Ă���B���͌����𗁂тȂ���A�Q�Â܂����n�����ƁX�̑O���s���B �E����i��j�̒�ɂ킪������邯���̏H�c�H�̒��A����ɂЂ����Ă̂�т莩���̑������Ă����B �E������č��i���j�ɂ��ǂ낭��~�ؗ��c�~�ؗ��̒��A�͖Ǝv���ĕ�������ƐV�N�Ȗ̍��肪���Đ����͂ɋ������i57�j���O�������ŕ�����Ȃ��̂͐l�Ԃ��������ˁB �E�g�ɂ��ނ�S�Ȃ̋���聁i�˂�j�ɓ��ށc�Q���ɂ��������ݍȂ������Ă��܂������Ƃ��Ђ��Ђ��Ɗ����� �E�g�ЂƂ���i�J�C�c�u���j�̕�������u���F�i�����j�c�g��Œu���R�^�c�ɂ������Ă��鎄�͒����������ɂ���悤���i�ŔӔN�j �y���j����5��z �E���H�a�ܘZ�R�������앪�i�̂킫�j���ȁc���̒��A���H��c�̌�a�ցA�܁A�Z�R�̕��҂��삯�Ă����i52���j �E���蓢���̕v�w�Ȃ肵���X�߁i����������j�c�s�`��Ƃ��蓢���ɂȂ�Ƃ����Ă������O�Ǝ��B�{���ɁA�悭�X�߂̋G�߂܂ł��ꂽ���̂�B �E�䂭�t��I�҂����މ̂̎�c����̉̂��I�ɂ��ꂽ�̉r�݂��A�G�߂��ς�낤�Ƃ��Ă��܂���s�������Ă���B�i52���j �E�h�����Ɠ����o���ᐁ�i�ӂԂ��j�Ɓc�Ґ���̒��A�h��݂��Ă��������Ƃ����O�ɓ��𓊂��o���Ă��闷�̎ҁB �E���~��n�i���݁j�F�i����j�������e�فi�����납��j�c���e�ق͑嗤����̋q�l��ڑ҂���ׂɑ�ɕ{���g�ɐ݂���ꂽ�Ќ���B���̍��e�ق̍L�Ԃł͑����̕��l�n�q���������A�����������n�┒�~�̍��Ŗ����Ă���B���~�̔��Ɩn�̍��̑Δ�A�F�ƍ���̑Δ�A���l�Ɠ��{�l�A�l�X�Ȏ����������������쒆�̖���B |
�u���̒��ɂ͓��ނ̐l�Ԃ������Ȃ��B�����ɋ����l�ƁA�s�K�ɂ��ĕ�����m�炸�ɏI����Ă��܂��l�Ƃł���v�i�������A��Ɓj

�w�x�ԗ}�x
 |
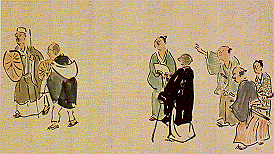 |
 |
| ������̔m�ԑ� | �w�����̂ق����}�����x�́g�������h | �w�R���}�����x�i�d�v�������j |
���R�� �Ԑl/Akahito Yamabe ���v�N�s�ځE�`�ޗǎ��� �i�ޗnj��A�Y�����A�R�ӎO�j2001
 �@ �@ �@ �@ |
| �ޗǂ̎R���ɂЂ�����Ɩ���Ԑl�̕�́A���̌��ɕ�܂�ĐÂ��ɂ�������ł��� |
| �R���h�H�i�����ˁj�Ԑl�B�ޗǑO�����\����{��̐l�ł���A�O�\�Z�̐�̈�l�B�I�єV�́w�Í��a�̏W�x�̒��ʼn̐��E�`�{�l���C�Ƌ��ɖ��������č����]�����A�唺�Ǝ��͏��ȂŁu�c������g�R�`�h��2�l���t�Ƌ��ʼn̂��r�v�Ə̂��Ă���B�Ԑl�́w���t�W�x�ɒ���13��A�Z��37��̌v50����c�����B �Ƃ��낪�A�����L���`������ŁA�{�l����镶���͑S���������炸�A�Ԑl��m���|��͉̂̐���N�Ƃ��̓��e�����Ȃ��B�킸���Ɍ����鉡��́A�����V�c�Ɏd�����������l�i���ʂ̋L�ڂ��F���j�ŁA�I�Ɂi724�N10���j�E�g�쁕��g�i725�N�j�A�d��������i726�N9���j�A��g�i734�N3���j�A�g��i736�N6���j�ւ̓V�c�̍s�K�i���傤�����j�ɏ]�������ƁA�ɗ\�E���㉷���x�m�R�A��t���s���i�����^�Ԗ��q�̕�j�֒������������ƁA�����s�䓙�@�́u�R�r�v���r��ł��蓡�����ƊW�������ł��邱�ƁA�ȏ�Ɍ�����B�o�g�n��v�N�͂܂�����������Ȃ��B �̂��r�܂ꂽ�����͐����V�c�̑�Ɍ����A������̉̐l�ɂ͎R�㉯�ǂ�唺���l�������B �R�����̈ꑰ�͑�a���쒼���̎R�ъǗ���S�����Ă���A���ׂ̈��낤���A�̂���͎��R�ւ̈����������Ă���B���i��̂悤�Ɏ��R�̌i�ς��r�ݍ��݁A������₷���ȑf�ȉ̕������ސ����A�l�X�̐S�ɐÂ��Ȋ������ĂыN�������B�ÂƓ������a���ꂽ�L���Ȏ��R�`�ʁA�D�����@�ׂɉ̂�������ꂽ���R�^�̂͂��܂ł��S�ɋ����A��̕��������̉̐l�����ɂ��傫�ȉe����^�����B ��͊z��x�i��a�x�m�j�R�[�́A�X��������R���ɂ���B���C���R�����ɉ����āA�̕��p�i���j�������Č�����2.1���̑傫�Ȍܗ֓������ꂾ�B�n��̖��͐Y����R�ӎO�i��܂ׂ���j�B���n�͂��ĎR�ӑ��ƌĂ�Ă����B��̑��ɂ͎��̉̔肪������--�w�����Ђ��̎R�J�z���Ė�Â����ɍ��͖������̐��x�i�t�̎R�J���z���āA��������ł͍��������Ă��邾�낤�Ȃ��j�B�O�т̒��ŁA�R���̂��������Ԑl�̕悪�y����ł���悤�������B ���P�H�s�����i�����܁j�ɎR���Ԑl�_�Ђ�����A�Ԑl�͐M�̑ΏۂƂ��Čh���Ă���B �����I�@7�̖��́i���t�W�j �E�w�t�̖�ɂ��݂�E�݂ɂƗ����䂼�@����Ȃ����݈��i�ЂƂ�j�Q�ɂ���x�i��8���j �i�t�̖�ɃX�~����E�݂ɗ������́A��̂��܂�̔������ɐS�D���A�Ƃ��Ƃ����𖾂����Ă��܂�����j�@ �E�w�������͏t�ؓE�܂�ƕW�i���j�߂���Ɂ@����������i���Ӂj����͍~��x�i��8���j �i��������t��E�����Ǝv���ăV���������ɁA������������Ⴊ�~�葱���Ă���j�@ �E�w�S�ϖ�i������́j�̔��̌Î}�i�ӂ邦�j�ɏt�҂Ɓ@���i���j�肵�����ɂ��ނ����x�i��8���j �i�S�ϖ�̔��̌Â��}�ɁA�W�b�Ǝ~�܂��ďt��҂��Ă������̉��́A�������n�߂Ă��邩�Ȃ��j ���S�ϖ�c�ޗnj��k����S�L�˒��S�ς̖� �E�w�c�q�i�����j�̉Y��ł��o�Č���ΐ^���ɂ��x�m�̍���ɐ�͍~�肯��x�i��3���j �i�c�q�̉Y��ʂ��Č����炵�̗ǂ��ꏊ�ɏo�Ă݂�ƁA�^�����ȕx�m�R�̍���ɐႪ�~��ς����Ă����j �E�w�ʂʂ̖�̍X���䂯�v�i�Ђ����j���ӂ鐴���쌴�ɐ璹���Ζ��x�i��6���j �i�邪�X���Ă䂭���A�v�̐����鐴�炩�Ȑ쌴�Ő璹��������ɖ��Ă����j �E�w���Ί��i����)�����i���قЁj�̓��𖾓����͉��i���j�܂����މƋ߂Â��x�i��6���A726�N�j �i���ΊC�݂̒��������������A��������͐S�ŃR�b�\�����݂Ȃ���������낤�A����Ȃ̑҂Ƃ��߂Â�����j �E�w�O���i�݂���j�́@�_�����R�i���ނȂт�܁j�Ɂ@�ܕS�}�i���ق��j�����@�����ɐ��Ђ���@�́i���j�̖́@����p���k���Ɂ@�ʂ��Â�@���邱�ƂȂ��@������@�~�܂��ʂ͂ށ@�������́@�����s�́@�R���݁@��Ƃق��낵�@�t�̓��́@�R�������ق��@�H�̖�́@�삵���i����j�����@���_�Ɂ@�߁i���Áj�͗���@�[���Ɂ@���͂Â͑����@���邲�ƂɁ@�L�i�ˁj�݂̂�������@�Ái���ɂ��ցj�v�ւx�i��3���j �i�_�̏Z�ސ_�ޔ��R�Ŗ����̎}�����Đ�����̖̂̂悤�ɁA���X�Ɛ₦�邱�ƂȂ��K�ꂽ���Ǝv���������̌Ós�́A�R�����A��͂ƂĂ��Y�傾�B�t�̓��͎R�������Ƃ蒭�߂Ă������B�H�̖�͐쉹���������A���_�ɒ߂���ь����A�[���̒��ł̓J�G���������������B�K���x�Ɏ��͐��������ċ����o�������ɂȂ�c���ĉh���Ă��������v���āj |
���� ����/Sanetomo Minamoto 1192.8.9-1219.1.27 �i�_�ސ쌧�A���q�s�A������ 26�j1999��09
 |
 |
| �̐l�Ƃ��� �����c�������R |
�����̕�͊�A�̒��ɂ���A �t���b�V���������Ȃ��ƌ����Ȃ� |
 |
 |
|
| 1999�@���q�����̕�X�^�C�� | 2009�@10�N��ɍĕ�Q�B�܂������ω��Ȃ��I | �������Ԃ��������Ă��� |
| �������Ɩk�𐭎q�̎��j�B�c���甦�B11��3�㏫�R�ɂȂ������̂́A�����͐��q�̉��E�k����ɒD���Ă��܂��B�������牓������ꂽ�����͓�����ƂɊw��ŁA�a�̂̐��E�ɖv�����w���Řa�̏W�x���܂Ƃ߂�B2�㗊�Ƃ̎q�E���łɂ����26�̎Ⴓ�ňÎE���ꂽ�B �u��C�̈���Ƃǂ�Ɋ�g�@����čӂ��ėĎU�邩���v�i�w���Řa�̏W�x�j ��Ƃ����i���ʐ�����悤�ɁA�̂Ƃ����J���o�X�Ɏ��R���r�ݍ������́A���̉̕���700�N��̐����q�K�ɂ܂ʼne����^�����B��͉������Ƃ������ɒ��������́B�ׂɂ͕v�̗��������K�ɕ~�����Ƃ���������e�E�k�𐭎q�������Ă���B |
���� ���x/Tadanori Taira 1144-1184.2.7 �i���Ɍ��A���Ύs�A���x�� 40�j1999
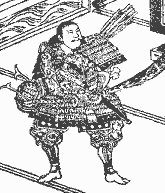 �@
�@ �@
�@ �@
�@
| �������ٕ̈ꖖ��i26�ΔN���j�B��͉̐l�����ג��̖��ƌ����Ă���B�ǂ��������������Ȃ����ǁA���x�͋��̓s�ł͂Ȃ��A�a�̎R�E�F��̑厩�R�̒��ň�Ă�ꂽ�悤���B�������a�̂�������S���p���A�R�͂̒��ł��ς��Ɉ炿�A�����̑��ƂӂƂ�������Ȓj�ɂȂ����B�F���K�ꂽ�������s�ɘA��A�����ƌ����Ă���B1180�N�i36�j�A�F����ɏA�C�B���Ɖ��������Ƃ̒��ŕ��|�ɏG�ł����x�̑��݂͋M�d�ŁA�킷��Ƃ���K�����x�̎p���������B1181�N�i37�j�̎��́u�n���i���̂܂��j��̐킢�v�ł͌����̌��s�Ƃ̎q���߂炦�镐���������Ă���B 1183�N�i39�j�A���X�ƕ��Ƃɑ��锽���E�������������A�k���E�u�ێR�Œm�x�i�Ƃ��̂�A�����̎��j�j�Ƌ��ɖؑ]�i���j�`���̌R���ƑΌ��B���̐킢�Œm�x�́A���ƈ��̒��ŏ��̐펀�҂ƂȂ����B���x�͕��Ƃ����̏t��搉̂�������́A���S�ɋ��������Ƃ�Ɋ�����B �������E��̕��Ɠ����E���@���́A�s�ɍU�ߍ���ŗ���ł��낤�`���R�Ƃ̐������A�����ւ̈ړ��i�s�����j������B�h���ւ������ƈ��͋��s�𗣂�邱�ƂɂȂ����B �u�����Ɍォ��ǂ����܂��I�v���Ƃ̈ꑰ�Y�}���_�˂Ɍ������r���ŁA���x�͔n�̂��т���Ԃ��ċ��s�֖߂����B���ɂ��`���̑�R���s�ɓ����ė���Ƃ������ɁA�g�̊댯��`���Ĕނ��ڎw�����ꏊ�́A�̂̎t���E�����r���i69�j�̉��~�B�锼�ɓ����������x�́A�x���ɖK�˂����Ƃ�l�тA�t�ɕʂ�̈��A�������B �u���ƈ��̉^���A���ɐs���܂����B����܂ł̂��ƐS���犴�ӂ��Ă���܂��B�₪�Đ��̒������a�ɂȂ�a�̏W���쐬���邱�Ƃ�����܂�����A���̒���肹�߂Ĉ���ł��̂��Ē���������h�ł���܂��v�B�ނ͘a�̂������Ԃ����������r���Ɏ�n�����B�u�����A�������ł�����c�m���ɂ��a���肵�܂����B�����S�Ȃ���v�u����ł����A�r���ɎN���Ă��A���̐��Ɏv���c�����͂���܂��ʁB����ΉɁi���Ƃ܁j�\���܂��v�u���x�a�c�v�B�r���͉��~�̖傩��A��ł̒��ɏ����Ă�����q�̔w�����A�܂��ׂČ��������B���ꂪ2�l�̍Ō�̕ʂ�ƂȂ����B ����̎����o�債�Ă������x�́A���̐��ɐ������Ƃ��āA�S�]��̉̂��t���ɑ������B ���ƈ��͐_�ˁA�l���A��B�ւƓs�������Ă����B��1184�N�A����������������i�`��VS�����j���Ă��錄�ɁA�����Ő��͂�Ԃ������ƌR�͕��ɁE�{���܂œ��i���A�_�ˈ�тɌ��łȐw�����B����ŋ`�������`�o�E�͗��i�̂���j�A���R�́A�����������Đ_�˂ɐi�R���A2�T�Ԃŕ��Ƃ̐w�n�ɓ��������B ���ƌR�͓����y�іk���ɍL�͈͂ȕz�w���Ђ����i�쑤�͊C�j�B���݂�JR���O�{�`�{���w�܂�7�w���Ƃ����L�����B�{�w�̓����E����i�O�{�j�̎�����̑叫�͒m���A�k��͒ʐ��A�����Đ{���̐���͒��x���叫�ɂȂ����B���ƌR�͗���ׂ�����ɔ����čԂ�h��ǂ�z���Ė��S�̑Ԑ��𐮂���B������2��7�����A�u��m�J�̍���v�̉ΊW�����ė��Ƃ��ꂽ�I ����̍U�ߎ�͌��͗��R�B���x���Ό���������̍U�ߎ�́A��̓V�ˁE���`�o�̌R�B�u�����f�Ŏ��点��I�v���x�͎���������サ�A�苭���`�o�R�ɑR�����B�����R�͓���ł�����ł��A���Ȗh��ǂɑj�܂�čU�߂����ˁA�ˌ����Ă͋|��Ɏ˂��A�Ȃ��Ȃ��h�q����˔j�ł��Ȃ��ł����B��ǂ͈�i��ނ̂�������ԂɊׂ����B���̋ύt��j�����̂��`�o�R�̕ʓ���70�R�B�`�o�͐�����U���������ŁA��s�����������A��ĎR�x�n�тɓ���A���Ƃ̐w�̑��ʂ̊R�����C�ɋ삯���肽�i���Ɍ����g�`�o�̂Ђ�ǂ�z���h�j�B �˔@�Ƃ��Đw�̓����Ɍ��ꂽ�����R�ɁA���Ƃ͑�p�j�b�N�B�u���蓾�Ȃ��I�v�킸��70�R�̊�P�����A�g��̓����Ȃ���v�h�Ɩ��f���Ă������Ƒ��ւ̏Ռ��͐�傾�����B�������`�o�����ꂽ�|�C���g�́A���ƑS�R�̑��叫�E�@��������V�c������ꏊ�ɋ߂������B�u����̂��Ƃ������Ă͂Ȃ�ʁv�ƁA�@���͂����Ɉ����V�c��{���̊C��ɔ������B�u���叫�ƒ邪�ޔ��I�H�v���̓�����m�������ƑS�R�͑�����ɂȂ����B����̓Y�^�Y�^�ɂȂ�A�e�������ɂƕl�ӂ֔s�������B �u�Ȃ�Ƃ��������B�����́A�ЂƂ܂��������̑D�ɖ߂���𐮂��˂v�B���x�͉ʊ��ɐ��������Ă������A�g�����Ȃ��Ă͎d���Ȃ��h�Ɣn���삯�Đ{���C�݂�ڎw���B �����������E�������̉��������i�������݁j��\���R���P���|�����Ă����B�u�Â���I�v���x�͔��]���Ă�����3�l��������B�����������Ђ�܂Ȃ��B�ނ͔n��������ъ|���Ă����B���x��������3�x�ł�������Ɖ����͗��n�����B�����Ē��x���g�h�����h�����Ƃ������̏u�ԁA�w�ォ��삯����������z���̎ᕐ�҂����x�̉E�r��I����藎�Ƃ���--�u�s�o�I�v�B �g���͂₱��܂ł��h�B���x�͕������������B�u�����҂āB���ܔO����������B�I�������a��v���������āA����ɏ�y������Ƃ��������Ɍ������ĔO�����������u�����ՏƁA�\�����E�A�O���O���A�ێ�s�́v�B�����͌�납�����͂˂��B �����͑��肪�N���m��Ȃ��B�u���̉ؗ�Ȑg�Ȃ�͕��ƈ��ɂ͊ԈႢ�Ȃ����낤���c�v�B�ނ���������Ƃ���ƁA�����ⷁi���т�A�����j�Ɏ��Ђ�����Ă��邱�ƂɋC�Â����B�����ɂ́u���h�̉ԁv�Ƒ肵�āA���̈������Ă����B �E�u�s������� �̉������� �h�Ƃ��� �Ԃ⍡���� ��i���邶�j�Ȃ�܂� / �F���璉�x�v �i����œ�����ꂻ�����B���̖؉A���h�ɂ���Ȃ�A�Ԃ������̏h�̎�l�ɂȂ�̂��Ȃ��j �g���x�I�H�h�����������͓���Ŏ�������グ�A�u��͎F���璉�x���������I�v�Ɩi�����B���������̒��x�͕��m�̊ӂƂ��ė��R�ɖ����m���Ă���A�u���|�ɂ��̓��ɂ����o���Ă���ꂽ�叫�R�ł������̂Ɂv�ƁA��̉^���Ƃ͂����A���̎���ɂ��ݓ��ސ������w�c���畷�������B �������͂��̐�̌�A���x�̕����ׂɁA�̋��̍�ʌ��[�J�s�̐��S���ɋ��{�����������A�����̉̂ɉ�����悤�ɍ��̖Ŏ�����͂B �y�킢�I����ā`��m�J����̑����z ����i���c�G���A�A�O�{�j�c�叫�E�m���i�E�o�j/�����E�d�t�i�����Ђ�A�ߗ����a��j/�����E�m�́i�����jVS���͗� ����i�{���G���A�A��m�J�j�c�叫�E���x�i�����j/�����E���i�����jVS���`�o �k��i���c�G���A�j�c�叫�E�ʐ��i�����j/�����E���o�i�E�o�j/�����E�o���i�����j�A�Ɛ��i�����j�A�o�r�i�����j�A���r�i�����jVS�����A���R ���Ƒ��ɂƂ��āu��m�J�̍���v�́A�m���Ƌ��o���������т������ŁA��ȕ�����11�l��9�l�����S����Ƃ�������Ȑ킢�ɂȂ����B���̒m���Ƌ��o��1�N��ɒd�m�Y�̊C���֏����Ă������B ���x�̎���3�N��i1187�N�j�A���a�ɂȂ������̒��œ����r���́w��ځi�����j�a�̏W�x�������������B�r�������x���琶�O�Ɏ���������͌`���ƂȂ��Ă��܂����B�����ɂ͗D�ꂽ�a�̂������r�܂�Ă���A���̌��ĂĂ�肽���Ǝv�����B�����A���Ɍ����̓V���ł���A���Ƃ̉̂����̘a�̏W�ɍڂ��邱�ƂȂǕs�\���B���Ƃ͎�������G�ł���A���O�͏o���Ȃ��B�ނ͉��Ƃ����Ē�q�Ƃ̖����ׂɁA�����ꂽ�a�̂������I�сu�ǂݐl�m�炸�v�Ƃ��Čf�ڂ����B �E�u�����Q�� �u��̓s�� ����ɂ��� �̂Ȃ���� �R�����炩�ȁv�i�ǂݐl�m�炸�j �i���i�̂����g���鎠��̋��s�́A�����r��ʂĂĂ��܂������A�����R�̍��͐̂Ȃ���ɔ������炢�Ă��邱�Ƃ��j ���ƖŖS��A���q�A�����A���R�A�]�˂ƁA���܂��̕��������Ɍ���Ă͏����A�قƂ�ǂ̐l�Ԃ��Y�ꋎ���Ă������B���̒��ŁA�����x�͂��̉̂���ڏW�ɓ��������Ƃ���A�����ɗD�ꂽ�����Ƃ��č������̑��݂����p����Ă���B�i�����������A���O�ŋ��s�ɖ߂��Ęa�̂�n�����w�͂̂��܂��́j ���x�̕�͖��Ύs�́u���x�ˁv�u�r�ː_�Ёv�A�_�ˎs���c��́u���ˁv�u�r�˓��v���m���Ă���B�r�߂���Ƃ����̂͑S���ł��������B�u���x�ˁv�̋߂��ɗL���ȓV���䂪����̂ŁA���̖��O���V���������ǁA���ē��n�́u���x���v�ƌĂ�Ă����B�܂��t�߂ɂ́u���x�����v�Ƃ����Z���e���̏ꂪ����A�����ɒ��x���n���ŕ���Ă�����������B �s���x5�I�t �E�u���Ў��Ȃ� ��̐��܂ł� �v�Џo�� �E�ԐS�� ����ӂ��肩�v �i�j�āA���ł���Ď��ɂ������B�����܂ł̎v���o�́A�݂��Ɋ����E�A���̔�߂����S�����Ȃ̂��j �E�u���Ђ킽�� ���i�����j�����Ƃ� �v�АQ�� ���H�ɂ��ւ� �͂邯���肯��v �i�����Ɨ��������Ă���M���̉Ƃ́A�M�����v���Ȃ���Q���茩��A���̘H�ł������y���ɉ����̂ł��B���߂Ė��̒����炢�߂�������̂Ɂc�h���b�X�j �E�u�g�̂قǂ� �v�Ђ��܂�� �������ɂ� ���Â��Ƃ��Ȃ� �䂭�u���ȁv �i�B�����ꂸ�Ɉ��o��v�����A�ƂȂ�R����悤�ɁA�������ƂȂ����ōs���u����j �E�u���̉��� �H�̖�Ԃ��� �Q�o���� ���͂Ăʖ��� �Ȃ�������v�Ӂv �i�H�̖锼�Ɋ��X�Ƃ������̉��Ŗڂ��o�߂āA���̑������v���Ȃ��疼�c�ɐZ���Ă���킽�����j �E�u�~�i�ނ߁j�̉� ��͖��ɂ� ���Ă����� �ł̂��� ���ӂ���Ɂv �i��D���Ȕ~�̉Ԃ��A������̒��Ō��Ă��������̂��B���Ƃ��ł̒��ł��A���̈ł������قǂɂˁI�j �����x�̑��̉̂́w�Q���ޏ]�x�́u�����x���b�W�v�Ƃ��Ďc���Ă���B ���\�́w���x�x�͐�ڏW�Ŕނ��u�r�ݐl�m�炸�v�ƂȂ����̂ŁA�r���̎q�E������ƂɁg���O��t���ė~�����h�Ɨ��ޘb�B ����ژa�̏W�͌㔒�͉@�������r���ɕҎ[���������́B�g��ځh�Ƃ͐�N��܂ł��̉̏W���`��鎖������Ė������ꂽ�B�a���A���s�ȂǁA������̉̐l�̉̂��悭�����Ă���B���x�̂ق��A�o���i�˂���j���u�r�ݐl�m�炸�v�őI��Ă���B �����̖��O����u�F����v�i�����̂�j�͖�����Ԃ̉B��ɂȂ��Ă���B�ÓT�ɂ͑D�����L�Z������m���o�ꂷ�鋶���w�F����x�Ȃǂ�����A�����̍�����V�����̃l�^�ɂ���Ă���悤���B�ނɂ͎���Șb���˂��i�j�B |
���ē� �g/Mokichi Saito 1882.5.14-1953.2.25 �i�����s�A�`��A�R�쉀 70�j1991��2002��06
 �@ �@ |
| 2006�N |
 |
 �@ �@ |
|
| 1991�N�@�g�g�V��h�Ƃ��� | 2002�N | �ŏ��݂̉͊ɂ� |
| ���Ƃ��₵���Ȗg�̕�i�[���A��̕�n�c�j | ���̔N�͉Ԃ��������I�w��͑�v�ۗ��ʂ̈ꑰ |
|
�R�`���̔_�Ƃɐ��܂��B15�̎��ɐŊJ�ƈ�����Ă����e�ʂɌĂ�ď㋞���A�����w���ɐi�ށB23�A���܂��ܑݖ{���Ő����q�K�̉̏W�w�|�̗��́x�Əo��A����܂ʼn͓̂�����̂Ǝv������ł����Ƃ���A����̌��i��W�X�Ɖ̂��q�K�̍앗�i�ʐ��Z�́j�Ɋ������A������M���Ƃ�悤�ɂȂ����B���N�A�ɓ�����v�̖剺���ƂȂ薜�t���̉̂�����悤�ɂȂ�B26�A�̎��w�A�����M�x�̑n���ɎQ���B��w���ƌ�͈�҂Ƃ��Đ��_�a�̌����ɑł����݁A31�̎��Ɏt�̈ɓ����S���Ȃ��Ă���́A�A�����M�h�̒��S�I���݂ƂȂ��Ċ����B���N�A�����̋���Ȋ����������������̏W�w�Ԍ��i����������j�x�\���āA���Ԃɂ��̖������������B
39�A���̏W�w���炽�܁x�����s�A���N�����ȍ݊O�������Ƃ��ăE�B�[���ƃ~�����w����4�N�ԗ��w����B�A����A�{���̐R�]�a�@���S�Ă��A�ނ͉@���̐E���p���Ő��_�Ȉ�Ƃ��čċ��ɓw�͂����i�H�열�V��̎厡��ł��������j�B64�A��ōēx�a�@���Ď��������ƂƂ���ɑ����s��Ŕ߈��ɒ��ޖg�́A�Ƃ�R�`����Γc�Ɉڋ��B�m�ԉ��̔@�����X�ŏ��ƌ��������A�V���ɒ��v�ٍl����Ȃ���16�̏W�w�����R�x�̐⏥�i���O�̍ŏI�̏W�j�ݏo���Ă䂭�B
�u�ŏ��́@���ɂ��ā@�c���́@���܂����������@���̒f�Ёv
�u�ŏ��@�t���g�i��������Ȃ݁j�́@���܂łɁ@���Ⴍ�䂤�ׂƁ@�Ȃ�ɂ��邩���v�i���Ɂg�����R�h���j
69�A�����M�͂���܁B�S�����̂���70�ʼni�������B�쐫�I�ȗ͋����ƖL���Ȋ����琶�܂ꂽ�̂́A17�̏W�A18000��B�u�Z�̂͒����Ɂg���̂���͂�h�łȂ���Ȃ�ʁv�����_�������B���j�͍�Ƃ̖k�m�v�B �u�[���ȍD�l���A�������ꂽ��l�v�i�����t�v�j�ƕ]���ꂽ�A��������2�̊�����g�B�������N���o�ł�c��ȃG�l���M�[���A�܁E���E�܁E���E���̌܋�O�\�ꉹ�ŕ\����鏬�F���i�Z�́j�ɍ��߂��B��̓A�����M�̏��Ƌ��Ƀ|�c���Ƃ���A�{�l�̏��Łg�g�V��h�Ə��������܂�Ă���B
|
|
���l�̍D���Ȗg�̒Z�̂�N�㏇�Ƀs�b�N�A�b�v�I
�ӂ邳�Ƃ́@���̔����ׂɁ@�����߂��@����g�ɟ��ށ@�ӉĂ̂Ђ���i10��O���j
�̋��́@�n�}���Β��߁@���Â��Ɓ@���̉��ɋ����@������肯��i20����j ���ɋ߂��@��ɓY�Q�́@����Ɓ@���c�̊^�i���͂Áj�@�V�ɕ����i30����j �R�ӂ����@�т̂Ȃ��́@���Â����Ɂ@���ɒǂ͂�ā@����䂠��i30��㔼�j
�Ă����ƂɁ@���͗�������@���͕��ā@���̂���₦���@�ނȂ����̂͂āi40�㔼�j �����Џo�Â�@�O�\�N�́@���݂��@���ɔR���ā@������������i40�㔼�j �킪�A����@��������ԁ@�킪�q���Ɂ@���̂������Ԃ��@����АQ�ނƂ��i50����j ����݂��@����������ӂ́@��Ԃ݂�@���łɂЂ������@�N�����ʂ� �i�g51�A�H���7����ɉr�́B�H��͖g���10�ΔN���������j |
������@����/Komachi Ono 809��-901�� �i���s�{�A������A��ɗ��� 92�j2005
 |
 |
| �\��P�𒅂鏬���i���`���ԉ�j | ���� |
�嗤�̉e���������A�E�ޗǎ���Ɠ��������i�V�����j�̈ߑ��𒅂Ă������ăT�I���\��P��200�N��̕��������ɓo�ꂷ��Ƃ̂���
 |
 |
 |
| �Ɣn���ʂɌ������r���A�s���w���� | �K�i���オ�������ɂ�����̂��c | ����̏�������b�I�I |
���c���j�̒����ɂ��Ə��쏬���̕�͑S����36��������炵���B�u����ڏ����v�Ƃ����������̏����̕悪�����������{�l�̕�
�Ɠ`������Ă�����A�ʐ^���}�X�R�~���Ȃ�����Ȃ̂ŁA�F��ȏ������u�䂱���͏����{�l�v�Ɩ���������Ƃ����R�Ȃ��āB
| �����O���̉̐l�B�I�єV���w�Í��a�̏W�x�������̒��Łu�߂����ɂ��̖���������l�v�Ƃ��āA���쏬���A���ƕ��A�Տ��A�����N�G�A���@�t�A��F�����6�l�̖��������̕���]�������Ƃ���A�����͌�Ɂu�Z�̐�v�ƌĂ�����1�l�ɂȂ����B�����ɔޏ��̖��́A�C�P�����̑㖼�����ƕ��Ƌ��ɁA�����̑㖼���Ƃ��Č��p����Ă����B���@�g�̏��얅�q��c��Ƃ����̐l����⹁i�����ނ�j�̑��ŁA�o�H�S�i����ǐ^�̖��Ƃ��ďH�c������s����ɐ��܂ꂽ�Ɠ`�����Ă���B13���ɋ��ւ̂ڂ�{��ɓ���X�߁i�������j�ɂȂ����Ƃ����B �X�߂Ƃ͓V�c�̍ȁB���������Ɛ������ǁA�����̋{��ł͍Ȃɂ����ʂ������āA�c�@�A���{�A�܁A����Ƒ����A�Ōオ�X�߂������B�Ⴂ�g���̍X�߂ɂ͌�a���^����ꂸ�A��L�Ԃ̒����ŊȒP�Ɏd���������́u���v�ƌĂ�镔���ɕ�炵�Ă����B�����{��L�ɂ́A���傤�Ǐ����������Ă���������ɁA�m���V�c�̍X�߂̒��ɏ���g�q�i�������j�̖������邱�Ƃ���A�ޏ��������Ƃ�������L�͂��B���䂩��c�@�ɂȂ����҂��������Ƃ���A���������̒j���̋�����f�葱�����̂́A�X�߂����荂���ʂɂ����邱�Ƃ����҂��āA�Ƃ������ł���B ���������̈���ŁA�������X�߂ł���A�������̒j����������������Ƃ����̂�������Ȃ��B�X�߂Ƃ͂����V�c�̍ȁB����Ȕޏ�����������_�ȋM�������l������Ƃ͎v���Ȃ��B���ہA�����ɂ͛ޏ����A�я��i���˂߁A��{�Ŏd�����V�c�̐H���W�j���ȂǏ��������āA�����͕s�����B���������A���{�S���ɂ͖�30�̓s���{���Ɂu���쏬���䂩��̒n�v��100�����ȏ������A�X����{��܂Ő��a�n��I���̒n���_�݂��Ă���B���܂�ɏ�������Ă���ׁA�N�Ɉ�x�u�S�������T�~�b�g�v���J�Â���Ă���قǂ��B ���ƕ��̋����������˕t�����Ƃ����S�ǃK�[�h�̏��������A����ɂ����������������������j�͑��������Ƃ����B���ł��L���Ȃ̂��[�������i�ӂ������̂��傤���傤�j�B�ނ͏�������u�S��A���Œʂ��l�߂���_������т܂��傤�v�Ɩ���A�Г�90���i��6�L���j�̓��̂�ӗ����������Ēʂ������A���悢��Ō�̖�ƂȂ���99���ڂɑ��ɂ����ēr���œ������Ă��܂����Ƃ̂��ƁB�n���ɂ���Ă��̘b�͔����ɈقȂ�A����䉖�̊���A���������Ƃ��A�Ёi����j�̎��������Ă����Ƃ��A���ɕ�������������ŋ����Ɨ����ꂽ�Ƃ����������B�܂��A�����͏����̈���������ׂɕS��ʂ����������̂ł͂Ȃ��A���傤�NJ���vጂ��ł��Ă����̂Ŋ�������̂ɕS�邩����������Ƃ��B �ޏ��̌㔼���͂ǂ̓`�����ߎS�ȓ_�ŋ��ʂ��Ă���B�Ⴆ�A�M���̒j�������̋�����f�葱������A�ꑰ���v�����ċ��t�ƌ����A�q�ǂ����Y�ނ��A�v�ɂ��q�ɂ��旧����A��H�ƂȂ��ĘH�������܂悢�A92�Ŗ쐂�ꎀ�ʐ���o�b�h�G���f�B���O�B�܂��A�[�������̉���ɂƂ����A��H�̘V���ƂȂ��ďo�Ƃ�����̂�A�������g���H��ɂȂ��Ă��܂��b������B�����͗w�Ȃœ`����ꂽ���̂Ƃ͂����A�Â����̂ł͊��ɕ�������̂����ɍ��ꂽ���̂�����A���ۂ̕s���ȔӔN�����f���ꂽ���̂Ǝv����B�������������Ă����m���V�c��40�̎Ⴓ�ő��E�B�V�c�̌�p�ґ����ŁA���c�q�𐄂�������ꑰ�́A���������o�b�N�ɕt�������c�q�ɔs��ĉƉ^���X���Ă��܂��i���̑��c�q�̕�͋I�Əo�g�B�I�єV�������ɓ���I�������̂͂����ɂ���Ƃ����j�B 30��㔼�Ɍ̋������������Ȃ��ďH�c�ɋA��A���ɓ������Ƃ���������邪�A�S���Ŏj�ՂɂȂ��Ă��鏬�����̑唼���A�␢�̔����ł͂Ȃ��A���Ɣ�ɂȂ����V�k�̂��̂����������Ƃ���A�ӔN�̓`���̃C���p�N�g�ɂ����̂����B���s�R�ȋ�ɂ͏���ꑰ���Z�u����v�Ƃ����n��������A�����̓@��������Ƃ����ꏊ�Ɍ��ݐ��S�@������B�����ɂ͐[�������珬����z���j�����̗������u��ʁv����������Ă��镶�˂�A�������[�������̋��{�ׂ̈ɎT�����Ђ̎������������Ƃ����A�O��ڂ̞Ђ̖��Ȃǂ���B ���쏬����Ƃ���Ă���̂́w�Í��a�̏W�x�w���a�̏W�x�w�V�Í��W�x�w�V��a�̏W�x�w�����W�x�ȂǂɌ����邪�A100�����S�ɏ����{�l�̉̂ƒf��ł���̂́A�Í��a�̏W��18��ƁA���a�̏W��4��݂̂��Ƃ����B���̉̏W�ɂ͑�ʂɑ��l�̉̂�U�삪�������Ă��邻�����B�Í��W�ʼn̂��Ă���̂͂ǂ����M�I�ȗ��̉̂���B�I�єV�͏����̍앗���u���t�̍��̐������ƗD���ȉ����Q������Y�킹�Ă���v�Ɛ�^�����B����ȏ����̖��̂�9��s�b�N�A�b�v�������B �E�Ԃ̐F�� ����ɂ���� �����Â�� �킪�g���ɂӂ� �Ȃ��߂����Ԃ� �i�Ԃ������F�Ă��܂����c���v���ɒ^���ċ��������J�߂Ă���ԂɁj ���w�S�l���x�ɂ����߂�ꂽ�����̑�\��B �E�����ɂ͑����₷�߂�����ւǂ����ɂЂƂߌ������Ƃ͂��炸 �i���H�ł͑����x�߂������ɒʂ����ł����A���Ƃ���ڂ����ł������Ɍ�������������ł��j �E�F������ ����ӂ��̂� ���̒��� �l�̐S�� �Ԃɂ����肯�� �i�F�������Ȃ��܂ܕς���Ă����ԁA����͎�������l�̐S�̒��̉ԂȂ̂ł��j �E�H���� ���ӂ��݂̂��� �߂����� �䂪�g�� �Ȃ�ʂƎv�ւ� �i�S�ς��́u�O�����v�Ɉ����Ă��܂����߂����B�����Ƃ������݂����Ȃ��Ă��܂��܂����j �E�v���@�Q���l�� ������� ���ƒm�肹�� ���߂���܂��� �i�������v���Ȃ���Q���������炩�A���̐l�����ɏo�ė����B���ƋC�Â��Ă���ڊo�߂Ȃ������̂Ɂj �E��тʂ�� �g���������� ���������Ă����Ӑ������ ���Ȃ�Ƃ��v�� ���Z�̐�̕����N�G���O�͂��牓�o�ɗU���Ă��ꂽ�A���̕ԉ� �i�̂��������Ȃ̂ŁA�������̍�����Ď��R�ɗ����悤�ɁA�U���ĉ�����Ȃ�V�тɍs�����Ǝv���܂��j �E��̏�� ���Q������� ���Ɗ����ۂ̈߂� ��ɑ݂��Ȃ� �i����̊�̏�Ŗ�������ƂĂ���������A���Ȃ��̑m�߂��H�D�点�ĉ������j ����ɑ���m���Տ��̕ԉ̂����V����Ȃ̂ɑ�_�I �u�������ނ��@�ۂ̈߂́@�����ЂƂց@�����˂��Ƃ��@������l�˂ށv �i�m�߂͈�d��������܂���A��l�ňꏏ�ɐQ��Βg�����ł���j �E�l�Ɉ���� ���̂Ȃ��ɂ� �v�Ђ����� ������� �S�Ă����� �i���̐l�Ɉ����Ȃ��Ŗ�ɂ́A�F��Ȃ��Ƃ��l���ċ������̉ŐS���Ă��Ă��܂������ł��j �E�H�̖�����݂̂Ȃ肯�肠�ӂƂ��ւΎ����Ƃ��Ȃ������ʂ���̂� �i�H�̖钷�Ƃ�������ǖ��O�����ł��ˁB���������Ă���Ƃ����Ƃ����Ԃɖ邪�����Ă��܂��܂����j ���s������̕�ɗ����i�ʏ̏��쎛�j�͏���c���@�̎R�����������ꏊ�Ɍ����A�����Ɛ[�������̋��{��������B�����ɓ`���b���܂����܂����B�V���������͐l���̍Ō�ɂ����֒H�蒅���A����Ȏ����̋���c�����ƌ����u�ᎀ�ȂΏĂ��Ȗ��ނȖ�ɎN���@�������錢�̕���₹�v�B��N�A�살�炵�����������̕������Ɏv�����V��@�̍��m�E�b�S�m�s���������Ƃ����B ��ɗ����ɂ͉b�d�Ɣn���̎s���w�ʼn��Ԃ��A�Ɣn�X������5���قǕ����B�������̊ŔƋ}�ȐΒi����������A�����o�肫��Ƃ���B �������̋{��ł̐g�����X�߁i�������j���ď��������ǁA�X�߂ő��ɒ��L���Ȃ̂́w��������x�̋˚�X�߂����B ���ٖD�́u�҂��j�v�͏������ꌹ�Ƃ����B�ޏ��������̋����҂�f�葱�����ׁA���̂Ȃ��j�̂��Ƃ��u�����j�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����Ƃ̎��B �k���w���쏬���E�䂩��̒n�ژ^�x�����̓����T�C�g���Q�l�ɏ������܂����l ������i�ˊ܂ށj���H�cX2�A�{��X2�A�R�`X3�A�����A���X3�A�ȖA�Q�n�A��t�A�_�ސ�A�É��A���m�A����X2�A���sX5�A���A�a�̎R�A����A���R�A�R��X4�i�v32�����j �������a�n���H�c�A�����A��t�A����A�{�� �[�������恨�H�c�A�����A���sX3 |
 |
 |
 |
 |
| �����̉��~�Ղɂ���A�ޏ��� �g�����Ƃ�����ˁi���S�@ 2008�j |
���S�@�̗���ɂ���т� ��������ƁA�����ɂ���̂́c |
�[�������Ȃǂ��܂��̒j������ ����ꂽ���������߂�ꂽ���ˁI |
�[���������S��ʂ��������ہA������ ��������ʂ��Đ������Ƃ����Ђ̎� |
���� �ƕ�/Narihira Ariwara 825-880.5.28 �i���s�{�A������A�\�֎� 55�j2005&12
 �@ �@ |
 |
 |
| �S�l���̋ƕ� | ���̊�͍��ƈႤ����� | �\�ʁi�����j�ɁI |
 |
 |
| �\�֎��̗��R�ɂāA�؉A�ɂ������ޕ�B�f���炵�����������I�I�i2005�j | |
 |
 |
| ���s�s������E�g�c�R�̋g�c�_�Ђɂ��ƕ��˂�����i2012�j | |
���������̉̐l�B�Í��a�̏W�Œm����Z�̐��1�l�B�ÓT���E�Ŕ��l�̑�\�Ƃ����Ώ��쏬�������ǁA�ƕ��͔��j�̑�\�Ƃ���Ă���B����V�c�i�����j�A�����V�c�i����j�̑��B�����̌ܒj�Ȃ̂ō܁i�������j�����Ƃ��Ă��B���̈��ېe���́g��q�i�������j�̕ρh�ŕ����c���ɂ�����ō���V�c�ɑ�ɕ{�֍��J����A14�N��ɋ��֖߂������̗��N��825�N�A�ƕ������܂ꂽ�B
�������̎j���w���{�O����^�x�ɂ́A�ƕ����g���j�q�Ő������͎��R�z���A�o���ɕK�v�Ȋ��������w�ԋC�͂Ȃ��A����ʼn̐l�Ƃ��Ĕ��ɗD��Ă����h�ƋL���Ă���B�n���T���ʼn̂̍˔\���o�c�O���ɂ���A�����������͓I�Ȑl��������A�ނ͎���ɕ����O���̉̕���w�ɐ�����x�̎�l���̃��f���ƂȂ����B�쒆�ɂ́A����̍@�E�������q�i���������j��ɐ��̍{�Ƃ̋֒f�̈��A�����ɉ��������G�s�\�[�h�Ȃǂ��`����Ă���B 841�N�A�ƕ���16�ʼnE�߉q���ĂƂȂ蒩��ɓ���B�ȗ��A�m���V�c�̑��l�i���낤�ǁA�V�c�̋@����������舵�����j���o�āA848�N�A23�ɂ��ď]�܈ʉ��܂ŏo�����邪�A���������V�c�̑�ƂȂ��Ă���́A862�N�i37�j�܂�14�N�Ԃ����i���X�g�b�v����B
�ނ͂��̊ԁA34�̎��ɋ{����17�̕��P�E�������q�Əo����Ă���B���q�͓V�c�̏���ƂȂ���26�Ŏq���Y�݁i��̗z���V�c�j�A�ƕ��̖v��ɍc���@�ɂ܂łȂ����i������51�̎��ɑm���Ɩ��ʂ����^���ōc���@��p���ꂿ�Ⴄ���ǁc�j�B
�ƕ��͕s���Ȏ������߂�������A���a�V�c�̑�ɂȂ��čĂя��i���n�߁A�ŔӔN��879�N�i54�j�ɂ́A���l�����E�߉q�������Ƃ������E�����̗v�E�܂ŏ��߂��B�ނ͍��q�̉̉�ʼn̂��r��ł���A�o���ɂ͔ޏ��̃o�b�N�A�b�v���傢�ɊW���Ă���B ���N55�B�Ȃ͋I�L�폗�i���̂���˂̂ނ��߁j�B�q�ǂ��̓����A���t�A���̌����A�݂�ȉ̐l�ɂȂ����B
�ƕ��̉̕��͌�������M�I�ŁA���E����25�N��A�Í��W��30����I�ꂽ�B�����Ē���W�S�̂ł�86�̗p�����B�ƏW�́w���ƕ��W�x�́A�Í��W�E���W�E�ɐ�����E��a���ꂩ��ƕ��Ɋւ���̂��W�߂����́B�Í��W�̑I�ҁE�I�єV�́A�ƕ��̉̂��u����قƂ����āA���i���Ƃj�����ǂ������Ă���B�Ԃ����ڂݐF�Ă��Ȃ��A���肾�����c���Ă��銴���v�ƕ]�����B
�y���ƕ��̖���14�I�z �u�v�ӂɂ͂��̂Ԃ邱�Ƃ������ɂ��鈧�ӂɂ����ւ����������v�i�V�Í��W�j �i�l�ڂ����̂�ŗ}���Ă����z�����A���������Ƃ����C���ɕ����Ă��܂����B�����A�ǂ��Ƃł��Ȃ�I�j �u�����ł��͒��̂Ȃ���ސl���ꂸ�v�ӐS�͂܂���Ԃ����Ɂv�i�����W�j �i�ǂ����āA�����{������c�M���ւ̗��S�����Ƃ��`�������Ǝv���Ă邤���ɒ��ɂȂ��Ă��܂����̂��j �u���݂ɂ��v�ЂȂ�Ђʐ��̒��̐l�͂��������Ƃ��ӂ�ށv�i���Í��W�j �i�M���̂������ł���ƕ�����܂����I���̒��̐l�͂��̋C�����g���h�ƌĂ�ł���̂ł��˃b�I�j ������܂ő����̏����ƕ����𗬂����ƕ����g���ɖ{���̗���m�����h�Ɗ��ɂ܂��Ă���� �u�l����ʂ킪����Ђ��̊֎�͂�Ђ�Ђ��Ƃɂ������Q�ȂȂށv�i�Í��W�j �i��������ʂ��Ă��������̉Ƃ̑O�̓��ɁA�Ƃ̎҂����Ă��������A�ǂ������Ӗ��肱���Ă�����j �u�H�̖�ɍ��킯�����̑��������͂ł����邼�Ђ��܂��肯��v�i�Í��W�j �i�M���̉Ƃ��璩�A�肷�鎞�ɏH�̖�̍��I�ŔG�ꂽ�������A�������ɖ߂��ė�����̕����܂ő����G���b�X�j �u���₠��ʏt��ނ����̏t�Ȃ�ʉ䂪�g�ЂƂ͂��Ƃ̐g�ɂ��āv�i�Í��W�j �i����t���̂Ɠ����ŕς��ʂ悤�ɁA�������̂܂ܕς���Ă��Ȃ��B�M���̋C���������ς���Ă��܂����j ���D���ȏ����������z������N��ɁA�ޏ��̓@�̑O�ŒQ���Ă���B �u���̒��ɂ����č��̂Ȃ��肹�Ώt�̐S�͂̂ǂ�����܂��v�i�Í��W�j �i���̒���������Ȃ��Ȃ�A�炭����҂���������A�U��̂�߂��肹���A�̂�т�Ət���y���߂�Ɂj �u���͂�Ԃ�_������������c�삩�炭��Ȃ��ɐ�������Ƃ́v�i�Í��W�j �i��̂̐_�X�̑�ł������������Ƃ��Ȃ��B���c�삪�g�t�Ő���^�g�ɍi����߂Ă���Ƃ́j ���S�l���ŗL�� �u���݂�тʍ��͌���ƎR���Ƃɂܖ���ׂ���ǂ��Ƃ߂Ăށv�v�i���W�j �i�������̓s�Ő�����̂����ɂȂ����B�R���Őd�p�̏��}���E���Ȃ���B������h��T�����j �u����炵���[�߁i�D�P�j�ɏh����ޓV�̐�̉͌��ɉ�͂��ɂ���v�i�Í��W�j �i�������Ă�����A�Ƃ��Ղ������ꂽ�B�V�̐�̉͌��ɗ��Ă���̂�����D�P�ɏh����悤���j �����ɂ͗���ɍ�������V���Ƃ������̐삪����A�����V�̐�Ƃ����Ă���B �u�����݂������͂Ђ�ߗ܉͐g���֗���Ƃ������̂܂ށv�i�Í��W�j �i�v�������瑳���G�����x�Ȃ̂ł��傤�B�܂̐�ɐg�̂��Ɨ������قǂȂ�A���Ȃ��̋C�������܂��傤�j ���Ȃ̖���������Ă����j���u��Â�̂Ȃ��߂ɂ܂���܉͑��݂̂ʂ�Ă��ӂ悵���Ȃ��v�i���J�̐��������������鎄�̗܁B�����������G��邾���ň����p���Ȃ��̂ł��j�Ƒ����Ă����̂ŁA�ƕ��͔ޏ��̑�M�ł��̉̂�Ԃ��Ă�����B �u���������Ɏv�Ўv�͂���Ђ����ݐg������J�͍~�肼�܂����v�i�Í��W�j �i�M�������̂��Ƃ�z���Ă���̂����Ȃ��̂��A��X�ƔY��ł�����A���Ȃ��J�̕����d�v�������̂ł��ˁj ����M�̑�2�e�B���2�l�̈������n�܂�����A�j����́u�����ɍs�������̂ł����A�J���~���ĂĂ܂��Ƃɂ��܂��v�Ƃ����莆�����āA�ƕ����u�J���ȂI�v�Ƒ�M�����Ԏ��B�j�͑f�����ŗ����Ƃ����B �u���߂��Ȃ�ɂ��܂�����͂�邫�ʂ闷�������v�Ӂv�i�Í��W�j �i�����ꂽ�����̂悤�ɐe�����v���Ȃ��s�ɂ���̂ɁA���͂���ȉ����܂ŗ��Ă��܂����j ���s�Ɏ����̋��ꏊ���Ȃ��Ǝv�����ƕ��́A�����C�������L���Ă����F�l�����ƁA�����爤�m�֓��ɖ�������A�����ɂ��ǂ蒅���B��̂قƂ�ŐH�����Ă���Ɩڂ̑O�ɂ͉��q�ԁi�������j���炫����Ă����B�F����g�������h��5��������̋�ɂ��ĉ̂��r�߂Ƒ����ꂽ�ƕ��͂����̂����g���炱���/���Ȃ�ɂ�/���܂������/����邫�ʂ�/���т����������Ӂh�B�i�ɐ�����j �u�䂭�u�_�̂��ւ܂ł��ʂׂ��͏H���ӂ��Ɗ�ɂ������v�i���W�j �i���ł䂭�k�����l�u��A�_�̏�܂ōs���̂Ȃ�A�����H���������Ă���Ɗ�ɍ����Ă�����j ���ƕ��̂��Ƃ�Бz�����Ă����������a�ɕ����A�ޏ��̐e���C����`���ɗ����B�}���ʼnƂɋ삯�������A���ɑ��₦���ゾ�����B�ޏ��̍�����ɂȂ��Ď����Ă��ė~�����A����Ȉ��̎v�������߂Ĕނ͂��̉̂��r�B�i�ɐ�����j ---------------------------------------------------------------------------------- �ƕ��̈⍜��16�����ɕ������ꂽ�Ƃ����B�ł��L���Ȃ̂́A�ƕ��̔ӔN�̏Z���ՂƂ����\�֎��ɂ����B�{���̗��R��o���čs���ƁA�����̖؉A�ɏ����ȋƕ��̕悪����A�����ł͖����ɂ�����5��28���Ɂu�ƕ����O���@�v�v���s�Ȃ��Ă���B�܂��A�����̕����ɂ͍�����g�c�R�Ɍ�_���z���ꂽ�Ƃ���A�����R���̒|����ЁE�V���{�̖k���ɋƕ��˂�����B���ɁA�ޗǎs�s�ގ��A�g��̓V�쑺�A�����s��莛�A����̍��A���m�����C�s��쎛�A���m���m���s�������ɂ����˂��������Ă���B
���\�֎��̕�̑��ɂ́A�ƕ����݂������}�i�������܁j�̐Ղ�����B�ނ͑���g����C�����^���A�������ɗ��s�����C���𐆂��ĉ��ɂ���V�сA�u���Ă��v�̕������y���B���Ă��̉��ɓ�����Ɗ肢�����������v������Ƃ���A�ƕ��͉A�z�̐_�Ƃ��Đ��߂��Ă���B���ł͖��N11��23���ɂ́u���}���i�������܂���߁j�Ձv���Â���Ă���B
���\�֎���K�ꂽ���A���̑����ɂ����̂̓X�������J�̐N�m���ŋ������B���w�m�̔ނ̓p�[���[��ł��o��ǂ݁A�����ɂ̓X�������J�̕���������Ƃ̂��ƁB
�����s�̃K�C�h�{�ɂ��Ɣނ̕�͗������A�̗͂�����炵���B���̂����v�������Ȃ�ď��߂ĕ������I
|
 �@
�@
�ƕ��@�Ղ̐Δ肪���s�s�������r�ʊԔV���̃I�t�B�X�X�ɂ������c����[���I
| �s�a�̃~�j�����炢�t �E���́i���傤���j�c�a�̂̃��C���E�{�f�B�B5��7���ł����ƌJ��Ԃ��i�Œ�3��ȏ�j�A��ԍŌ��5�E7�E7�Ō��ԁB�w���t�W�x�̒���265��̂����ŒZ��7��B���ʂ͏\���傩���\���傾���ǁA�`�{�l���C����O���̍Œ�149��u�q�{(�Ђイ)�҉́v����̂��Ă���A����́g�a�̂̃G�x���X�g�h�ƌĂ�Ă���B �E�Z�́c5�E7�E5�E7�E7��5��31���ō\�������Z���B �E���́c���̂̌�ɓY����Z�́B�莆�́uP.S.�v�݂����Ȃ��́B �E�����i���傱�Ƃj�c���C���̌��t�ւ̓��ē��B�����i�܂��炱�Ƃj�Ɩ��������Ă邯�ǁA������1��A������2��ȏォ��Ȃ�B �E�|���i�������Ƃj�c1�̌��2�̈Ӗ�����������Z�@�B�v����ɃV�����B �E��c�����̒��ŁA�����悤�ȋ�╶����ׂ�\���Z�@�B �s���t�W�t 630�N������760�N���ɂ����Ė�130�N�Ԃɉr�܂ꂽ�̂����߂��ŌẨ̏W�B4500�]��20���Ɏ��߂��Ă���B�唺�Ǝ����Ҏ[�̒��S�X�^�b�t�B�V�c���珎���܂ŗl�X�Ȑl�Ԃ̐S���r�܂�Ă���A�����ɖ��������̂������B���̊|���������r�u�����v�A����������ʼnr�u�҉́v�A�G�́i�������j�ɑ�ʂ����B�w���t�W�x���g���̌��t�̗t�h�ɂ��Ă���̂́A�l���C��Ǝ���������L���̂ł͂Ȃ��A�w��ɂ���2100�]��ɋy�ԍ�Җ��ډ̂Ƃ������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �k�����̉ߒ��l ��1���u�������t�v�c629�N�̘����i����߂��j�V�c���ʂ���672�N�̐p�\�̗��܂ł����߂��Ă���B��\�̐l�́A�����V�c�A�V�q�V�c�A�L�ԍc�q�A�z�c���ȂǍc���������B�f�p�ŗ͋������ׂ̌Ñ�I�Ȕ�����������B ��2���u�l���C�̎���v�c710�N�̕��鋞�J�s�܂ŁB��\�̐l�́A�`�{�l���C�A�V���V�c�A�����V�c�A���s���l�A���Ӌg���C�i�Ȃ��̂����܂�j�A�唌�c���i�������̂Ђ߂݂��j�A�u�M�c�q�ȂǁB���̂����B���\���ɂ��l�X�ȍH�v���o�ꂷ��B���ɐl���C�͖����⏘������g���āA�S����i�������r�ݍ��V�ˉ̐l�B ��3���u�R���Ԑl�A�R�㉯�ǂ̎���v�c733�N�܂ŁB���i�̂̎R���Ԑl�A�����w�ɏڂ����������������唺���l�A�l���̋�Y���r�R�㉯�ǁA�e�n�̓`����N���ȕ\���ʼnr���������C�ȂǁA���L���ȉ̐l�������Ǝ��̋��n���̂����B ��4���u�唺�Ǝ��̎���v�c759�N�܂ŁB��\�̐l�́A�唺�Ǝ��A�}�Y���i�����̂���߁j�A�k���Z�A�������i��͂�̂������݁j�ȂǁB�헐����������Ŗh�l�̂��ڗ��B 1269�N�ɐ�o���u���t�W���߁v�ŁA�ߑ�ł͐����q�K�炪���t�W���^���A���̗���͍֓��g��A�����M�h�̉̐l�Ɏp���ꂽ�B |

�\��P�߂͐F�Ⴂ��12���̌��߁B���̒����������ÂقȂ邱�Ƃ���A����12�F�S�Ă̐F��������Ƃ��������Ȃ����B
�M�w�l�����͂��̔z�F�Z���X����X�����Ă����B���̒����͕���3�����������Ƃ̂��ƁB�Ȃ�ł���ȕ����ɂȂ����낤�H
����c �R����/Santoka Taneda 1882.12.3-1940.10.11 �i�R�����A�h�{�s�A�썑�� 57�j2006
  |
 |
 |
|
| �����ɋ�肪500��ȏ������A������܂���́g���a�̔m�ԁh | 19�̎R���� | 56�A���̑O�N�̎R���� | |
 |
 |
|
| 7�N�Ԃ��߂������w�������x�ɂ� �u�J�̓��͉J���v |
�i�q�V�R���w�O�̎R���Α� �u�܂������_���Ȃ��}���ʂ��v�Ƒ���ɕ������M�ō��܂�Ă��� |
|
 |
 |
 |
 |
| �u�������߂ĕ��̒��䂭�v �u�����������l������v |
�R���̐��a�n�B�Δ�Ɠ��唠�������� |
�����w�R���x�� ���������� |
�u��֎�|�̂Ȃ�݂Ȃ��v �u�����Ă����났�ƐQ�Ă�����v |
 |
 |
| �R��������썑���B�R������������ | �h�Ŏ��]�Ԃ���Ă���ė����� |
  |
 |
|
| �썑���̋����ɂ͂�������̋�肪����B���j�[�N�������̂́A���� �B�����B�w�썑���x�̕W�̓������ɂ���A�w��̐Βi�ɏ���Ȃ��� �����Ȃ��B���܂ꂽ��́u���̒����̂��ӂ߂����v�ƐȂ�MAX |
�R���̌̋��h�{�ɂ́A�ނ̋�肪 ��������B����͎s���̋���1���� �u�J�ӂ�̗��͂͂����ŕ����v |
|
  |
  |
|
| �u�o�l��c�R���ΔV��v�B�Ă̒��z�ɏƂ炳���R���B���ׂ͕�t�T�B �ꏡ�r���ۂ��Ƌ������Ă��������߂Č����B�������Q�{�I�����̎R���炵�� |
�{�����w�R���x�B���r��J�b�v��������� �g�[�^���T�{����O�ɁB�[�����܂���i�j |
|
��������@�F�{���E�����T��
 |
 |
  |
| �F�{�s�̕�����B�ȁE���ƈ�l���q�������� | �u��c�ƔV��v | ������̒������~���^�掏�i2014�j |
���I���̒n�u�ꑐ���v ���Q��
 |
 |
 |
| ���Q�����R�s�̎R���ΏI���̒n�ցi2008�j | �R�����l���̍Ō�ɂ��ǂ蒅�����ꏊ | �ނ͂������u�ꑐ���v�Ɩ��t���� |
  |
 |
 |
| ���̈����Љ�Ă��ꂽ�m�l�ɕ������� �u�������� ���˂����� ���͂��v |
�R���͂W������ɑ��E���� |
�ꑐ����������B��������͌㐢�ɑ��z���ꂽ �̂ŁA���̏����Ȉ��ɖ߂��\��Ƃ̂��ƁI |
|
�吳�E���a�̔o�l�B�G���܁E���E�܂Ƃ����o��̖������A���g�̃��Y�������d��u���R���o��v���r�B�{���͐���B�R�����h�{�̑�n��̉Ƃɐ��܂��B���͑��̏����߂����A���������|�җV�тɖ����ɂȂ�A����ɋꂵ��͎R����10�̎��ɁA����̈�˂ɐg�𓊂����B��˂ɏW�܂����l�X�́u�L���������A�q����͂������֍s���v�ƎR����ǂ����������A�ނ͑�l�����̑��̊Ԃ����̈�̂�ڌ����A�S�ɐ[�������c���B���E�h�{���Z����Ȃő��Ƃ�����A����c�ɓ��w�B������22�Ő_�o�ǂׂ̈ɒ��ނ��ċA������B���̍��A���Ƃ͑���������Ɏ��s���Ėv�����Ă���A���Ē����ׂ̈ɐ�c��X�̉Ɖ��~��A�ނ͕��ƎƂ��J�n����i24�j�B27�Ō����A�q�����B
10�㒆������o��ɐe����ł����R���́A28����g�R���h�𖼏���āA�|��A�]�_�ȂǕ��|�������J�n�B31�A�o���{�i�I�Ɋw�юn�߁A�o�厏�Ɍf�ڂ����悤�ɂȂ�B34�A���͂��F�߂��Ĕo�厏�̑I�҂̈�l�ɂȂ邪�A�����Ɂu��c��v���|�Y�i�𑠂̎������s����Ȃ�2�N�����Ŏ�Ɏ��s�����j�B���͉Əo���A�Z��͗��U����B�R�����铦�����R�ōȎq��A���B�ɓn�����B�����A�Ï��X�i��Ɋz���X�j���F�{�s���ɊJ�Ƃ��邪��������s�B36�A�킪�؋��ɑς��ꂸ�Ɏ��E�B37�A�s���l�����R���͐E�����߂ĒP�g�㋞���A�}���قŋΖ�����悤�ɂȂ�B38�A�F�{�ɂ���Ȃ��痣���͂�����悵���B40�A�_�o�ǂׂ̈ɐ}���ق�ސE�B��1923�N�Ɋ֓���k�ЂŏĂ��o����A�F�{�̌��Ȃ̂��Ƃŋ���ƂȂ�B 42�A�F�{�s���œD�������R���͎s�d�̑O�ɗ����͂������ċ}��Ԃ����鎖�����N�����i������ɂ�鎩�E�����ƌ����Ă���j�B�s�d�̒��œ]�|������q�����͓{���Ĕނ����͂��A����ɋ����킹���V���L�҂��ނ��~���T���i�����@���j�ɕ��荞�B���N���ꂪ���ŎR���͏o�Ƃ��čk���i�����فj�Ɖ����A�x�O�̖���i�݂Ƃ�j�ω����̓���ƂȂ����i43�j�B������ׂɑ�i�����͂j�𑱂���1�N�]���o����1926�N�i44�j�A4���ɕY���̔o�l������Ƃ�41�̎Ⴓ�Ŏ����B�R����3�ΔN���̕��Ƃ̍�i���E�ɋ������A���ւ̎v�������܂�A�@�߂Ɗ}���܂Ƃ��ƓS���������ČF�{���琼���{�e�n�ւƗ��������B���̍s��i���傤���A�H�ו��̎{������s�j�̗���7�N�Ԃ��������ƂɂȂ�A���̒��ő����̉̂����܂�Ă����B �ŏ��Ɍ��������̂͋{��A�啪�B��B�R�n��i�ގR���͗��n�߂̋����������r��-- �u���������Ă����������Ă����R�v�B �����Ē����n�����s��A46�Ŏl�����\������������B�������ł͓���̕��Ƃ̕��K�ꂽ�B1930�N�i48�j�A�v���Ƃ��낪����ߋ��̓��L��S�ĔR�₷-- �u�Ă��̂Ăē��L�̊D�̂��ꂾ�����v�u��������ĎR���C������������v�B 1932�N�A50���}�����R���́A���̓I�ɍs��̗�������ƂȂ�A��F�̉������ĎR�������S�̏����ȑ����ɓ���u�������i�����イ����j�v�Ɩ�������B���c����ɂ��߂��A������7�N�ԗ����������ƂɂȂ�B�[���͑��ς�炸�ŁA�����͋ߗׂ̐l�X����s�R�ȗ��m�ƌ����Ă������A�����Ȕo�l�E������i���������j���R�����]�������ƁA�������ł̋��ɑ����̋�F���W�܂������Ƃ���A����ɔނւ̐ڂ������������Ȃ��Ă������B ���R���̎����Ԃ�̓n���p����Ȃ������B�{�l�H���D���ւ̉ߒ��́u�܂��A�ق�ق�A���ꂩ��A�ӂ�ӂ�A�����āA���ł��ŁA���낲��A�ڂ�ڂ�A�ǂ�ǂ�v�ł���A�ŏ��́u�ق�ق�v�̎��_�Ŋ���3���������B���Ɣo��ɂ��Ắu���̂Ɏ��A�S�ɋ�A���͓��̂̋�ŁA��͐S�̎����v�ƌ���Ă���B �����Ă��̔N�A�o�Ƃ��炱��܂ł̍�i���܂Ƃ߂�����W�w���̎q�x�����s�����B��B�A�l���A�����n����������������X�A�R���̍��̕��������ɍ��܂ꂽ�B ������W�w���̎q�x�i�����j1932�N �����̒��̐�ӂ肵���� �}�ɂƂ�ڂ��Ƃ܂点�Ă��邭 �����Â���ފ݉ԍ炫�Â��� �܂������ȓ��ł��݂��� �܂����邱�Ƃ��Ȃ��R���������� �ǂ����悤���Ȃ��킽���������Ă��� ���ׂ��Ă����ŎR���Ђ����� ���ꂽ�r�ւƂ�ڂƂ܂��� �̂Ă���Ȃ��ו��̏d���܂ւ����� ���̉_�����Ƃ����J�ɂʂ�Ă��� ����Ȃɂ��܂��������ӂ�Ă��� �܂������_���Ȃ��}���ʂ� �悪�Ȃ��ł����܂Ŕg�������悹�� �����Ă����났�ƐQ�Ă����� �J����̉����N�Ƃ��� ����ӉƂ��Ȃ��Ȃ�R�ɂ͉_ �悢������悢���֏o�� �}�ւۂ��Ƃ�ւ����� �����ė��N�̕��ɑ�j��W�����s���ꂽ�B ����j��W�w���ؓ��i���������Ƃ��j�x�i�����j1933�N �������������܂��� ���b�ς����ւƂ�ڂƂ܂낤�Ƃ��邩 �����肱���艹�����Ė��ʒ������� ���������݂�ȍ炢�Ă��� �R�̂����ɂ��a�����邢�Ă��� �_���������ł悢���ɂ��� �i�A���j�Ђ��т��ɂ��ǂ��⡂ɂ悫�ɂ悫 52�A�����M�B�ɖ���]�ˌ���̔o�l�E���䌎�i�������j�̕�Q�ׂ̈ɓ��Ɍ������B�䌎�͌������ˎm�B���m���̂Ă����Q�o�l�Ō�H�䌎�ƌĂꂽ�B�������A�M�B�ɓ������Ƃ���Ŕx���ƂȂ�ً}���@�B��Q�͉ʂ����Ȃ������B���̏H�A���L�Ɂu�������҂̊�т͗͂����ς��Ɏ����̐^�������������Ƃł���B���̈Ӗ��ɂ����āA���͒p���邱�ƂȂ��ɂ��̊�т���т����Ǝv���v�ƋL���B1935�N�i53�j�A��O��W�����s�B ����O��W�w�R�s���s�i�������������j�x�i�����j1935�N �[��������Ă������֎q������ �R�̂��Ȃ��ւ������܌��������тɂ��� �������܂��n�����܂ɂ������Ȃ�܂��� ���t��ŗ��ė��l�Ɉ������ȂǂƂ��� �ӂ��낤�͂ӂ��낤�ł킽���͂킽���ł˂ނ�Ȃ� ���������G���Ƃ��Ă��������� �߂Ĉ�l�̏�q�𒎂����Ă����� �Ƃ���������������Ă͂���G���̒� �R���͑�O��W�������甼�N���8���A������i�J�����`���j�𑽗ʂɈ��ݎ��E�������N�����B�����Ă�Ԃɑ̂����┽�����Ė��f���o���A�ꖽ����藯�߂��B�N���̓��L�Ɏ��̔@�����ށu���̈�N�ԂɎ��͏\�N�V�������Ƃ�������B�V���Ă܂��܂��f���̑������Ƃ������Ȃ��ł͂����Ȃ��B������݂ĐS�̐Ǝ�i�������Ⴍ�j�A��̕n����p���������ł���v�B 1936�N�i54�j�A��l��W�w�G�����i�x�����B���̔N�͊��A�����A�V���A�R�`�A���A�����ĉ�����蕽��܂ŗ��������B�u�����܂ŗ���������ŋ���v�i����ɂāj�B ����l��W�w�G�����i�x�i�����j1936�N �����������������ƂȂ���� �Ȃ�ڂ��l���Ă��������Ƃ̗��t�ӂ݂��邭 �����邱����ɓ����Ƃ菬�����Ė��� �͂�䂭���̂��������ɂ���� ��֎�|�̂Ȃ�݂Ȃ� �������߂镗�̒��䂭 1937�N�i55�j�A���K���H�̂����D�����x�@����5���ԗ��u�B���N�A�u�M�ɂ����ɂ��̕��������܂�ƎO�����v�u���ӂ͖،͂炵�̂͂����ꖇ�v�����r������܋�W�w�`�̗t�x�����B�u���ȓ����̊������������g����������Ȃ������邯��ǁA�l��W�ł͋�����Ȃ��ł�����܂��ƍl���āA�����č̘^�����B�����������̐S���͉����Ă��炦��ƐM���Ă���v�B 1938�N�i56�j�A�ϔN�̕���ő������͋����ʂĕǂ����ꂽ�ׁA�V��������T���ė������A�R���s�̓��c����Ɏl���Ԃ���u�������v�Ɩ��t�����B�F�l�����������J�[�ŏ��S���瓒�c�܂ʼnו����^��ł��ꂽ�Ƃ����i��12�����j�B1939�N�i57�j�A1���ɑ�Z��W�����s�B ����Z��W�w�NJ��i������j�x�i�����j1939�N �ЂȂ��͊y�����e�i�ȁj�������e���ʒ��� �M������⡁i�����̂��j�����ۂ� ���̒����̂��ӂ߂��� �Ȃ�ƂȂ����邢�ĕ�ƕ�Ƃ̊� �P����܂Ȃ��w�����������肪�Ȃ� �������đ������ς��̏t �t��ɋߋE����ؑ]�H�𗷂��A6�N�O�ɔx���ŕ�Q�ł��Ȃ��������䌎�̕�ɏ�����ʂ����B���̕�O�ɂāu���敏�ł�����A�͂��܂���܂����v�B10���A�R���͎��ɏꏊ�����߂Ďl���ɓn��A�������ōĂє�����Ƃ̕�Q������B���������O�Łu�ӂ����т����ɁA�G�����ւāv�B�N�̕��ɏ��R�ŏI�̐��ƂƂȂ�u�ꑐ���v���ނ��B�R���͂��̈������āu���������Ď��˂������v�Ɗ�Ƃ����B���N�̓��L���--�u���܂�Ƃ��낪�Ȃ��ǂ���ƕ�ꂽ�v�u�����܂ł�肷���锈�����Ƃ��Ƃ��邩�v�u���Ă��錢�您�܂ւ��h�Ȃ����v�B 1940�N1���A�R����炤��F�������u�`�̉�v�������A�ꑐ���ŏ������J���B�����̓��L�Ɂu���F�͎�����m�邱�Ƃł���B���͎��̋�����낤�v�ƍ��ށB3���A��̑�l�\�����ɂ́u����ۂۂ���₵����ɂ����ӕ�̎��̂��Ɓv�Ɖr�B4���ɂ���܂ł̔o��l���̑����Z�ƂȂ����W�w���ؓ��x�i����W�Ɠ����薼�j�����s�B����W����̑S�Ă̋��莩�I���Ď��߂��B�����Ē�������B�n���̐��b�ɂȂ����F�l�����Ɂw���ؓ��x�����悷�闷�ɏo��2������Ɉꑐ���ɋA���B7���A�u�Q���܂Ō������Q��Ƃ���v�Ȃǂ��܂ޑ掵��W�w��x�����s�B 10��10���̖�A�ꑐ���ŋ��s���钆�A�R���͗��ŃC�r�L�������Ă����B���Ԃ͐��������Ė��肱���Ă���Ǝv���Ă������A���͔]�쌌�ł������B��I���ƊF�͎R�����N�����Ȃ��悤�ɋA�������A���̒m�点���������҂������ɖ߂��Ă݂�ƁA�R���͊��ɐS����Ⴢő��E���Ă����B���S�����͐���4���B�{�l�O��́g�R���������h�������B�R���͐��U��8��4���Ƃ����c��Ȑ��̍�i���c���A���̐��������čs�����B���N57�B�ŔӔN�̓��L�ɂ́u���ʂɖ��ʂ��d�˂��悤�Ȉꐶ�������A����Ɏ��������������ŁA�������琶�܂ꂽ�悤�Ȉꐶ�������v�Ə������B�����̋���u������萷�肠����_�ւ���ށv�B�����������R���́A�n�������痧�����閾�邢�_�̒��֗n������ł������B �u�O�����Ȃ��̋�Ƃ������̂͂Ȃ��Ƃ�������B���̑O�����Ƃ͍�҂̐����ł���B�����Ƃ����O�����̂Ȃ��o��͂��肦�Ȃ��v�B�R���̐����l������l�X�ɒm����ɂ�A�ނ̌����u������O�����ɂ����v��̐l�C�͂ǂ�ǂ܂�A�f70�N��O����17������������肪�A'90�N�㏉����150�����𐔂��A2006�N�ɂ�500�������Ă���Ƃ����B�l�̕��w��̐��Ƃ��Ă͎R������Ԃł͂Ȃ��낤���B�̋��̖h�{�ɂ͐��ƐՂ��c��A�s�������ŋ�肪81�������B �R���͑��E�̔��N�O�ɏo������\��w���ؓ��x�̖`���ɂ�������--�u�Ⴄ���Ď������������܂ւ���̗�O�ɖ{�������ւ܂�v�B ���� �R���͐��n�̎R�����h�{�s�E�썑���ɕ�t�T�ƕ���Ŗ����Ă���A��ɂ́u�o�l��c�R���ΔV��v�ƒ����Ă���B���B�ɓn���Ă������q���}篋A�����������B���݁A�썑���̖{���ł͎��M��∤�p�i���������J����Ă���B�܂��A���Ȃ��Z�F�{�s�E�����T���ɂ������悪����B |
������ ����/Hosai Ozaki 1885.1.20-1926.4.7 �i���쌧�������A�y�����A������ 41�j2006
 |
 |
 |
| ���w�Z�̍� | ���܂�ɑ@�ׂ����� | ���ƏI���̒n�A������ |
 |
 |
 |
| ���Ƃ���炵�����i������j�́A���w�L�O�قɂȂ��Ă���B ��̑叼�͔ނ̔o��ɉ��x���o�ꂷ�遦����2��ڂ̏� |
������C�݂܂ł̓X�O�I �u��q�����Ēu�� �C������v |
�����ɂ��������唠�B �N�Ɉ��R�������� |
 |
 |
 |
 |
| ���Ƃ̈��̋߂��ɕ悪���� | �G�߂̉Ԃ��₦�鎖���Ȃ��Ƃ��� | �r�[���E���{���E���C���A�S�������Ă�I | �������菑���́u���Ƃ���̂���v |
 |
 |
 |
|
| �����ق̕ʊق͓��鉿�l������B �����}���قŌ�����悤 |
����͋M�d�I���M�̋��莆���W������Ă����i�B�e���ρj |
||
  |
 |
 |
 |
| ���Ƃ�4�����Ԃ�ɓ������Ƃ����K���́A���ɃT���n�� �Ȃ��Ă������A�K���̊Ŕ����͋L�O�ّO�ɂ����� |
���Ƃ̈��ɂ����������B �����݂͐������{���ɂ��� |
���̓��A�e�ɎԂł��������� �ē����ĉ��������n���� I ���� |
�������̎O�d���B���� ��������Ƃ������Ă� |
|
�吳���̔o�l�B���Z�̒n�����߂ė��Q����������Ƃ́A�g���a�̔m�ԁh��c�R���Ƌ��Ɂw�Y���̔o�l�x�ƌĂ��B���҂͋��ɁA�G���܁E���E�܂Ƃ����o��̖������A���g�̃��Y�������d��u���R���o��v���r�B
���Ƃ͒���s�o�g�B�{���A����G�Y�B���͒n���ٔ����̏��L�B�q�ǂ��̍��͎����̎��͂��ň͂��A��l�œǏ�������̂��D��ł����B14����o���Z�̂����n�߁A���N�ɂ͊w�F��ɔo����Ă���B���w����̍�i�́u������̎������肯��~�̎}�v�u���ł��ĐÂ��ȉƂ�Ă�Ȃ��v�ȂǁB
����w���Ƃ܂ł͖���������o����r��ł���B 1902�N�i17�j�A�㋞���Ĉꍂ�ɓ��w���A���N������i�������E���������j�Əo��B��͕��Ƃ̈�w�N��B��Ɏ��R���o��^���̎w���҂Ƃ��ĎR������Ƃ𐢂ɑ���o���A�o�d�̏d���ƂȂ����l�����B���Ƃ͍ő�̗����҂ƂȂ��Ă��ꂽ��U�ɂ킽���Ďt�ƕ炢�A�e�������悤�ɂȂ�B 20�A����@�w���ɓ��w�B���N�A�w�z�g�g�M�X�x��V���ɓ��債�f�ڂ����B���̍��A���Ƃ��̏����ɍ��ꍞ�ނ����̋߂�����e���ɔ����ꎸ���B�N�w��@���ɂ̂߂荞�݁A�D�����J��Ԃ��悤�ɂȂ�B1907�N�i22�j�A�����u�F�Ɓv����u���Ɓv�ɉ��߂��B 24�ő��Ƃ���ƁA����@�ȏo�g�̃G���[�g�Ƃ��ĒʐM�Ђœ����n�߂邪�ꃖ���őސE�i�����͕s���j�B���q�̑T���ɑ����^�ԁB1911�N�i26�j�A�����ی���ЂɏA�E�B���N�A�����̉����̖��ƌ����B�܂����̔N�ɂ͈���厏�w�w�_�x��n�����Ă���i2�N��ɎR���A4�N��ɕ��Ƃ̋傪�f�ڂ����B���҂����ɏo���̂́w�w�_�x�����Ă����I�j�B ���ȉ��A���Ƃ̋�U�ɉ����ĔN�㏇�ɑ}�����Ă����B �ӂƂ�ς݂����Ē���|���o�� ��͐��ꂽ�鏬����̐��ɓ������� ������Ȃ��̂т���Ẳ_���ς�� ��i�ǂāj�̏�ӂƊ�o���������肯�� �킯���܂ɂ������Z�������Ŗ��킯�� �v�w�ł�����݂��ď��� ��������̏I��̏����������邭 �d���̋Ɛт͓��������D���ŏo�����Ă��������A�₪�Đl�ԊW�̃X�g���X�ɔ�ꂫ��A��Ȃł̎��s���d�Ȃ��ċΑ�10�N�ڂɕ��Ј��ɍ~�i�A������@��36�őސE�����i1921�N�j�B���N�A�V���ɕʂ̕ی���ЂɈڂ苞��i���\�E���j�ɕ��C���邪�A��1�N�ŖƐE�ɂȂ�B���Ў��̋֎��̐����j�����Ƃ��A�����̒����������Ƃ������Ă���i38�j�B���Ƃ͖��B�ōċN�����݂邪�O�N�ɔ��a�����]�������������A���n�̕a�@��2�������@�B�A����A�Ȃ�藣�������B�ނ̐l���ɂ͒��w���瑱���Ă����o�傾�����c�����B ���Ƃ͉�Ћ߂�3�x���s�������ƂŁA���Љ�ŕ�炷���Ƃ͕s�\�Ǝ��o�B���ꕨ�ƂȂ��ĔN�̕��ɋ��s�̏C�s��E�ꓕ���ɓ���A��A�J����d�A�njo�̓��X�𑗂�B ���Â��҂����䂪�e�擮�����Č��� �z�c���z�c���łɐZ��ċA�藈��l�X �˂��ׂď����ċ���莆���{�ɔ`����� ����߂�Ē����莆�������o��
1924�N�i39�j�A�~�̈ꓕ���̊����ƘJ����d�̌������ɓ��̂̌��E�����������Ƃ́A3������m���@�����E��̉@�ɓ���B�����A�������K�ꂽ�ۂɍĉ�̊�т���D�����A�킸���ꃖ���ŏZ�E�ɒǂ��o���ꂽ�B6���A�m�l�̏Љ�Ő_�˂̐{�����ɐg��u���B���ꂩ�玀�Ɏ���܂ł�2�N�ԁA��ʂ̖���ݏo���Ă䂭�B ��q���߂��ė҂������݂��� ����Ȃ悢������l�Ō��ĐQ�� �D���ƎR�̉���ɗ��ĉJ�������Ă� ���ق̒r�ɋT�������� �����ċ�����̗]�C�̒� �Q�ł����ւ����l�Ɉ�l�𓊂��o�� �킪���炾���ɂ��炨���Ă��Ԃ� ������߂�傫�ȉ������Ă������Q�� �����̖����͂Â��l�ܐl�c�ċ���
�ɂ�����v�Џo����������� �������킮�����Œ��̊����i�����j���ւ炵�ċ��� ���悿�����قǔ����ӂĂ���� �J�̊������Â����ƌ��Ă���
���ɑ������͂����H��ɕ���
���������ċ��邪���������͂�
������݂̂Ȓ��Ă��܂Е��ׂЂ��Ă���
�����҂��˂������Ă���������ɏo��
���ɓ���鎙�����ɂ��Â߂��
�Ԃ��炢����̂������炠���Ă���
�l��҂����ȍ��~�ŊC��������
�������܂ւ���Ŏ����M����o�ė��� ���̂���������������͂Ȃ��Ă�� 1925�N�i40�j�A���͑����̓����ŗh���{�����𗧂�����A5�����畟�䌧���l�̏퍂���Ɉڂ�B �����A2������Ɏ����j�Y���Ă��܂��B ����̐S�ɊႪ������Ă��� �����Ɖ��ɂȂ鍡�����I�ċ��� ��{�̂��炩����݂��Ă��܂� ������������̓y�n�̌��ƂȂ��݂ɂȂ��Ă��� �|�̎q�|�ɂȂ��Ĕ`���ɗ��鑋�ł��� �a�������ɋ��ĕԎ�����Ȃ� �����X�̂����̉�������Ђ� ���������o�ʼn��t��������ۂ� �����֕Ԏ����Ē��̖��X�������ċ��� ���ɗ��ċ��Đt�̑�~��ƂȂ�
���������̂��ʂ��� �s��������������Ƃ͋��s�ň�l��炵�������̉��ɐg�����i���2�N�O�̊֓�
��k�ЂōȎq�������Ă����j�B ���Q�̑��̂��炪�����Ă���K�� ���̂����Ȃ��̉Ԃ�k���ŌN�Ɍ����� �a�C�����ɂȂ������Ƃ͎�����\�������̂��A��Ɂu�C�̌����鏊�Ŏ��ɂ����v�Ƒi����B��͍Ȏq�ɐ旧���ꂽ��ɕH����ŏ�������K��Ă���A���̎��ɒm�荇���������́w�w�_�x��F�ɊC�ӂ̈���T���ė~�����ƈ˗������B �g�������k���̓y���Ɉ�����h�ƘA���������Ƃ́A8��20���ɓ��֓n�萼�����E�싽�i�݂Ȃj���ɂ��ǂ蒅���B�g����������낤���Ƃ����叼�h�����ɂ�����B�������I�̐��ƂƂȂ����B���j�Ƃ��ďZ�ݍ��ނ̂ł͂Ȃ��A����Ƃ��Ă̌ǓƂȕ�炵���n�܂���--�u�l�̐e�ɋ������ꍡ�邩���l�ŐQ��v�B 1926�N�A�싽���Ŕo��̑n��ɖv�����Ă����ނ́A2���ɔx���j�Ɛf�f����A���悢��悪�Z�����Ƃ����B�����ɂ͍A�̔S�������ǂ��N�����ĐH�����s�\�ɂȂ�A4��7���ɐ▽�����B�����Ŏ�����̂͗Ƃ̘V�k������l�������B���N41�B���j�ƕ������Ă���2�J�������������Ȃ������B 2����A����K�ꐼ�����ɖ��������B�����͑����Ƌ��m�B�����̋�́u�t�̎R�̂����납���|�i���ނ�j���o�������v�B����2�J����A��͕��Ƃ̖������F���ċ�W�u���i���������j�v�����s�����B ���Ƃ̎���A�싽���͋����ʂĂ����A1994�N�Ɋ��S��������w������ƋL�O�فx�Ƃ��Č��J����Ă���B�ނ̕�͓싽���ɗאڂ��鋤����n�̍���ɂ���A��O�ɂ͉ԂƎ����₦�Ȃ��B ���Ƃ͎���3�N�O�Ɏ��Љ�Ɨ���Ă���A�[���ǓƂ������ċꂵ��ł������A����Ŗ���ς����ޓ������A�B�ς������E���ȂǂŁA�t�ɋ�͍Ⴆ�n���Ă������B ���ɏ������ł�8�J�����炸�̐����̒��ŁA�a�ɋꂵ�݂Ȃ��炱�̐��ɐ����������ݕt����ׂ��A��3���Ƃ����c��Ȑ��̋���c���A�o�l�Ƃ��Ĕ���I�ɐ����𐋂����B���Ƃ͈�l�ڂ����̈��̒��Ŏ��R���o��̂ЂƂ̒��_���ɂ߂Ď���ł������̂��B ���Ō��8�J���̍�i���� �P�����Ă���l
���������ė������ƕl�ӂɋ��� �Ƃ�ڂ��҂������ɂƂ܂�ɗ��Ă��ꂽ �r�N�Ƃ����Ȃ��叼��{�Ǝc���ɂ͂���
��q�����Ēu���C������ ���̂����ւΔ����Ȃ�
�Ȃ�{���}�b�`�̖_�������C���ɘb�� �������Ȃ����Ă��܂ĒT���ċ��� �R�͊C�̗[�z�������Ă������Ƃ��떳�� �|�ւɗ[�z�������ċ���
�P��ԁi�ق����j�̎����͂˂����Č��Ă��҂��� �n��������ł��ǂė��� ��̖̔��Ɏ��Y�ւđ҂� ��q�̌�����`���Č��Ă�����ł��� ������̂���������Ŏ� �����w�̂т��Ĕ`��������
�ق�C�Ō{�����ċ��� ����̈����܂�Ƃ� ��̂���ɉ�� �����͌��������镧�Ƃ킽���� �[�Ă����H�̔��Ƃ� �͎}�ق��ق��܂�ɂ悵 ���Ƃ������� �������������Ȕ��̎� ���َq�̂������ł������K�����܂� �����߂����������쒃�� ����ł����O�ɓ����Ȃ��ł����Ȃ�� �����₹�Ă��鑾�����ł��� ��̓��ۂ�u���Ăނ��Ă��� ���X�����ė��鐶���Ă��� �t�̎R�̂����납���|���o������ �����Ƃ͎�c�R�����3�ΔN�������A14�N�������E�����B�R����2�x���Ƃ̕�ɖK��Ă���B���Ɂw�Y���̔o�l�x�Ƃ��Ēm���邪�A�R�������狁�߂ĕ��Q�̗��ɏo���g���h�̔o�l�ł���̂ɑ��A���炬�̓y�n�����߂Ă���������ς�������������r���Ƃ́g�Áh�̔o�l�ƗႦ����B |
���NjL�`�ӔN�̖����\��e���灦1996�N�ɖ�2700����������ꂽ�B �o�P�c�[�t�̌��������ݍ���Œu�� �����̂������C�ɂ��Ęb�����ċ��� �P�����邭��܂킵�čl�������Ă��� �Â��荻�����Ȃ߂��킪��̂�낱�� �Ƃ�ڂ��H�ӂ����n�̐Â����ӂ��� �z�L�Ɛ܂�̎}�悢���Ђ����� ���̏Ί������Č����Č����� �|�̗t���~�鑋�Ŏ����K���Ă��� ���J������T�l�\�j�ȂȂ� �j�ꂽ�܂�܂̏�q�ʼnĂɂȂ��Ă��� �ĂѕԂ��Č������b�������� �����������Ă�����ɗ��Ă��܂��� ���������͂Ȃ�������_ �����ċ��邤���ɔ��̐����܂���ė��� �����t�������b���œc�ɂ̖邪�X���� ���̕�ɂ͂��~�̗[�� �F�X�v�͂��ᒠ�̂Ȃ������Ƌ��� �X�̓������������Ă���ڂЂɂ͂��� �V�炵���B��ł��ĉĖX�������� ���ނ�ɍs���������������Ȃ����� �܂�����Ȃ킪���̒��ɋz�͂�� ����͂��Ă��܂��Ă���C�����Ă��� �O�����������ނ��ڂ蕗�ׂ��Ђ����� ���������͂ǂ��֍s���ėV�������̒� �~�x�݉J�ƂȂ�ʓ��̏������ƁX ���̓y�ƂȂ�Ă��~�ɎQ���ċ��� �����Ƃ̖����M�w�x�����ďЉ��B�ނ��g�h�̑f���炵������M�I�Ɍ���Ă���B ����̓��[���A�������Ė{���ɑf���炵���G�b�Z�C�Ȃ̂Ő���I�i�Z����I�j �����E�ߎQ�l�T�C�g http://www2.netwave.or.jp/~hosai/�@������ƋL�O�� http://homepage2.nifty.com/onibi/housai.html�@�N�㏇�S��W |
������ �/Takamura Onono 802-852.12.22 �i���s�{�A�k��A�������揊 50�j2008
 |
 �@ �@ |
| �e�r�e�։� | ����̌Â��˂�⹂̕�B���Ȃ݂ɁA���̎������ƕ悪����ł���I |
| ����⹁i�����ނ�j�͕��������̉̐l�E���w�ҁB���얅�q�̎q���ŏ��쏬���̑c���ɂ�����B腖��̑��߂Ƃ��`����Ă��邪�A�����ƂȂ����͓̂����̉E��b�E�����Ǒ��i�ӂ����̂悵��/813-867/����b�E�����~�k�̌ܒj�j�̘b�B�����Ǒ��͗Վ���ԂɊׂ�������腖��{�ŏ���⹂ɏo��A�ނ������Ԃ点�Ă��ꂽ�ƍ��������B�����A���Ǝv���������Ǒ����h���������Ƃ���l�X�͂��̏،���M�����B�ł͂Ȃ�150�N��Ɋ����������ƕ悪�אڂ��Ă���̂��B���������ʂƁA�ޏ��͏����Ől�S�����Ԃ炩�����i�U����j�߂Œn���ɑ��A�����̓ǎ҂����߂Ƃ����\���������ɗ��ꂽ�B⹂ɂ�腖��剤�̑��߂Ƃ��������`�����������ׁA�l�X�́g腖��Ɩʎ��̂���ނȂ玮�����~���Ă����n�Y�h�ƍl���A���אڂ������Ƃ̂��Ƃ��B ��⹂͒���ᔻ�̎��������č���V�c�̋t�ɐG���ȂǁA�����̐��_�̎�����ł��������B ���Ǒ��͊w���ł���������⹂��߂�Ƃ����ۂ����ٌ삵�������������B��ɗǑ��͕a�Ĉ�U�������n����腖��剤�̖ڑO�Ɉ����������邪�A腖����{�̐b�Ƃ��čٔ�����`���Ă���⹂̎��萬���ɂ���Ď͂��ꖻ�E����A�҂����Ƃ����B |
������ ���/Seisensui Ogiwara 1884.6.16-1976.5.20 �i�����s�A�`��A������ 91�j2008
 �@
�@
| �{���E�����Y�̂����g�B�������܂�B���w����o����n�߂�B���啶�w�����ƌ�A1911�N�i27�j�A�V�X���o��@�֎��w�w�_�x����ɁB�G����g�킸�Ɏ��R�̃��Y�����d���������R���o����r�B���N�A���̋�W�w���R�̔��x�����s�B���̍�����w�w�_�x�ɂ͎�|�ɋ�����������Ƃ��c�R���������B���ƂȂ������Ƃ��R�����n�����j�œI�Ȑ����𑗂��Ă���A��͔ނ�̋���w�����邾���łȂ��A��������������ׂɖz�������B91�������剝���B |
����R �q��/Bokusui Wakayama 1885.8.24-1928.9.17 �i�É����A���Îs�A��^�� 43�j2006
 �@
�@ �@
�@
| ���Ɨ����������̐l�B�{�茧�o�g�B�{���A��R�ɁB18�̎��ɍ���q���Ƃ����B1908�N�i23�j�ɑ���c�𑲋Ƃ��A��1�̏W�u�C�̐��v�\�B�Q�N��ɉ̏W�u�ʗ��v�����s���A���R��`�̐l�Ƃ��Ęb����W�߂�B1912�N�i27�j�A�e���̂������ΐ��̎����Ŏ�����B���N�A��u�q�ƌ����B1920�N�i35�j�A��{�����̌i�ςɖ��������ÂɈڏZ�B1923�N�i38�j�A�̏W�u�R���̉́v�𐢂ɑ���B�q���͈���ꏡ�̎��𗁂т�悤�ɓۂ����ŁA�̍d�ς̂��߂�43�ő��E�B���t�W�������A�̂̃X�^�C���͑f���������B��i�͐l�X�ɐe���܂�A�����悭�������Ƃ�����{�e�n�ɉ̔肪���B�����͌Ï��@��_�q�����m�B ���w��R�q���S�W�掵���x���� �킪�����ɂ��̋��邱�Ɩ̎}�ɋ��̐��ނ�肤�炳�т�����
���������̏��ɛ����߂Ă��Ɛg�̌ċz�i�����j���邱�Ƃ̂����ɂ��т���
��C�̂Ђт��Ɏ�����Ȃ������킪��̑O����f�i�Ђ��j�ɂ��܂�
|
������ �ꒃ/Issa Kobayashi 1763.5.5-1828.11.19 �i���쌧�A�㐅���S�M�Z���A���ێR��n 65�j2008
  |
 |
| �u�j�ՁE���шꒃ����v�B��Ύ��ŏĂ��o���ꂽ�ꒃ����������������u�I���̓y���v | JR���P�w����߂��u�ꒃ�L�O�فv |
  |
 |
| �ꒃ�L�O�ق̗���ɂ���o�~���ƈꒃ���B���̉��ɕ悪���� | �u�����ɌË������ė܂��ȁv |
 |
 |
 |
| �������ς��̈ꒃ�̕�I�ڈ�̋���Β��ł����ɕ������� | ���щƈꑰ�̕�ɍ�������Ă��� | �u�o�~���@�ꒃ����v |
 |
 |
 |
| �u���炪���� ������̑��� �݂ɂȂ�v�i�ꒃ�j ���̃��[���A���ꒃ�̖��́� |
�u����������m�̕���i�Ȃ�j�@�~�̉ԁv�c�ޗǁE ���J���̋��B1798�N�i35�j�̌��U��B�Ӗ��� �g�����A�g���S������ƂȂ莩�������m�̒��� ���肵��������B���C�əz�ƍ炭�~�̉Ԃ̔@���h |
���̏����Ȏʐ^�� ���ׂĈꒃ�̋��I ������Ă���̂������� �i�ꒃ�L�O�فj |
|
�]�ˌ���̔o�l�B���U�ɖ�Q������̍���̂������B�{���A���і푾�Y�B����̔_�Ƃɐ��܂��B�R�ŕꂪ���E�B�p��Ƃ͋C�����킸14�Ō̋����o�č]�˂ցB�l�X�Ȕo�l�ƌ𗬂��A30����U�N�Ԃقǔo�~�C�s�̂��ߋߋE�E�l���E��B�𗷂��ĉ�����B1813�N�i50�j�ɐM�Z�A���B52�̔Ӎ��Œ��������܂��B1819�N�i56�j�A��\��ƂȂ�啶�W�u���炪�t�v���܂Ƃ߂�i�o�ł͎���25�N��j�B���̌�A�ȂƎq���S�l�ɓV�R����ɕ��Ŏ��X�旧����A�Q�Ԗڂ̍Ȃ͔��N�ŗ����i�Ȃ��������H�j�A�R�x�ڂ̌����Ő��܂ꂽ����������l�ɂȂ����i���͈ꒃ�̎���ɐ��܂�Ă���Ζʂ��Ă��Ȃ��j�B1827�N�ɒn���̑�ʼnƂ������A���̂S������ɏĂ��c�����y���̒��Ŏ��������B���N65�B�ꒃ�͐����Ƃ���������̂������A�D�����ɖ������ӂꂽ��𑽂��r�B
�u��Ɨ��ėV�ׂ�e�̂Ȃ����v�i���g�̗c��������z�j
�u���^�i�₹���ւ�j�܂���Ȉꒃ���ɂ���v
�u���̎q�����̂������̂���n���ʂ�v
�u����������Ă����Ƌ����q���ȁv
�u�ڏo�x�������ʂȂ肨�炪�t�v�i�����̎��̒���ɉr�ށj
|
���NJ�/Ryokan ���8�N10��2���i1758�N11��2���j-�V��2�N1��6���i1831�N2��18���j �i�V�����A�����s�A���� 72�j2008
�����a�n�i�V�����o�_��j
 |
 |
 |
 |
| ���̒n�ŗNJ��͐��܂ꂽ | ���݂͗NJ��������� | �w�NJ��a���a���V�n�x | �w�NJ����a�n�k���Ձx |
 |
 |
| ��̌̋��A���n�������߂�NJ��i�r�V�Ō������j | �NJ����̌���ɍ����Ă����܂� |
 |
 |
 |
| ���a�n�ɋ߂��w�NJ��L�O�فx | �L�O�ى��̌����Ɏ�܂�����NJ��Ǝq�� | ���̗NJ����͉��₩�ŗǂ�����I |
 |
 |
 |
| �w�NJ��L�O�فx�̗���ɂ́c | �NJ��̕�̕�i�R�{�Ɓj | �w�NJ��L�O�فx�ɂ͎��M�̉̂������� |
�������揊�ցi�V���������s���j
 |
 |
 |
 |
| �X�^���h�E�o�C�E�~�[�I | �V����JR�����J�w�͖��l�w | ���Ԃ̗�Ԃ͂R�{ | �g���ԓ`��80�~�I�z�I |
11���̓d�Ԃł���ė����B����13������16���܂ŗ�Ԃ��Ȃ��̂ŁA�������ł��Q���Ԉȓ��ɖ߂��Ă���K�v���������I
  |
 |
| �q���Ǝ�{������NJ�����̃����[�t�����̗����ɂ������B�n���̐l�Ɉ�����Ă�Ȃ� | �I���̒n�B���n�̈��ő��E���� |
  |
 |
 |
| �揊�̂��闲�ɓ����I �NJ�����̓������؉A�ɂ�������ł��� |
�����ɗNJ�����̏������̂��Y�����I |
��O�ɃX�Y���o�`�̑� ������A��т܂����Ă��I �댯�����鏄�炾�����I |
 |
 |
 |
| �NJ����M�̓얳����ɕ��B �͂����y���ȕM�v�ɖ��A�� |
�ӔN�͖ؑ��Ƃ̐��b�ɂȂ�B���͖ؑ��Ƃ̕�B �NJ�����̍����Ɍ�����̂͒�E�R�V�̕� |
�u�NJ��T�t��v �����Ȑl�i�������ꂽ |
 |
 |
  |
| �������ɂ���u�NJ��̗����p�فv�B���M�̏���W�� | ���p�ق̑O�ɂ��傱��ƍ��� | �����p�قɂ͓�m�Ƃ̃��u���u�����B�NJ�����A�߂������Ă�I(*^v^*) |
 |
  |
 |
| �B��̒�q�E�Ր��̕�i�������j | ���̋ߏ��̖������ŋ��R�������u���Ϗ�v�B���O���J�b�R�C�C�I | �������̒ނ���͍��E����I�H���߂Č����I |
|
�̐l�⏑�ƂƂ��ėL���ȍ]�ˌ���̑T�m�i�����@�j�B1758�`1831
�B�o�g�͌��E�V�����o�_��B�����A�R�{���F�i�c���h���j�B���͑���i���������I�j�B���͏o�_��n��̖��傩�_��B1775�N�i17�j�A�NJ��͒��j�ł����������̐Ղ��p�����ɗב��̎��ɏo�Ƃ��A21�̂Ƃ��ɉz���K�ꂽ���m�E����a������@���u�NJ��v��^�����A����a�������ĉ��R�E�~�ʎ��ɓ���A12�N�ɂ킽���ďC�s�ɖ�������B25�̎��ɕꂪ���E�B28�A�����B�����A��̗R�V�i�䂤���j����������p�����B1790�N�i32�j�A����a��������̏ؖ����ƂȂ�����������A���N���珔�����s�r�ŏ���n�߂�B37�A�l�ԊW�ɔY�������s�j��ɂē��g���E���A�NJ��͗��N�ɋ��y�ւ̋A�r�ɂ��B
1797�N�i41�j������o�_��t�߂ꕶ�œ]�X�ƈڂ�Z�݁A1804�N�i46�j��荑�㎛�i�������傤���j�E�܍����ɒ�Z�A�\���N�������ʼn߂����B1812�N�i54�j�A��\��ƂȂ鎩�I�̏W�E�w�z���U���i�ӂ邳�Ɓj�x�������B1816�N�i58�j�A���q�i���Ƃ��j�_�Ћ����̑����ɋ����ڂ��A���̒B�l�ł������NJ��͂����ő����̖��M���c�����B�����ˎ�E�q�쒉���i��������j�����X�ɉ��q������K��A�u�鉺�ɏ��������v�Ɛ����ɂ����ہA�NJ��́u���i���j���قǂ́@�������ė���@���t���ȁv�i�ϐ����ɕK�v�ȗ����t�͕����^��ł���A�R���̕�炵�ɉ��̕s�����Ȃ��j�̈����Ŏw�������A�v����f�����Ƃ����B
1826�N�i68�j�A�NJ��͘V����������30�N�߂���������R���牺��A���葺�i�������s�j�̖ؑ��Ƃɐg���čŌ�̂T�N�Ԃ𑗂�B���N�A40���N���̎Ⴂ��m�E��S��i28�A��t�̖��S�l�j����q���肵�A�����萶����B1831�N�P���U���ߌ�S���A�������ɂɋꂵ�݁A�Ŋ��͒�S��ɊŎ��ꑼ�E����B�NJ��́u���t�W�v������Ȃ������A���̂S�N��ɒ�S�NJ��̘a�̂��W�߂��̏W�w�@�i�͂����j�̘I�x�i1835�j��ҏW�����B�NJ����E��41�N��i1872�N�j�A��S��͔���ɂ�75�Ŗv�����B
�NJ��͖��~�Ő��U�����̎��������Ȃ������B�S�Ă̐l�Ɉ���[���ڂ��A����Ȑ��@�͂����A�����ł������镽�ՂȌ��t��I��ŕ������L�߂��B�����āA�u�q���̏��^�ȐS���������̐S�v�ƌ��A��ɉ��ɂ͎�{�����A�D��Ŏq�������Ƃ悭�V�B�������ڂʼnB�ꂽ�܂ܒ��ɂȂ����Ƃ�����b���c��B���i������j�̉��ɐ����Ă����|�̎q�ׂ̈ɁA���Ɍ����J�����Ƃ����D�����b������B�T�m�ł���Ȃ�������D�Ɠ`�����A�e���݂₷���NJ��̎p���v���`�����B
�NJ��̏��͐��O����D�������ɂȂ�قǐl�C������A�l�X����ɕۊǂ������ߌ㐢�ɖ�1200�c��A��[�N���A����ׂȂǗNJ��̌����҂͑����A���a�ȍ~��100���ȏ�����������s����Ă���B
��͔ӔN�ɐ��b�ɂȂ����ؑ��Ƃ̕�ł��闲�i�����s�j�ɗ����A�\�ʂɎ��̉̂����܂��u��܂��Â� �����Ђ̉��� �������i���������j���Ă� ���݂ȂÂ� ���J�̉J�ɔG����Ă�v�i�������̋u�ɗY���������Ă���B10���̗₽�����J�ɔG��Ȃ���ꣂƗ����Ă���j�B�����́u�`���Ƃā@���c����� �t�͉� �ĂقƂƂ��� �H�͂��݂��t�v�i�`���ɉ����c�������B�t�͉ԁA�Ă͂قƂƂ����A�H�͍g�t�̗t���ς��ȁj�B���R�̌b�݂�������S���ɂ��ĉ̂������ė~�����Ƃ����A�㐢�̎������Ɍ��������b�Z�[�W���B �f�p�Ȑl�����ɂ��ݏo�鐔�X�̉́B
�u�����@�i���t���Ɂ@�q�ǂ���Ɓ@��܂���@���̓���炵�v�i�����t�ɂȂ�q�ǂ������Ǝ�܂�����Ȃ������߂�������j
�u���̗��Ɂ@��܂���@�q�ǂ���Ɓ@�V�ԏt���́@��ꂸ�Ƃ��悵�v�i���Ŏ�܂�����Ȃ���q�ǂ���ƗV�ԏt�̈���́A���Ȃ������Ă��܂�Ȃ��j
�u�����@�邲�Ƃɕς͂�@�h��ɂ��@���Ԃ͓����@�ӂ邳�Ƃ̖��v�i���̏h�͖��Ӕ��܂�Ƃ��낪�قȂ邪�A���͂��������̋��̂��̂��j
�u�̂Ă��g���@�����ɂƖ�͂@�v���́@�J�~��~��@�������ΐ����v�i�o�Ƃ����C��������ꂽ�Ȃ�A�J�͍~��ɂ܂����A���͐����ɂ܂�����Ɠ�����j
�u���̎q���@�킪�Y���ǂ��@���l�͂Ȃ��@���̎q���͂�v�i��Ɏg����Ȕ��̎q�[�ɖY��Ă��܂������A�N��l��낤�Ƃ��Ȃ������B���S�ɑς��Ă��锫�̎q�����Ƃ����j
�u�����Ƃ��@�݂Ȑ̂Ƃ��@�Ȃ�ɂ���@�܂����@�`���Ȃ�܂��v�i�����Ƃ��S���̂̂��ƂɂȂ��Ă��܂����B�܂��������Ȃ��̌`�����j���m�l�̍��w�ҁE�呺���}�i�݂��j���]��ɍۂ��B
�u���т����Ɂ@���̂��ق���@�o�Č���@��t�����Ȃ݁@�H���������v�i�₵���ɕ�܂�đ�������o�Ă݂�ƁA�H������̗t�������Ȃт����Ă����j
�u�́i���j�낵�߂��@�������i���j�����@�䂩��Ɓ@�g���߂Ă�@�����������v�i�̖����������Ƃ�����A����͎��߂Ă���䂪�g�������Ǝ��g��ӂ߂�j�������i���̒��j�̐S�\���B
�u���炿�˂́@�ꂪ�`���Ɓ@���[�Ɂ@���n�̓��ׂ��@�������邩���v�i�o�_�肩�璭�߂鍲�n���̌`���Ǝv���Ē��߂Ă����j
�u�킪�҂����@�H�͗��i���j�ʂ炵�@���̂�ӂׁ@���ނ炲�ƂɁ@���̐�����v�i�����҂��]��ł����H������ė����悤���B�[���̒��A���ނ炲�Ƃɒ������Ă����j
�u���i���j��݂́@����҂��ā@�A��܂��@�R�H�͌I�́@�{�i�����j�̗���v�i���̌����˂��̂�҂��Ă��A��Ȃ����ȁB�R���͌I�̂����������Ċ�Ȃ��ł���j�����q�ɁB
�u��܂��Ấ@�����Ђ̉��Ɂ@�������i���������j���Ă�@���݂ȂÂ��@���J�̉J�ɔG����Ă�v�i���������̋u�ɗY����ꣂƗ����Ă���B10���̗₽�����J�ɔG��Ȃ���Ǎ��ɗ����Ă���j���NJ��̕�̍��ʂɂ��ꂪ�����Ă���B
�u�ʂ��܂́@�����͐��Ђʁ@�����Ɂ@�N�������ނ�@���̂����Ɂv�i����͂��܂����ɐ����Ă��܂�����B�N�������߂Ă����A���̂��܂����Ɂj
�u�R���́@�^�i���킸�j�̐��Ɓ@�Ȃ�ɂ���v�i�t�ɂȂ��ĎR���͊^�̐��������Ă���Ȃ��j
�u�閾����@�X�̉����i�������فj�@���炷���@���ӂ��������́@�l�̐������v�i�閾���ɂȂ�A�X�̈��̂܂��ł��J���X�����Ă���̂���������B�����������Ă��̐��̐l�̐��ɓ����Ă����j
�u�����Ȃ�ʁ@���܂͌u���@���Ȃ��@�����̐����@�N�����܂͂ށv�i�������芦���Ȃ�A���͌u�������Ă��Ȃ��B�����̐������������Ȃ��ȊO�ɒN�������Ƃ����̂��j�����������˂��肵�Ă���́B
�u���Ă݂�@���O�l�ܘZ�����i�Ђӂ݂悢�ނȂ�j�@��i�����j�̏\�i�Ƃ��j�@�\�������߂ā@�܂��͂��܂���v�i�ꏏ�ɂ܂�����Ă����B���O�l�ܘZ������\�ƁA�\���I���Ƃ܂��ꂩ��n�܂�ˁA���ꂪ���̋�������j����S��A�܂���ɂ�镧�@�̋Ɉӂ���āB
�u�����Ɓ@�҂��ɂ��l�́@�����肯��@���܂͑����ā@�����v�͂ށv�i�����邩�A�����邩�Ƒ҂��������l�����ɗ��Ă��ꂽ�B�������Ċ炪�����āA�����v���c�����Ƃ͂Ȃ��j
�u�`���Ƃā@���c����ށ@�t�͉ԁ@�ĂقƂƂ����@�H�͂��݂��t�v�i�`���ɉ����c�������B�t�͉ԁA�Ă͂قƂƂ����A�H�͍g�t�̗t���ς��ȁj�������̉̂Ɠ`���B���R�̌b�݂�������S���ɂ��̂������ė~�����Ƃ������b�Z�[�W�B
�u����������@�����Ă������ā@�U����݂��v�i����\�������Ȃ���U��g�t�̂悤�ɁA�����l���̗��\�����炯�o���Ȃ��玀��ł����̂���j
�u�U��� �c����� �U����v
����S��Ƃ̗L���ȁu���炷�ⓚ�v
�NJ��u���Â��ւ��@�����Ă��s���ށ@�������́@���炷�ĂӖ����@�l�̕t����v�i��������͂ǂ��ɂł���ї��Ƃ��B���Ă��Ŕ������@�߂��������߁A���炷�Ƃ�������l�����Ă��ꂽ�̂Łj
��S��u�R���炷�@���ɂ��s�i��j���@�q���炷���@�����ȂЂčs���@�H����킭�Ƃ��v�i�R���炷�����X�ɍs���Ȃ�A�q���炷�̎����U���ĉ������ȁA�H�����キ����܂Ƃ��ɂȂ����Ƃ��Ă��j
�NJ��u�U�Ђā@�s���s���߂ǁ@�l�̌��ā@���₵�ߌ���@�����ɂ��Ă܂��v�i�U���čs���Ă��ǂ��̂����A���l���j���̎����������ĕςɎv��Ȃ����낤���j
��S��u�͂Ƃс@���͂����߁@��͂����@�G�͂��炷�@���i�Ȃ�j�����₵���v�i�͓Γ��m�A���͐����m�A��͍듯�m�A�G�͉G���m�ōs������̂ɁA�����ςȂ��ƂȂǂ���܂����j
��S��Ɉ�{���ꂽ�NJ��ł������B
���NJ��͑�m�ʼnƁX������Ă����B��n��ŐH�����������Ă��ꂽ��ǁi����j�ƁA�����̈��{�ƁA���E�w�F�ň�t�̌��c�ƁA���̌�O�Ƃ��ً}���悾�����B
���܍����͗NJ�������܍��̕ĂŎ������Ƃ������Ƃ��疼�t����ꂽ�B
���܍����̋߂��ɋ��u�����قǂ͕������ė��闎�t���ȁv�����B
|
 |
| �Ԃɍ����܂����I(*^o^*) |
���� �j/Akira Sturu 1909.1.1-1938.9.14 �i��茧�A�����s�A���Ǝ�
29�j2009
���ɓ� ����v/Sachio Ito 1864�N9��18���i�������N8��18���j-1913�N7��30�� �i�����s�A�]����A����@ 49�j2010
���ݖ{ ���{/Suifu Kishimoto 1892.2.29-1965.8.6 �i���s�A�V������A�@�� 73�j2014
 �@
�@ �@
�@
�W�����P���u�O���R�v�Ă����吳�E���a�̃R�s�[���C�^�[�A�����ƁB�O�d���o�g�B�{���͗��Y�i�����j�B
�u�O���R�v�u�扮�i���T���g���[�j�v�u�������܁v���̍L����S���B1936�N�i44�j�A�u�ꗱ300���[�g���v�̃R�s�[���u�[���ɂȂ����B
������ �Ɨ�/Fujiwara-no-Ietaka �ی�3�N�i1158�N�j-�Ò�3�N4��9���i1237�N5��5���j �i���s�A�V������A�Ɨ��� 79�j2014
���A�C�E�G�I��/�C�O�҂̖ڎ���
���A�C�E�G�I��/���{�҂̖ڎ���
���W�������ʌ����̖ڎ���
 |
 |
| ���̎���ɍŌ� �܂Ŕ�����т��� |
�����s�̏����ω���n�ɂ́A�ߕj�̔��� ��肪����w��Ƒ����������ۑ��ɂ��Ă������x |
 |
 |
 |
| �ߕj�̕�A���Ǝ��B�����ɕ�n���Ȃ� �̂ŏZ�E����ɕ�n�̏ꏊ��q�˂� |
��n�͌��Ǝ����班������Ă���A �{�����̒ʗp���������E���ɂ��� |
�ߕj����I��ォ�炠�Ȃ��� ����߂ɐ����܂ŗ��܂����I |
 |
 |
 |
| ���Ɂu�ߕj�̕�v�̗��D�������� | �����ɕ��C���Ă����Z���⍜���������A������������Ƃ��� | ����ɂ͖{���́u�쑽�Ɓv�̕��� |
|
��������ƁB�ΐ쌧�����o�g�B�{���A�쑽 ���i�����E�����j�B���͒|�H�E�l�B�c�����ɗ{�q�ɏo����B�W�Ŏ�����S�����B���w���̍�����V���̎q�ǂ����ɔo���Z�̂𓊍e���A1924�N�i15�j�A�g�쑽�ꎙ�h�̖��O�Ŗk���V���̉̒d�R�[�i�[�ɍ�i�\�B���N�A������ɍ�i���f�ڂ���n�߂�i���̔N�A�����ێ��@���{�s�����j�B1926�N�i17�j�A�{�����o�c����H�ꂪ�ׂ�A�P�N�ԑ��̍H��œ����B����ɘJ���҂̗���ɗ�������i�i�v�����^���A����j�������A������Ɍf�ڂ����ۂ���Ă��܂��B18�ŏ㋞���Đ���ƂɎt���B1928�N�i19�j�A�̋��ɖ߂�n���ɐ��������g�����A�v�����^���A����̎w�����n�߂�B�������A���ǂ���e�����A���ԂƋ��ɂS�������������B���̍�����M�����u�� �j�v�Ƃ���B
1930�N�i21�j�A�����������̑�9�t�c������7�A���ɓ���������A���R�L�O���̑ԓx�����ƂȂ�c�q�ɕ��荞�܂��B1931�N�i22�j�A���B���ς��N����B�����ɍ����̋@�֎����������ނȂǔ���^����W�J�����g���A���ԉ������h�̎�ƂƔ��f����A�����ێ��@�ᔽ�ő��̊č���1�N8�����̊Ԏ��Ă����B1935�N�i26�j�A�㋞�B1937�N�i28�j�A�؍ޒʐM�ЂɏA�E�B�嗤�ł�ḍa�����������������ɓ����푈���u���B�ߕj�͎����������R�I�ƌ��Ȃ���A�E��ɏo���Ă����Ƃ���荞�݂̓����x�@�ɑߕ߂���A�Ăю����ێ��@�ᔽ�ɖ����B�����̖�����ɗ��u����A�ߕ߂���X������ɓ����Őԗ��Ɋ������a�������B���N29�B �ߕj�̓x�b�h�Ɏ���Ōq���ꂽ�܂ܐ▽�����炵���A�����ɂ���ēŁi�ԗ��ہj��ꂽ�Ƃ�����������B���E����1938�N�ɍ��Ƒ������@�����肳��A���{�͂܂��܂��푈�̓D���ɗ�������ł������B ���M�������̂�1937�N�̎��_�Œߕj���u����߂����Ԗ��ԉł̗�֎��������q�b�g���[�v�u���_���̌����Ă����̌����c�����v�ƁA����E���J����Q�N���O�ɁA�i�`�X�̋��C���������Ă��邱�ƁB�A�E�V���r�b�c�������̂͂��̂R�N�ゾ�B���{�ɂ����āA���������l���s���ɂ������Ɓi�O�����ł͂Ȃ��j�A�C�O�̏�͂��Ă������Ƃɋ����B�m��w�͂�����Βm�蓾���B �ߋ��̐푈������鎞�A�u���{�ɂ��܂��ꂽ�v�u���̍��͉����m��Ȃ������v�Ƃ������t���悭���ɂ���B���ہA���{�ȂǏ�������������A������^�����낤�B�������A������ߕj�A�K���H���A�h�C�c�l�ł���Ȃ��甽�i�`�^�������ď��Y���ꂽ�w���]�t�B�[�E�V�����A�ނ�̂��Ƃ��v���ƁA�u�����͎d���Ȃ������v�̈ꌾ�ŕЕt���Ă��܂��Ă����̂��ƍl���Ă��܂��B ��茧�̐���E�L�u��1982�N�ɋ����������A���N�ߕj�Ղ��Â��Ă���Ƃ̂��ƁB ���ߕj�̖{���g�쑽 ���h�́A�����x�@�̍���ŎE���ꂽ�U�ΔN��̍�ƁE���ё����ƁA���R�ɂ��悭���Ă���B���҂͖��O�����ʂ��Ă������ł͂Ȃ��A�v�z�ƂƂ��Đ���ߕ߂���A�S�����Ɏ��N�29�Ƃ����̂��������B�т�����B �ȉ��A�ߕj�̐����20��Љ�i�ꕔ�����ɕϊ��j�B �E�t�W���}�ƃT�N���̍��̎��Ǝ� �E���ꂩ����s�������Ȃƕ\���� �E�����Ԃŋюсi����j�ŕn���X���@ �E�����ɓ����a��H�������� �E�����z�����܂܂̃x���g�ň��S�f�[ �E������~���ʕ���c���Ă��� �E�݂Ȕx�Ŏ��ʂ鏗�H�̕�W�D �E�ӂ邳�Ƃ͕a���ƈꂵ��ɋA��Ƃ�
�E���B�̌��ɂ���ǂ������E�n�} �E�����̃A�S�q���i�{�R�j�͑���̂悤�ɉ̂��Ȃ� �E�҂�����E���M�͂ł��܂��Ȃ� �E������ځi�ނ��j���R�n�͔w���킳�� �E���œǂ� ����莆 �E�r�̂��Ȃ��j���[�X�f��ŗE�܂��� �E��Ƒ����������ۑ��ɂ��Ă����� �E���Ƃ����čs�������嗤�ւ����ė��� �E�e���ŒD�����c�̈ږ��� �E�D��ꂽ�c���Ƃ肩�����ɗ��ĎˎE���� �E�͂�ł�I�c�������ďt��҂�
�E�ٓ��̓����m�邱�덜�����i���Ō�̋�B�����̐Ԃ����̑ٓ��������n�߂����ɁA�펀�����v�̈⍜���͂����Ƃ�����j
|
���ɓ� ����v/Sachio Ito 1864�N9��18���i�������N8��18���j-1913�N7��30�� �i�����s�A�]����A����@ 49�j2010
 |
 |
 |
| �̐l�����w��e�̕�x�� ��҂Ƃ��Ă��m���� |
��̒ɂݕ����������I �����l�Ȃ̂ɂȂ��I�H |
�w��ɂ��T��B ���}�ɕۑS���K�v |
| �̐l�A�����ƁB�{���͍K���Y�B��t���o�g�B�Z�̂̐������u���сv�ɂ���Ǝ咣�B1900�N�i36�j�A�����q�K�Ɏt���B���X�N�Ɏq�K���v���A���̌�A�Z�̎G���w�n���i�����сj�x�w�A�����M�x�Ȃǂ��A�ʐ���`�����������B 1905�N�i41�j�A�����w��e�̕�x���g�z�g�g�M�X�h�ɔ��\���A�����獂���]�������B1913�N�A�]�쌌�ɂ�葼�E�B�剺�ɍ֓��g�B�揊�͋T�˂̕���@�B ����t�̎R���i����ށj�s���j���������قׂ̗�ɐ��ƁB���s�̌����Ɂw��e�̕�x�̐��v�Ɩ��q�̑��B |
���ݖ{ ���{/Suifu Kishimoto 1892.2.29-1965.8.6 �i���s�A�V������A�@�� 73�j2014
 �@
�@ �@
�@
�W�����P���u�O���R�v�Ă����吳�E���a�̃R�s�[���C�^�[�A�����ƁB�O�d���o�g�B�{���͗��Y�i�����j�B
�u�O���R�v�u�扮�i���T���g���[�j�v�u�������܁v���̍L����S���B1936�N�i44�j�A�u�ꗱ300���[�g���v�̃R�s�[���u�[���ɂȂ����B
������ �Ɨ�/Fujiwara-no-Ietaka �ی�3�N�i1158�N�j-�Ò�3�N4��9���i1237�N5��5���j �i���s�A�V������A�Ɨ��� 79�j2014
 |
 |
 |
| ���đ��p�̊C�݂��߂��܂ł��Ă��� |
�Ɨ��̌ܗ֓��B�������琅������ ���ޗ[�z�����łĂ����Ƃ����i2014�j |
��O�̉̔�u�_�肠��Γ�g�i�Ȃɂ�j�̗��� �h�肫�Ĕg�̓�����q�݂邩�ȁv�i�Í������W�j |
| ���q�����̉̐l�B���́u����イ�v�Ƃ��B������̓�����Ƃƕ��я̂����̐l�ŁA���U�ɉr�̂͘Z����I�u�V�Í��a�̏W�v�̐�҂̂ЂƂ�B���i�̂����ӂŁA���s�ɍ˔\��F�߂���B�����Ȑ��i�ŁA�㒹�H�@���B��ɔz�����ꂽ����e�����������B�ӔN�A�ےÍ��l�V�����̗[�z�u��茩����u���ʂ̊C�i���p�j�v�̗[�����D��ňڂ�Z�݁A�u�̏�ɑ��������āu�[�z���v�Ɩ��t�����B�����ė[�z�̌������A�����Ɋy��y�ւ̉�����������B�w�V����a�̏W�x�ɂ͍ő�43���߂��Ă���B�]��ʋ{�����B �u���i�����݁j�����̏��R�ق̂ڂ̂Ɣg�ɂ͂Ȃ�鉡�_�̋�v �u�u��̉Y�≓������䂭�g�Ԃ�蓀��ďo�Â�L���̌��v |
���A�C�E�G�I��/�C�O�҂̖ڎ���
���A�C�E�G�I��/���{�҂̖ڎ���
���W�������ʌ����̖ڎ���
��i���j�Agrave�i�p�j�Atombe�i���j�Agrab�i�Ɓj�Atomba�i�Ɂj�Atumba�i���j�Asepultura�i�|���j
��n�i���j�Acemetery�i�p�j�Acimetiere�i���j�Afriedhof�i�Ɓj�Acimitero�i�Ɂj�Acementerio�i���j�Acemiterio�i�|�j
|

